評者:川嶋周一(明治大学政治経済学部 専任講師)
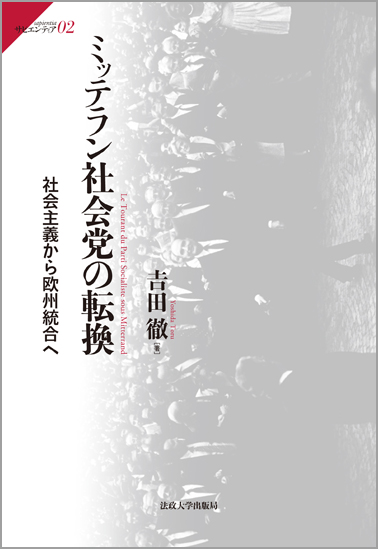 いわゆる新自由主義が良かれ悪しかれグローバルな政治経済的原則として登場して久しいが、このような政治経済上の原則はなぜそもそも先進国の間に登場したのか。英米のレガーノミックスとサッチャリズムの登場というのが通常の理解であろうが、本書が指摘するように、新自由主義の興隆を裏側から支えたのは、フランスのミッテラン政権の社会主義的経済政策の失敗だった。
いわゆる新自由主義が良かれ悪しかれグローバルな政治経済的原則として登場して久しいが、このような政治経済上の原則はなぜそもそも先進国の間に登場したのか。英米のレガーノミックスとサッチャリズムの登場というのが通常の理解であろうが、本書が指摘するように、新自由主義の興隆を裏側から支えたのは、フランスのミッテラン政権の社会主義的経済政策の失敗だった。
1981年にフランスに登場したミッテラン社会党政権は、野党時代に社会主義に基づく政権構想(社会主義プロジェ)を掲げ、政権獲得後は国有化路線という経済運営に乗り出す。しかし、その「実験」は二年後に脆くも放棄され、国家介入を控えた新自由主義的な経済政策へとパラダイム的転換、すなわち「転回」を果たすのである。
この社会主義の放棄は、欧州統合への選択の帰結として表れた。なぜミッテランは社会主義を捨て欧州統合を選んだのか。筆者の吉田徹北海道大学法学研究科准教授が東京大学大学院総合文化研究科に提出した博士論文を基にした本書は、この問いに対し、リーダーシップ論の視角から答えを出す。結論を先に述べれば、ミッテランが欧州統合を選択したのは、それが合理的な計算だったからでも外的圧力を受けたからでも、また欧州統合論者だったからでもなく、政権における自らのリーダーシップの維持のために必要だったからである。
本書の構成と概要
本書の構成は次の通りである。以下、本書の内容を要約して紹介したい。
序論
第一章 先行研究と本書の視角
第二章 「プログラムの政治」の生成過程:リーダーとフォロワーの相互作用
第三章 夢-プロジェの始動とリーダーシップ・スタイルの完成
第四章 挫折-モーロワ・プランの開始:リーダーシップ・スタイルの継続
第五章 転回-緊縮の決断:リーダーシップ・スタイルの変容
第六章 社会主義からヨーロッパの地平へ:新たなリーダーシップの獲得
結論
序論は、「転回」の意味について、政策的変容、政策的変容、そして歴史的変容という三つの側面から明らかにすることで、この転回の射程を明らかにしている。第一の政策的変容とは、従来のフランス経済政策の特徴だったディリジズム的政策からの決別によるインフレ抑止と財政均衡政策の実現を意味し、その結果、欧州通貨統合の実現性は飛躍的に高くなった。第二の政治的変容とは、それまでフランスの左右という枠組が融解し、左派であれ右派であれ、政権与党が取りうる政治の内容は同一化していったことを意味する。第三の歴史的変容とは、党派的政治から政権担当を前提とした政策論争、社会主義から新自由主義、国民国家から欧州統合という歴史的シフトが、この転回をきっかけにして起こったことを意味している。
次に第一章では、「転回」の要因を論じた先行研究を紹介したうえで、リーダーシップ論という本書の視角を紹介している。先行研究として紹介されるのは、モラヴチックによる国際政治経済学理論およびパーソンズの欧州統合理論研究である。前者については経済的要因を、後者は欧州統合のアイディアの強さが転回をもたらした要因と分析するが、筆者はこの分析を退ける。筆者は、ミッテランによるEMS離脱の放棄は政権党内での権力争いに起因する政治的決断であったという当事者の証言を重視し、ミッテランというリーダーシップと社会党および政権後は政権内におけるフォロワーとの相互関係を分析視角として採用する。そのリーダーシップ・スタイルとは、「取引的」「変革的」「選択操作的」の三種類である。
第二章は、1970年代を通じて、ミッテランがリーダーシップをどのように確立させていったのかを、社会党内の新生と社会主義プロジェの採択の二つの過程を通して見ていったものである。ここでは、旧社会党の主流派であるモーロワ派と連携しながら、自由主義色の強いロカール派とマルクス主義の強いシュヴェヌマン率いるCERESという均衡する勢力間の対立状況を巧みに演出し、有利な派閥の上に立つことで全体を統括するという「取引的リーダーシップ」が取られていた。
第三章は、ミッテランが大統領に当選した後、社会党の政策綱領である「社会主義プロジェ」と大統領公約として提示されたその要約版である「110の提案」を、実際の政策として実現していく過程が描かれる。社会主義プロジェに従い国有化政策を実行に移した。他方で内閣は社会党の主要派閥の勢力が反映された派閥均衡型だった。これは、派閥の個別利害を認めないミッテランの取引的リーダーシップを反映したものであった。
第四章は、社会主義プロジェの実施に伴う国有化路線が、国際経済の面で多くの問題を引き起こし、これに「近代人」たるドロールが国有化路線の修正を度々迫ること、そしてそのような問題がEMSの離脱か維持か、緊縮財政の実施か更なる国有化路線の徹底か、という政権内における経済的路線対立へとつながっていく過程を描いている。特にミッテランの忠実な僕であったモーロワはドロールとその周りに登場した経済テクノクラットの説得を受けて、反プロジェ勢力の一員となり、緊縮財政を小規模に行うモーロワ・プランの発動に至る。しかし、ミッテランの取引的リーダーシップ・スタイルそのものには変化はなかった。
第五章は、政権内でEMS離脱派(=国有化路線の維持)とEMS残留派(=その代わりに緊縮財政の実施、すなわち国有化路線の放棄)の路線対立が激しくなり、遂にはミッテランによる政治的決断に至る過程を描いた、本書の白眉に当たる部分である。モーロワ・プランは経済的成功を収めたとは言えない一方で、国際収支の赤字増加とフランの価値の下落により経済的な危機的状況は増していった。そこで政権内では、EMS離脱による輸入制限の実施を行うか、EMSに残留しつつもフラン切り下げと緊縮財政を行うかという二つの選択肢が争う状況が生じる。ミッテランはEMS離脱に傾き、1983年三月の欧州理事会の開催に合わせて、EMS内の平価調整に失敗すればEMS離脱を行うことを考えることとなった。これは、取引的リーダーシップが機能しなくなっていった結果、特定の価値を提示することで、その価値の下にフォロワーを牽引していこうとする「変革的リーダーシップ」の顕れだった。しかし、この欧州理事会開催前後、EMS離脱の指示に明確に抵抗したモーロワの態度を契機に、ミッテランの行動と方針は二転三転する。最終的に、EMS離脱派の筆頭ファビウスが国庫局長から直接外貨準備高の額を知ったとき、ファビウスは、EMS離脱を行えばフランは完全相場制へと移行し、弱い通貨価値のために高金利政策を余儀なくされ、国有化政策の推進は不可能になることを理解する。そのためファビウスはEMS離脱を諦め、ミッテランにEMS残留を提案する。ここでミッテランはEMS残留を決断する。政権はEMS残留一色で染まることで、ミッテランが提示したEMS離脱という価値提示による「変革的リーダーシップ」は、破綻するのである。
第六章は、転回後のミッテランの政策とリーダーシップを論じたややエピソード的な章である。EMS残留を決め、国有化路線を放棄し、緊縮財政に取り組んだミッテランは、その後急速に欧州統合にコミットメントすることになるが、そのミッテランによる欧州統合への取り組みが本章では描かれる。ここにおいて、固定されたフォロワーにリーダーシップの基盤を求めるのではなく、状況に応じて資源を組み替えてはリーダーシップを追求する「選択操作型リーダーシップ」をミッテランは取ることになった。多様なイシューが複雑に絡み合いながら常に新しい目標を追い求める欧州統合というプロジェクトは、このような新しいリーダーシップの場としてうってつけであり、以後ミッテランは欧州統合を自らのリーダーシップが発揮される場として活用することになるのである。
結論において、以上本論で展開された議論がまとめられている。社会党政権が国有化路線を放棄するまで二年の年月を要したが、経済的要因だけで説明するならば、通貨水準は政権開始後すぐに十分過ぎるほどに悪化しており、この二年間という年月を説明できない。他方で、ミッテランが欧州統合を選択した理由は、そのアイディアの強さからでなくリーダーシップとフォロワーとの関係ゆえである。そして、最終的に選択した欧州統合は未完のプロジェクトであるが故に、そこでの政治的リーダーシップは永遠であり、政治に希望を託すことが出来るのである。
狙いと評価
本書の視角は一貫しており、エピソードは豊富であり、筆致は華麗である。また本書のあとがきにもあるように、本書の関心は欧州統合へのコミットメントに対するミッテラン(と彼を取り巻く政治家)の政治的思惟と決断の精神を掬いだすことにあり、社会主義に対してではない。そのことが社会主義や人間ミッテランに対する距離感となり、また社会科学的な分析枠組の設定も手伝い、ミッテラン政権を政治学的な切り口から見事に分析することにつながっている。筆者の狙いを、本書では十分に達成されていると評価できよう。
本書は、ミッテラン政権における複雑な人間関係を丁寧に解きほぐし、ミッテランという稀代の政治家の下に形成された制度を必ずしも介さない人間関係に基づく独特の政治過程を再現し、どのタイミングで誰がなにを考えていたのかを詳らかにすることに成功している。特に、社会主義プロジェの行き詰まりからEMS離脱/保持をめぐる過程における、ミッテラン、モーロワ、ドロール、ロカール、シュヴェヌマンというキーとなる政治家の理念と行動の描写は圧倒的である。これに説得力を与えているのが、大統領府文書およびカルル文書という一次史料の利用とドロール、シュヴェヌマン、ギグーといった主要な当事者へのインタビューである。筆者の再構成能力と行動力の高さには脱帽である。社会科学としての政治学と歴史学としての政治史を巧みに架橋し、両者を行ったり来たりしているのが本書の方法論的な特徴でもあろう。
ただし、評者にも幾つかの疑問は残った。
第一に、「転回」におけるリーダーシップのスタイルについてである。ミッテランが一旦決意したEMS離脱という決断を撤回するという決断を基礎付けたのは、自らのフォロワーが、経済的合理的計算に基づき全員反離脱派となったことは、筆者が論じたとおりである。ではなぜそのミッテランの決定を経済的な条件に基づいた決定と説明してはいけないのか、やや釈然としない面も残る。さらに、たとえそれがリーダーシップ論として説明しなければならないのだとしても、「転回」はリーダーシップの「確立」というより、リーダーシップの破綻として説明した方がより適切ではないのだろうか、という疑問も残る。またミッテランのリーダーシップを論ずるのであれば、社会主義プロジェ・EMS以外の主要な政策における彼の取り組み方を比較政策的に検討することも必要だったのではないだろうか。
また第二に、ミッテランが稀代の政治家だったことは評者も重々に承知しているが、ミッテランは何故にこれほどまでにリーダーシップの追求に当たったのだろうか。筆者が描くミッテランのリーダーシップ戦略に拠れば、ミッテランは権力の追求と維持に汲々とする理念なき政治家と解釈されても仕方がないように見受けられる。理念なき政治家がなぜこれほどまでに人々を魅了し、そして動かすことが出来たのだろうか。リーダーシップ論にミッテラン政権の決定要因を絞り込めば込むほど、なぜそもそもミッテランがリーダーシップを必要としたのかという問いに戻らざるを得ないように思われるのである。
そして第三に、あとがきにもあるように、ミッテランの実験とは「フランスがヨーロッパの〈普通の国〉へと変化し、ヒロイックな政治的決断が日常的行政的決定へと変化していく過程」であるという。ならば「実験」の前は全てヒロイックな政治的決断に満ちた時代だったのだろうか。欧州統合にコミットするミッテラン以降政治は単なる行政的決定だけなのだろうか。筆者は「転回」の歴史的意義を華麗な筆致で語ってはくれるが、その転回が位置する歴史的な文脈も同様に明確にすべきではないのだろうか。つまり、「転回」は社会党政権にとっては「転回」だったのかも知れないが、例えば西独の視点に立てばバールへの回帰とも見えよう。言うなれば、「転回」とは「転回」ではなく、逸脱状態からの正常状態への復帰とも解釈できるのではないのだろうか。確かにミッテラン政権は第五共和制初の社会党政権であるが、ミッテラン政権を以って従来の政治と外交のすべてが変わる訳ではなかろう。ミッテランはそれまでの政治・外交の何をリセットし何をリセットしなかったのかを、もう少し包括的に整理することも必要ではなかっただろうか。
これに関連して最後に、「転回」の射程の論証と転回の要因分析はどこまで調和的なのか、評者は判断できなかった。本書で筆者はミッテランの転回の歴史的画期を優麗な筆致で説得的に述べている。しかし本書の分析はあくまで転回の要因であり、実のところ、転回の歴史的画期性そのものが論証されたわけではない。緻密に転回の要因を詰める一方で、やや唐突に転回の歴史的射程を語るその乖離に、評者は戸惑いを覚えたのである。
以上幾つかの疑問を呈しはしたものの、本書は、ミッテランというプリズムを通して国内政治と国際政治がどのような結節点を作りながら連動するのかという国際政治経済学的主題と、ミッテラン政権における政策過程と政治構造のフランス現代史の政治学的分析の双方を同時に検討することに成功した貴重な研究である。フランス政治研究は、語学的制約に加え、現地の研究文脈と日本のそれとの乖離のためになかなか日本人読者にとってリーダブルな本格的な研究成果が生まれにくい分野である。フランス政治外交の実証研究の蓄積が、本書を基礎として続くことを願うばかりである。
