評者:高橋和宏(防衛大学校 准教授)
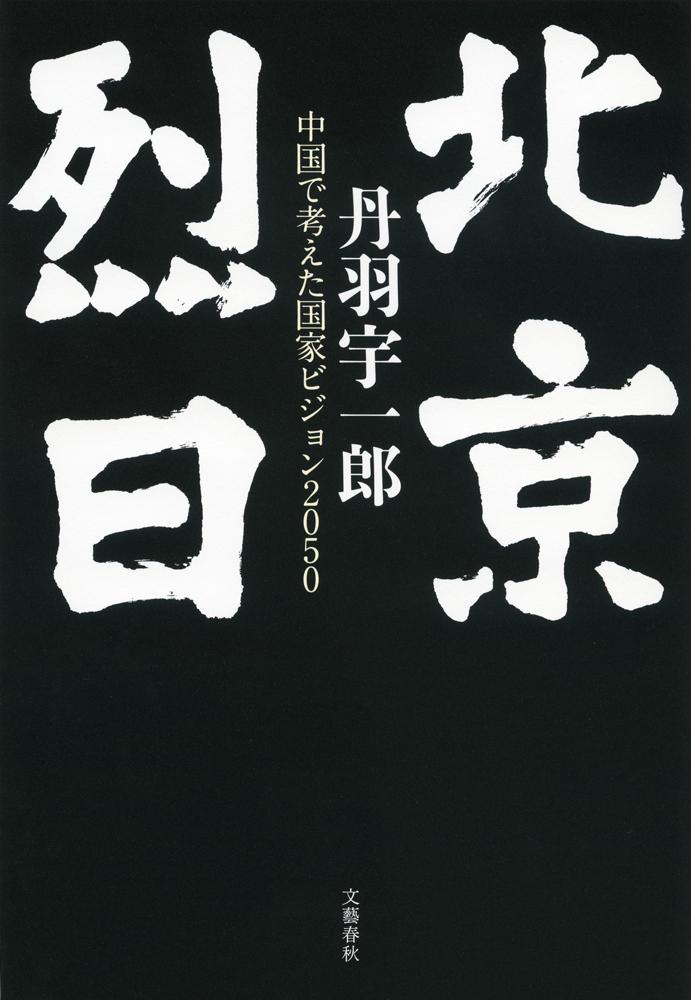
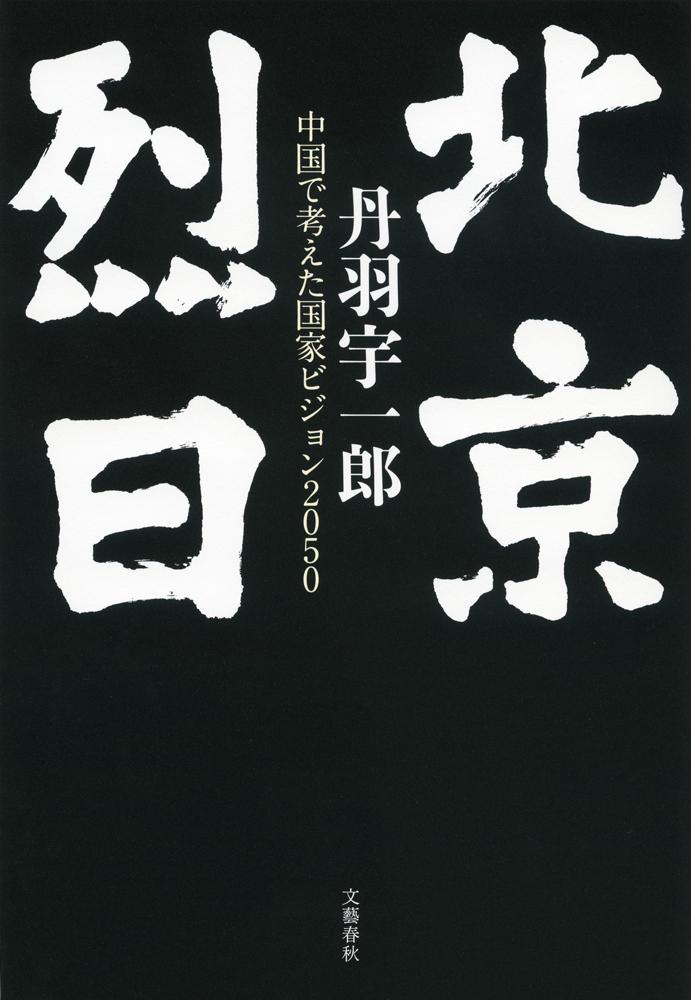
1.はじめに
表紙に『北京烈日』と大書されている本書は、一見すると、駐中国大使として尖閣をめぐる日中対立の渦中にあった筆者の回顧録かと連想させる。実際、尖閣をめぐる経緯についても最初の1章分が割かれているが、本書の意図はそうした「過去」あるいは「結果」を振り返ることにはない。中国在勤中に示唆を得た「日本にいては見えない事、中国でしか見えなかった事」をふまえて、日本の「新しい国家像」を描くことに筆者の狙いは定められている。その意味で、副題の「中国で考えた国家ビジョン2050」のほうが本書の内容を正確に示しているといえよう。
本書で展開される議論は「2050年の日本」のグランドデザインの大きな柱として、人口減少(とくに生産人口の減少)をふまえた経済政策の在り方と、中国政治経済を分析しつつ将来の日中関係のあるべき姿を提示することの二つに大きく分けられる。以下ではまず、この二点についての論点をまとめ、最後に本書から見えてくる尖閣をめぐる当時の政府内の動きについてコメントすることとしたい。
本書で展開される議論は「2050年の日本」のグランドデザインの大きな柱として、人口減少(とくに生産人口の減少)をふまえた経済政策の在り方と、中国政治経済を分析しつつ将来の日中関係のあるべき姿を提示することの二つに大きく分けられる。以下ではまず、この二点についての論点をまとめ、最後に本書から見えてくる尖閣をめぐる当時の政府内の動きについてコメントすることとしたい。
2.「2050年の日本」のグランドデザイン
2050年の日本の人口は2050~60年には8700万人にまで減少し、人口構成も非生産人口の割合が5割を超すと予想されている。そうした人口減少を前提としつつ、2050年の日本が世界の中でプレゼンスを示すにはどうすればよいか。筆者の答えは、「質(クオリティ)」の価値を上げることで実質的に成長する社会を作り上げ、質で勝負できる商品を世界に売り込んでいくことにある。「質」とは、日本が得意としてきた「3A(安心・安全・安定)」であり、その意味でも、信頼ある製品作りを支えるブルーワーカー教育が日本の将来を決するほどに重要だという。一方、急増する世界人口をまかなうだけの食糧増産が難しいと予想する筆者は、日本の農業政策について、日本の環境に最も適したコメを農業の牽引役とすべきと論じ、そのためには農地と農民のクオリティを高めて「自給力」を強化しつつ、自立した農業が国際競争力の高い農産品を生産していくことが必要だという。そのうえで、こうした製造業や農業の「質」向上のためには、「国民―企業―政府」の三角形のバランスを保つことが重要で、国が経済の前面に出る国家資本主義に陥らないよう警告している。
一方、中国経済について筆者はバブル崩壊を予期する見方を排し、「世界の工場」から「世界の市場」への変貌を予測する。すなわち、自らの欠点に気付いている中国共産党は、民生部門の強化や経済の民主化に向け、先進国資本主義の失敗例を(教科書ではなく)参考書として研究しながら「壮大な実験」に乗り出しており、これが国民生活の向上につながって、内需主導の第二次資本主義の段階へと移行するのである。こうして生まれる巨大な市場に日本企業はいかに参入すべきか。筆者はいわゆる「チャイナ・リスク」を背負うかどうかはそれぞれの経営者が判断すべきとしつつ、製造業ではgoogleやdellを参考に償却残を遺さない方法、小売業では「3A」ブランドへの信頼や従業員のサービス精神など日本の良さを売ることを提案している。
筆者は、「日本と中国は住所変更することができない」と「思想で経済はコントロールできない」を持論に掲げる。この二つは、経済面での協調によって地理的隣接性から生じる政治的な不安定を抑制する、という日中関係の将来像に収斂する。すなわち、日中は隣国であることを前提に国民の憎悪を越えて友好関係に努めるしかなく、そのためには、中国を国際経済へと引き出して相互依存関係をいっそう深め、経済分野を軸に協調しつつ、安定した政権が外交交渉に臨むことを提言するのである。さらに筆者は、日本の外交方針として、日米同盟一本槍でない「日米中正三角形」という東アジア地域秩序像を描いている。
以上のように、本書は経営者ならではの視点をふんだんに交えながら、長期的な日本の「国家戦略」を提示している。「経済力」を国力の重要な要素とみなすこと、「思想で経済はコントロールできない」という経済活動の特性に基いた外交の在り方、国家資本主義によらない経済政策の重要性、政策デザインに長期的時間軸や「残償却」という概念を持ち込むこと、中国の「農民工」から逆照射してみるブルーカラー教育の大切さ、コメの国際競争力の可能性など、興味深い論点が数多く書かれており、「新日本国家ビジョン」を考える上で大変示唆に富む内容となっている。
一方、中国経済について筆者はバブル崩壊を予期する見方を排し、「世界の工場」から「世界の市場」への変貌を予測する。すなわち、自らの欠点に気付いている中国共産党は、民生部門の強化や経済の民主化に向け、先進国資本主義の失敗例を(教科書ではなく)参考書として研究しながら「壮大な実験」に乗り出しており、これが国民生活の向上につながって、内需主導の第二次資本主義の段階へと移行するのである。こうして生まれる巨大な市場に日本企業はいかに参入すべきか。筆者はいわゆる「チャイナ・リスク」を背負うかどうかはそれぞれの経営者が判断すべきとしつつ、製造業ではgoogleやdellを参考に償却残を遺さない方法、小売業では「3A」ブランドへの信頼や従業員のサービス精神など日本の良さを売ることを提案している。
筆者は、「日本と中国は住所変更することができない」と「思想で経済はコントロールできない」を持論に掲げる。この二つは、経済面での協調によって地理的隣接性から生じる政治的な不安定を抑制する、という日中関係の将来像に収斂する。すなわち、日中は隣国であることを前提に国民の憎悪を越えて友好関係に努めるしかなく、そのためには、中国を国際経済へと引き出して相互依存関係をいっそう深め、経済分野を軸に協調しつつ、安定した政権が外交交渉に臨むことを提言するのである。さらに筆者は、日本の外交方針として、日米同盟一本槍でない「日米中正三角形」という東アジア地域秩序像を描いている。
以上のように、本書は経営者ならではの視点をふんだんに交えながら、長期的な日本の「国家戦略」を提示している。「経済力」を国力の重要な要素とみなすこと、「思想で経済はコントロールできない」という経済活動の特性に基いた外交の在り方、国家資本主義によらない経済政策の重要性、政策デザインに長期的時間軸や「残償却」という概念を持ち込むこと、中国の「農民工」から逆照射してみるブルーカラー教育の大切さ、コメの国際競争力の可能性など、興味深い論点が数多く書かれており、「新日本国家ビジョン」を考える上で大変示唆に富む内容となっている。
3.尖閣をめぐる経緯
「命もいらず名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に困るものなり。この始末に困る人ならでは、艱難をともにして国家の大業はなし得ぬなり」という西郷隆盛の言葉と、高崎達之助から連なる経済界の先人達が築き上げた戦後日中関係を壊すことがあってはならないという想いを抱いて赴任した筆者の中国での滞在は、「尖閣に始まり尖閣で終わった」。
中国赴任からわずか1カ月後余りで起きた2010年9月の漁船衝突事件では、「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び」、中国側からのたび重なる深夜の呼び出しにも応じて日本政府の立場を伝え続けた。2012年6月には、東京都による尖閣諸島購入計画について、「もし計画が実行されれば、日中関係にきわめて深刻な危機をもたらす」とフィナンシャル・タイムズ紙(FT紙)とのインタビューで発言した。周知のとおり、この発言は国内で強い非難を引き起こすことになったが、筆者自身は「これは大変なことになる」という中国の古くからの友人との会話も踏まえて、そのタイミングについての警告を発したのであり、外務省や民主党の政治家にも「現場の声」を尊重するよう伝えたものの、確たる反応は得られなかった。2012年9月のAPECにおける日中首脳「立ち話」の直後に、日本政府が尖閣を国有化したことは、中国側からみると、メンツを重んじる胡錦濤、そして中国人のこころを踏みにじる結果となったという。
一連の経緯について、筆者の視線は、自らの意図に反することとなった結果について論じることを超えて、ヒートアップする両国関係の帰着点をさぐることに注がれている。すなわち、日本側として、「領土問題はないけれども外交上の係争はある」と認めて尖閣を管理する「すべ」について話し合いを始めることや、「待つ」・「休む」のカードを切り、現場レベルでの情報収集・分析をふまえて長期的視点で外交に取り組むことを提起する。そして、日中両国に対して、首脳間の信頼関係は世界の歴史を変えることをかみしめるべきと大局に立った対応を訴えるのである。
中国赴任からわずか1カ月後余りで起きた2010年9月の漁船衝突事件では、「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び」、中国側からのたび重なる深夜の呼び出しにも応じて日本政府の立場を伝え続けた。2012年6月には、東京都による尖閣諸島購入計画について、「もし計画が実行されれば、日中関係にきわめて深刻な危機をもたらす」とフィナンシャル・タイムズ紙(FT紙)とのインタビューで発言した。周知のとおり、この発言は国内で強い非難を引き起こすことになったが、筆者自身は「これは大変なことになる」という中国の古くからの友人との会話も踏まえて、そのタイミングについての警告を発したのであり、外務省や民主党の政治家にも「現場の声」を尊重するよう伝えたものの、確たる反応は得られなかった。2012年9月のAPECにおける日中首脳「立ち話」の直後に、日本政府が尖閣を国有化したことは、中国側からみると、メンツを重んじる胡錦濤、そして中国人のこころを踏みにじる結果となったという。
一連の経緯について、筆者の視線は、自らの意図に反することとなった結果について論じることを超えて、ヒートアップする両国関係の帰着点をさぐることに注がれている。すなわち、日本側として、「領土問題はないけれども外交上の係争はある」と認めて尖閣を管理する「すべ」について話し合いを始めることや、「待つ」・「休む」のカードを切り、現場レベルでの情報収集・分析をふまえて長期的視点で外交に取り組むことを提起する。そして、日中両国に対して、首脳間の信頼関係は世界の歴史を変えることをかみしめるべきと大局に立った対応を訴えるのである。
4.コメント―外交に対する民主的統制―
こうした筆者の提案には、むろん賛否両論あろう。そのことについてコメントすることは、本書評の意図するところではない。以下では、政策的な論点ではなく、このケースが内包する「外交に対する民主的統制」というテーマについて考えてみたい。
2009年の政権交代後、民主党政権は外交体制の改革として、いわゆる「密約」問題の調査と主要国大使人事への政治的関与(民間大使の登用)を行った。いずれも、それまで外務官僚(と一部の自民党政治家)の手中で内部的に処理されてきたことに政治的なコントロールを加えようとしたものであった。「密約」調査は有識者による調査結果の公表と関連文書の大量公開という結果を残し、民間大使の目玉として駐中国大使に任命されたのが筆者であった。
日本でも講和後初期には、米国などの主要国を含む各国に民間大使を派遣していた(新木栄吉駐米大使、古垣鉄郎駐仏大使など)。また現在でも、米国のように、職業外交官ではない人物が大使に任命されることは珍しいことではない。民間大使には職業外交官に比べて、本国政府首脳とのホットラインが期待できること、組織内からは出てきにくい意見やアイデアを提示すること、民間時代の経験を活かして派遣国政府とのネットワークを拡大することといった有利な点がある。また、大使人事を通じて派遣国政府に政治的なメッセージを込めるといったこともあろう。
実際、筆者が中国大使に任命された時には、大型投資プロジェクトでの商機拡大や日中FTAの推進といった「経済外交」の活性化や、商社時代からの独自ルートを対中外交に活用することが期待されていた。「丹羽大使」人事は、対中外交に政治のイニシアティブを注入すると同時に、日中経済関係をさらに拡大させるというメッセージが込められていたのである。
他方で、そもそも大使には、本国政府の意向を派遣国政府に伝達する役割に加えて、外交政策立案の一翼を担うことも期待されている。具体的には、本国政府に対する意見具申という方法のほかに、沖縄返還交渉時における下田武三駐米大使の発言(「下田発言」)のように、本国の国民に対して派遣国の事情を伝え、望ましいと考える政策へと世論を誘導・喚起するという役割も含まれていよう。FT紙での筆者の発言も、日本国内世論に向けて発した警鐘という意味を持つものであったと考えられる。
問題は、政府の側がこうした大使の動きをどうサポートするか、である。ニコルソンが「素人外交官」を厳しく批判したように、民間大使には外交経験の乏しさやそれまでの経歴が外交活動を制約する可能性など、つねに批判の種が付きまとう。これをはねのけて期待された役割を十分に果すためには、政治任用した政権と大使とがしっかりと意思疎通を行い、互いに支えあう関係を築くことが必要である。
ところが、FT紙上での筆者の発言が国内各方面から厳しい糾弾にさらされたとき、当時の民主党政権はこれを擁護せず、むしろ東京都や野党、世論に同調して、「個人的見解」「不適切」「国益から逸脱する可能性」と、その発言を論難した(この点は、「下田発言」をめぐる佐藤内閣の対応と対照的である)。こうした対応の背後には、FT紙に記事が掲載の時点(2012年6月7日)で、尖閣国有化に向けた地権者や東京都との水面下での接触が官邸主導で始まっていたことが関係していよう(春原剛『暗闘 尖閣国有化』新潮社、2013年)。
筆者の発言は、こうした動きを承知したうえで尖閣国有化交渉を押しとどめようとするためのものだったのか、それとも、事情を知らずになされたものだったのか。現時点でははっきりしないが、前者であれば、筆者がプレスを通じてまで伝えようとした「現場の声」が顧みられなかったということになろうし(なお、筆者は尖閣国有化のタイミングについても外務省や民主党政治家に伝えた「現場の声」が尊重されなかったと証言している)、後者の場合には、重要な対中政策立案に中国大使が関与していなかったことの証左となろう。いずれであったとしても、尖閣をめぐる一連の経緯において、中国大使が政策決定に与えた影響は限定的であり、筆者が懸命に伝えようとした「現場の声」は政府首脳の判断に強く響くことはなかったのである。
むろん、本国政府と大使館との関係において、現場からの意見具申が本省サイドで採用されないという事態はしばしば起こることである。政治任用された民間大使には、そうした時にこそ、政府首脳とのホットラインを活用して、本国政府と現場との間で意見の調整を図ることが期待される。だが、尖閣をめぐる一連の経緯において、中国大使であった筆者がそうした役割を果たしえたようにはみえない。その原因は、大使個人にではなく、大使と政府首脳とのコミュニケーションが十分に機能しなくなっていたこと、さらに言えば、民間大使が活躍するための基盤である政治の安定が欠けていた点に求められるべきであろう。
民主的統制のもとで外交を円滑に展開するため、あるいは、外交における政治主導と職業外交官の専門性とを機能的に連動させていくためには、その前提として政治の安定が不可欠である。外交の民主的統制のための一つの手段である民間大使も、政治が安定していなければ、政治任用された強みを発揮することができない。本書に描かれた一連の経緯からは、そうした自明の教訓が改めて浮かび上がってくるのである。
2009年の政権交代後、民主党政権は外交体制の改革として、いわゆる「密約」問題の調査と主要国大使人事への政治的関与(民間大使の登用)を行った。いずれも、それまで外務官僚(と一部の自民党政治家)の手中で内部的に処理されてきたことに政治的なコントロールを加えようとしたものであった。「密約」調査は有識者による調査結果の公表と関連文書の大量公開という結果を残し、民間大使の目玉として駐中国大使に任命されたのが筆者であった。
日本でも講和後初期には、米国などの主要国を含む各国に民間大使を派遣していた(新木栄吉駐米大使、古垣鉄郎駐仏大使など)。また現在でも、米国のように、職業外交官ではない人物が大使に任命されることは珍しいことではない。民間大使には職業外交官に比べて、本国政府首脳とのホットラインが期待できること、組織内からは出てきにくい意見やアイデアを提示すること、民間時代の経験を活かして派遣国政府とのネットワークを拡大することといった有利な点がある。また、大使人事を通じて派遣国政府に政治的なメッセージを込めるといったこともあろう。
実際、筆者が中国大使に任命された時には、大型投資プロジェクトでの商機拡大や日中FTAの推進といった「経済外交」の活性化や、商社時代からの独自ルートを対中外交に活用することが期待されていた。「丹羽大使」人事は、対中外交に政治のイニシアティブを注入すると同時に、日中経済関係をさらに拡大させるというメッセージが込められていたのである。
他方で、そもそも大使には、本国政府の意向を派遣国政府に伝達する役割に加えて、外交政策立案の一翼を担うことも期待されている。具体的には、本国政府に対する意見具申という方法のほかに、沖縄返還交渉時における下田武三駐米大使の発言(「下田発言」)のように、本国の国民に対して派遣国の事情を伝え、望ましいと考える政策へと世論を誘導・喚起するという役割も含まれていよう。FT紙での筆者の発言も、日本国内世論に向けて発した警鐘という意味を持つものであったと考えられる。
問題は、政府の側がこうした大使の動きをどうサポートするか、である。ニコルソンが「素人外交官」を厳しく批判したように、民間大使には外交経験の乏しさやそれまでの経歴が外交活動を制約する可能性など、つねに批判の種が付きまとう。これをはねのけて期待された役割を十分に果すためには、政治任用した政権と大使とがしっかりと意思疎通を行い、互いに支えあう関係を築くことが必要である。
ところが、FT紙上での筆者の発言が国内各方面から厳しい糾弾にさらされたとき、当時の民主党政権はこれを擁護せず、むしろ東京都や野党、世論に同調して、「個人的見解」「不適切」「国益から逸脱する可能性」と、その発言を論難した(この点は、「下田発言」をめぐる佐藤内閣の対応と対照的である)。こうした対応の背後には、FT紙に記事が掲載の時点(2012年6月7日)で、尖閣国有化に向けた地権者や東京都との水面下での接触が官邸主導で始まっていたことが関係していよう(春原剛『暗闘 尖閣国有化』新潮社、2013年)。
筆者の発言は、こうした動きを承知したうえで尖閣国有化交渉を押しとどめようとするためのものだったのか、それとも、事情を知らずになされたものだったのか。現時点でははっきりしないが、前者であれば、筆者がプレスを通じてまで伝えようとした「現場の声」が顧みられなかったということになろうし(なお、筆者は尖閣国有化のタイミングについても外務省や民主党政治家に伝えた「現場の声」が尊重されなかったと証言している)、後者の場合には、重要な対中政策立案に中国大使が関与していなかったことの証左となろう。いずれであったとしても、尖閣をめぐる一連の経緯において、中国大使が政策決定に与えた影響は限定的であり、筆者が懸命に伝えようとした「現場の声」は政府首脳の判断に強く響くことはなかったのである。
むろん、本国政府と大使館との関係において、現場からの意見具申が本省サイドで採用されないという事態はしばしば起こることである。政治任用された民間大使には、そうした時にこそ、政府首脳とのホットラインを活用して、本国政府と現場との間で意見の調整を図ることが期待される。だが、尖閣をめぐる一連の経緯において、中国大使であった筆者がそうした役割を果たしえたようにはみえない。その原因は、大使個人にではなく、大使と政府首脳とのコミュニケーションが十分に機能しなくなっていたこと、さらに言えば、民間大使が活躍するための基盤である政治の安定が欠けていた点に求められるべきであろう。
民主的統制のもとで外交を円滑に展開するため、あるいは、外交における政治主導と職業外交官の専門性とを機能的に連動させていくためには、その前提として政治の安定が不可欠である。外交の民主的統制のための一つの手段である民間大使も、政治が安定していなければ、政治任用された強みを発揮することができない。本書に描かれた一連の経緯からは、そうした自明の教訓が改めて浮かび上がってくるのである。
0%
