細谷 雄一
政治外交検証プロジェクト・サブリーダー/慶應義塾大学法学部准教授、プリンストン大学客員研究員
はじめに
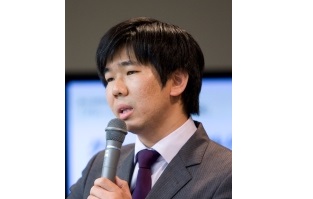 今から40年前の1969年に刊行された『海洋国家日本の構想』と題する著書の中で、故高坂正堯教授は「外交が世論の強力な支持を得たとき、日本は外交政策を持つといえるようになるのだ」と語り、日本における「外交政策の不在」を嘆いた。その30年前の1939年には、『危機の二十年』の中でイギリスの国際政治学者で歴史家のE・H・カーが「意見に影響を与えるパワー」の重要性を指摘していた。はたして日本はいま、健全な世論の上に、確かな「外交政策」を打ち立てているのだろうか。
今から40年前の1969年に刊行された『海洋国家日本の構想』と題する著書の中で、故高坂正堯教授は「外交が世論の強力な支持を得たとき、日本は外交政策を持つといえるようになるのだ」と語り、日本における「外交政策の不在」を嘆いた。その30年前の1939年には、『危機の二十年』の中でイギリスの国際政治学者で歴史家のE・H・カーが「意見に影響を与えるパワー」の重要性を指摘していた。はたして日本はいま、健全な世論の上に、確かな「外交政策」を打ち立てているのだろうか。
本研究プロジェクトではこれまで、毎年数多く刊行される外交史や国際政治学の専門書の中から限られた良書を選別し、それを丁寧に検証し議論を重ねて ブックレビュー として公表してきた。ひとたび街に出て書店に入るならば、そこには過激な主張や商業的なタイトルで目をひこうとする大量の「歴史書」が溢れていることに気づく。その中には、学界では常識となっている基本的な史実さえも誤認しその誤認にさえ気づいていないものも、残念ながら少なくない。本プロジェクトリーダーの北岡伸一主任研究員(東京大学教授)は、プロジェクトのメールマガジン、「東京財団外交史ブックレビュー」の冒頭で、「現代の外交政策や外交世論が、正確な外交史の知識の上に築かれているとは、決して言えないのではないか」と疑念を示している。
本プロジェクトをスタートさせてからこれまでに、若手を代表する才能豊かな評者によって書かれたブックレビューを通して、優れた専門家による毎年数多く刊行される外交史関連の専門書と、政策や実務の最先端で多忙な日々を送る人々との間を、いわば「橋渡し」をするべく成果を果たしてきたと自負している。ここでは2008年の一年間に刊行された良書を、ブックレビューでとりあげたものを中心に数点とりあげることで、研究動向の現状を概観してみたいと思う。また部分的に2007年に刊行されたものも含めることにしたい。ただしここでは、数多くの優れた成果を必ずしも網羅できないことをあらかじめお許し頂きたい。
1.日本外交
日本外交史研究は近年、以前よりも改善された史料公開状況を基礎に、多くの優れた研究書が刊行されてきた。しかしながらそれは同時に、日本外交の全体像を提示することが次第に困難となってきていることも示してもいる。豊かな構想力を持つ著者のみが、そのような試みに成功することになる。以下、戦前と戦後にわけていくつかそのような試みを紹介したい。
戦前期については、千葉功昭和女子大准教授による 『旧外交の形成 ―日本外交 一九〇〇~一九一九』 が刊行された。これは日清戦争後から第一次世界大戦終結までの日本外交の本質を描こうとする試みであり、「自立化する外務省」の制度的発展や日英同盟を基軸とした「多角的同盟・協商網」を通じた日本外交の動きを考究した労作である。とりわけ興味深いのが第?部である。そこでは従来の一般的理解を大きく修正して、「日英同盟」と「日露協商」を「多角的同盟・協商網」として一つに括って、日本の「旧外交」の全体像を描いている。小宮一夫氏の表現を借りるならば、本書では「静かにゆっくりと『旧外交』を習熟していく群像劇」を描いており、また「東アジア国際社会で生き残るため、必死で安定した『秩序』を作ろうと模索する『孤独な』日本の姿」を浮かび上がらせている( 東京財団外交史ブックレビュー )。「未熟さ」もあわせもった日本の「旧外交」が、しかしながら日本を取り囲む大国の狭間で自らの道を模索する姿は、現在の日本にも数多くの示唆を与えるであろう。
さらに戦前の日本外交を考える際の大きな貢献をなしたのが、服部龍二中央大学准教授による 『広田弘毅 ―「悲劇の宰相」の実像』 の刊行である。本書は、「城山三郎氏の小説『落日燃ゆ』によってつくられた」であろう「悲劇の宰相」としての広田弘毅の人物像を、多くの史料を用いて検証し、広田外交が内在的に抱えていた問題点を抽出している。本書はすでに「最近まれに見る評伝」(橋本五郎評『読売新聞』)と称賛され、幅広い読者を獲得することに成功した。すでに著者は幣原喜重郎についての外交評伝を2006年に刊行しており、その旺盛かつ堅実な研究姿勢によってこの分野の指導的立場に立っている。丁寧に史料を読むことで、より正確な戦間期の日本外交の実態を描こうとする作業は、価値あるものである。
戦後期についても斬新な新しい研究をいくつも見た。その中でも特筆すべきが、宮城大蔵政策研究大学院大学助教授(本プロジェクト・サブリーダー)による 『「海洋国家」日本の戦後史』 である。本書の焦点は、戦後日本の対インドネシア政策を軸としてアジア外交を描くことである。しかしそれにとどまってはいない。むしろその特長は、戦後日本外交の本質とその可能性を現代的な問題意識を含めて描いていることであろう。著者は、過度に日本とアジアの結びつきを強調しているわけでも、また日本のアジア政策を経済援助政策に偏って論じているわけでも、あるいは日米同盟を軸としてそれを描いているわけでもない。むしろ、戦後日本外交あるいは戦後国際政治全体の流れを、「脱植民地化から開発へ」と静かに変容させた日本の政治的影響力に着目して、それを冷静に描いている。はたして日本外交に何が可能なのか。読者は本書を読むことで新たな広がりのある戦後日本外交の視座を得ることになるであろう。ただ、はたして「開発」の先には何があるのであろうか。1990年代以後の日本のアジア外交の変容について、もう少し深く著者の主張を読みたかった。なお戦後日本のアジア政策については、田中明彦 『アジアのなかの日本』 ( 佐藤晋評・東京財団外交史ブックレビュー )および保城広至 『アジア地域主義外交の行方: 1952-1966』 ( 宮城大蔵評、同上 )が長く読まれるであろう重要な研究である。異なる角度から論じられたこの三冊をあわせてお読み頂きたい。
2.米国
2009年1月にはアメリカでバラク・オバマ政権が誕生し、2008年は日本でもアメリカ大統領選挙に関する報道と論壇が溢れていた。他方でアメリカ外交史について近年優れた業績がいくつも刊行されており、これらを読むことで今後日本が目指すべき方向が見えてくるのではないか。
まずこの分野の新しい古典となるであろう五百旗頭真編 『日米関係史』 が刊行された。若手と中堅の、それぞれの時代を代表する研究者が集まって、開国からイラク戦争後の現在に至るまでの日米関係を概観している。すでにこの分野では、細谷千博編『日米関係通史』や細谷千博・本間長世編『日米関係史 ―摩擦と協調の140年〔新版〕』などが広く読まれてきた決定版であったが、とりわけ戦後史を中心として本書ではその後の研究成果を盛り込んでおり、新しい数多くの知見を得ることが出来る。また本書の執筆者の何名かは日本を代表する国際政治学者でもあり、それゆえに従来の二国間関係史を越えた国際システムとの連関が描かれていることが、本書の大きな強みとなっている。執筆者の世代や専門に広がりがあるためにやや叙述にばらつきがあるが、現時点での望みうる最良の到達点ともいえるのではないか。
アメリカ外交史関連の専門書としては、佐々木卓也 『アイゼンハワー政権の封じ込め戦略 ―ソ連の脅威、ミサイル・ギャップ論争と東西交流』 が傑出している。アメリカ外交史の分野で指導的立場にある佐々木卓也立教大学教授による本書は、トルーマン政権の封じ込め戦略を扱った前著の続編ともいえるものである。ダレスが論じる、全面的に冷戦に米国が勝利する上での鍵となる「アメリカの自由の魅力」を世界でさらに広げるためにも、アイゼンハワー政権は従来考えられていたよりも柔軟に「封じ込め戦略」を進めていた。「いかにもアメリカらしい楽観的な理想主義が冷戦のイデオロギーを支えていた」( 昇亜美子評・東京財団外交史ブックレビュー )ことを想起することで、冷戦後のアメリカ外交の成功と挫折の双方を理解することができるのではないか。いかなる国も、真っ白なキャンバスの上に新しい絵を描くのではない。つねにさまざまな歴史的アナロジーと国民的記憶の上に、新しい政策をつくっていくのであろう。
3.アジア
アジアについての最も注目すべき成果は、川島真・服部龍二編 『東アジア国際政治史』 である。本書は、「最も生産的な研究者集団による堅固な実証に支えられた通史の巨大プロジェクトの成果」である( 井上寿一評・東京財団外交史ブックレビュー )。他言語でも類書は少なく、これだけの広がりと奥行きを持ってこのような通史を日本語で描くことは画期的である。日本、中国、朝鮮半島、台湾といった北東アジアを軸として、これらの国や地域が複雑な多国間関係を構築する様子を丁寧に描いている。萌芽的試み故に、各章ごとの繋がりや焦点の当て方、全体を貫く問題意識の強さなどいくつかの課題が見られるものの、近現代の東アジア国際政治史の全体を俯瞰することで得られる知見は限りなく大きい。満州事変、日本の植民地支配、アジア太平洋戦争と、現在東アジアが抱える歴史問題の多くについて、膨大な先行研究と史料読解を基礎とした安定的でバランスの良い知識を、われわれは本書を通じて得ることが出来るであろう。
4.政治思想
政治思想の分野では、真壁仁 『徳川後期の学問と政治 ―昌平坂学問所儒者と幕末外交変容』 および松田宏一郎 『江戸の知識から明治の政治へ』 の二冊を、いずれも五百旗頭薫東京大学准教授(本プロジェクト・サブリーダー)がブックレビューにてとりあげている。前者は第30回角川源義賞および第6回徳川賞を受賞し、後者は第30回サントリー学芸賞を受賞している。これだけ重厚な思想史の研究成果が、このようなかたちで広く注目されることは、日本の読書文化の成熟として誇るべきことであろう。いわばこの二人の優れた研究者を筆頭に、日本政治思想史研究はルネッサンスに入ろうとしているのかもしれない。
いずれの著書も、「知識」と「政治」の連鎖について、異なる角度から光を当てている。『徳川後期の学問と政治』においては、現代の外交を考える上でも多くの示唆を与える。徳川後期の日本では、明治・大正期に「近代外交」が確立する以前に、すでに豊穣な外交の基礎がかたちつくられていた。これまで「幕府の正統性を擁護した古色蒼然たる集団という印象がなお強かった」学問所について、他の追随を許さぬ圧倒的な史料読解を基礎として、その「知的中枢から開国に耐え得る外交文化が発酵した」という著者の主張を、評者の五百旗頭氏は「鮮烈な印象を与える」と高く評価している。五百旗頭氏はその ブックレビュー の中で森鴎外の『渋江抽斉』を引いて、「飽くなき研鑽を続けた学者」として、「学問」と「政治」との関係が「ゼロサムな関係であった」渋江と、「幕府日本の政治的想像力の拡大に寄与した」古賀三代を対比させている。そして、「学問と政治の幸福な結びつき」の可能性を語っている。その「結びつき」の本質を理解することは、学問の商業化と軽量化が進んでいく現在の日本においてとりわけ大きな意義を持つのではないか。
同様の問題意識は、『江戸の知識から明治の政治へ』の中でも見ることが出来よう。本書は、「日本と西洋との間で共振した問題群として、統治のための人材のあり方を取り上げることで、思想史と政治史にまたがるインプリケーションをもっている」と評される( 五百旗頭薫評・東京財団外交史ブックレビュー )。他方で本書は、従来の日本での政治思想史研究に疑義を抱いたこともあり、時間的および空間的な広がりをその舞台装置として用いていて、独創的な新しい方法論的試みを提示している。そしてその舞台の上に登場する多くの著名な思想家たちも、やはり従来の一般的な理解とは異なる新鮮な姿を見せている。「日本と西洋」という空間軸、そして「前近代と近代」という時間軸を自由自在に移動して、重要な「問題史」(丸山眞男)にその独創性をもって果敢に取り組む高い意欲を著者は示している。そこに「平成の思想」の期待を語るのは、妥当なことであろう。
おわりに
2008年8月に日本を離れ現在私はアメリカで在外研究を行っている立場上、これを執筆する際にまわりにここでとりあげた著書の数々を並べて、その内容を確認することが出来なかった。またその後年末にかけて刊行された数多くの出会うべき良書にも触れていない。それ以上に深刻なのは、私自身の視野の狭さ、能力の欠如、理解力の限界であった。とはいえ、それぞれの専門に近い評者による「東京財団外交史ブックレビュー」の数々の文章が、知的武装をする上でのありがたい武器となった。優れた映画の作品が、それを支える膨大な数のスタッフを必要とするように、健全な「対外政策」を支えるべき日本にいても膨大な数の専門家、およびその研究成果が必要となるであろう。膨大な年月をかけて完成させた誇るべき数々の新しい研究成果を、野ざらしにするべきではあるまい。
北岡伸一教授はその著書『国連の政治力学』において、外交を「知的格闘技」と論じ、「知的理論武装が重要だ」と述べている。民主主義国においては、幅広い裾野から知識という栄養分を抽出し、優れた「対外政策」を支える土壌としてそれを活用していかなければならない。かつて高坂正堯教授は、「外交世論の不毛」を論じ「対外政策の不在」を懸念した。今の日本ではどれだけ「外交世論」が成熟し、またどれだけ「対外政策」が確立したであろうか。本ブックレビューが引き続き、優れた多くの良書を紹介していくことで、そのような土壌がつくられる一助となれば何よりも嬉しい。最後に、本ブックレビューをお読み頂いている読者の方々、その知的空間を提供して頂いている東京財団、そして丁寧なブックレビューを書いて頂いているプロジェクトメンバーの専門家の方々に、感謝申し上げたい。
(ほそや ゆういち)
0%

INQUIRIES
お問合せ
取材のお申込みやお問合せは
こちらのフォームより送信してください。











