評者:細谷雄一(慶應義塾大学法学部准教授)
本書の概要
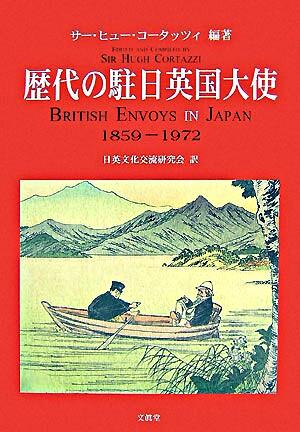 本書は、1859年から1972年までの期間を対象に、歴代の駐日英国大使(1906年に公使館が大使館に昇格する以前は公使)の評伝を集めた論文集である。
本書は、1859年から1972年までの期間を対象に、歴代の駐日英国大使(1906年に公使館が大使館に昇格する以前は公使)の評伝を集めた論文集である。
本書の目次は、以下の通りである。
まえがき サー・ヒュー・コータッツィ
第I部 初期の先駆者たち
序文 サー・ヒュー・コータッツィ
第1章 サー・ラザフォード・オルコック /サー・ヒュー・コータッツィ
第2章 エドワード・セントジョン・ニール /サー・ヒュー・コータッツィ
第3章 オルコック、日本へ復帰する /サー・ヒュー・コータッツィ
第4章 サー・ハリー・パークス /サー・ヒュー・コータッツィ
第5章 サー・フランシス・プランケット /サー・ヒュー・コータッツィ
第6章 ヒュー・フレイザー /サー・ヒュー・コータッツィ
第7章 パワー・ヘンリー・ル・プア・トレンチ /サー・ヒュー・コータッツィ
第8章 サー・アーネスト・サトウ /イアン・ラックストン
第II部 同盟から疎遠化まで
序文 イアン・ニッシュ /イアン・ニッシュ
第9章 サー・クロード・マクドナルド /イアン・ニッシュ
第10章 サー・ウィリアム・カニンガム・グリーン /ピーター・ロウ
第11章 サー・チャールズ・エリオット /デニス・スミス
第12章 サー・ジョン・ティリー /後藤春美
第13章 サー・フランシス・リンドリー /イアン・ニッシュ
第14章 サー・ロバート・クライブ /アントニー・ベスト
第15章 サー・ロバート・クレイギー /アントニー・ベスト
第III部 戦後の時代
序文 ピーター・ロウ
第16章 サー・アルヴァリ・ギャスコイン /ピーター・ロウ
第17章 サー・エスラー・デニング /ロジャー・バックリー
第18章 サー・ダニエル・ラッセルズ /サー・ヒュー・コータッツィ
第19章 サー・オスカー・モーランド /サー・ジョン・ホワイトヘッド
第20章 サー・フランシス・ランドール /サー・ヒュー・コータッツィ
第21章 サー・ジョン・ピルチャー /サー・ヒュー・コータッツィ
付録I 英国艦隊の鹿児島砲撃 サー・L・キューパー提督とニール中佐 /サー・ヒュー・コータッツィ
付録II 陸海軍の下関作戦 /サー・ヒュー・コータッツィ
今年2008年は、日英修好通商条約締結から150周年にあたる。この条約締結の翌年、1859年に駐日英国公使館が設置され、サー・ラザフォード・オルコックが横浜に到着し初代駐日公使として着任したときから、本書の第1章は始まる。1972年で本書を閉じているのは、編者のコータッツィによれば、「国立公文書館によって施行されている三〇年規制によってまだ公開できていないので、我々はこの概説を一九七二年で故意に打ち切った」(まえがき)からである。言い換えるならば、本書の対照する時期に関しては、いずれの章も、豊富な一次史料に基づいた信頼できる研究成果といえる。
ここ十年ほどで、日英関係史は実に豊かな研究成果を生み出してきた。日本に関係する二国間関係で、これほどまで充実した研究成果が得られた領域は、日米関係以外には見られない。2000年から2001年にかけて、『日英交流史1600-2000』(東京大学出版会)として、細谷千博、イアン・ニッシュ両教授の監修によって、全4巻の広範な論文集が完結した。また邦訳された論文集として、サー・ヒュー・コータッツィ/ゴードン・ダニエルズ編『英国と日本 架橋の人々』(思文閣出版、1998年)とイアン・ニッシュ編『英国と日本 日英交流人物列伝』(博文館新社、2002年)の二冊が刊行されている。これらを読むことで、多角的に日英関係を学ぶことが出来る。さらにその上で、本書の刊行により、日本に駐在した歴代の英国大使の人物像が浮かび上がってくるだろう。ちなみに、本書の姉妹版として、Ian Nish (ed.), Japanese Envoys in Britain 1862-1964 (Global Oriental, 2007)が刊行されており、いずれ翻訳も刊行されるであろう。
本書は、3部構成となっているが、それぞれ大きく異なる日英関係の姿が浮かび上がる。第I部は、編者のサー・ヒュー・コータッツィによる章が中心を占めており、幕末から日英同盟締結前の時期までが対象となっている。この時期の日英関係は、双方がお互いを理解することに大きな力が割かれており、文明間の親睦の時期でもあった。同時に条約改正が主たる外交課題となっており、日本は西洋列強と対等な地位を求めていった。第II部は、日英同盟成立から太平洋戦争終結までが対象となっており、日英同盟の終焉、日英間の対立の深刻化、そして宥和政策と戦争回避の努力が日英関係の争点となっている。イアン・ニッシュ、ピーター・ロウ、後藤春美、アントニー・ベストなどの、戦間期日英関係の専門家が、高い水準の論文を仕上げている。第III部は戦後期を対象としており、占領と講和の時期を扱う前半部分と、日英貿易と日英交流の拡大を扱う後半部分に分かれている。占領と講和の時期には、とりわけ戦時中の捕虜問題を原因とするイギリス国内の対日不信、嫌悪感が浮き彫りになっている。それがユーモア溢れるピルチャー大使の頃には、イギリス王室と日本の皇室の間で友好的な関係が築かれて、次第に日英交流が広がっていく様子が伺える。
本書に登場する英国大使を概観すると、彼らがイギリス外務省の中核的な外交官ではないことが分かる。それは英軍出身の駐在武官を経験した外交官であったり、領事部出身の日本語を操れる知日派であったりする。それはイギリス外務省にとって、日本という国が必ずしも最重要の関係国でないことを明らかにしている。むしろ理解するためには特殊な語学と能力を必要とする相手であるという認識に基づくものであろう。ただし、彼らの日本外交を見る目は冷静で、曇りのない場合が多い。例えば戦後のランドール大使は、日本人が「軍国主義者でも平和主義者でもなく、世界一の実用主義者である」と評している。また次のように述べている。「日本は友邦国に忠実であった。もし彼らにわれわれを友邦国として受け入れるように説得し、そして高いレベルでの人的繋りが拡大拡充できれば、われわれの国力以上の影響を日本に及ぼすことが出来るだろう。」
本書の難点は、日英交流、日英友好という色彩がやや色濃いために、客観的な学術的記述というよりも、日英交流に貢献したイギリス人を評価するという性格が強いことだ。従って戦間期の日本の中国侵略に関する記述や、戦後の捕虜問題をめぐる記述など、きわめて控えめな描き方となっており、厳しい評価はあまり見られない。また日本語としてやや読みにくい箇所も散見される。とはいえ、広範な史料に基づいて可能な限り冷静に彼らの行動を記録にとどめようとする本書の努力には、高い評価をすべきであろう。
0%

INQUIRIES
お問合せ
取材のお申込みやお問合せは
こちらのフォームより送信してください。











