評者:武田知己(大東文化大学法学部政治学科教授)
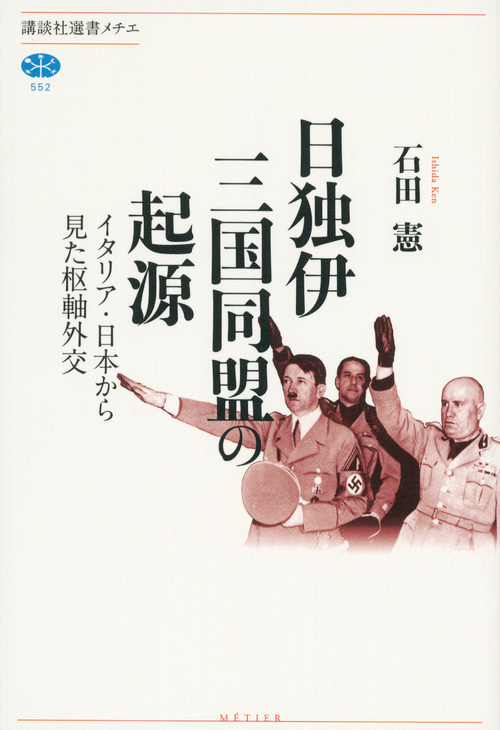
本書は、著者の専門であるイタリア史から大きく逸脱するものではないものの、当時の国際関係史を描きつつ、日本がその一翼を担った枢軸形成過程そのものに対して示唆するところが少なくない。著者の作品の中でも最も日本外交への言及が多いことは、本書の第一の特徴である。また、「おわりに」でのべられているように、著者の結論は、枢軸三国の関係が「空虚」なのは、「三国それぞれの思惑が異なっただけでなく相互不信を深めつつ、排反する利益追求へと走った」(199頁。以下、ページ数のみを記す)という、リアリズム的観点からすれば矛盾としか言えない性質をもつからであるが、その様相を主として日伊両国の外務省に視点を据えつつ論じた点が本書のもう一つの特徴となっている。著者には「外務省という同様の組織に着目することで、共通点の中から相違点を抽出し、類似した過程の中から固有の構造を明らかに」するという企図があるが(199頁)、国益の交換をなりわいとするはずの外交官・外務省が、なぜ枢軸形成に賛同したのだろうか。こうした視点をも有する本書は、広い意味での「外交政策研究」(Foreign Policy Analysis.FPA)の側面をも有するものといえる。
はじめに
第一章 日伊外務省と反共主義的国際観――対外政策のイデオロギー的背景
一 一九三〇年代の日伊外務省
二 相違点としてのファシズム
三 結節点としての反共主義
四 善悪二元論と友敵関係
五 「空虚なる同盟」の始まり
第二章 同床異夢の枢軸形成――現実政治の蹉跌
一 日独伊枢軸の位置づけ
二 東アジアの危機と枢軸の世界化
三 新たな膨張をめぐるイメージ
第三章 同盟抑制の機能不全――対外政策決定過程の構造的崩壊
一 不従順な体制派
二 追随する抑制者
三 崩壊する対外政策決定の組織構造
著者によれば、第一章では、日伊の外務省が枢軸形成に批判的な伝統的勢力を含む「多様な行動主体」を擁しながらも、「なぜ世界大の枢軸へと向かったのか」を組織内在的に解明することが目指される。第二章では、にもかかわらず形成された日伊独枢軸三国は、枢軸形成によって利害関係を一致させることがなかったことを、1930年代後半の文脈で位置づけることが目指される。そして、最後の第三章では、なぜ外務省が「枢軸の世界化」を抑制できなかったのかを説明するのである(13-14頁)。
それぞれの章の結論を先取りすれば、著者が「反共主義(的国際観)」(13頁)と呼ぶイデオロギーが外務省の浸透していったことが、外務省が枢軸形成に積極的にかかわって行った理由とされる(第一章)。また、そうしたイデオロギーの浸透による枢軸相互のイメージが現実の利害関係をある意味で無視した枢軸結成の決定的な理由の一つとなった(第二章)。さらに、こうしたイデオロギーとイメージを持つ外交指導者が、組織的な対外政策決定構造への影響力を低下させる外務省のトップに座ることで、ついに外務省が枢軸形成の抑止機能を果たすことがなかった(第三章)ということになる。
こうした明快な筋書の一方で、本書には多様な分析概念や視点が混在している。それは著者の近著の一つである『ファシストの戦争』(千倉書房、2011年)の特徴でもあるように思われる。しかし、それ故にというべきか、あるいは、著者がいうように、イタリア史あるいは1930年代の欧州に関する知識が(評者を含めて)日本ではあまりにも不足しているということも関係しているのか、その叙述は時折少なからず分析的であり、風通しがやや悪いように見える部分も少なくない。
以下では、まず、著者が積極的に提示している分析概念や理論モデルをなるべく平易に整理しながら、各章の構成に従って概要を紹介してみたい。
まず、第一章で着目されるのは、1937年11月のイタリアの防共協定参加に象徴される、日伊提携の鍵概念となった「反共主義(的国際観)」と言うイデオロギーの果たした機能である。
その際、著者は、そもそも、日本とイタリア両国の外務省は、1936年までの過程で、積極的に接近する意図を持つことはなかったことから説き起こす。ただし、両国はともに1932年に第一の転機を迎えていたことも事実である。 同年、日本は、五・一五事件により、政党という雑音がない対外政策運営が可能となり、1933年9月には若い広田弘毅が外相に、また重光葵が外務次官となって、二・二六事件まで継続して外交運営に関わった。対するイタリアでは、1932年にムッソリーニがディーノ・グランディにかわり外相を兼任(フルヴィオ・スーヴィッチ次官)となり、同様に比較的長きにわたって継続した強い外交運営が可能となった。その間、日本は中国への侵略を継続し、イタリアはエチオピアに侵攻を開始するのだが、こうした時、36年、第二の転機が両国に訪れた。日本ではこの年に二・二六事件が起き、軍部外交が台頭する。他方、イタリアでは、ムッソリーニの女婿であるチャーノが外相になり、外務省の個人支配を強め、伝統的外交官を排除しはじめることになる。しかし、伝統的な外交官たちは、両国ともに国際連盟へも冷静に対処し、対英協調も主張していたが、日伊両国は、中国市場、エチオピア問題などをめぐって、相互に敵対的でさえあった。にもかかわらず、1936年11月から37年11月までの間に、日伊接近(日独伊三国防共協定締結)がなされたのは「反共主義」という結束点ゆえである(19-22頁)。
しかし、著者によれば、反共主義は「反コミンテルン・反ソ連を意味するだけでなく、国際連盟、中国、スペイン、イギリスといった異なる対象をめぐる対抗イデオロギーとして広範に利用された」ものであるとされる。言い換えれば、「共産主義という体系性を有したイデオロギーに比べ、敵を指定する方便として利用され、可変的で融通無碍なもの」であり、「シンボル」として利用され、それは「イデオロギーとしての内実が問題にされるというより、国際観などのあいまいな概念に基づくことで、重宝に利用された」(18-19頁)ものであるとされる。
「政務型」と「交渉型」
次に第一章で著者が提示する概念は外交官の分類に関わるものである。著者によれば両国の学界では「親英(米)派」対「親枢軸派」という外交官の分類は共通しているという。しかしながら、実際の対外政策では「外務省内の「親英派」が実質的な枢軸接近政策を担っていた場合も多い」。この点も両国の実態に共通しているとされる(23頁)。
しかし、個人の外交官が「固定的にその信念を奉じて、一貫した政策を遂行した」と誤解される。そのようなことは現実にはあまりないし、逆に主要な外交官はみな「親英派」ということにもなってしまう。そこで著者が提起するのが、「政務型」と「交渉型」という分類である(23頁)。
「政務型」は「自らを政策決定に直接関わる立場にあると位置づけ、国内の論理を対外政策認識に強く反映させる」。「それ故、彼らは本国を中心とする政治的判断に左右されやすくなる」。対する「交渉型」は「現場で直接交渉に携わる発想法から、ここの案件を現地との関係性に鑑みて処理する傾向にある。このため彼らは、本省とことなる視点で問題をとらえることにより、国内的論理への歯止めとなる可能性があった反面、権力中枢の対外政策決定に対する影響力を喪失する危険性も高かった」(以上、25頁)。こうした分類により、「固定化された派閥的解釈による静態的な分類」よりも、「国内的論理と国際的文脈の矛盾や相克をも考慮した理解」が可能になり、「ダイナミックな変動に対する有効な分析方法が確立できる」とされる(23頁)。また、両者の間には移動(著者の言葉を用いれば「移項」25頁)が、構造的原因、主体的原因の双方から起こりうるとされる。
著者なりの人物の具体的な分類は、本書25頁に掲げられているので参考にされたい。ここでは、この四象限を包括して各タイプに共有されるのが、反共主義とされていることを確認するにとどめたい。
反共主義の三種類
さて、著者によれば、日伊両国において、反共主義には、①対外政策の阻害要因として規定する機能、②敵としての認識を策定する基準としての機能、③仲間を作るための名目としての機能の三機能が付与されたとする(35頁)。こうした機能はもちろん「国際的反共主義」(36頁)の文脈を超えるものとなり、①が国際連盟=第一次大戦後の秩序批判に(38頁)、②が武力介入=エチオピア、中国への膨張主義の正当化の根拠に(42頁)、③が反共的国際秩序の形成原理=西欧を抱合した新秩序形成の原理に(49頁)、それぞれ利用されることになる。
注意すべきは、こうした機能が、すぐさま破壊的な軍事衝突を正当化したわけではないことであるが、そうした過程で、外交官自身が「伝統的反共主義の肥大化により生じた包括的な反共イデオロギーを指導者層の最大公約数として受容」するようになり、やがて外交は「「友敵」関係へと収斂する危険」をはらみはじめる(54ー55頁)。著者によれば、反共主義は、「(1936年から37年の一年間で)日伊両国にとって反ソや反連盟という文脈のみならず、中国もしくはスペインさらにはイギリスを取り込むという文脈を超えて、「親枢軸」「反西欧」という新たな「友敵」関係を形成し始めた」のである(63頁)。日本ではたとえば、佐藤尚武外相などは共産主義は内政問題とするが、彼でさえ「国内的論理」を忖度する必要に迫られはじめる(64頁)。
こうして、「空虚なる同盟」は始動するのである。
以上のようにイデオロギーに着目した第一章に対し、第二章では、「(日独伊枢軸の)期待された成果を達成した」事例と言うより、「むしろ日独伊枢軸のゆがんだ結束を象徴する事例」(79頁)という性格を持つ、ブリュッセル九カ国会議、三国防共協定締結、イタリアの満州国承認、日中和平調停工作、イタリアの連盟脱退の御事例を取り上げ、三国の現実の利害関係がいかに相反するものであったかを実証してゆく。以下にそれぞれの例の分析結果を掲げてみる。
ブリュッセル会議(80頁以下)
・ドイツは親中的であり、日中戦争では日本を非難していた。日本は日中戦争は共産主義勢力に対する武力発動であるとして、日独防共協定に基づく委員会の設置を提唱するが、ドイツは拒否する。
・ドイツの軍人ファンケルハウゼンはイタリアを排除して蒋介石の軍事顧問団長に就任
・こうした行為に日本はトラウトマン大使の召還さえ要求した。
・こうした中開催されたブリュッセル会議にイタリアは出席して日本の不興を買う。ドイツは出席すれば親日的態度を取らざるを得ないという理由で欠席を決めた。
日独伊三国防共協定(84頁以下)
・イタリアと日本は当時人種問題で対立していた。
・イタリアは三国防共協定が反英的にならないように注意していた。日本も中国との防共、イギリスとの防共を重視していた。しかし、日本のそれは不可能であった。広田外相など外交官は「内向きの現実主義」(88頁)を取っていた。
・日中戦争後日本への接近を拒否していたドイツでは、極東政策をめぐり、外務省とリッペントロップの間で激しい権力闘争が展開されていた。
イタリアの満州国承認(94頁以下)
・イタリア1934ー35年に空軍使節を中国に派遣し、ドイツと競合していた。
・ドイツは満州国承認を渋り続ける(1938年2月20日の承認を宣言)。日本は逆にイタリアのエチオピア征服の承認を渋る。エチオピアの繊維製品の9割を日本が占めていたため。
日中和平調停工作(99頁以下)
・ムッソリーニは独伊の調停を申し出る。トラウトマン工作が始動するが、日本は採取的に翻意する。
・ドイツのディルクセン駐日大使は一貫してイタリアを軽視していた。
イタリアの国際連盟脱退(103頁以下)
・イタリアは、国際連盟を敵対視(1937年11月脱退)。ドイツは日本の行動と防共協定が同一視されることを警戒するが、ここでイタリアと運命をともにする。
三つのイメージ
以上のように、防共協定締結時下においてさえ、三国間には利害相反の例が極めて多かったのである。にもかかわらず、1939年5月の独伊同盟、40年9月の三国同盟と、「枢軸結合」(113頁)は確実に進んでいくのはなぜだったのか。著者によれば、それは各国の国際情勢の認識方法が似ていたからである。
著者が提示する認識方法には三つのパターンがあった。カウンターイメージ、パラレルイメージ、ミラーイメージの三つである。
カウンターイメージは「自分たちの反対する価値体系と対置させた疑似対抗イデオロギーが投影される」。言い換えれば、ヴェルサイユ体制、連盟体制、共産主義批判がこうしたイメージから導き出されることになる。
パラレルイメージは「他国が成功した膨張の事例や他国の国際環境に関する思い込みを、自分たちの打算に基づき並行して援用する」。それは枢軸間での同質性のイメージを増長させるよりも、むしろ「孤立にともなう疑心暗鬼と相互不信の悪循環」が生まれる原因となる。
ミラーイメージは「自分たちの姿を相手にも映し出して、同様の行動様式を想定、期待するもの」である。これは特に「イギリス」に対する自己投影となり、イギリスが自国の政策を許容することを一方的に期待する背景となった。
著者によれば、こうしたイメージには体系性はなく、あくまでイメージにとどまるが、それゆえに強固に作用したのであった(以上、114頁)。
最後の第三章では、著者は、本書の分析視角にも関わる対外政策決定構造に改めて踏み込んでいるが、そもそも、日独伊三国の外務省には「理性的で、西欧との協調を追求したという説明」は成り立たないとし、むしろ外務省を中心としつつ「どのように対外政策が作り出されていたのか」を論じる必要があるというのが著者の立場であった(7-9頁)。そのうえで、日独伊の対外政策構造を、著者は以下のように整理している。
ナチ・ドイツ
多頭制ではあるが、ヒットラーを頂点とするヒエラルキーは確固としている。権限の縄張り争いが生じても、その構造自体が自滅することはなかった。
ファシスト・イタリア
ムッソリーニが、独立性の高い軍、外務省、党の調整者となっている。
日本
陸軍、海軍、外務省などの各機関が「非妥協的抗争」を繰り返していたが、昭和天皇は「御輿」であり、宮中グループがクッションとなっていた。しかし、各機関の頂点が不明瞭な円錐台構造であった。
こうした三国の対外政策決定構造には相違もあるが、類似点も少なくなかった。それに対し、三国の共通の敵国となってゆくイギリスは、政府・外務省・議会・世論の綱引きにより政策決定がなされるという点で他の三国と大いに異なっていた。しかもイギリスでは外務省の独立性・権威が高かったとされる(9-10頁)。なお、この点については本書10-11頁の図を参照されたい。
こうした整理を背景に、著者は日伊両国の対英関係に着目し、第一に、現地の責任者である駐英大使、第二に、首相・外相・次官ら、第三に組織の下僚たちにそれぞれ着目し、外務省が枢軸形成の抑止機能を果たせなかった様相と理由を考察してゆく(142頁)。
吉田とグランディ
1930年代後半の決定的な瞬間において、ロンドンで出先の責任者となったのは、日本は吉田茂、イタリアはディーノ・グランディであった。彼らに共通していたのは、枢軸結合が強まっていた当時、イギリス大使と言うポストは一種の「左遷」のポスト(144頁)だったという事実である。しかし、たたき上げのファシストであったグランディと宮中政治家と言ってよい側面を持つ吉田とでは出自も異なる。また、グランディは、同時代のソ連の大使・Iマイスキーも高く評価する辣腕の交渉家であった(149頁)。やはり同時代の駐英大使であったドイツのリッペントロップはグランディを毛嫌いしているが(同上)、イギリスは吉田を「不十分な交渉者」と呼ぶほど評価が低かった。それはイギリスのリッペントロップ評価とも共通するものであった(152頁)。
しかし、それ以上に対照的だったのは、著者によれば、「吉田が象徴的な「友好」を力説し、「親日的」な相手による「善意」の接近を待つ姿勢に終始した」のに対し、グランディは「具体的な交渉の可能性を掘り起し、妨げとなる「反伊的」人物は相手国の外相であっても「悪意」をもって排除するという攻撃的姿勢」を続けたことであった(155頁)。いわば、吉田は交渉と言う名に値しない受動的態度に終始し、グランディは交渉と言うよりも攻撃と言うべき能動的態度を示したのである。
振り子外交論の類似と相違
もっとも、吉田とグランディの対英交渉の要点は、イギリスを反共戦線にとりこむことであり、それにより自国の膨張政策や新秩序外交を容認させることであった。しかし、そのための二人の交渉態度には、以上のような大きな違いがあった。
著者によれば、第一に、この二人の交渉家が認識していた国内政治の図式が大きな影響を与えていたという。吉田は、「急進派」と「穏健派」(155-56頁)という比喩を用い、イギリスが友好的な態度を示せば、日本国内の穏健派を勇気づけ、「振り子は軍国主義的政策から国際主義的政策へ揺り戻される」として吉田はイギリスを説得しようとした(155-156頁)。対するグランディは「イギリス派」と「ドイツ派」(156ー57頁)という一見吉田ともよく似た図式に依拠していたというが、ファシスト的な情勢認識によれば、これはイタリアがイギリスかドイツかを積極的に選び取れることを意味した。その意味でこの図式は「能動的」だというのが著者の見方である。
国内における割拠と競争
また、第二の理由は、両者が国内における割拠と競争に否応なく影響されたことが挙げられる。吉田が置かれていたのは、国内における政府内・外務省内での激しい割拠と競争の実態であった。そこでは統一見解が出せずに、総花的であいまいな要求に終始した。状況を打破するには相手からの譲歩を待つしかなかったとされる(158頁)。対するグランディは、ファシストの領袖として、ムッソリーニが最終調停者であるイタリアの政策決定過程の一翼を担っていただけでなく、ムッソリーニを「君」づけできる地位にあったグランディは、対英接近と同時に枢軸接近へといわゆる「二股」をかけており、いざと言うときの「保身」をも怠らなかったとされる(159-60頁)。
こうした混乱の中で日伊両国は政府あるいは組織レベルでも政策の調整機能を喪失してゆく。たとえば、1936年から翌37年にかけての防共協定交渉と対英関係をめぐる有田八郎外相と東郷茂徳の対立は激しかった。しかし、有田が枢軸への接近に邁進したわけではない。有田が防共協定強化問題に抵抗したのも事実であり(その際有田がこだわった抵抗の論理は「反共主義」であった。173-75頁)、ナチスドイツはイタリアのパスティアニーに同様、有田を「二枚舌」として信用しなかった。にもかかわらず、有田が対英接近を主導したわけでもなかったのであり、その意味で、有田は「小広田」であり、パスティアニーには「小チャーノ」であった(175-76頁)。
個人と組織・構造
こうして30年代を通じて同様の論理や動向が再生産される理由を、個人の資質にもとめるのは不十分である、というのが著者の第三章での結論である。こうした枢軸形成は、外務省を迂回して進められるようになった。また、出先と本国、政府内、組織内での細かな調整機能も発揮されなかった。こうした機能不全はイギリスと対照的であったのである(181頁)。
第一に、著者の「反共主義(的国際観)」についてである。著者の「反共主義」認識は、少なくとも従来の日本外交史研究では明示的には議論されてこなかった点を明らかにしている。すなわち、30年代における反共主義は、反連盟、平和の名の下での武力介入、新秩序外交といった諸特徴に援用される概念であり、30年代を他の時代から区別する独特の要素だったのと言うことである。たしかに、日本の例を取り上げても、そうした際に共産主義の脅威が語られ続けたことは事実であり、そのことを体系的に指摘したことは高く評価したい。それは著者の描く時代に防共協定が強化されるという課題がいつの間にか軍事同盟にすり替わってゆくという謎を解明する一つの視点に他ならないともいえる。
しかし、そのことはすぐさま反共主義が「持てる国」「持たざる国」あるいは「現状維持」「現状打破」という概念よりもより普遍的に利用されたのかどうかという疑問を生じさせる。たとえば、イタリアでは、「反共主義」と「現状打破」論とが具体的な言説分析においてどのような関係にあるのかを改めて聞いてみたい。
第二に、第二章で、三国の関係がいかに空虚であるかを、特にイタリアの視点を加味して明らかにした点を高く評価したい。だが、第二章で論じられている三つのイメージと第一章で論じられている反共主義との関係が今一つすっきりと整理できない。また、政務型・交渉型と言う外交官の分類との関係もやや複雑である。
第三は、それとも関係してくるが、外交政策研究としての新機軸を打ち出そうとしたことである。特に日独伊英四か国の対外政策決定構造の比較は評者には大いに参考になった。このような指摘は従来必ずしも多くないと思われるので、もう少し詳細な分析を独立論文として著者にお願いしたい。逆に、著者が「静態的」であるとして批判する日本外務省の「親英米派」「アジア派」などの派閥論であるが、この派閥論は実は1930年代に幾度かおこなわれた当時の「革新政治」の動向を追っていたジャーナリズムによる分類である。また、そのグルーピングは30年代を通じて変化していった。その意味でこの派閥論は学術的な分析概念というよりは、当時まさにダイナミックに動いてゆく外交政策主体の変容を追うことのできるものであり、そうした議論を踏まえたさらなる精緻化が必要だと思われる。
以上が本書の評価であるが、評者の指摘は逆に「それこそ今後の日本外交史の課題ではないか」とすぐさま著者に切り替えされるはずの指摘である。我々日本外交史の研究者こそ、こうした指摘に触発されて新しい研究展開を試みねばなるまい。著者の鋭い分析を大胆に平易に言い直したため、ニュアンスがそぎ落とされてしまっていることを恐れるが、本書が30年代の日本外交史研究にも大いなる刺激を与えてくれたことを強調して結びとしたい。
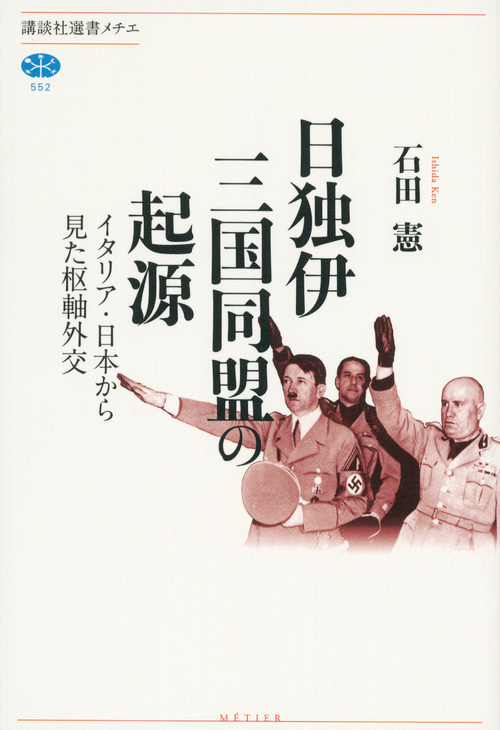
はじめに
著者は、近年すぐれた国際関係史の単著を公刊し続けている日本人研究者の一人である。本書『日独伊三国同盟の起源 イタリア・日本から見た枢軸外交』は、2000年から2008年までに断続的に書かれた三つの論文を基礎とする三章からなる著者の最新作で、全体として、1930年代後半からときおこし、著者が「空虚な」あるいは「ゆがんだ」と称する日独伊三国同盟締結過程、言い換えれば、枢軸の形成過程を描くものである。本書は、著者の専門であるイタリア史から大きく逸脱するものではないものの、当時の国際関係史を描きつつ、日本がその一翼を担った枢軸形成過程そのものに対して示唆するところが少なくない。著者の作品の中でも最も日本外交への言及が多いことは、本書の第一の特徴である。また、「おわりに」でのべられているように、著者の結論は、枢軸三国の関係が「空虚」なのは、「三国それぞれの思惑が異なっただけでなく相互不信を深めつつ、排反する利益追求へと走った」(199頁。以下、ページ数のみを記す)という、リアリズム的観点からすれば矛盾としか言えない性質をもつからであるが、その様相を主として日伊両国の外務省に視点を据えつつ論じた点が本書のもう一つの特徴となっている。著者には「外務省という同様の組織に着目することで、共通点の中から相違点を抽出し、類似した過程の中から固有の構造を明らかに」するという企図があるが(199頁)、国益の交換をなりわいとするはずの外交官・外務省が、なぜ枢軸形成に賛同したのだろうか。こうした視点をも有する本書は、広い意味での「外交政策研究」(Foreign Policy Analysis.FPA)の側面をも有するものといえる。
一 本書の構成・概要
本書の各章の構成は以下のようになっている。はじめに
第一章 日伊外務省と反共主義的国際観――対外政策のイデオロギー的背景
一 一九三〇年代の日伊外務省
二 相違点としてのファシズム
三 結節点としての反共主義
四 善悪二元論と友敵関係
五 「空虚なる同盟」の始まり
第二章 同床異夢の枢軸形成――現実政治の蹉跌
一 日独伊枢軸の位置づけ
二 東アジアの危機と枢軸の世界化
三 新たな膨張をめぐるイメージ
第三章 同盟抑制の機能不全――対外政策決定過程の構造的崩壊
一 不従順な体制派
二 追随する抑制者
三 崩壊する対外政策決定の組織構造
著者によれば、第一章では、日伊の外務省が枢軸形成に批判的な伝統的勢力を含む「多様な行動主体」を擁しながらも、「なぜ世界大の枢軸へと向かったのか」を組織内在的に解明することが目指される。第二章では、にもかかわらず形成された日伊独枢軸三国は、枢軸形成によって利害関係を一致させることがなかったことを、1930年代後半の文脈で位置づけることが目指される。そして、最後の第三章では、なぜ外務省が「枢軸の世界化」を抑制できなかったのかを説明するのである(13-14頁)。
それぞれの章の結論を先取りすれば、著者が「反共主義(的国際観)」(13頁)と呼ぶイデオロギーが外務省の浸透していったことが、外務省が枢軸形成に積極的にかかわって行った理由とされる(第一章)。また、そうしたイデオロギーの浸透による枢軸相互のイメージが現実の利害関係をある意味で無視した枢軸結成の決定的な理由の一つとなった(第二章)。さらに、こうしたイデオロギーとイメージを持つ外交指導者が、組織的な対外政策決定構造への影響力を低下させる外務省のトップに座ることで、ついに外務省が枢軸形成の抑止機能を果たすことがなかった(第三章)ということになる。
こうした明快な筋書の一方で、本書には多様な分析概念や視点が混在している。それは著者の近著の一つである『ファシストの戦争』(千倉書房、2011年)の特徴でもあるように思われる。しかし、それ故にというべきか、あるいは、著者がいうように、イタリア史あるいは1930年代の欧州に関する知識が(評者を含めて)日本ではあまりにも不足しているということも関係しているのか、その叙述は時折少なからず分析的であり、風通しがやや悪いように見える部分も少なくない。
以下では、まず、著者が積極的に提示している分析概念や理論モデルをなるべく平易に整理しながら、各章の構成に従って概要を紹介してみたい。
二 反共主義の広がりと外交官分類の新機軸
反共主義(的国際観)まず、第一章で着目されるのは、1937年11月のイタリアの防共協定参加に象徴される、日伊提携の鍵概念となった「反共主義(的国際観)」と言うイデオロギーの果たした機能である。
その際、著者は、そもそも、日本とイタリア両国の外務省は、1936年までの過程で、積極的に接近する意図を持つことはなかったことから説き起こす。ただし、両国はともに1932年に第一の転機を迎えていたことも事実である。 同年、日本は、五・一五事件により、政党という雑音がない対外政策運営が可能となり、1933年9月には若い広田弘毅が外相に、また重光葵が外務次官となって、二・二六事件まで継続して外交運営に関わった。対するイタリアでは、1932年にムッソリーニがディーノ・グランディにかわり外相を兼任(フルヴィオ・スーヴィッチ次官)となり、同様に比較的長きにわたって継続した強い外交運営が可能となった。その間、日本は中国への侵略を継続し、イタリアはエチオピアに侵攻を開始するのだが、こうした時、36年、第二の転機が両国に訪れた。日本ではこの年に二・二六事件が起き、軍部外交が台頭する。他方、イタリアでは、ムッソリーニの女婿であるチャーノが外相になり、外務省の個人支配を強め、伝統的外交官を排除しはじめることになる。しかし、伝統的な外交官たちは、両国ともに国際連盟へも冷静に対処し、対英協調も主張していたが、日伊両国は、中国市場、エチオピア問題などをめぐって、相互に敵対的でさえあった。にもかかわらず、1936年11月から37年11月までの間に、日伊接近(日独伊三国防共協定締結)がなされたのは「反共主義」という結束点ゆえである(19-22頁)。
しかし、著者によれば、反共主義は「反コミンテルン・反ソ連を意味するだけでなく、国際連盟、中国、スペイン、イギリスといった異なる対象をめぐる対抗イデオロギーとして広範に利用された」ものであるとされる。言い換えれば、「共産主義という体系性を有したイデオロギーに比べ、敵を指定する方便として利用され、可変的で融通無碍なもの」であり、「シンボル」として利用され、それは「イデオロギーとしての内実が問題にされるというより、国際観などのあいまいな概念に基づくことで、重宝に利用された」(18-19頁)ものであるとされる。
「政務型」と「交渉型」
次に第一章で著者が提示する概念は外交官の分類に関わるものである。著者によれば両国の学界では「親英(米)派」対「親枢軸派」という外交官の分類は共通しているという。しかしながら、実際の対外政策では「外務省内の「親英派」が実質的な枢軸接近政策を担っていた場合も多い」。この点も両国の実態に共通しているとされる(23頁)。
しかし、個人の外交官が「固定的にその信念を奉じて、一貫した政策を遂行した」と誤解される。そのようなことは現実にはあまりないし、逆に主要な外交官はみな「親英派」ということにもなってしまう。そこで著者が提起するのが、「政務型」と「交渉型」という分類である(23頁)。
「政務型」は「自らを政策決定に直接関わる立場にあると位置づけ、国内の論理を対外政策認識に強く反映させる」。「それ故、彼らは本国を中心とする政治的判断に左右されやすくなる」。対する「交渉型」は「現場で直接交渉に携わる発想法から、ここの案件を現地との関係性に鑑みて処理する傾向にある。このため彼らは、本省とことなる視点で問題をとらえることにより、国内的論理への歯止めとなる可能性があった反面、権力中枢の対外政策決定に対する影響力を喪失する危険性も高かった」(以上、25頁)。こうした分類により、「固定化された派閥的解釈による静態的な分類」よりも、「国内的論理と国際的文脈の矛盾や相克をも考慮した理解」が可能になり、「ダイナミックな変動に対する有効な分析方法が確立できる」とされる(23頁)。また、両者の間には移動(著者の言葉を用いれば「移項」25頁)が、構造的原因、主体的原因の双方から起こりうるとされる。
著者なりの人物の具体的な分類は、本書25頁に掲げられているので参考にされたい。ここでは、この四象限を包括して各タイプに共有されるのが、反共主義とされていることを確認するにとどめたい。
反共主義の三種類
さて、著者によれば、日伊両国において、反共主義には、①対外政策の阻害要因として規定する機能、②敵としての認識を策定する基準としての機能、③仲間を作るための名目としての機能の三機能が付与されたとする(35頁)。こうした機能はもちろん「国際的反共主義」(36頁)の文脈を超えるものとなり、①が国際連盟=第一次大戦後の秩序批判に(38頁)、②が武力介入=エチオピア、中国への膨張主義の正当化の根拠に(42頁)、③が反共的国際秩序の形成原理=西欧を抱合した新秩序形成の原理に(49頁)、それぞれ利用されることになる。
注意すべきは、こうした機能が、すぐさま破壊的な軍事衝突を正当化したわけではないことであるが、そうした過程で、外交官自身が「伝統的反共主義の肥大化により生じた包括的な反共イデオロギーを指導者層の最大公約数として受容」するようになり、やがて外交は「「友敵」関係へと収斂する危険」をはらみはじめる(54ー55頁)。著者によれば、反共主義は、「(1936年から37年の一年間で)日伊両国にとって反ソや反連盟という文脈のみならず、中国もしくはスペインさらにはイギリスを取り込むという文脈を超えて、「親枢軸」「反西欧」という新たな「友敵」関係を形成し始めた」のである(63頁)。日本ではたとえば、佐藤尚武外相などは共産主義は内政問題とするが、彼でさえ「国内的論理」を忖度する必要に迫られはじめる(64頁)。
こうして、「空虚なる同盟」は始動するのである。
三 「ゆがんだ結束」の内実
「ゆがんだ結束」の実例以上のようにイデオロギーに着目した第一章に対し、第二章では、「(日独伊枢軸の)期待された成果を達成した」事例と言うより、「むしろ日独伊枢軸のゆがんだ結束を象徴する事例」(79頁)という性格を持つ、ブリュッセル九カ国会議、三国防共協定締結、イタリアの満州国承認、日中和平調停工作、イタリアの連盟脱退の御事例を取り上げ、三国の現実の利害関係がいかに相反するものであったかを実証してゆく。以下にそれぞれの例の分析結果を掲げてみる。
ブリュッセル会議(80頁以下)
・ドイツは親中的であり、日中戦争では日本を非難していた。日本は日中戦争は共産主義勢力に対する武力発動であるとして、日独防共協定に基づく委員会の設置を提唱するが、ドイツは拒否する。
・ドイツの軍人ファンケルハウゼンはイタリアを排除して蒋介石の軍事顧問団長に就任
・こうした行為に日本はトラウトマン大使の召還さえ要求した。
・こうした中開催されたブリュッセル会議にイタリアは出席して日本の不興を買う。ドイツは出席すれば親日的態度を取らざるを得ないという理由で欠席を決めた。
日独伊三国防共協定(84頁以下)
・イタリアと日本は当時人種問題で対立していた。
・イタリアは三国防共協定が反英的にならないように注意していた。日本も中国との防共、イギリスとの防共を重視していた。しかし、日本のそれは不可能であった。広田外相など外交官は「内向きの現実主義」(88頁)を取っていた。
・日中戦争後日本への接近を拒否していたドイツでは、極東政策をめぐり、外務省とリッペントロップの間で激しい権力闘争が展開されていた。
イタリアの満州国承認(94頁以下)
・イタリア1934ー35年に空軍使節を中国に派遣し、ドイツと競合していた。
・ドイツは満州国承認を渋り続ける(1938年2月20日の承認を宣言)。日本は逆にイタリアのエチオピア征服の承認を渋る。エチオピアの繊維製品の9割を日本が占めていたため。
日中和平調停工作(99頁以下)
・ムッソリーニは独伊の調停を申し出る。トラウトマン工作が始動するが、日本は採取的に翻意する。
・ドイツのディルクセン駐日大使は一貫してイタリアを軽視していた。
イタリアの国際連盟脱退(103頁以下)
・イタリアは、国際連盟を敵対視(1937年11月脱退)。ドイツは日本の行動と防共協定が同一視されることを警戒するが、ここでイタリアと運命をともにする。
三つのイメージ
以上のように、防共協定締結時下においてさえ、三国間には利害相反の例が極めて多かったのである。にもかかわらず、1939年5月の独伊同盟、40年9月の三国同盟と、「枢軸結合」(113頁)は確実に進んでいくのはなぜだったのか。著者によれば、それは各国の国際情勢の認識方法が似ていたからである。
著者が提示する認識方法には三つのパターンがあった。カウンターイメージ、パラレルイメージ、ミラーイメージの三つである。
カウンターイメージは「自分たちの反対する価値体系と対置させた疑似対抗イデオロギーが投影される」。言い換えれば、ヴェルサイユ体制、連盟体制、共産主義批判がこうしたイメージから導き出されることになる。
パラレルイメージは「他国が成功した膨張の事例や他国の国際環境に関する思い込みを、自分たちの打算に基づき並行して援用する」。それは枢軸間での同質性のイメージを増長させるよりも、むしろ「孤立にともなう疑心暗鬼と相互不信の悪循環」が生まれる原因となる。
ミラーイメージは「自分たちの姿を相手にも映し出して、同様の行動様式を想定、期待するもの」である。これは特に「イギリス」に対する自己投影となり、イギリスが自国の政策を許容することを一方的に期待する背景となった。
著者によれば、こうしたイメージには体系性はなく、あくまでイメージにとどまるが、それゆえに強固に作用したのであった(以上、114頁)。
四 対外政策決定構造
日独伊英の四か国比較最後の第三章では、著者は、本書の分析視角にも関わる対外政策決定構造に改めて踏み込んでいるが、そもそも、日独伊三国の外務省には「理性的で、西欧との協調を追求したという説明」は成り立たないとし、むしろ外務省を中心としつつ「どのように対外政策が作り出されていたのか」を論じる必要があるというのが著者の立場であった(7-9頁)。そのうえで、日独伊の対外政策構造を、著者は以下のように整理している。
ナチ・ドイツ
多頭制ではあるが、ヒットラーを頂点とするヒエラルキーは確固としている。権限の縄張り争いが生じても、その構造自体が自滅することはなかった。
ファシスト・イタリア
ムッソリーニが、独立性の高い軍、外務省、党の調整者となっている。
日本
陸軍、海軍、外務省などの各機関が「非妥協的抗争」を繰り返していたが、昭和天皇は「御輿」であり、宮中グループがクッションとなっていた。しかし、各機関の頂点が不明瞭な円錐台構造であった。
こうした三国の対外政策決定構造には相違もあるが、類似点も少なくなかった。それに対し、三国の共通の敵国となってゆくイギリスは、政府・外務省・議会・世論の綱引きにより政策決定がなされるという点で他の三国と大いに異なっていた。しかもイギリスでは外務省の独立性・権威が高かったとされる(9-10頁)。なお、この点については本書10-11頁の図を参照されたい。
こうした整理を背景に、著者は日伊両国の対英関係に着目し、第一に、現地の責任者である駐英大使、第二に、首相・外相・次官ら、第三に組織の下僚たちにそれぞれ着目し、外務省が枢軸形成の抑止機能を果たせなかった様相と理由を考察してゆく(142頁)。
吉田とグランディ
1930年代後半の決定的な瞬間において、ロンドンで出先の責任者となったのは、日本は吉田茂、イタリアはディーノ・グランディであった。彼らに共通していたのは、枢軸結合が強まっていた当時、イギリス大使と言うポストは一種の「左遷」のポスト(144頁)だったという事実である。しかし、たたき上げのファシストであったグランディと宮中政治家と言ってよい側面を持つ吉田とでは出自も異なる。また、グランディは、同時代のソ連の大使・Iマイスキーも高く評価する辣腕の交渉家であった(149頁)。やはり同時代の駐英大使であったドイツのリッペントロップはグランディを毛嫌いしているが(同上)、イギリスは吉田を「不十分な交渉者」と呼ぶほど評価が低かった。それはイギリスのリッペントロップ評価とも共通するものであった(152頁)。
しかし、それ以上に対照的だったのは、著者によれば、「吉田が象徴的な「友好」を力説し、「親日的」な相手による「善意」の接近を待つ姿勢に終始した」のに対し、グランディは「具体的な交渉の可能性を掘り起し、妨げとなる「反伊的」人物は相手国の外相であっても「悪意」をもって排除するという攻撃的姿勢」を続けたことであった(155頁)。いわば、吉田は交渉と言う名に値しない受動的態度に終始し、グランディは交渉と言うよりも攻撃と言うべき能動的態度を示したのである。
振り子外交論の類似と相違
もっとも、吉田とグランディの対英交渉の要点は、イギリスを反共戦線にとりこむことであり、それにより自国の膨張政策や新秩序外交を容認させることであった。しかし、そのための二人の交渉態度には、以上のような大きな違いがあった。
著者によれば、第一に、この二人の交渉家が認識していた国内政治の図式が大きな影響を与えていたという。吉田は、「急進派」と「穏健派」(155-56頁)という比喩を用い、イギリスが友好的な態度を示せば、日本国内の穏健派を勇気づけ、「振り子は軍国主義的政策から国際主義的政策へ揺り戻される」として吉田はイギリスを説得しようとした(155-156頁)。対するグランディは「イギリス派」と「ドイツ派」(156ー57頁)という一見吉田ともよく似た図式に依拠していたというが、ファシスト的な情勢認識によれば、これはイタリアがイギリスかドイツかを積極的に選び取れることを意味した。その意味でこの図式は「能動的」だというのが著者の見方である。
国内における割拠と競争
また、第二の理由は、両者が国内における割拠と競争に否応なく影響されたことが挙げられる。吉田が置かれていたのは、国内における政府内・外務省内での激しい割拠と競争の実態であった。そこでは統一見解が出せずに、総花的であいまいな要求に終始した。状況を打破するには相手からの譲歩を待つしかなかったとされる(158頁)。対するグランディは、ファシストの領袖として、ムッソリーニが最終調停者であるイタリアの政策決定過程の一翼を担っていただけでなく、ムッソリーニを「君」づけできる地位にあったグランディは、対英接近と同時に枢軸接近へといわゆる「二股」をかけており、いざと言うときの「保身」をも怠らなかったとされる(159-60頁)。
こうした混乱の中で日伊両国は政府あるいは組織レベルでも政策の調整機能を喪失してゆく。たとえば、1936年から翌37年にかけての防共協定交渉と対英関係をめぐる有田八郎外相と東郷茂徳の対立は激しかった。しかし、有田が枢軸への接近に邁進したわけではない。有田が防共協定強化問題に抵抗したのも事実であり(その際有田がこだわった抵抗の論理は「反共主義」であった。173-75頁)、ナチスドイツはイタリアのパスティアニーに同様、有田を「二枚舌」として信用しなかった。にもかかわらず、有田が対英接近を主導したわけでもなかったのであり、その意味で、有田は「小広田」であり、パスティアニーには「小チャーノ」であった(175-76頁)。
個人と組織・構造
こうして30年代を通じて同様の論理や動向が再生産される理由を、個人の資質にもとめるのは不十分である、というのが著者の第三章での結論である。こうした枢軸形成は、外務省を迂回して進められるようになった。また、出先と本国、政府内、組織内での細かな調整機能も発揮されなかった。こうした機能不全はイギリスと対照的であったのである(181頁)。
五 評価と分析
以上が、本書の概要であるが、以下、三点について、本書の貢献を指摘し、さらに疑問あるいはお願いを提示して結びとしたい。第一に、著者の「反共主義(的国際観)」についてである。著者の「反共主義」認識は、少なくとも従来の日本外交史研究では明示的には議論されてこなかった点を明らかにしている。すなわち、30年代における反共主義は、反連盟、平和の名の下での武力介入、新秩序外交といった諸特徴に援用される概念であり、30年代を他の時代から区別する独特の要素だったのと言うことである。たしかに、日本の例を取り上げても、そうした際に共産主義の脅威が語られ続けたことは事実であり、そのことを体系的に指摘したことは高く評価したい。それは著者の描く時代に防共協定が強化されるという課題がいつの間にか軍事同盟にすり替わってゆくという謎を解明する一つの視点に他ならないともいえる。
しかし、そのことはすぐさま反共主義が「持てる国」「持たざる国」あるいは「現状維持」「現状打破」という概念よりもより普遍的に利用されたのかどうかという疑問を生じさせる。たとえば、イタリアでは、「反共主義」と「現状打破」論とが具体的な言説分析においてどのような関係にあるのかを改めて聞いてみたい。
第二に、第二章で、三国の関係がいかに空虚であるかを、特にイタリアの視点を加味して明らかにした点を高く評価したい。だが、第二章で論じられている三つのイメージと第一章で論じられている反共主義との関係が今一つすっきりと整理できない。また、政務型・交渉型と言う外交官の分類との関係もやや複雑である。
第三は、それとも関係してくるが、外交政策研究としての新機軸を打ち出そうとしたことである。特に日独伊英四か国の対外政策決定構造の比較は評者には大いに参考になった。このような指摘は従来必ずしも多くないと思われるので、もう少し詳細な分析を独立論文として著者にお願いしたい。逆に、著者が「静態的」であるとして批判する日本外務省の「親英米派」「アジア派」などの派閥論であるが、この派閥論は実は1930年代に幾度かおこなわれた当時の「革新政治」の動向を追っていたジャーナリズムによる分類である。また、そのグルーピングは30年代を通じて変化していった。その意味でこの派閥論は学術的な分析概念というよりは、当時まさにダイナミックに動いてゆく外交政策主体の変容を追うことのできるものであり、そうした議論を踏まえたさらなる精緻化が必要だと思われる。
以上が本書の評価であるが、評者の指摘は逆に「それこそ今後の日本外交史の課題ではないか」とすぐさま著者に切り替えされるはずの指摘である。我々日本外交史の研究者こそ、こうした指摘に触発されて新しい研究展開を試みねばなるまい。著者の鋭い分析を大胆に平易に言い直したため、ニュアンスがそぎ落とされてしまっていることを恐れるが、本書が30年代の日本外交史研究にも大いなる刺激を与えてくれたことを強調して結びとしたい。
0%
