評者: 松本 佐保(名古屋市立大学人文社会学部教授)
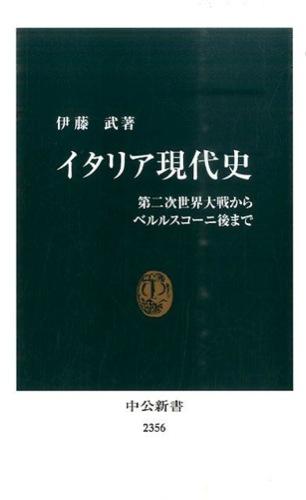
本書の全体像と論点
日本語で書かれた最新の戦後イタリア政治史の概説書がほぼ皆無であるという中で、本書は希少な一冊である。日本語で読める従来の戦後イタリア史は極端に入門書的なものか、逆に専門的な分野に特化した著書がほとんどで、本書のように網羅的であり、さらに非常にバランス良く書かれているものは極端に少ない。本書は、政治のみならず、経済や文化にも触れるなどの配慮がなされ、政治記述において右にも左にも偏らない絶妙なバランス感覚に富んでいる。
戦後のイタリア政治史は1943年から終戦までのパルティザンによるレジスタンスの歴史で培われた共産主義のイデオロギーやグラムシ神話、それによる戦後共産党の存在感の大きさから、左翼的な政治・歴史研究が盛んであり、日本語で出版された著作もこうした傾向を反映している。しかし本書はこれらの研究を踏まえながらも、ストイックなまでに政治色を出すことを拒否し、客観的な記述に終始している。所々に映画の事例の引用など文化的な記述もあるが、基本的に政治・経済を中心に禁欲的であるが的確な言葉を選んで書かれており、これは一般的なイタリアの明るいイメージとは裏腹に、政治汚職や政治的暴力を孕んだ激しさを行間に滲ませている。政治史というよりむしろ政党政治史であることから、少々ドライな印象も否めない。
しかも戦後のイタリア政治史は主要政党以外に多くの政党が乱立し、政党によっては名前を何度も変更するなど複雑極まりない経緯があり、それを分かり易く書くこと自体が至難の業である。本書の執筆にかなり時間を要したことが著者の苦心を物語る。巻末の「主要政党一覧」や「イタリア共和国歴代政権」の表だけでも画期的で、これを見るだけでも波乱に富んだ戦後イタリア政党政治の一端を垣間見ることができる。
1861年~2015年という実に150年近い時代を扱い、しかも戦後政治についてはある程度詳細に記述し、高い水準を維持していることは称賛に値する。
著者は政治学者らしく戦後のイタリアが「普通の国」、つまり民主主義国家となるために突き付けられてきた数々のチャレンジにどう立ち向かってきたか、時には立ち向かうことを忘れて危機や汚職に身を委ねてしまった様を、冷静沈着に淡々と描いている。民主主義国家としてのイタリアは半ば実現し、半ば途上にあり、しかしこれこそ達成するべき目的であるという強い目的意識、また比較政治学者としてイタリアは特殊な国ではなく、他国との比較、恐らくは同じ敗戦国である日本やドイツとの比較を意識し示唆している。
著者の比較政治学者としての力量は政党政治と選挙制度についての叙述において如何 実 なく発揮される。まず政党政治については最大の与党であったキリスト教民主党が、連立政権という形での与党の組み換えはあったにせよ、長期間政権の座にあったことで生じた問題や、派閥的なもの、また数々の汚職についての詳細が述べられている。二大政党政治による定期的な政権交代が民主主義政治の理想的なモデルとするなら、イタリアは未熟な民主主義と言うことになる。この点に関しては日本における自由民主党との類似点を意識しているとも言えるだろう。冷戦崩壊後、キリスト教民主党は、汚職を糾弾する「清い手」運動などによってその勢力を失い、解散を強いられ、第一イタリア共和制の崩壊へと繋がった。
選挙制度では、75%を小選挙区、25%を比例代表制とする新しい選挙制度が1993年に導入されたものの、それで安定的な二大政党政治が確立したわけではなく、小政党乱立による不安的な政治が続き、ベルルスコーニの「フォルツァ・イタリア」や、現在の草の根ポピュリストの運動「5つ星運動」の台頭へと繋がっている。そうした意味で本書は政治研究としての主張の一貫性、偏りのなさ、客観性については文句なしの良書であり、イタリア政治概説書としての役割も十二分に果たしている。
ただ歴史研究としては、多少なりの批判を免れ得ない。評者は歴史研究者として以下本書の内容に沿って批判的な考察を行う。これはあくまでも評者が戦前のイタリア史に関心があること、また評者の専門である政治・外交と宗教の関係に引き付けての書評となること、場合によっては無い物ねだり的な批判も多々あることを断っておきたい。
本書の内容紹介と批判的考察
(男子普通選挙法から戦後憲法まで)
まず序章でリソルジメント(国民統一国家成立)から終戦までをたった15頁にまとめる困難さは承知であるが、少し不足していると感じる点について指摘しておこう。自由主義時代の男子普通選挙法成立期のジョリッティ首相によるトランスフォルミズモ(変異順応主義)について、「政策的共通性よりも個別利害の調整に基づく多数派形成の手法」と説明され、これが後のファシズム体制を招いたことや「腐敗や妥協にまみれた政治手法」となることが触れられているが、もう少しこの点を強調する必要性を感じた。なぜならば、これがイタリア政治に戦後から現在に至るまで一貫して見られる特徴と言えるからである。ジョリッティが「妥協による多数派形成」として行った有名なジェンティローニ協定については触れられていない点が少し残念だ。「カトリック選挙連合」との最大の妥協政策であった同協定は、戦後のイタリア政治において「なぜキリスト教民主党が戦後50年近く万年与党でいられたか」を説明するにも重要な要因であるからである。
それで言うなら、キリスト教民主党の前身となった「イタリア人民党」についての言及があまりされていない。ストルツォ神父というカトリック聖職者が主に、保守と左派のカトリック運動を調整しながら組織した「イタリア人民党」を立ち上げ、ファシズム時代には非合法化されたが、終戦末期に戦後体制を築くデ・ガスペリが「イタリア人民党」から「キリスト教民主党」を誕生させたからである。このストルツォ神父については第2章に「ストルツォ作戦」が失敗した選挙工作として登場するが、この前史を知らないで読むと理解が難しいであろう。またバチカンやカトリックと政治の関係を研究する評者は、キリスト教民主主義の起源について言及する必要性が戦後政治を理解する上でも重要であると考える。
もう一つの批判点は、イタリアの植民地政策についても殆ど言及がないことだ。確かにイタリアは敗戦国として植民地を失うのだが、戦争犯罪の問題や現在の移民・難民問題に関わる軽視はできない問題である。
一方で第1章のファシズム時代からレジスタンス、そして戦後のイタリアにおける社会・経済的な「継続性」については、非常に明確に、かつスムーズに叙述されている。ファシズム時代に確立した国家官僚機構や経済テクノクラートの存在は、戦後イタリア理解の上で重要な要因である。特に後者の経済テクノクラートは、産業復興公社(IRI)や全国保険事業団(INPS)を運営し、しかも国家官僚や民間産業界とは異なる人脈に位置付けられ、国家による経済への関与を拡大した。これは戦後イタリアの奇跡の経済復興をも支え、冷戦終結後の政治的危機の時代に「救世主」のごとく現れ、2011年にも再来する。これについては後述する。
そしてレジタンス期とサロ共和国(ファシスト)とバドリオ政権による内戦期から戦後にかけての短期間の占領政策による不十分な戦後処理、パルティザンゆえの共産党への支持、君主制の廃止、戦後憲法の制定という流れが示される。これらの中で重要な共産党書記長トリアッティによる「サレルノ転換」は、パルティザンに支配された共産主義者の武装解除を意味し、ソ連流の革命による改革ではなく議会制による改革、後に社会民主主義、いわゆるユーロコミニズムの起源となった。戦後西側では最大支持を誇ったイタリア共産党の誕生である。これらについての説明、そして新憲法については政治学者らしくその制定議会についての明瞭な説明が為されている。
(デ・ガスペリ政権の戦後再建)
第2章ではデ・ガスペリ時代の戦後再建(1943~47年)、つまり戦後イタリアの基礎が築かれた時代が批判的に叙述される。同じ敗戦国であったドイツのアデナウアー、日本の吉田茂と並び称されるデ・ガスペリは、「戦後イタリア再建の父」と美化される傾向もあるが、著者はこのような神話化されたデ・ガスペリ像を崩すことに躊躇しない。1947年~53年のたった6年間に7度も組閣したデ・ガスペリ政権期は政治的には波乱の時代でもあったことが見て取れる。初期冷戦時代にあってその地政学的な位置付けからも、米国から冷戦最前線として扱われたイタリアが受けた恩恵と共に、この内部に孕んだ政治的な矛盾が如何なく露呈する様が鮮やかに描き出される。
右派はファシスト党が「イタリア社会運動」として再出発すると共に、左派の社会党や共産党との連立を余儀なくされるキリスト教民主党が、米国やバチカンの圧力により左派政党との決別を迫られるジレンマ、そしてその圧力ゆえに右旋回するものの、左派は激しく反発し、ゼネストの決行や武力による公共施設の占拠など、「奇跡の経済復興の時代」(1954~67年)を挟んで、1968 年 ~78年の「鉛の時代(銃弾を意味する極右と極左による武力闘争)」の予兆が示唆される。また序論や第一章であまり触れられなかったバチカンやカトリック教会、またカトリック票と政党政治の関係がこの章では述べられる。
こうした左右の対立は労働組合運動にも反映され、19世紀末からイタリアを悩ませてきた急進的な左翼の労働運動と、キリスト教民主党系の労働組合運動は袂を分かつことになる。キリスト教民主党は既述のテクノクラートを味方に付け、経済による権力基盤を強化していく。これは対外的にはやがて欧州政治共同体やNATOの設立メンバーとなり、国際的な地位の向上に繋がるが、内政的には「敗戦国」でありながら「再軍備」に着手したことは国民からの反発を齎し、結果的にキリスト民主党はいくつかの選挙制度をめぐる改革の試みにもかかわらず、議席を減らすことになる。この辺りの記述も決して左翼寄りでなく、イタリア労働運動については膨大な研究と論争があるにもかかわらず、あっさりとした論調である。
(奇跡の経済復興と赤軍)
こうして、議席を減らした与党を救ったのが戦後の奇跡の経済復興であり、それは第3章の「高度成長と新たな政治路線の模索 1954~67年」として展開する。ファンファーニというキリスト民主党内の左派の政治家による政権は、常に右にふれたり左にふれたりする政治的には模索の時代であったと著者は説明する。つまり順調な経済発展の陰で政治は決して安定的ではなかったことを示唆している。デタントの時代でありながら、フルシチョフによるスターリン批判やハンガリー事件は共産党に路線変更を迫り、それゆえに与党はファシスト党である「イタリア社会運動」に支持された右派のタンブローニ政権を成立させ、国民の激しい非難を買い総辞職に追い込まれる。
63年になると有機的な中道左派政権と言われた第一次モーロ政権が誕生する。急速な経済発展でイタリアは先進国の仲間入りを果たし、これには既述のテクノクラートの役割もあり、北部工業地帯が特に飛躍的に発展し、一方で取り残された南部との格差も拡大する。その南部に起源を持つマフィアと、政治の癒着である汚職やマフィア裁判をめぐる問題については第5章と第6章で扱われているが、いわゆる「南部問題」については議論されていない。
こうした経済発展はイタリア社会に大きな変化を齎すと共に、その反動が次の第4章の「社会運動の高揚とテロリズムの横行の時代 1968~78年」とコントラストをなす。それは極左の赤いテロリズムと極右による暴力の連鎖の時代であった。こうした現象はイタリアだけでなく、敗戦国の日本やドイツにも共通に見られた現象であり、赤い旅団、連合赤軍、バーダマインフォフであった。著者はこの時代を「熱い秋」として日本やドイツとの比較を示唆しながらも、「緊張の戦略」として、極右によるクーデターの可能性にも触れ、危機の時代が熱く語られる。その危機がピークに達したのが、首相を5回も務めたモーロの誘拐と殺害事件であり、単なる極左テロリスト「赤い旅団」による重要政治家の殺害ではなく、モーロが共産党のベルリグェルとの「歴史的妥協」を模索した矢先に起きた事件という重要性である。彼のライバルであるアンドレオッティが、キリスト教民主党の共産党との妥協を阻止するために見殺しにしたという陰謀説、また与党の共産党との妥協を何よりも忌避した米国のCIAによる暗殺説、イタリアにはこうした陰謀論に基づいた著作が多く存在するが、著者はそんな俗説を鼻にもかけず、淡々とこの危機の時代を書ききっている。
(政治の硬直化)
第5章の「戦後政治の安定と硬直化 1979~88年」では、モーロのライバルで72年以降4回政権に就いた「魔王」と呼ばれたアンドレオッティの第5次政権、そして共和制の政治の枠組みに組み込まれ、得票率を減らした共産党に代わって台頭したクラクシの社会党との鬩ぎ合いの中から、社会党、社会民主党、共和党、自由党とキリスト教民主党による「5党連合政権」が出現する。「プロパガンダ・ドゥーエP2」という極右組織に現職閣僚政治家や軍人などが関与し、またバチカン銀行のスキャンダルも露呈した。こうした政治不信を受けて1983年にはこの社会党のクラクシ政権が誕生する。
当該期の政治過程や政権運営など内政については記述が詳細なのに比べ、外交政策についての記述は限定的にとどまっている。日本とほぼパラレルとも言える米国との密接な関係やそれゆえの経済成長、バブル経済については触れられるが、中東アラブ世界や共産圏との「自立外交」の重視とあるが、これらの詳細については述べられていない。他の章でも冷戦の動向が国内政治に影響を及ぼしたと述べるなら、これらの「自立外交」についてもう少し頁を割く必要があったのではないだろうか。
(第一共和制終焉から第二共和制へ)
第6章は「第一共和制の危機と終焉 1988~93年」として、冷戦の終結に伴う共産党の左翼民主党と共産党再建党への分裂、そして最大与党のキリスト民主党の解散劇、これに伴う選挙制度の改革案、小選挙区制度の導入の過程が示される。終始政治制度や国内政治を淡々と記述し、魔王アンドレオッティのマフィアとの繋がりや汚職についても触れられるが、禁欲的な叙述にとどまっている。ただしバランサーとしてのスカッファロ大統領の描き方は非常に的確である。イタリアの大統領は首相に比して権限もなく象徴的な存在であるが、政治的混乱期にあってバランサーとしての役割を担ったという説明は非常に説得力がある。
冷戦の終焉や「清い手」による構造汚職の摘発によって解散したキリスト教民主党、そして念願の小選挙区制の導入によって、民主主義がより進化することが期待されたが、それが見事に裏切られる様が第7章で明らかにされる。ベルルスコーニ政権の誕生である。プローディなどによる「オリーブ連合」左派連合の96年~98年の一時的成功はあったが、ユーロの導入をめぐって「オリーブ連合」に亀裂が生まれ、左派民主党のダレーマなどの短期政権を経て、結局2001年の選挙でポピュリストのメディア王ベルルスコーニが返り咲く。
第8章では、「オリーブ連合」を立て直しての「マルゲリータ」による2006~8年の第二次プローディ政権を挟むものの、結局再びベルルスコーニに政権を譲ることになる。こうした右派のポピュリストの台頭とその政権の長期化には、左派の内部闘争やリーダシップの欠如という左派側にも大いに責任があると評者は見ているが、著者は「苦しい舵取り」とトーンダウンし、飽くまで客観的な政治学者たろうとする強い信念がうかがえる。この頃になるとベルルスコーニには汚職疑惑、マフィアとの癒着、未成年との性的な関係など多くの裁判を抱えながら、なおも政権の座に居座り続けた。腐敗しきったイタリア政治、そしてそれを打破した救世主は、テクノクラートのモンティ政権であった。
長期化したベルルスコーニ政権時代に破綻寸前だった財政を緊縮財政政策で救い、ギリシア危機の二の舞を回避したモンティ政権は高く評価されるべきであるが、選挙で選出されなかったこと、緊縮財政政策への反発から現在台頭している「5つ星運動」が力を付けてくる。結局2013年の総選挙を経て、現在の民主党のレンツ政権が2014年に誕生するが、2016年の「5つ星運動」の地方選挙でも躍進が目覚ましい。この運動はEU懐疑派のポピュリスト運動であり、顕著な少子高齢化、高い失業率と若者の頭脳流出、移民と難民問題、再び頭をもたげる金融危機、これらの困難な状況につけこんで躍進しているように評者には見える。しかし筆者は「5つ星運動」については草の根運動として必ずしも否定的ではない見方をしている。
本書の意義
こうして本書を概観してくると、著者が言うように発展途上の民主主義のイタリア戦後政治の姿がくっきりと浮かび上がってくる。選挙で選ばれた政権よりも、テクノクラート政権の方が政治が機能するような印象を持つのは評者だけであろうか。
イタリアだけでなく、国民投票によるブレグジット(EU離脱)に揺れる民主主義発祥国イギリスでも「国民投票は間違えだった。政治は政治のプロフェッショナルに任せるべき」との声も聞かれる。難民問題やテロ問題に揺れるドイツ、フランスやアメリカでもポピュリストの台頭や二大政党政治の危機が囁かれる。
今ほど、民主主義とは何か、ポピュリズム政治とは何かを問い直すことが求められる時代はない。そのような時代にあって本書はその格好の題材をイタリア政党政治の歴史を通じて提供してくれるのである。
