
※本稿は、2020年11月6日に開催されたポピュリズム国際歴史比較研究会の第六回会合(ヘレナ・ローゼンブラット『リベラリズム――失われた歴史と現在』合評会)で報告した内容の一部である。
古田拓也(広島大学特任助教)
リベラリティの呼び声
リ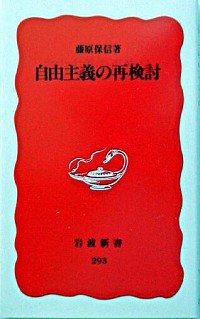 ベラリズムについての入門書といえば、長いこと藤原保信の『自由主義の再検討』であった。今でもある程度はそうである。しかしこの藤原の新書は、「再検討」というタイトル――原案は『自由主義への反省』というタイトル――からも察せられるように、単なる歴史というよりは、リベラリズムの乗り越えを図った著作でもある[1]。では藤原にとってこの〈イズム〉の何が問題なのか。一言でまとめるなら、リベラリズム世界の利己主義化である。同書の「あとがき」に従うなら、現代若者論で知られた「都内の某有名私立大学のA教授」によれば、
ベラリズムについての入門書といえば、長いこと藤原保信の『自由主義の再検討』であった。今でもある程度はそうである。しかしこの藤原の新書は、「再検討」というタイトル――原案は『自由主義への反省』というタイトル――からも察せられるように、単なる歴史というよりは、リベラリズムの乗り越えを図った著作でもある[1]。では藤原にとってこの〈イズム〉の何が問題なのか。一言でまとめるなら、リベラリズム世界の利己主義化である。同書の「あとがき」に従うなら、現代若者論で知られた「都内の某有名私立大学のA教授」によれば、
すでに何年かまえから、たまたまゼミの途中で休憩時間をとると、何人かの学生は少し離れたスタンドからコーヒーを買ってきて、勝手気ままに飲んでいるという。かつてはそのようなばあいには、先生や友人にもコーヒーを買ってくるか、あるいはそこまでいかなくとも、コーヒーを買いにいきますけれどもお飲みになりますか、という声くらいはかけたというのである。教授は、今の若者があまりにも自己中心的になり、他人への思いやりや気配りに欠けていることを嘆いている。[2]
しかし、これは若者のせいとばかりは言い切れない。「公共心を失い利己主義的なのは日本の社会そのもの」だからである。『自由主義の再検討』の端緒は、「このような状況へのある種の危惧と憤りに発している」。かつて確かに「解放」の契機となったリベラリズムが、今では自分勝手な行為の正当化原理に堕してしまったのである。
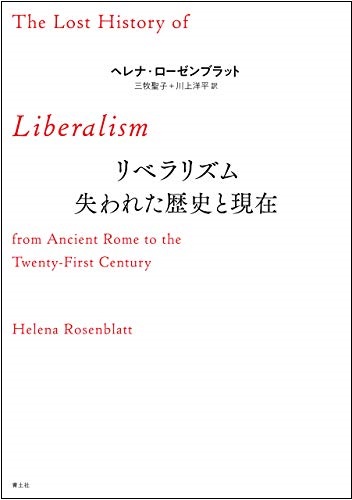 不安と不満をもってリベラリズムを見つめる藤原に、真のリベラルはコーヒーを買ってきてくれるのですよと教えるのが、ヘレナ・ローゼンブラットの『リベラリズム――失われた歴史と現在』である。藤原の新書は、ロックからロールズまでのリベラリズムの歴史を辿った後、一般的にコミュニタリアンと呼ばれる歴史・共同体を重視する理論家たちを論じて閉じられている。リベラリズムを乗り越える原理として、コミュニタリアニズムが呼び出されるわけである。これに対してローゼンブラットは、利己主義を乗り越える道は他にもあると提起する。それは、失われたリベラリズムを取り戻すことによってである。ローゼンブラットはリベラリズムにはliberality+ismとliberty+ismの二つがあり、前者こそ古代にまで遡りうる価値あるリベラリズムだと語っているように思える。彼女はこのストーリーの前史をキケロから始める。ローマの伝統においてliberalityは貴族的な徳であった。それが後に民主化されたり制度化されたりはするが、しかし――以前に流行った歌で言うと――人間が「ありのままで」でいいよとやさしく語っているわけではない。実際あの歌でも、「ありのままで」と言いつつ、高そうで貴族的な服に変身している。まさにそうした道徳的変身をliberalityは要求する。この要求が、宗教としばしばセットになって、リベラリズムの核心にあるとローゼンブラットは見ている。つまり、コーヒーを買ってきてくれないリベラルは、古代のliberalityを忘れたリベラルもどきなのである。
不安と不満をもってリベラリズムを見つめる藤原に、真のリベラルはコーヒーを買ってきてくれるのですよと教えるのが、ヘレナ・ローゼンブラットの『リベラリズム――失われた歴史と現在』である。藤原の新書は、ロックからロールズまでのリベラリズムの歴史を辿った後、一般的にコミュニタリアンと呼ばれる歴史・共同体を重視する理論家たちを論じて閉じられている。リベラリズムを乗り越える原理として、コミュニタリアニズムが呼び出されるわけである。これに対してローゼンブラットは、利己主義を乗り越える道は他にもあると提起する。それは、失われたリベラリズムを取り戻すことによってである。ローゼンブラットはリベラリズムにはliberality+ismとliberty+ismの二つがあり、前者こそ古代にまで遡りうる価値あるリベラリズムだと語っているように思える。彼女はこのストーリーの前史をキケロから始める。ローマの伝統においてliberalityは貴族的な徳であった。それが後に民主化されたり制度化されたりはするが、しかし――以前に流行った歌で言うと――人間が「ありのままで」でいいよとやさしく語っているわけではない。実際あの歌でも、「ありのままで」と言いつつ、高そうで貴族的な服に変身している。まさにそうした道徳的変身をliberalityは要求する。この要求が、宗教としばしばセットになって、リベラリズムの核心にあるとローゼンブラットは見ている。つまり、コーヒーを買ってきてくれないリベラルは、古代のliberalityを忘れたリベラルもどきなのである。
リベラリズムの原型を古代に求めたことで、知ってか知らずか、ローゼンブラットの解釈図式は、レオ・シュトラウスのそれとの重なりをみせる。シュトラウスは藤原の学問上の師であり、かつ今日でも参照されるリベラリズム理解を提示した重要な思想家である。シュトラウスにとって、liberalismとはnatural rightによる政治である。そのため、natural rightの意味が変化すると、リベラリズムの意味も変化する。意味上の最も大きな断絶は、古代と近代の間にある。古代ではnatural rightは「自然的な正しさ」と理解されていた。正しいとは魂の調和であり、魂の調和とは欲望がしっかりと知性の下に置かれていることである。こうして古代のリベラリズムは、人が欲望をコントロールし、他者に対しても有徳に振舞える高貴な存在になるよう要求した[3]。「本来の意味でのリベラルであるとは、寛大さ(liberality)という徳の実践を意味する」[4]。そうした高貴な善を却下し、それに代えて最高悪としての「死」を持ってきたのが近代のトマス・ホッブズである。逆に言えば、死の回避が最高善となった。ゆえに最高善は各人バラバラになってしまう。それに応じてnatural rightは「自然的権利」として個人に固有なものに変わる。権利中心的な近代のリベラリズムはここから始まる[5]。ローゼンブラットが、ホッブズをリベラリズムの理論家と数えるのはおかしいとわざわざ述べているのは、この解釈を念頭においてであろう。
 だが本当のリベラリズムとは何かという論点になると、両者の主張はかなり近づいてくる。近代リベラリズム(の堕落版)が広がった現代において、シュトラウスは古代のリベラリズムを学ぶ必要を説く。古典を通じてこれを教えるのがリベラルアーツの眼目である。詳述はしないが、これがローゼンブラットの視点と重なるのは明らかであろう。試みにシュトラウスの著書『リベラリズム――古代と近代』の訳者による帯の文言を見てみると、本書の「「リベラリズム」は、今日の自由主義全盛の中で次第に脇に追いやられるようになってしまった「有徳的な」生を可能にする、あるいはまた「高邁な」生、卓越した生を可能にするようなリベラリズムである」と書いてある[6]。帯を取り換えてもたぶん気づかれない程度には、着目点が似ていると言えそうである。シュトラウスにとって、これは単に卓越せよという命令ではなく、政治的にどうしても必要な要素である。シュトラウスは、近代的リベラリズムが変質し、〈なんでも寛容主義〉になってしまったことが、ワイマール共和国の脆弱性であったと考えている。このなんでも寛容主義、もう少しまともな言葉に言い換えると価値相対主義が、ワイマール共和国に広がっていた。のみならず、アメリカにも広がっていた。これは危険な兆候である。ゆえに、たとえ近代的なリベラリズムであっても、それを支えるには、市民を高貴なものとするリベラルアーツ教育が必要とされるのである。
だが本当のリベラリズムとは何かという論点になると、両者の主張はかなり近づいてくる。近代リベラリズム(の堕落版)が広がった現代において、シュトラウスは古代のリベラリズムを学ぶ必要を説く。古典を通じてこれを教えるのがリベラルアーツの眼目である。詳述はしないが、これがローゼンブラットの視点と重なるのは明らかであろう。試みにシュトラウスの著書『リベラリズム――古代と近代』の訳者による帯の文言を見てみると、本書の「「リベラリズム」は、今日の自由主義全盛の中で次第に脇に追いやられるようになってしまった「有徳的な」生を可能にする、あるいはまた「高邁な」生、卓越した生を可能にするようなリベラリズムである」と書いてある[6]。帯を取り換えてもたぶん気づかれない程度には、着目点が似ていると言えそうである。シュトラウスにとって、これは単に卓越せよという命令ではなく、政治的にどうしても必要な要素である。シュトラウスは、近代的リベラリズムが変質し、〈なんでも寛容主義〉になってしまったことが、ワイマール共和国の脆弱性であったと考えている。このなんでも寛容主義、もう少しまともな言葉に言い換えると価値相対主義が、ワイマール共和国に広がっていた。のみならず、アメリカにも広がっていた。これは危険な兆候である。ゆえに、たとえ近代的なリベラリズムであっても、それを支えるには、市民を高貴なものとするリベラルアーツ教育が必要とされるのである。
ここでシュトラウスを持ち出したのは、もちろん全部同じだと言いたいのではなく、ローゼンブラットのオリジナリティをよりはっきりさせるためである。シュトラウスは、おそらく経済的なレッセフェールを念頭に置いて、とりわけ一九世紀以後にリベラリズムは「高貴さ」への嗜好をはっきりと失いはじめ、それが本来持っていたリベラルさとは正反対の意味になってしまったと語る。ローゼンブラットはそうではないと教える。むしろ一九世紀こそ、コンスタンなどを通じて、古代からのリベラリズムがはっきりと政治原理の形をとった時期なのである。たしかにレッセフェール原理主義者もいるにはいた。ただそれは例外であって、リベラルの本流の思想家は道徳的成長を求めた。シュトラウスにとって「古典的政治哲学は、そのもともとの意味においてリベラルであった」[7]。これはローゼンブラットも共有できる見方であろう。だがローゼンブラットの著書では、古代の重要なliberalityのストーリーはあくまで「前史」であって、それ自体がリベラリズムではない。要するに古代まで戻らなくてもよい。二十世紀半ばという、意外なほど最近まで高貴なリベラルの理念は生きていた。古代におけるリベラルさに注目しつつ、シュトラウスが想像していなかった時と場所でのリベラリズムの誕生と、思った以上に長生きであった「リベラル」の理念を描いたことが、本書の大きなポイントだと言えるだろう。
シュトラウスもローゼンブラットも(そしてもちろん藤原も)、歪んだリベラリズムからの脱出経路をどこに求めるかの違いはあれど、そろって「非リベラル・デモクラシー」には大いに反対する。この二人の観点からは、「非リベラル」であるとは、単に立憲的制約が無視されるという意味に留まらず、貴族的要素が消えるという意味でもある。シュトラウスは「一般教養教育(liberal education)とは、我々がそれによって大衆民主主義から本来の民主主義へと上昇しようとする梯子である」と表現する。「一般教養教育は、民主主義的な大衆社会の中に優秀者支配制を基礎づけようとするために必要とされる努力なのである」[8]。この着想はローゼンブラットにも見出せる。『リベラリズム――失われた歴史と現在』を支えるキーフレーズのひとつは、「デモクラシーがリベラルなものとなる」ように努力せよという、モンタランベールの言葉である(180)。まさしくこれは、「デモクラシーの民主化(democratization of democracy)」というエルネスト・ラクラウのラディカルデモクラシーおよびポピュリズム擁護のスローガンとの見事な対照となっている[9]。
リベラリズムに高貴さを求める視点は、今では評判は良くないが、かつての大衆社会論とも重なってくる。とりわけ、リベラルな価値の「不自然」さと、にもかかわらずその意義を説いたオルテガの次の一節は、ローゼンブラット自身も大いに共感するのではないかと思われる。
政治において、最も高度な共存への意志を示したのは自由主義的デモクラシーであった。(…)自由主義とは、至上の寛容さなのである。(…)自由主義は、敵との共存、そればかりか弱い敵との共存の決意を表明する。人類がかくも美しく、かくも矛盾に満ち、かくも優雅で、かくも曲芸的で、かくも自然に反することに到着したということは信じがたいことである。したがって、その同じ人類がたちまちそれを廃棄しようと決心したとしても別に驚くにはあたらない。自由主義を実際に行うことはあまりにもむずかしく複雑なので、地上にしっかりと根を下ろしえないのである。[10]
たとえば選挙に勝ったから勝者総取りと考えるのか、それとも勝ったからこそ分断を埋めようと努力するのか。後者を選ぶのは「不自然」であり、ゆえに――オルテガ風に言えば――大衆には期待しえない道徳的陶冶が要求されるのである。『リベラリズム――失われた歴史と現在』は、こういった道徳的陶冶を訴える伝統を、歴史を語ることを通じて、再度活性化する試みともみなしうるかもしれない。
リベラリズム、アナクロニズム、ポピュリズム
こういった面白さがあることを確認したうえで、歴史叙述そのものと、本書の現代的意義について、多少の不満点が残るのも事実である。まず、ローゼンブラット本人が最初に立てた方法論的準則がどうみても守られていない(これも訳者解説における川上執筆分でも指摘されている)。ローゼンブラットは、現状の歴史叙述に強い不満を示す。それは既存の研究が、リベラリズムの定義をしてから歴史に向かうため、アナクロニズム(時代錯誤)に陥っている(ということにされる)からである。「序章」においても、ホッブズ、ロック、スミスなどをリベラルに数え入れる議論に対して、「その言葉もその概念も、どちらも彼らの時代には存在しなかった」と反論している(10)。同じことは、一九世紀にレッセフェールを唱えた思想家たちにも当てはまる。フレデリック・バスティアは、自由貿易論を説いているが、ローゼンブラットによれば、「彼はみずからを、まだ存在してもいない古典的リベラリズムの主唱者とも、ましてや創始者ともみなすことはなかった」とされる(120)。実際「リベラリズムの今日の議論においてかくも重要な役割を果たしているこの概念は、いま考察している時期には決して本当には存在しなかったのである」(127)。
しかし、コンスタンやスタール夫人といった、本書の主人公の説明をするときは、まったく違った準則が適用されている。ローゼンブラットは、一通り二人の政治思想について述べた後、「彼〔=コンスタン〕にしてもスタール夫人にしても、「リベラリズム」という言葉を用いることはなかった」と語る。「この用語はまだ造られていなかった」からである。むしろ「われわれが今日「リベラリズム」として認識する一連の規範を、彼らはゆるやかに発見していったのである」(63)。まず、我々の原理であれば、そもそも失われていないのではないかという揚げ足取りもできるが、とりあえずそれは脇に置いておいて、ここで言われている「リベラル」の基準は、先に適用されたものとは明らかに違う。ここで論点になっているのは、単語の歴史ではない。むしろリベラルという単語でまとめられた一連の原理である。別の言い方をすれば、ローゼンブラットも暗黙裡に定義を持ち込んでいるのである。(定義はどちらにせよ不可避なので、それを責めているのではない。できない約束をしたことを責めているのである。)
ゆえに、ローゼンブラットが何をリベラリズムとみなしているかをはっきりさせる必要がある。すると、思いのほか馴染みのある原理が登場する。まずは、権力は制限されねばならないという原理である。これを理由として、コンスタンを「リベラリズムの最初の理論家とさえ呼ぶことができるであろう」(78)。次に、それに劣らず重要なのが政教分離である。権威的な宗教という問題が、「コンスタンをして、リベラリズムの創設原理となるところのもの、つまり教会と国家の分離を表明せしめたのである」(79)。別の個所でローゼンブラットは、リストにして「リベラルの原理(liberal principles)」をまとめてくれている。それによれば、「この原理が意味したのは、法の支配と市民の平等、立憲的および代表制による統治、そして数々の権利(rights)、とりわけ出版の自由および宗教の自由」を支持することである(63)。これを聞いて驚く人はいないだろう。驚くべきだとすれば、リベラリズムが権利中心になってしまったと語るローゼンブラットが、ここで権利についてためらいなく語っていることかもしれない。
これが「リベラルの原理」であるとすれば、そしてリベラリズムという言葉を用いるかどうかが無関係なのであれば、教科書的ストーリーの通り、ジョン・ロックをリベラリズムの創始者にもってきて何が悪いのか、という疑問が浮かんでくる。ロックの『統治二論』のメッセージのひとつは、疑いなく、権力は制限されねばならないという原理である。ロックの『寛容書簡』のメッセージのすべては、国家と教会を分離せよ、である。「福音の下においては、キリスト教政治共同体(respublica Christiana)などというものは絶対に存在しないのです」[11]。ロックは自然権を重視して語っているが、先の基準では、それが排除の理由にはならないようである。もしかすると道徳的陶冶についてロックが語っておらず、その点がコンスタンとは違うということなのかもしれない。しかし、ロックにもそういう側面があると第一章で述べていたのは、他ならぬローゼンブラットである。
このように絞っていくと、コンスタンが上述の諸原理をまとめて「リベラルの原理」と呼んだという事実が残る。たしかにロックは、自身の政治思想を「リベラルの原理」の名で統括しようとは考えなかった。ゆえに二人を分ける要素がたしかにここにある。ここから、なぜローゼンブラットがコンスタンをリベラリズムの創始者としているのかが分かる。彼女の判断基準では、リベラルと後から名づけられる諸要素が先に存在するか否かとは無関係に、それらが「リベラルの原理」と呼ばれた時点から、リベラリズムが始まるのである。逆に言えば、リベラリズムともリベラルとも呼ばれていなかったとしても、後にそう呼ばれるようになる諸要素が先立って存在していたことを、本書は原理的に否定できない。
この事実は、ローゼンブラットの主張する、アナクロニズムを乗り越えたという本書の意義に、小さな疑問符をつけるように思われる。先に述べたように、ローゼンブラットはアナクロニズムを大いに警戒している。しかし一般的にリベラリズムの原理を歴史の中に探そうとする人々は、特定の諸原理が「リベラル」と呼ばれた歴史ではなく、どう呼ばれていようとそうした諸原理がいかにして現れてきたかに注目する。結果として、我々のよく知っているロックが中心となるストーリーが組み立てられているのである。そしてここまでの議論から分かったのは、ローゼンブラットの実際に用いている準則からは、それを否定しえないということである。「われわれが今日「リベラリズム」として認識する一連の規範を、彼らはゆるやかに発見していったのである」(63)と言えてしまうからである。もちろん「リベラル」とは呼ばれていなかったのだからアナクロニズムだと反論することは常に可能である。だがこの批判が正当なのは、特定の諸原理が「リベラル」と呼ばれた歴史だけが、真正のリベラリズムの歴史だという前提が共有されている場合だけである。そしてローゼンブラットは、この前提の正当化を本書においてなしえていない。多くの研究者は、呼称だけの歴史を求めているわけではないのである。
これが歴史叙述に関する疑問だとすると、次は現代的意義に関する疑問である。そのうち一つ目は、ローゼンブラットが道徳的陶冶の動機として、宗教を挙げていたことに関係する。この論点は川上執筆分の「解説」でも触れられているが、リベラリズムには高貴さが必要であるという主張と、その高貴さのために宗教が不可欠だと理解されてきたという主張は、忘れられたリベラリズムの今日的意義を考える上では無視できない困難を突き付ける。理由はもちろん、現代において、皆で「人類教」を信じてリベラリズムを支えましょうとは言えないからである。この論点は、コンスタンの宗教論とリベラリズムの結びつきを論じた堤林剣が、ある論文の最後でレトリカルに指摘していた。
となれば、立憲主義に一定の価値を見出す人間は、コンスタンと同じような目標を掲げながらも、別の道を切り拓くほかない。しかも、相対主義の嵐が吹きすさぶなかでその道を共に探し共に歩むことは、これまでになく険しい営みになるだろう。しかしコンスタンの道案内にしたがってこの荒地に立ったならば、引き返す道もまたないことをわれわれは知っているのである。[12]
 もちろん、だからローゼンブラットの主張に意味がないというわけではない。ただ、この論点を考えると、失われたリベラリズムの今日的意義を無条件に支持しうるかどうか、なかなか難しそうである。
もちろん、だからローゼンブラットの主張に意味がないというわけではない。ただ、この論点を考えると、失われたリベラリズムの今日的意義を無条件に支持しうるかどうか、なかなか難しそうである。
もうひとつはポピュリズムとかかわる。先に私は、本書はポピュリズム一般に対するリベラリズムの再活性化になるかもしれないと書いた。しかし他方、今日のポピュリズムについて言えば、むしろそれを後押しする要素もある。水島治郎は、ポピュリストに分類される政治家の用いる正当化言説が、かつてと今ではかなり異なっており、それがポピュリズム躍進の要因ではないかと論じている[13]。かつてはネオナチに代表されるあからさまな人種差別的主張を繰り返していたポピュリスト政党が、いまではより「リベラルな」主張によって人々に訴えかけるようになっている。例えば政教分離である。人種差別には賛同しかねる市民も、これなら賛成しやすい。これによってポピュリストはイスラムへの批判をおこないつつ、しかも人気を維持しうる。水島よりもはるかにポピュリズムに厳しいヤン=ヴェルナー・ミュラーもまた、近年のポピュリストの戦略変化には意識的である。だが彼にとって、この変化は大した問題ではない。排除のための看板が何であろうと、ポピュリズムは、「要するに、リベラリズムではない」のである[14]。
しかしリベラリズムの失われた歴史を知った我々は、果たしてここまで自信をもって言い切れるだろうか。ローゼンブラットは「リベラル」の多様性に繰り返し注意を促していた。だがその中で、ほぼ完全に一貫していたのは、頑固なカトリックに対するリベラルの強い反感であった。カトリックは「リベラルな憲法の敵であり、社会保障の敵であり、人間の知性を解放するすべての敵である」(134:『フランス便り』の引用)。まさに同じ主張によって、イスラムを攻撃するのが今日のポピュリズムである。ローゼンブラットは、女性差別や帝国主義に対しては、リベラルの意見が分かれていたと論じている。おそらくその改善もまた、「寛大さ」という理念からくるのだと想定しているのだろう(ただし説明がないため、何が要因で立場が決まっているのかが不明である)。しかし反カトリックだけは、ほとんど改善の余地もなさそうである。そして改善されぬままこのリベラリズムが失われてしまった。ローゼンブラットは、リベラリズムの豊饒な歴史を現代の議論に接続すべきだと考えているようにみえる。だが実際に接続したとき、それが彼女の期待通り反ポピュリズムとして機能する保証は特に存在していない――もしかしたら、コーヒーを買ってきてくれるポピュリストが増えるだけかもしれない。
[1] 藤原保信「競争の論理から共生の論理へ」(遺稿・未完)、『藤原保信著作集9――自由主義の再検討』(松園伸・山岡龍一[編])、新評論、2005年、156頁。
[2] 藤原保信『自由主義の再検討』(1993)、『藤原保信著作集9――自由主義の再検討』、147頁。
[3] 松尾哲也『神々の闘争と政治哲学の再生』、風行社、2018年、60, 66頁。
[4] レオ・シュトラウス、石崎嘉彦・飯島昇蔵(訳者代表)「序文」『リベラリズム――古代と近代』、ナカニシヤ出版、2006年、viii頁。
[5] レオ・シュトラウス、塚本智・石崎嘉彦(訳)『自然権と歴史』、筑摩書房、2013年、248頁。
[6] 石崎嘉彦「訳者あとがき」『リベラリズム――古代と近代』、440頁。
[7] シュトラウス「古典的政治哲学のリベラリズム」『リベラリズム――古代と近代』、43頁。なお、「自由主義的」を「リベラル」に訳し変えた。
[8] シュトラウス「一般教養教育とは何か」『リベラリズム――古代と近代』、7頁。
[9] 引用は、カス・ミュデ、クリストバル・ロビラ・カルトワッセル、永井大輔・髙山裕二(訳)『ポピュリズム――デモクラシーの友と敵』、白水社、2018年、121頁より(ただし訳語は変更した)。なおこの段落の私の議論は、専門家が疑義を呈するであろう見方、すなわちポピュリズムを大衆民主主義と直接結びつける見方を前提にしてしまっているが、ローゼンブラットがポピュリズムと「非リベラルデモクラシー」に言及するとき、彼女もまたこの結びつきを当然視しているように思われる。したがって、ここでの議論は、その限りにおいてのみの両者のつながりの話である。
[10] オルテガ・イ・ガセット、神吉敬三(訳)『大衆の反逆』、筑摩書房、1995年、107頁。「至上の寛容さ(la suprema generosidad)」は、「至上の高邁さ」とも訳しうる。よって、価値相対主義の表明ではない。本の内容からしても、オルテガが「なんでもあり」を認めているとは思えない。そもそも大衆の伸張に対して寛容ではない。
[11] ジョン・ロック、加藤節・李静和(訳)『寛容についての手紙』、岩波書店、2018年、77頁。
[12] 堤林剣「コンスタン――立憲主義の基礎づけを求めて」『岩波講座政治哲学3――近代の変容』(小野紀明・川崎修[編集代表])岩波書店、2014年、72頁。
[13] 水島治郎『ポピュリズムとは何か――民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社、2016年、222頁。
[14] ヤン=ヴェルナー・ミュラー、板橋拓己(訳)『ポピュリズムとは何か』、岩波書店、2017年、原注5頁(注5)。ミュラーはリベラリズムの定義をここでおこなっているわけではないが、その一つの要素は、おそらく権利を中心とする失われていないリベラリズムではないかと思われる。(同書69頁。)
