評者:潘 亮(筑波大学人文社会科学研究科専任講師)
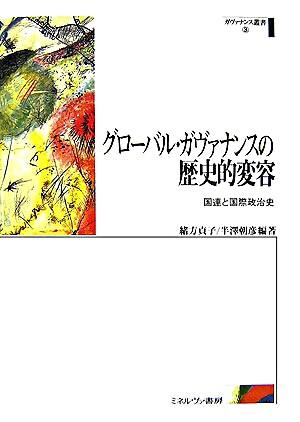 本書は二つの意味で国連に関する従来の研究と一味違うものである。まず、研究の対象であるが、国連の仕組みだけに的を絞る「孤立的な」国連研究ではなく、国連の役割を加盟国間で展開された国際政治のドラマのなかで検証する「開かれた」国連研究を目指す点で斬新な視点を提供してくれている。また、分析の手法に関しては、グローバル・ガヴァナンスというどちらかといえば冷戦後の国際情勢を議論する際によく使われる概念に焦点を当てたにもかかわらず、本書は国連をめぐる国際政治の変遷の経緯を一次資料に基づいて解明し、国連の発展のダイナミックスを歴史的な視角から明らかにしようとしている。こうしたアプローチが往々にして過去よりも未来への展望に重点を置く伝統的な国連及び国際機構論の研究に挑戦を挑む編著者の意欲の現われであるとすれば、本書の内容はこの目的に大いに貢献したといえよう。
本書は二つの意味で国連に関する従来の研究と一味違うものである。まず、研究の対象であるが、国連の仕組みだけに的を絞る「孤立的な」国連研究ではなく、国連の役割を加盟国間で展開された国際政治のドラマのなかで検証する「開かれた」国連研究を目指す点で斬新な視点を提供してくれている。また、分析の手法に関しては、グローバル・ガヴァナンスというどちらかといえば冷戦後の国際情勢を議論する際によく使われる概念に焦点を当てたにもかかわらず、本書は国連をめぐる国際政治の変遷の経緯を一次資料に基づいて解明し、国連の発展のダイナミックスを歴史的な視角から明らかにしようとしている。こうしたアプローチが往々にして過去よりも未来への展望に重点を置く伝統的な国連及び国際機構論の研究に挑戦を挑む編著者の意欲の現われであるとすれば、本書の内容はこの目的に大いに貢献したといえよう。
本書の議論は序章を除き、歴史的な文脈に基づいて、三部に整理することができるように思われる。その第一部に以下の三章が含まれている。
第1章 戦間期東アジアにおける国際連盟―国際協調主義・地域主義・ナショナリズム―(アントニー・ベスト)
第2章 中華民国の国際連盟外交―「非常任理事国」層から見た連盟論―(川島真)
第3章 帝国からガヴァナンスへ―国際連盟時代の領域国際管理の試み―(等松春夫)
これらの各章は国際連盟時代の事例を扱うものであるが、そこから提起された諸問題は何れも戦後の国際連合に受け継がれている。第1章のベスト論文では連盟によって代表されるグローバリズムの潮流が地域主義及びナショナリズムの流れと密接にかかわりながら、1920年代から30年年代に亘って東アジアの国際政治の形成と変容にいかなる役割を演じたかが主に日本と中国との関連で描かれている。その議論を別の角度から更に深めたのが第2章の川島論文である。本章は連盟内部での論争に注目した点で第1章と異なるものの、そこから浮かび上がった連盟とその「優等生」の中国と「反逆児」の日本との葛藤及びその背景はベスト論文でも触れられた東アジアにおける連盟の外交理念と地域主要国のそれとのぶつかり合いが逆に連盟そのものの有り方に変化を迫った事実を更に明確化したといえよう。連盟は本来欧州国際政治の変動によって生み出された国際機構であったが、その発展を阻害した最も重要な要因はむしろ欧州以外の地域における紛争処理にあった。日中の対立はその意味で氷山の一角にすぎず、連盟の抱えた問題は東アジアに止まらず、アフリカ、南太平洋まで及んでいたのである。この点を適確に捉えたのが第3章の等松論文である。限定的な形とはいえ、長らく国際政治を左右してきた列強の植民地支配にメスを入れた意味で、連盟による委任統治制度の実施は近代史のなかで特筆すべき一大事件であった。本章はこの連盟の努力をめぐる連盟、宗主国(統治受任国)並びに現地勢力間の利益の衝突もしくは妥協の過程を豊富な事例に依拠して実証している。ただ、この問題は第1章及び2章で提起された諸問題と同様、連盟の下で根本的に解決策が見出されなかったまま、次世代の普遍的国際機構に下駄を預けた形となった。この戦後の展開は第二部で次の各章によって検証される。
第4章 ソ連、国連と東アジアにおける冷戦―朝鮮戦争を中心に―(下斗米伸夫)
第5章 スエズ危機―国連の転回点―(W. R.ルイス)
第6章 イギリス帝国の終焉と国連―イギリスの対国連政策(1960-1961)―(半澤朝彦)
第8章 国連特別基金と台湾経済建設―国際機関と技術協力―(張力)
戦後の部分は引き続き東アジアをはじめ、欧米圏外の地域の紛争処理と国連との関連で議論が進められている。第4章の下斗米論文と第8章の張論文は第1章と第2章の分析に呼応する内容となっている。時代は冷戦に突入したが、東アジアの情勢は依然として混迷していた。かつての連盟「優等生」の中国は二つに割れ、台北に移った中華民国政府は影響力衰退のゆえに益々国連への依存を強めたが、北京の中華人民共和国は「国連の敵」として国際政治にデビューを果した。更に、ソ連の介入や北朝鮮の登場などにより、国連中心のグローバリズムは東アジアにおいて戦前以上の厳しい試練を迎えざるを得なくなった。同じことは国連を支えた欧米諸国についてもいえる。連盟によって中途半端な形で処理された植民地問題は再燃し、英仏などの老帝国は皮肉にも彼らによって創設された国連の場で反植民地主義の嵐に晒されるようになった。それは国際政治の転換を意味すると同時に、国連そのものの変容の予兆でもあった。この歴史的瞬間における大国の苦闘を詳細な史料によって見事に描き出してくれたのが第5章のルイス論文と第6章の半澤論文である。勿論、国連とそれが推進していた国際的協力は冷戦や民族解放の流れで消滅したわけではなかった。むしろ、本来想定しなかった分野で新たな活路を見出したのである。国連平和維持活動はその一つである。本書もこの点について、次の三論文を以って歴史、理論及び実践の角度から重厚な分析を展開している。
第7章 「非介入の名のもとでの介入」―ケネディ政権とコンゴ国連軍―(三須拓也)
第9章 平和維持活動-理論と実践―(ニール・S・マクファーレン)
第10章 国連平和維持活動の奇跡―PKOの光と影―(マラック・グールディング)
これら三章は歴史的な背景に言及しつつ、今日の国連平和維持活動の直面する諸問題をいかに理解すべきかについて、重要な手がかりを提示してくれた。また、その執筆者には外交史の専門家のみならず、政治学者や国連事務局の元高官も含まれているため、議論の幅が一段と広がっており、本研究に見られる学際的な特徴を遺憾なく発揮したと言っても過言ではなかろう。
以上のように、本書は国際機構と加盟国との関係に注目し、外交史と国際政治学双方の問題意識を視野に入れた「開かれた国連研究」の成功例として位置づけられるべきものである。国連問題に関心を有する研究者や一般読者にとって本書は必読文献になることは言うまでもないであろう。他方、ごくわずかだが、多少違和感を感じたところ、もしくは更に掘り下げてほしいところも二点ほどあげられる。まず、国際連盟を扱う部分は大変バランスの取れた構成になっているのに対し、国際連合の部分については若干英国の政策に集中し過ぎたきらいがあるように思える。勿論、これは執筆者の専門分野などを考えると、止むを得ないところもあることは承知しているが、例えば冷戦期の国連における多国間外交に多大なインパクトを与えた中国の対外姿勢の変化(反国連の旗手から国連擁護論者への転換)、1960年代末以降「国連離れ」へ急速に転じていった米国の国連政策の変容、もしくはいわゆる「南北問題」の変遷と国連との関係などに関する議論を補強することができれば、戦後の国際関係における国連の役割がより鮮明に映し出されるのではなかろうか。また、政策分野の面で経済開発や社会問題を扱う内容の比重はやや軽すぎるといえよう。これらは長い間国連にとっていわば本領が発揮できる数少ない分野であり、グローバル・ガヴァナンスを論じる上でも無視できない存在であるが、第8章での説明的な記述を除けば、余り言及されなかったのは惜しいことである。もっとも、いかにすぐれた映画でも「残念な芸術」であるとよく言われているように、学術研究についても完璧さを追求する必要はない。完璧主義よりも「発展性」の方がはるかに重要かもしれない。その点に鑑み、ほぼ全ての章において独立した著書に発展できるほどの問題提起が秘められている本書は第一級の研究成果との評価に相応しいものと認めねばならない。そして、国際組織の役割を加盟国の対外政策との関連で、且つ歴史的な観点から解明しようとする試みは本書をもって終ってしまわないことを祈ってやまない。
0%

INQUIRIES
お問合せ
取材のお申込みやお問合せは
こちらのフォームより送信してください。