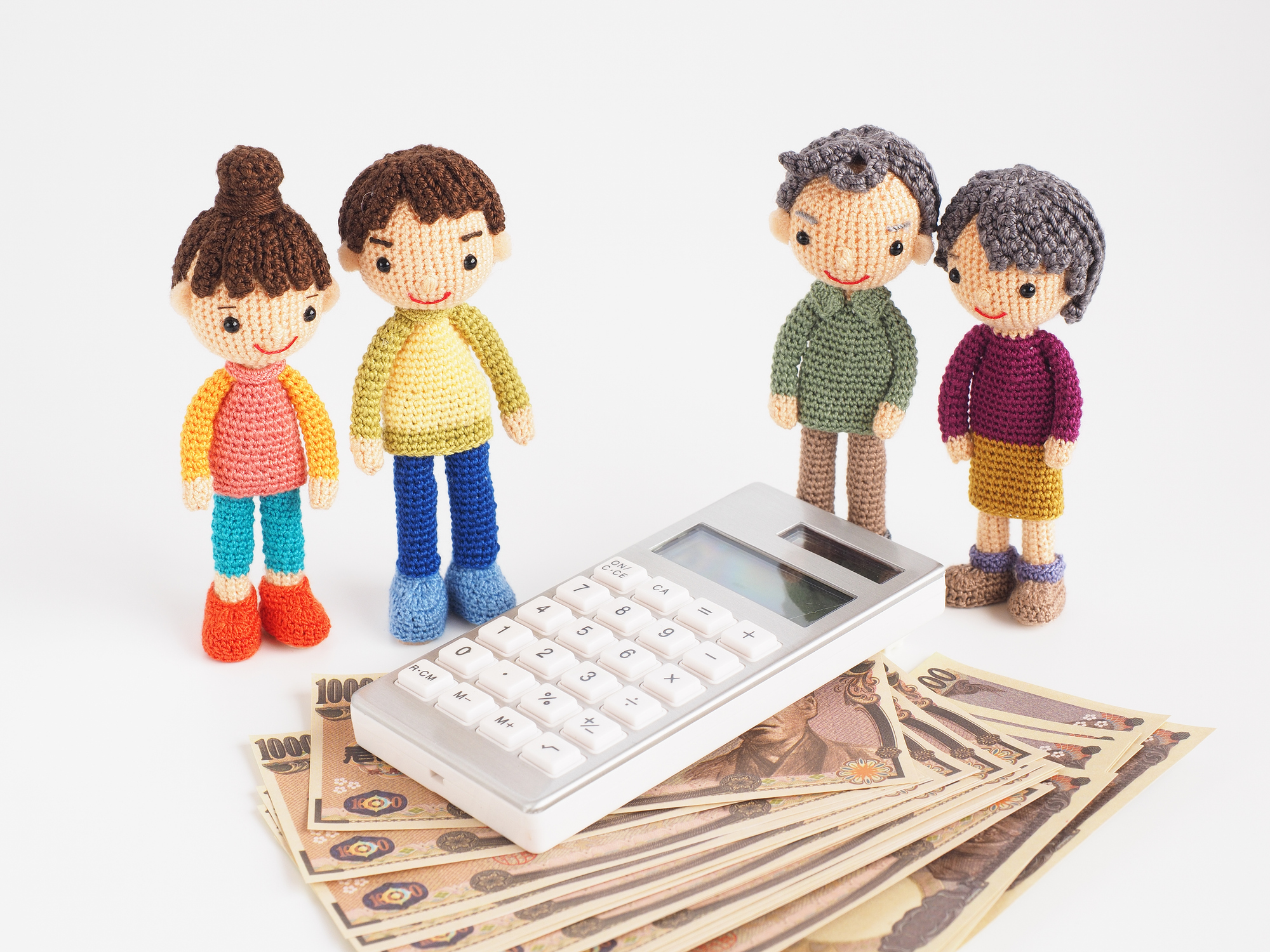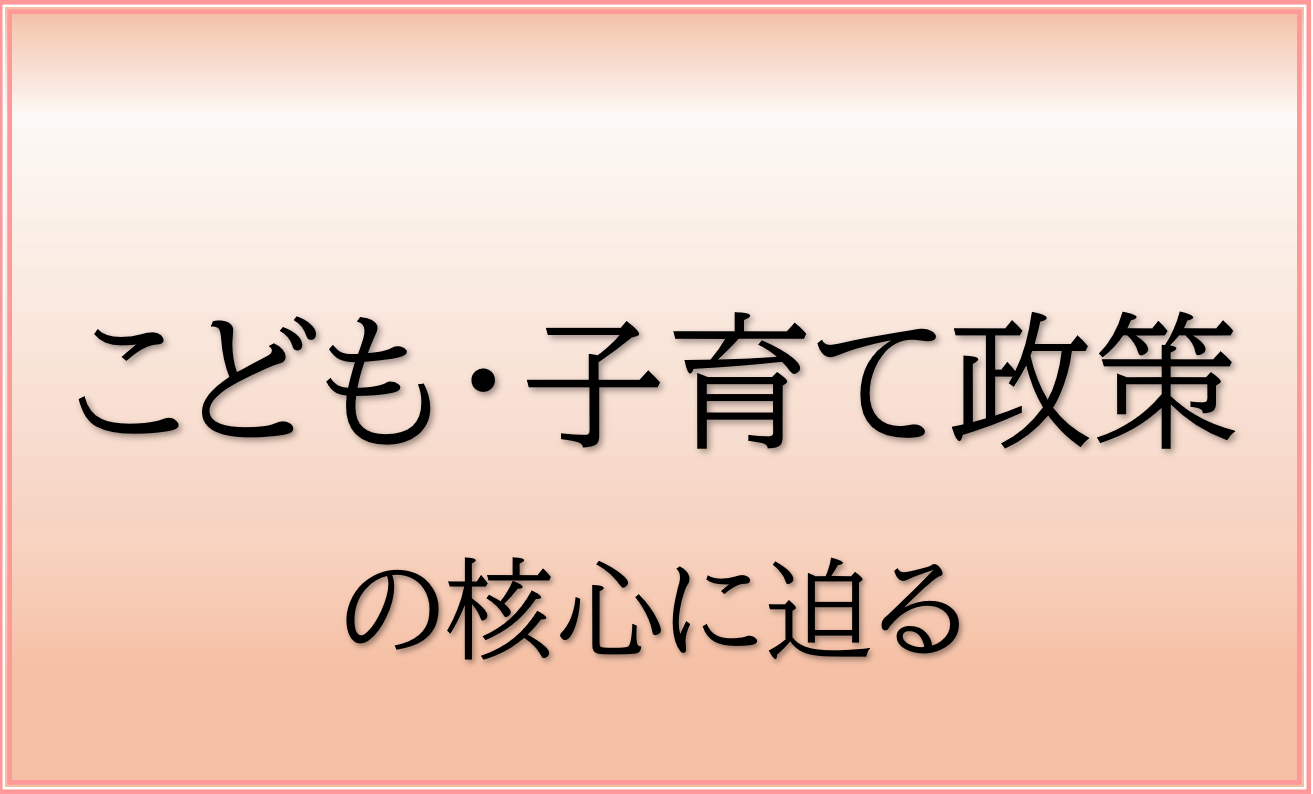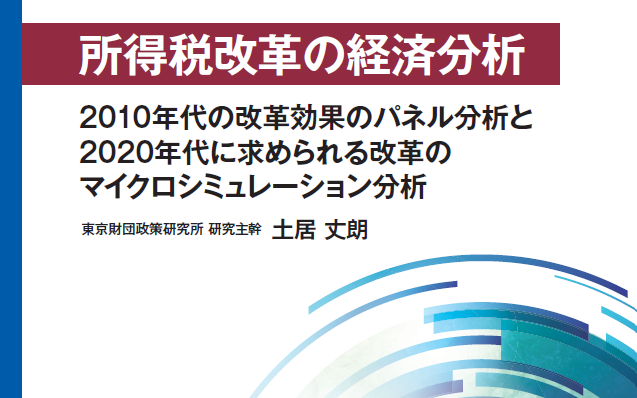X-2025-017
|
税・社会保障研究 レビュー・論考・コラム 令和7年4月より、「税」や「社会保障」をテーマとしたコラム(Review)を、以下の執筆者が交代で執筆してまいります。掲載されたコラムは「まとめページ」からご覧いただけます。 |
小学5年生の算数で、百分率を学ぶ。それがわかれば、次の問題に答えられるだろう。
*****
ある家族で今年稼いだ収入は合わせて400万円でした。そこから、稼いだ収入に対して税金が5%、またべつに社会保険料というものも15%とられました。とられた後に残ったお金すべてで、家族みんなでいろいろなものを買いました。そのとき、買ったものには消費税がかかり、払ったお金のうち9%になりました。
問1 稼いだ収入からとられた税金と社会保険料をのぞいた残りのお金は、稼いだ収入の何%ですか。
問2 買ったものにかかった消費税は、稼いだ収入の何%ですか。
問3 この家族で、来年旅行に行く計画を立てており貯金をするため、税金と社会保険料をとられた後に残ったお金の半分は貯金に回し、もう半分でいろいろなものを買いました。このとき、かかった消費税は、稼いだ収入の何%ですか。
問4 問3のかかった消費税ととられた社会保険料は、どちらが多いですか。
*****
小学5年生なら解けるこの問題の答え合わせをしよう。
問1は、税金(所得税と個人住民税を意図している)と社会保険料を合わせると、20%(=5%+15%)とられるから、残りのお金(可処分所得)は稼いだ収入(課税前収入)の80%になる。
問2は、残りのお金(可処分所得)が稼いだ収入の80%で、それをすべてものを買う(消費)のに費やし、そのうち9%は消費税として払うから、かかった消費税は稼いだ収入(課税前収入)の7.2%(=80%×9%)となる。
問3は、残りのお金(可処分所得)が稼いだ収入の80%で、その半分(50%)をものを買う(消費)のに費やし、そのうち9%は消費税として払うから、かかった消費税は稼いだ収入の3.6%(=80%×50%×9%)となる。
問4は、問3でかかった消費税は稼いだ収入の3.6%、とられた社会保険料は稼いだ収入の15%だから、とられた社会保険料の方が多い。
この問題に答えられれば、消費税減税よりも社会保険料負担の軽減の方が重要であることが理解できる。消費税の負担よりも社会保険料の負担の方が重いのである。前掲の問題は、小学5年生で習う百分率で答えが完結しているから、年収がいくらかは関係がない(問題では年収400万円としたが、400万円は解答の中では一度も使われていない)。つまり、低所得層だけでなく中高所得層も同様の家計の負担構造であることを意図している。
現に、所得税と個人住民税の負担は、低中所得層は問題文にある程度の負担しかしていない。その一方で、社会保険料の負担は多くの人が15%程度である。
他方、消費税の負担は、可処分所得をすべて消費に回しても、課税前収入に対する消費税負担率は高くとも7.2%である。[1] さらに、いくばくかは貯金をすることが考えられるため、貯蓄率が高くなるにつれて、課税前収入に対する消費税負担率はさらに低くなる。他方、社会保険料は、もはや天引きされており、逆立ちしても家計の負担は軽くならない。
加えて、2024年の定額減税を思い出せば、消費税減税しても家計は救われないことが、前掲の問題を解いた後だと理解できる。そもそも、2024年に定額減税があったことさえ忘れている読者もおられるだろうし、ましてやとても恩恵が大きかったという国民の好評はほとんど聞かない。
そんな2024年の所得税と個人住民税の定額減税は、1人4万円の減税だった。定額減税だから、百分率で表すのは難しいが、世帯年収400万円の家庭で、5%の所得税と個人住民税を負担しているとすれば、20万円の負担となる。そこに、4人家族だと合計で16万円の減税となる。ここで負担率に換算すると、400万円に比して16万円だから、4%である。
この定額減税が、忘れられさえすれ、好評はほとんど聞かないのだから、同程度の負担軽減となる消費税減税をしたところで、その後に国民の好評を博するような結果になるはずがない。
2024年度の定額減税と同程度の負担軽減となる消費税減税とは、どんなものか。それを前掲の問題で示せば、消費税率を半減させた(消費税率を10%から5%に引き下げる等)ときの問2の消費税負担か、消費税を全廃できたときの問3の消費税負担かという程度である。ほとんど貯蓄していない家計は、消費税率を半減させても、2024年の定額減税程度の負担軽減しかないということである。
負担が重いのは、消費税ではなく社会保険料である。その本質を見誤ってはならない。真に意味のある社会保険料負担の軽減を図ることで、家計は救われる。
ここで、より厳密なデータに基づいて、先の家計の負担構造についてみておこう。政府の公式な統計で、所得税と個人住民税の負担と社会保険料の負担に加えて、消費税の負担も網羅的に公表されているものはまずない。消費税の負担は、家計の消費構造に基づいて推計しなければならない。
そこで、コロナ禍の影響を受けていない時期で最も新しいデータとして、2019年の家計の所得と消費の構造について分析できる「日本家計パネル調査(JHPS)」を用いて、所得税と個人住民税、社会保険料、消費税の負担構造について分析した。「日本家計パネル調査(JHPS)」は、慶應義塾大学 経済学部附属経済研究所パネルデータ設計・解析センターが収集している。そして、所得階級を5分位に分けてその負担構造を示したのが、表1である。
表1 所得階級別所得税、個人住民税、社会保険料、消費税の年間負担額
|
所得階級五分位 |
世帯の |
所得税・住民税 |
社会保険料 |
消費税 |
|||||
|
年間収入 |
所得税 |
住民税 |
年金 |
医療 |
介護 |
||||
|
Ⅰ(最下位20%) |
~440 |
7.4 |
2.0 |
5.4 |
40.4 |
25.7 |
13.3 |
1.4 |
14.7 |
|
Ⅱ |
441~600 |
21.8 |
6.7 |
15.1 |
67.0 |
42.5 |
22.3 |
2.2 |
19.1 |
|
Ⅲ |
601~755 |
37.6 |
13.0 |
24.6 |
90.1 |
57.0 |
29.8 |
3.3 |
22.2 |
|
Ⅳ |
756~993 |
61.1 |
24.8 |
36.3 |
117.2 |
74.0 |
38.6 |
4.6 |
26.2 |
|
Ⅴ(最上位20%) |
994~ |
147.3 |
78.7 |
68.6 |
180.6 |
113.8 |
59.1 |
7.7 |
34.1 |
単位:万円
資料:総務省「2019年全国家計構造調査」、土居丈朗 (2020) 「人口減少が及ぼす社会保障財源への影響」, 『「人口減少と経済成長に関する研究会」報告書』, 第8章. https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2019/jinkou_report08.pdfより筆者作成
そして、表1について、課税前収入に比した負担率を示したのが、表2である。
表2 所得階級別所得税、個人住民税、社会保険料、消費税の負担率
|
所得階級五分位 |
階級平均 |
所得税・住民税 |
社会保険料 |
消費税 |
|||||
|
収入(万円) |
所得税 |
住民税 |
年金 |
医療 |
介護 |
||||
|
Ⅰ(最下位20%) |
320.5 |
2.3 |
0.6 |
1.7 |
12.6 |
8.0 |
4.1 |
0.4 |
4.6 |
|
Ⅱ |
518.4 |
4.2 |
1.3 |
2.9 |
12.9 |
8.2 |
4.3 |
0.4 |
3.7 |
|
Ⅲ |
671.2 |
5.6 |
1.9 |
3.7 |
13.4 |
8.5 |
4.4 |
0.5 |
3.3 |
|
Ⅳ |
861.5 |
7.1 |
2.9 |
4.2 |
13.6 |
8.6 |
4.5 |
0.5 |
3.0 |
|
Ⅴ(最上位20%) |
1318.6 |
11.2 |
6.0 |
5.2 |
13.7 |
8.6 |
4.5 |
0.6 |
2.6 |
単位:%
出所:筆者作成
前掲の問題は、デフォルメして見せたものだが、表2とかなり近似していることがわかる。所得税には累進課税されているので、高所得層になるとより高い負担率になっている。消費税は、一見すると逆進的にみえるが、それは貯蓄率が高所得者ほど高いためであり、前掲の問題の問4でみたように、同じ所得でも貯蓄率が高ければ消費税の負担率は低くなることが現れているまでである。
表2をみても、どの所得層でも、消費税負担率よりも社会保険料負担率の方が高い。前掲の問題は、フィクションではなく、客観的な現実を描写したものなのである。
確かに、現役世代の社会保険料負担の軽減については、政府も真剣にその方策について検討している。ただ、給付面の社会保障改革もセットで行わなければ実効性が伴わないため、社会保障制度に詳しくない国民からすると、負担軽減論議の手応えが感じにくいのかもしれない。
そうであっても、消費税減税は家計の負担にまつわる問題を解決することにならない。消費税減税で本質から目をそらすのではなく、社会保険料負担の在り方について直視する政策論議が必要である。
[1] 問題文では、簡単化のため、消費額の9%と設定しているが、現実にもそうであるといえる。消費税率が10%のとき、消費税込みの商品の値段が110円だと、消費税抜きの値段は100円(=110÷(1+0.1))である。だから、消費税込みの商品の値段が100円だと、消費税抜きの値段は100÷(1+0.1)=約90.9円で、消費税は約9.1円である。したがって、消費額の約9%が消費税となる。もちろん、わが国の軽減税率は8%であり、それを含めると、消費税負担率は、さらに低いのが現実である。