評者:佐藤 晋(二松学舎大学国際政治経済学部教授)
本書の特徴
本書は、1982年から1987年にかけて首相を務めた中曽根康弘に対するインタビュー調査の記録である。中曽根元首相に対する聞き取りの記録としては、『天地有情』などがあり、本人が出版した回顧録・著作の類も数多く存在する。そのような状況で、本書が刊行された意義は何であろうか? われわれ歴史研究者が回顧録やインタビュー調査を利用する価値は、(1)未知の事実の発見、(2)既知の事実の当事者による確認、(3)既知の事実の背後にあった動機の理解、にあるであろう。とりわけ、中曽根氏のような重要人物を対象とする場合は、(3)のポイント、すなわち過去に実施された重要な政策について、最高意思決定者を長く務めた人物に直接その動機または意図を問いただすという点にある。この観点から本書は、十分に研究者のニーズを充足するものとなっている。それでは、以下、この点を具体的に見ていく。
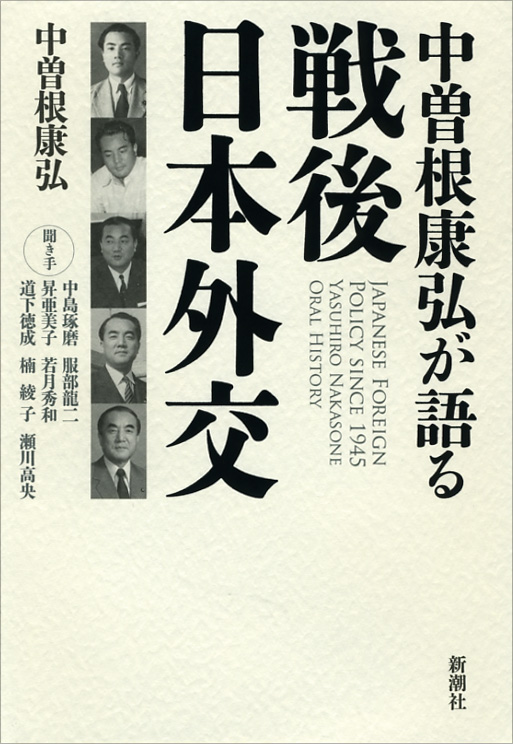
野党時代の思想
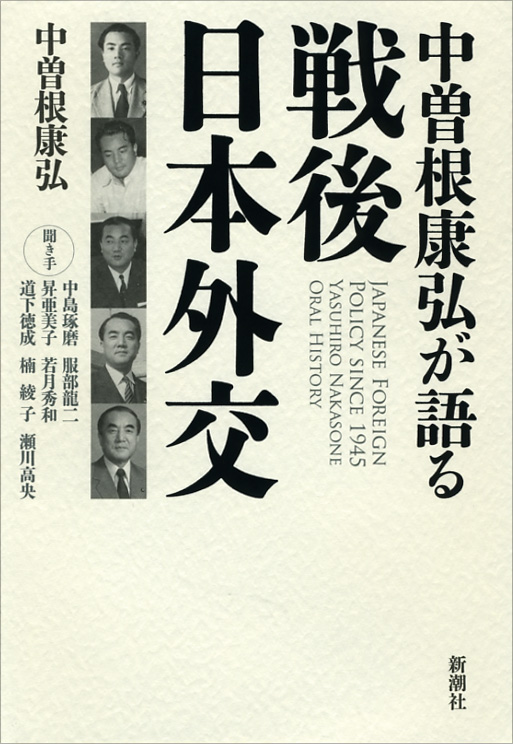
本書では、まず「反吉田」保守政治家としての立場・思想がおそらく初めて本人の口から率直に語られていることが注目される。青年将校としての威勢の良い「吉田政治」批判の言説の背景にあった考えとはなんであろうか? まず、安保条約に反対(本会議欠席)した中曽根氏の考えとは、主にその内乱条項、無期限を問題としてのものであったという。他方、当時自らが唱えていた有事駐留論が実現見込みはないことは熟知しており、米軍撤退の主張もあくまでも対米自主意識の表明としてのものであって、その証拠に極東条項には反対していなかったという。さらに核抑止面から、米軍駐留と、アメリカの軍事協力に依存することは避けられないことも認識していたという。つまり、冷戦初期における野党時代の中曽根氏は、その主張はともかく、本心ではアメリカの「核の傘」をはじめとして、アメリカの軍事力に多大に依存することはさけられないと考え、かつ極東の安全保障の観点からも日本における米軍のプレゼンスとその極東における軍事活動を望ましいと考えていたようである。ただ、独立国の国民の心構えとして自国の防衛は自らがなすという精神を涵養することが念頭にあったとものと理解できる。
また、改進党などが掲げた修正資本主義は、やはり有権者向けの政治的アピールを狙ったもので、戦前の政友会の流れをくむ自由党流のレッセフェールへのアンチテーゼであったこと、さらに保守合同に反対したのは古い体質が際立った自由党に対して清新なイメージの民主党の優勢を見込んだためであったことが吐露されている。さらに、右翼的・タカ派的と見られた中曽根氏が台湾寄り姿勢から距離をとったのは、将来対中関係打開において働けるような条件を維持するためであったという。
また、改進党などが掲げた修正資本主義は、やはり有権者向けの政治的アピールを狙ったもので、戦前の政友会の流れをくむ自由党流のレッセフェールへのアンチテーゼであったこと、さらに保守合同に反対したのは古い体質が際立った自由党に対して清新なイメージの民主党の優勢を見込んだためであったことが吐露されている。さらに、右翼的・タカ派的と見られた中曽根氏が台湾寄り姿勢から距離をとったのは、将来対中関係打開において働けるような条件を維持するためであったという。
「イメージ戦略」
以上は青年将校時代の言説の背景であるが、評者が本書から受けた強い印象は、当時から今に至るまで自らの政治家としてのイメージをどのように示すかについて精力を費やす姿勢である。具体的には、自身につきまとったタカ派イメージを払拭しようとした努力と、アメリカから自立した独自の考えで外交を押し進めたことを今になっても強調しようとする点である。これらが、当時から心がけていたことなのか、それとも現在において自分の政治人生を振り返って、そのようなイメージを世間に広めたいからなのかは判然としない。ただし、重要な点としては、中曽根氏は、自分のイメージとともに、いやそれ以上に日本という国家のイメージを対外的に「都合」よく提示しようとする意図が極めて強かったことである。
まず、佐藤内閣において、「非核二原則」を唱えていた佐藤首相を、「非核三原則」に変更させたという点がある。氏にとって「非核三原則」は、あくまで政治的ジェスチャーとしての「建前」であって、これは世界、特にアジア向け、さらに国民に向けて発信されるべき「日本イメージ」であった。つまり、具体的には沖縄返還が中途半端ではないことを国民に示すためのスローガンであり、またアジア諸国に日本軍国主義復活の危惧を抱かせないためにも必要なスローガンであった。他方、アメリカ向けには、非核「二原則」の制度化には特別な重要性があった。氏自身、当時から日本が核武装することは、アメリカの反対、アジア諸国の反発、国民感情を考えると不可能であると認識していた。ただし、核武装の意思も能力もない、というのでは周辺諸国に軽んじられるので、日本としては「核武装できる能力はあるがしない」と示すことが対外抑止上好ましいと考えた。そこで、原子力の平和利用、ロケット技術の推進という科学技術政策は、「核武装できる能力はある」ことを示すために推進したという。さらに、アメリカに「日本は核開発能力はあるが、核武装はしない」ことを知らしめておけば、日本の核武装を嫌うアメリカとしては、そうならないために、ならばアメリカが核の傘をさしかけておこうとなる、すなわちアメリカの拡大核抑止の対日保証が安定化するのであった。後述するように中曽根氏は、「三原則」目が実際には守られていないことも重々承知していたが、むしろ日本に核が持ち込まれることによって日本の安全が保てるのならば望ましいという考えであった。ようするに「三原則」は、裏でいろいろあることはそれとして、これを表面的に堂々と宣言することに、国民向け、アメリカ向け、アジア向けの価値があったのである。
一方、防衛庁長官時代に唱えた「自主防衛五原則」も、主な狙いは「日本が主、アメリカが従」と宣言することで国民に防衛の責任を自覚してもらうことにあったという。したがって、ニクソン・ドクトリンに示されたアメリカの退潮も、そこに日本への防衛力負担要求が見て取れたこともあり、氏にとっては日本の防衛力を充実させるチャンス(口実)として認識されていた。それ以前から常々言っていた米軍撤退、基地縮小は、対米対等を主張する気概をしめすスローガンと位置づけられており、そもそも実際に米軍がアジアから撤退することや、特に前線の日本から出ていくことは全く想定できないものであった。また、中曽根氏は、この「五原則」において文民統制の明文化をも主張していたが、それもやはり国民向け・アジア向けにポイントが稼げる、という意味合いからであった。
次に、これも当時中曽根氏が唱えていた「非核中級国家」論であるが、ここに何か具体的な国家像があったというわけではなく、核武装もしないし「大国」にもならないと言っておけば、アジアとの関係上都合がいいとの考えから持ち出されたものであった。つまり、「自主防衛」の「大国」だと刺激が強すぎ、核武装した「大国」だとなおさら問題が生じてしまうわけである。また、これと関連して、中曽根氏は70年9月の「中曽根・レアード会談」が「中曽根=核武装論者」イメージを払拭できた点で成功だったとし、これにより後に自分が首相になる障害がなくなったと回想している。やはり、当時の中曽根氏にも、アメリカに警戒された政治家は首相にはなれないといった認識があったことがうかがえる。
まず、佐藤内閣において、「非核二原則」を唱えていた佐藤首相を、「非核三原則」に変更させたという点がある。氏にとって「非核三原則」は、あくまで政治的ジェスチャーとしての「建前」であって、これは世界、特にアジア向け、さらに国民に向けて発信されるべき「日本イメージ」であった。つまり、具体的には沖縄返還が中途半端ではないことを国民に示すためのスローガンであり、またアジア諸国に日本軍国主義復活の危惧を抱かせないためにも必要なスローガンであった。他方、アメリカ向けには、非核「二原則」の制度化には特別な重要性があった。氏自身、当時から日本が核武装することは、アメリカの反対、アジア諸国の反発、国民感情を考えると不可能であると認識していた。ただし、核武装の意思も能力もない、というのでは周辺諸国に軽んじられるので、日本としては「核武装できる能力はあるがしない」と示すことが対外抑止上好ましいと考えた。そこで、原子力の平和利用、ロケット技術の推進という科学技術政策は、「核武装できる能力はある」ことを示すために推進したという。さらに、アメリカに「日本は核開発能力はあるが、核武装はしない」ことを知らしめておけば、日本の核武装を嫌うアメリカとしては、そうならないために、ならばアメリカが核の傘をさしかけておこうとなる、すなわちアメリカの拡大核抑止の対日保証が安定化するのであった。後述するように中曽根氏は、「三原則」目が実際には守られていないことも重々承知していたが、むしろ日本に核が持ち込まれることによって日本の安全が保てるのならば望ましいという考えであった。ようするに「三原則」は、裏でいろいろあることはそれとして、これを表面的に堂々と宣言することに、国民向け、アメリカ向け、アジア向けの価値があったのである。
一方、防衛庁長官時代に唱えた「自主防衛五原則」も、主な狙いは「日本が主、アメリカが従」と宣言することで国民に防衛の責任を自覚してもらうことにあったという。したがって、ニクソン・ドクトリンに示されたアメリカの退潮も、そこに日本への防衛力負担要求が見て取れたこともあり、氏にとっては日本の防衛力を充実させるチャンス(口実)として認識されていた。それ以前から常々言っていた米軍撤退、基地縮小は、対米対等を主張する気概をしめすスローガンと位置づけられており、そもそも実際に米軍がアジアから撤退することや、特に前線の日本から出ていくことは全く想定できないものであった。また、中曽根氏は、この「五原則」において文民統制の明文化をも主張していたが、それもやはり国民向け・アジア向けにポイントが稼げる、という意味合いからであった。
次に、これも当時中曽根氏が唱えていた「非核中級国家」論であるが、ここに何か具体的な国家像があったというわけではなく、核武装もしないし「大国」にもならないと言っておけば、アジアとの関係上都合がいいとの考えから持ち出されたものであった。つまり、「自主防衛」の「大国」だと刺激が強すぎ、核武装した「大国」だとなおさら問題が生じてしまうわけである。また、これと関連して、中曽根氏は70年9月の「中曽根・レアード会談」が「中曽根=核武装論者」イメージを払拭できた点で成功だったとし、これにより後に自分が首相になる障害がなくなったと回想している。やはり、当時の中曽根氏にも、アメリカに警戒された政治家は首相にはなれないといった認識があったことがうかがえる。
「密約」問題
ところで、いわゆる「密約」問題の中に、核搭載艦船トランジットに関する「密約」があるが、中曽根氏は、防衛庁長官就任後に、トランジットは事前協議対象外という「密約」を知ったという。これについての所感をあえて問われれば、陸揚げには反対だが領海通過・寄港はやむを得ないと答えるが、実際のところは、この密約は「当然だろう。外には言えないことなので、その時には密約の必要があったんだな」といった感じではなかったかと、思われる。要するに、中曽根氏にとって、持ち込みまで禁じた「非核国家」イメージは、あくまでも国民向け、アジア向けに必要な建前であった。安全保障上の観点からは、持ち込みは当然過ぎるほど当たり前に必要な話であった。ただし、それ以外の「二原則」については上述したような対米政策上の重要な意義があった。これとの関連で、NPT批准について氏は消極的であったが、これも「能力はあるが、あえて核武装しない」ことによる外交的効果は、自ら宣明する場合は有効だが、国際条約で制限されるとその効果はなくなるとの考えからであったという。
安全保障環境認識
では、次に現実の対外脅威認識について検討する。中曽根氏にとって外部からの脅威とはソ連の脅威を意味した。中国については、その核実験は予想外で脅威を感じたものの、現実の脅威についてはたいしたことはないと見ていた。一方、ソ連については、その北海道上陸を現実の脅威と考えていた。このような対ソ脅威感から、1970年代以降における米軍の撤退を、ソ連との軍事バランスが崩れることにつながるととらえて懸念していたという。ただし、在韓米軍撤退問題については、韓国に米軍がいることが象徴的に重要であって、その兵力の多寡は問題でなかったという。本書で初めて気づかされたのは、中曽根氏が日米安保条約第6条に関して、「極東」の範囲に日本海が含まれるものとして安保を運用してもらいたいと考えていたことである。ここからも、氏が、ソ連に対する強い脅威感とともに、実は米軍への強い依存心を抱いていたことがわかる。他方、アジアにおける脅威としては、ソ連が直接日本に侵略を仕掛けるという懸念のほかに、中ソ軍事衝突への危惧があったが、氏はソ連が中国と本気で戦争しようとしていたとは全く思っていなかったとし、国境紛争をめぐる圧力のかけ合いととらえていたという。
さらにソ連の脅威はブレジネフ時代に太平洋に海軍を進出させたこと、アジアにおいてSS-20を配備したことによって増幅された。ただし、アフガン侵攻については、これはソ連のいつもの膨張主義に違いないが、防衛的意図から出たもので、地域も戦略的価値のあるアフガン一国のみに限定されるという認識であったという。もっとも、その後の世界情勢において、米中対ソの構図が明確化したことを強く意識した。そこで、中国をどの程度強化して、ソ連の脅威に対するバランスに寄与させるかという論点になるのであるが、この点は後述する。また、氏の対ソ脅威認識にはソ連の東欧に対する侵略的な政策が強い影響を与えていたことがわかる。
一方、米中接近は全く予想できず、それは中曽根氏にとってまさしく「ショック」であった。その後、田中角栄内閣において対中国交正常化が実現するが、氏によれば田中は、当初、対中国交正常化に躊躇していたといい、その田中を踏み切らせたのは中曽根氏自身と三木・大平であったとする。後に争点となる「反覇権条項」については、中国が対ソ防衛配慮から日本を味方に引き込もうとするものととらえて歓迎したという。つまり、中国の国力増大と米中関係の強化は日本にとって悪いことではなかったのである。もっとも中曽根氏は、中国の次は日ソ友好条約締結を実現するつもりであった。中曽根氏にとってソ連との関係打開とは北方領土問題の解決を意味しており、日本は中国、アメリカとの関係を強化した上で、対ソ領土問題交渉で強く出る狙いがあったという。
さらにソ連の脅威はブレジネフ時代に太平洋に海軍を進出させたこと、アジアにおいてSS-20を配備したことによって増幅された。ただし、アフガン侵攻については、これはソ連のいつもの膨張主義に違いないが、防衛的意図から出たもので、地域も戦略的価値のあるアフガン一国のみに限定されるという認識であったという。もっとも、その後の世界情勢において、米中対ソの構図が明確化したことを強く意識した。そこで、中国をどの程度強化して、ソ連の脅威に対するバランスに寄与させるかという論点になるのであるが、この点は後述する。また、氏の対ソ脅威認識にはソ連の東欧に対する侵略的な政策が強い影響を与えていたことがわかる。
一方、米中接近は全く予想できず、それは中曽根氏にとってまさしく「ショック」であった。その後、田中角栄内閣において対中国交正常化が実現するが、氏によれば田中は、当初、対中国交正常化に躊躇していたといい、その田中を踏み切らせたのは中曽根氏自身と三木・大平であったとする。後に争点となる「反覇権条項」については、中国が対ソ防衛配慮から日本を味方に引き込もうとするものととらえて歓迎したという。つまり、中国の国力増大と米中関係の強化は日本にとって悪いことではなかったのである。もっとも中曽根氏は、中国の次は日ソ友好条約締結を実現するつもりであった。中曽根氏にとってソ連との関係打開とは北方領土問題の解決を意味しており、日本は中国、アメリカとの関係を強化した上で、対ソ領土問題交渉で強く出る狙いがあったという。
資源外交と田中角栄
本書の証言で新味があった点は、ロッキード事件に関する解釈についてで、「田中がメジャーズの尾を踏んだ」という説、一部に流布している一種の陰謀論を主張していることである。第一次石油危機をめぐる日本の資源外交においては、「日の丸原油」確保を掲げて二国間で確保したい通産省や中曽根と、メジャーズの力を認識し、アメリカの圧力を理解し、国際協調の枠組みでやるほかなしと考えていた外務省や大平の勢力があったという。これらはすでに知られているが、興味深いのは氏が自らも「メジャーズは怖い」と証言していることである。例えば、73年11月のキッシンジャーとの会見で「脅迫めいたこと」を口にされたといい、さらには「アメリカ即メジャー」とまで述べ、石油消費国会議もメジャーが中心になって開催されたものという。
首相時代の回想
中曽根内閣期に進展を見た日米中関係は、氏の言うところの「中国を害のない範囲内で味方につけ、対ソ共同戦線を張ろうという」戦略に拠ったもので、日米同盟に中国を引き込もうというものであった。本人の言を借りれば、「NATOに匹敵するアジアの壁」を作ろうとするものであったという。そこで、82年以降に認識しえた中ソ関係改善は懸念材料であったが、しかし、氏は国境問題などの存在から関係改善はしばらくないと判断していたという。そこで、「アジアの壁」の対象であったソ連であるが、この時期は、ソ連によるSS-20の極東への移転問題が最重要テーマであった。ソ連による日米離間策とも言えたこの動きは、日本にとっての深刻な脅威を形成するものと見られた。ただし、82年末に先鋭化したソ連による西欧での削減分の極東移転の動きには、中曽根氏にはアジアのことはほとんど頭にないと思えたレーガンからの再三の説得にも強硬に反対して、アジアへの移転は認められないというアメリカの対ソ交渉方針決定を導いたという。
中曽根氏は、自身の内閣以前には「東南アジア政策はないがしろだった」とし、名高い福田「ドクトリン」も高圧的で逆効果であったと述べる。そこで、東南アジア外交を重視したというが、それは中国がインドネシアなどに影響力を伸ばしてきているという懸念と、なによりASEAN諸国が石油の輸入ルート上にあることが重要であったであった。これに関連して、シーレーン防衛に関する日本の構想は1,000海里(台湾:バシー海峡・ルソン海峡・グアム島付近まで)についての通商航路の防衛であったとし、氏が強調する点は、これはアメリカからの防衛努力要請圧力の結果採用したものではなく、「自主防衛の一環」であったということである。
中曽根内閣期の中国政策については、おおむねこれまでに知られていた範囲の証言である。氏は、日米安保条約も容認していた胡耀邦のことを、親日家であり、反対意見を抑えて親日的政策を敢行していると見ていたのという。また、第二次円借款の供与額は、大平よりも多くしようという意図も働いたというが、主な狙いは、中ソ対立を現状のまま維持し、中国を自由主義陣営に入れてソ連に対抗させるためであった。その際、中国を過剰に強化してしまうのでないかとして日本側の懸念材料であった米国による対中技術移転についても、アメリカは日本に害のある所まではやらないだろう、との楽観的な観測から反対しなかったようである。氏としては、当時の国際関係においてはソ連こそが最大の脅威であって、一方の中国は中小国クラスで、西側にとってはあくまでも利用するカードとしての存在であったという。また、レーガン政権には台湾問題があって、対中関係改善が遅延しがちな一方で、日本は台湾問題がないという意味でフリーハンドを得ていたという。
この中国に対する経済協力について、中曽根氏はこれを賠償の代わりと認識しており、むしろ賠償を受けとらなかったのはそれが中国のプライドを傷つけるからであったとも述べている。もちろん、対中円借款は長期的には日本の利益に跳ね返るという認識もあった。ただし、対中円借款が中国の強大化につながり、対日脅威になるという危惧もある程度は共有していたようである。ちなみに氏は対韓円借款も賠償の代わりという認識であった。
次に、靖国神社参拝問題であるが、これを氏は、信教の自由に基づいた公式参拝であったという。靖国参拝問題における対中配慮については、事前の情報では「避けて欲しい」という程度のことであったので実施したが、実際にはあまりに反発が強かったため、親日派の立場を配慮して中止したという。さらに、中国の反発以降持ち出されたかの印象がある分祀論は、天皇が靖国に行けるようにするためというのがより重要な理由であったようである。その後の胡耀邦の失脚については、今日では親日が原因となったのではないと認識しており、ただしその口実にはなったのではないかと述べている。
日ソ関係では、大韓航空機撃墜事件を、逆にソ連の政策転換のきっかけになるのではないかととらえ、その後のソ連の働き掛けに呼応することを意図したという。ただし、同時にチェルネンコ新体制成立が転換のきっかけであったとも述べている。また、レーガン政策の対ソ政策転換に遅れないようにとも考えたとも述べている。ともかく、最終的にはゴルバチョフ登場によって、伝統的に対立していたソ連国内の「ヨーロッパ派」と「アジア派」が、前者の勝利に帰結し、アメリカとの対立は「対話の対決」へ移行したという。
中曽根氏は、自身の内閣以前には「東南アジア政策はないがしろだった」とし、名高い福田「ドクトリン」も高圧的で逆効果であったと述べる。そこで、東南アジア外交を重視したというが、それは中国がインドネシアなどに影響力を伸ばしてきているという懸念と、なによりASEAN諸国が石油の輸入ルート上にあることが重要であったであった。これに関連して、シーレーン防衛に関する日本の構想は1,000海里(台湾:バシー海峡・ルソン海峡・グアム島付近まで)についての通商航路の防衛であったとし、氏が強調する点は、これはアメリカからの防衛努力要請圧力の結果採用したものではなく、「自主防衛の一環」であったということである。
中曽根内閣期の中国政策については、おおむねこれまでに知られていた範囲の証言である。氏は、日米安保条約も容認していた胡耀邦のことを、親日家であり、反対意見を抑えて親日的政策を敢行していると見ていたのという。また、第二次円借款の供与額は、大平よりも多くしようという意図も働いたというが、主な狙いは、中ソ対立を現状のまま維持し、中国を自由主義陣営に入れてソ連に対抗させるためであった。その際、中国を過剰に強化してしまうのでないかとして日本側の懸念材料であった米国による対中技術移転についても、アメリカは日本に害のある所まではやらないだろう、との楽観的な観測から反対しなかったようである。氏としては、当時の国際関係においてはソ連こそが最大の脅威であって、一方の中国は中小国クラスで、西側にとってはあくまでも利用するカードとしての存在であったという。また、レーガン政権には台湾問題があって、対中関係改善が遅延しがちな一方で、日本は台湾問題がないという意味でフリーハンドを得ていたという。
この中国に対する経済協力について、中曽根氏はこれを賠償の代わりと認識しており、むしろ賠償を受けとらなかったのはそれが中国のプライドを傷つけるからであったとも述べている。もちろん、対中円借款は長期的には日本の利益に跳ね返るという認識もあった。ただし、対中円借款が中国の強大化につながり、対日脅威になるという危惧もある程度は共有していたようである。ちなみに氏は対韓円借款も賠償の代わりという認識であった。
次に、靖国神社参拝問題であるが、これを氏は、信教の自由に基づいた公式参拝であったという。靖国参拝問題における対中配慮については、事前の情報では「避けて欲しい」という程度のことであったので実施したが、実際にはあまりに反発が強かったため、親日派の立場を配慮して中止したという。さらに、中国の反発以降持ち出されたかの印象がある分祀論は、天皇が靖国に行けるようにするためというのがより重要な理由であったようである。その後の胡耀邦の失脚については、今日では親日が原因となったのではないと認識しており、ただしその口実にはなったのではないかと述べている。
日ソ関係では、大韓航空機撃墜事件を、逆にソ連の政策転換のきっかけになるのではないかととらえ、その後のソ連の働き掛けに呼応することを意図したという。ただし、同時にチェルネンコ新体制成立が転換のきっかけであったとも述べている。また、レーガン政策の対ソ政策転換に遅れないようにとも考えたとも述べている。ともかく、最終的にはゴルバチョフ登場によって、伝統的に対立していたソ連国内の「ヨーロッパ派」と「アジア派」が、前者の勝利に帰結し、アメリカとの対立は「対話の対決」へ移行したという。
全体の印象
評者が本書から受けた印象をまとめると、まず野党的政治家から政策担当能力ある実務者への転換を目指して、本人が意識的に「イメージ戦略」を展開していたことである。野党時代の「反吉田」的政治アピールの行き過ぎが、自らのタカ派イメージを形成してしまったため、その後において修正を図った。例えば、「非核」国家路線をアピールし、対アジア配慮・国民感情への配慮に努める政治家像を打ち出そうとしたように読める。しかし、結果的に、中曽根という政治家が、大筋でいえば「保守本流」的な範囲内の思想の持ち主であって、表面的には若い時期に過激な主張をしたが、実は防衛政策としては吉田路線の継続とでもいえる「常識的」なものであったという印象を与えている。なお、本書でしばしば言及されるアジア諸国への配慮は、本人いわく「中曽根ナショナリズム」懸念の払拭を狙ったものであったという。
以上のように資料価値豊富な本書であるが、聞き取り資料としての問題点を指摘しておきたい。質問者全員の専門領域が影響してか、質問事項が外交問題に特化しており、これは一面ではかなり細かな事実についてまでの質問を可能としているが、反面経済問題についての認識などが触れられずに終わっている。特に、中曽根氏自身が言及している内政と外交のオーバーラップ部分=経済政策面の重要事項、例えば三公社民営化をはじめとする「新自由主義的改革」については、その意図、着想の由来などについて、今後、本人の証言を引き出す必要があろう。
最後に、安全保障問題、若干の経済問題について、中曽根氏が自ら行った政策を「自主的」と解釈したいという願望がにじみ出ていることを指摘しておきたい。この点は、プラザ合意、それ以後の拡張的経済政策、バブルの発生など、本来日本にとって好ましくなかった政策を次々とアメリカに押し付けられ、現在の日本の衰退を導いた政治家とでも描けなくもない中曽根氏だけに、そうした歴史解釈への潜在的な抵抗心があるのかもしれない。また、そのようにいとも簡単にアメリカの圧力に屈した背景には、氏の過剰とも言える対ソ恐怖心があったとも思われる。さらに進んで、そういた対ソ認識も、アメリカによる操作によって形成されたものではないのかなど、多くの疑問点が残されている。ただし、表面的にせよ、アメリカに言われて行ったとか、アメリカへの配慮で仕方なかったなどと決して認めない態度はそこかしこに読み取れ、ここにこそ中曽根氏の政治家としての心意気が集約されているのではないだろうか。
以上のように資料価値豊富な本書であるが、聞き取り資料としての問題点を指摘しておきたい。質問者全員の専門領域が影響してか、質問事項が外交問題に特化しており、これは一面ではかなり細かな事実についてまでの質問を可能としているが、反面経済問題についての認識などが触れられずに終わっている。特に、中曽根氏自身が言及している内政と外交のオーバーラップ部分=経済政策面の重要事項、例えば三公社民営化をはじめとする「新自由主義的改革」については、その意図、着想の由来などについて、今後、本人の証言を引き出す必要があろう。
最後に、安全保障問題、若干の経済問題について、中曽根氏が自ら行った政策を「自主的」と解釈したいという願望がにじみ出ていることを指摘しておきたい。この点は、プラザ合意、それ以後の拡張的経済政策、バブルの発生など、本来日本にとって好ましくなかった政策を次々とアメリカに押し付けられ、現在の日本の衰退を導いた政治家とでも描けなくもない中曽根氏だけに、そうした歴史解釈への潜在的な抵抗心があるのかもしれない。また、そのようにいとも簡単にアメリカの圧力に屈した背景には、氏の過剰とも言える対ソ恐怖心があったとも思われる。さらに進んで、そういた対ソ認識も、アメリカによる操作によって形成されたものではないのかなど、多くの疑問点が残されている。ただし、表面的にせよ、アメリカに言われて行ったとか、アメリカへの配慮で仕方なかったなどと決して認めない態度はそこかしこに読み取れ、ここにこそ中曽根氏の政治家としての心意気が集約されているのではないだろうか。
0%
