評者:小宮一夫(東京大学文学部非常勤講師)
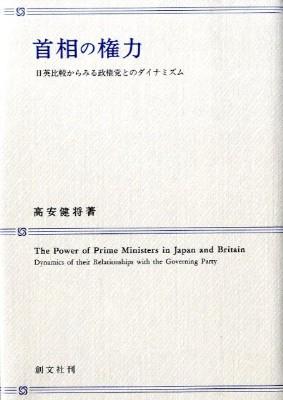
1.はじめに
立法部の多数派が行政部を支配する議院内閣制は、権力の融合をめざすシステムといえる。それゆえ、議院内閣制下の首相は、三権分立が徹底し、行政権のみしか付与されていないアメリカの大統領よりも、本来的に「強い」政治権限を有しているはずである。
しかし、我が国では、首相の権限は各省庁による「分担管理原則」によって制約され、その権限は「弱い」という議論が見受けられる。はたして日本の首相の権限は、本当に弱いのだろうか。印象論の域に止まることなく、建設的な議論を行うためには、具体的な事例の分析が欠かせない。その際、議論に広がりを持たせるのが比較の視点である。
こうした期待に応えてくれるのが本書だ。本書は、比較政治学・政治過程論を専門とする著者が、日英両国の政策決定過程における首相の権力の所在を検証し、首相の権力を支える諸要因の因果関係を解明したものである。本書の価値は、これだけにとどまらない。本書からは、議院内閣制という政治システムが抱えるさまざまな問題が浮かび上がる。これらは読者を思索する楽しみへと誘う。
2.本書の構成と概要
本書は、以下の通りである。
序章 問題の所在―日英比較分析の視座から
第一部 首相職を位置づける―政党政治と執政政治との間
第一章 首相の権力とは何か―政党政治と執政政治との間に位置する首相職
第二章 首相と執政府中枢―一九七〇年代における日英両国の政府内調整メカニズム
第三章 首相を操縦する―一九七〇年代における政権党組織の比較分析
第二部 首相の権力を検証する―比較事例分析
第四章 委任とコントロール―エドワード・ヒースと保守党(一九七三年一〇月~一九七四年一月)
第五章 競合するエージェントたち―田中角栄と自民党(一九七三年一〇月~一九七四年一月)
第六章 分裂する政権党・分裂する内閣―ジェームズ・キャラハンと労働党(一九七六年四月~一九七七年一一月)
第七章 党内抗争の激化と閣内の平和―大平正芳と自民党(一九七八年一二月~一九八〇年五月)
終章 議院内閣制と首相の権力
目次から一瞥できる通り、本書は、理論分析に主眼を置く第一部と事例分析に主眼を置く第二部の二部構成からなる仮説検証型の研究書である。
まず序章では、本書の課題と視角が述べられている。日英両国における首相の権力のあり方を比較事例分析によって検証し、同じ議院内閣制を採用しながら、なぜ「強力」な英国の首相と「受動的」で「脆弱」な日本の首相という対照的評価が生じるのか。このメカニズムの解明が本書の課題である。そして、本書はプリンシパル・エージェント論を援用して、この解明に挑む。以上のような課題と視角を有する本書は、著者の言葉を借りると、首相の権力を公的権力資源の配置と政権党組織との関係のなかで捉え直す政治学(政党政治)と行政学(執政政治)の結節点としての首相研究である。
理論篇ともいうべき第一部の概要は、以下の通りである。第一章では、政策決定ゲームにおける首相の権力は、地位維持ゲームにおける首相の立場に本質的に規定されるという仮説が提起される。
第二章では、執政府中枢が定義されている。執政府中枢とは、中央政府の諸政策を調整し、政府機構の異なる部門間において対立が生じた際、最終的調整者として振る舞う全ての組織と手続きのことである。そして、日英両国の執政府中枢の特徴が比較検討され、イギリスの首相の方が日本の首相よりも執政府中枢における権力資源が利用しやすい環境にあると結論づけられている。
第三章では、政権党内の組織と運用手続きが首相の関与する地位維持ゲームの構造を規定するという仮説が提起された。これをもとに、日本の自民党とイギリスの保守党及び労働党の党首の選出・審査手続きや党の意思決定・政策決定機関の特徴が比較検討された結果、次のような知見が得られた。三党のうち、保守党が首相にもっとも大きな裁量を付与する組織構造を有するのに対し、自民党は首相の裁量を強く制約する組織構造を有している。また、労働党の組織構造は両党の中間に位置する。
事例分析篇にあたる第二部では、1970年代の石油危機に際して、日英両国政府が対外政策、財政政策、国内石油政策という3つの政策領域において如何なる対応を取ったかが検証されている。さらに、それらを踏まえて、各首相の権力のあり方が抽出される。
まず第四章では、イギリスの保守党政権下におけるヒース首相の地位維持ゲーム及び政策決定ゲームにおける対応が検討されている。本章の結論は、イギリスの首相の権力が「強い」のは、首相の公的権力資源に対する優位性が確保され、政党組織において党首のもとへの集権化が進んでいるからだというものである。
続く第五章では、日本の田中内閣が取り上げられている。田中首相は、地位維持ゲームにおいて自民党の総裁選を争った福田赳夫や三木武夫ら派閥のリーダーを入閣させる「オールスター内閣」を作った。その結果、エージェントである官僚組織の逸脱行為を「政治」が封じ込めることを可能とした一方、閣内においてはライバルである福田らと対峙するはめに陥った。そして、本書が対象とする3つの政策領域における対応から、田中首相は自らの政策追求行動が地位維持ゲーム上において不利である場合には、政策決定ゲームへの介入を抑制したことが明らかとなったのである。
第六章では、労働党のキャラハン政権を事例に、キャラハン首相が党内で優勢を誇る左派の有力者たちを入閣させたため、田中首相と同じく地位維持ゲームで大きな困難に直面したことが論じられている。こうした困難な状況下、キャラハン首相は、自らの地位を維持するため、財政という重要な政策領域において自らの選好する政策を追求できないなど辛酸をなめることとなったのである。
第七章では、激しい党内抗争(40日抗争)に巻き込まれ、総選挙のさなかに急死した大平首相の地位維持ゲームと政策決定ゲームについて検証されている。大平は、福田や三木といった敵対する派閥のリーダーを入閣させなかったため、地位維持ゲームの次元で党内から強い制約を受けることになった。しかし、このことは、政策決定ゲームにおいて閣内の求心性を高めるという逆説的作用をもたらしたのである。
終章では、本書全体の結論として、議院内閣制下の首相は政党政治と執政政治との間に位置するアクターであること、政権を支える政党組織の権力構造とこれを反映する閣僚の構成が首相の権力を説明する本質的な変数であることが指摘されている。
3.論点
本書は、政治学の立場から政治学と行政学の相互浸透・交錯を試みた意欲作である。本書を読む限り、その試みは成功しているといってよい。近年の研究動向を顧みても、今後政治学と行政学の融合を意識する研究は増えることが予測される。首相研究という政治学と行政学の結節点に着目した著者のセンスの良さは評価されてしかるべきである。
また、本書では、日英両国の首相の権力を支える政治資源や首相を取り巻く政治環境が比較検討されている。日本の首相を、そもそもの政治制度が異なるアメリカの大統領と比較するのではなく、議院内閣制という共通の政治制度下にあるイギリスの首相と比較したことで、日英両国の首相の権力を規定する要因の共通性が解明された意義は大きい。具体的にいうと、首相(内閣)と与党の関係といった政権内の党内力学のみならず、党首の権限を左右する政党の組織構造も首相の権力のありかたを考える際、重要な規定要因であることが明らかとなった。これは、今後の政党政治研究に貴重な示唆を与える。イギリスの保守党の党首と比較した場合、自民党の党首は選任手続きや任期、審査手続きなどの面で「強い制約」を受けている。このことが、憲法や内閣法で首相に「強い権限」が付与されているにもかかわらず、首相の党内基盤が弱い場合、その指導力を発揮しにくくさせるのである。
評者としては、本書で得られた次のような知見に興味を覚えた。まず田中内閣のように党内のライバルたちを閣内に取り組んだ「オールスター・キャスト」内閣は、首相が選好する政策を追求、かつ実現していくうえでは必ずしも望ましいとはいえない。次に、大平内閣のようにライバルたちを入閣させない内閣は、与党と内閣の関係が緊張するものの、閣内の凝集性や安定度は逆説的に高まるということである。
ところで、本書の手法を応用すれば、戦前期日本の政党内閣に対し、さらなる明確な像を打ち出せるのではないだろうか。従来、政党内閣に関する研究は、もっぱら内閣そのものに関心を寄せ、内閣とこれを支える与党との関係には十分な注意を払ってこなかった。政友会の原敬や民政党の浜口雄幸は閣内を掌握し、政策決定において強い指導力を発揮したことはすでに明らかである。一方、「養子総裁」であった田中義一が政友会を十分に掌握しきれていなかったことが、田中内閣の迷走につながったことも、近年の研究によって明らかになっている(小林道彦「田中政友会と山東出兵―1927~1928―」(1)(2・完)<北九州市立大学『法政論集』33-1、34-3・4、2004~2005年>)。政党内閣期の各首相の政策決定ゲームと政権維持ゲームを詳細に分析すれば、堅強な実証に裏づけられた政党内閣のモデル化が実現できるかもしれない。戦前期の日本政党政治史を専門とする評者は、このような思いに駆られた。
しかし、本書にも不満な点がある。本書では、1970年代の日英両国の四内閣がそれぞれ取り組んだ対外政策、財政政策、国内石油政策が取り上げられている。合計で12もの事例が取り上げられているためか、ひとつひとつの事例分析について記述の厚みや深みにやや欠ける感があった。これは、評者が決定的事例研究を選好する政治史研究者であるということに由来する研究上の好みの問題であろうか。
次に、本書の特徴としてエリートへのインタヴューと未公刊資料の利用が挙げられているが、著者自身の関心が実証よりも理論的構築に向かっているため、これらの利用が実証面で十分有効に機能しているとは言い難いように見受けられた。著書が収集した未公刊資料(「藤原一郎日記」)や膨大なインタヴュー記録は、事実関係を裏づけるための補足資料として引用されているに過ぎない。もっと引用量を増やしても論旨は損なわれず、むしろ作品としての読み応えは増したのではないだろうか。
本年8月30日の総選挙によって、政権交代が実現し、「政府と与党の一元化」を掲げる民主党の鳩山内閣が誕生した。鳩山内閣は、これから如何なる政策決定ゲームと地位維持ゲームを展開していくのだろうか。今後の日本における首相のあり方を考えるうえで、本書が議論のたたき台となることは間違いない。
