評者:森 聡(法政大学法学部教授)
1.本書の目的と構成
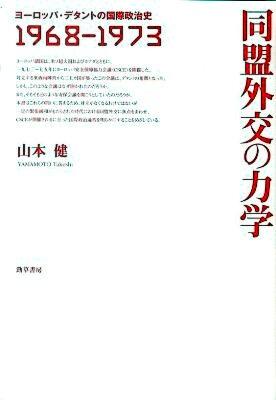
ヨーロッパ安全保障協力会議(CSCE)は1973年からおよそ2年間にわたって開催され、アルバニアを除いたヨーロッパ35ヵ国とアメリカ及びカナダが、ヨーロッパにおける現状の承認、信頼醸成措置、経済交流、人道問題といった議題に関する共同文書を策定するための交渉を行った。その最終段階となった1975年夏の首脳会議では、こうした諸議題に関する参加国の合意内容をまとめたいわゆるヘルシンキ最終議定書が採択された。
本書は、CSCEの開催に至る国際政治の展開、特に西側陣営内における外交に焦点を絞りながら、次の二つの問いを解明しようとするものである。第一に、なぜ1970年代初頭に多国間のヨーロッパ・デタントが実現し、CSCEが開催されるに至ったのか。第二に、西側はヘルシンキ最終議定書に人道的要素を盛り込むにあたって、会議手続きというものをいかに利用したのか。
本書はこれらの問いを解き明かすべく、ヨーロッパの多国間デタントの潮流が生み出されていく過程を描く。前半では東西ドイツ問題、ベルリン問題、軍縮・軍備管理問題(相互兵力均衡削減・MBFR)という3つの縦糸を紡いでいく。一方後半では、CSCEの会議形態と交渉戦術という2つの横糸でCSCEそのものをめぐる外交を描く。そしてこの横糸と縦糸を結び合わせるのが、CSCE開催の前提条件をめぐる西側陣営内や東西間のせめぎ合いという糸になっている。つまり、本書は少なくとも6つの外交上の争点に関して、西欧諸国、カナダ、アメリカさらにはソ連という多数のアクターが繰り広げた外交を分析しているのである。著者は、以下のような構成をとって、この気の遠くなるような複雑なプロセスの展開を活写している。
序 論 ヨーロッパにおける冷戦と本書の視角
第一章 1960年代のデタント
第二章 ヨーロッパ安全保障会議と人道的要素の起源―1968年1月~1969年12月
第三章 イギリスとNATOの多国間交渉への関与―1970年1~5月
第四章 交渉の停滞―1970年6~12月
第五章 イギリス、フランス、西ドイツ―1970年6月~1971年1月
第六章 ベルリン、MBFR、ヨーロッパ安全保障会議―1971年
第七章 ヨーロッパ政治協力の出現―1971~1972年
第八章 軍縮・軍備管理デタントとCSCE―1972年1月~1973年7月
エピローグ
結 論 多国間デタントと冷戦
本書は大変複雑な外交をたどる内容であるので、複数のプロセスが入り組む場面を取り上げる章の末尾には小括が設けられている。流れを振り返り、内容を確認できる工夫は読者の理解を助けている。
2.本書の概要
まず序論において筆者は、先行研究のレビューを行うとともに、本書の分析の枠組みを設定する。とりわけデタントを分析するにあたって、次の三つの軸に沿って分析対象の明確化を図っている。まず二国間デタントと多国間デタントを区別する。著者によれば、二国間デタントが冷戦を安定化させることに貢献したのに対し、多国間デタントはヨーロッパ分断の克服に貢献した。第二に、ヨーロッパ・デタントと超大国デタントを区別し、1960年代から70年代にかけて米ソのデタントが、ヨーロッパの問題から独立して主に核軍備管理の分野で発展したのに対して、ヨーロッパにおけるデタントはドイツ問題によってなかなか進展しなかったとする。そして第三に、デタントは多面的な現象で、そこには経済・文化交流、現状維持、軍縮・軍備管理という三つの柱があったと著者は指摘する。ヨーロッパ安保会議構想を当初提案したのは東側であったが、西側こそがCSCEの議題内容や手続を形作り、ヘルシンキ最終議定書の合意内容に多大な影響を及ぼしたとして、本書がもっぱら西側陣営内の外交に焦点をあてる意義もここで説明されている。
第一章では、本書で描かれるデタントの起点が設定される。まず著者は、1963年の部分的核実験禁止条約(PTBT)の交渉過程において、超大国デタントとヨーロッパ・デタントが分裂したとの見方を示す。ドイツ問題が米ソのデタントから切り離され、二つのドイツの問題が棚上げされることでPTBTが調印可能となったが、著者によれば、この時点で米ソ間のデタントがヨーロッパに波及することはなかった。
第二章では、1968年の学生運動がいかに西側を多国間デタントへと突き動かしていったかが説明される。1969年にワルシャワ条約機構は「ブダペスト・アピール」(3月)や「プラハ宣言」(10月)を採択して、ヨーロッパにおける現状の承認や貿易・経済・科学技術についての関係拡大を呼びかけた。これに対して西側は疑いの目を向けたものの、NATO諸国の指導者たちは、若い世代にNATOの存在意義を訴えなければ同盟を維持することはできないと考えるようになっていた。スチュワート英外相がNATO外相会議の宣言を作成する過程を先導し、アメリカやフランスも対案を出した結果、69年12月のNATO外相会議は「東西関係に関する宣言」を採択した。この宣言には、”freer movement of people, ideas, and information between the countries of East and West”という文言が盛り込まれ、ヘルシンキ最終議定書のいわゆる「第三バスケット」の重要な基盤が作られたのである。また本章では、1969年9月に西ドイツでSPD/FDPが連立してブラント政権が発足し、東ドイツの存在を事実上承認する意向が表明され、ベルリンの地位に関する四大国(米英仏ソ)交渉が再開されるという転換局面にも一節が割かれている。
第三章は、1970年の1月から5月にかけて、米仏が反対する中、他のNATO諸国が条件を付けながら多国間交渉を受け入れる余地を徐々に示していく過程が描かれる。イギリスはヨーロッパ安保会議の代替案として「常設東西関係委員会」を構想・提案し、西ドイツはシュミット国防相がMBFR構想の推進を主導した。やがて1970年5月のローマNATO外相会議では、「これらの[軍縮]交渉や、とくにドイツ及びベルリンに関する現在進行中の交渉の結果、進展が見られる限りにおいて、同盟国政府はすべての関係国政府と多国間交渉に入る用意がある」との文言が含まれたコミュニケが採択された。
第四章では、MBFRとベルリン交渉をめぐって関係国が立場を一致させられず、交渉が停滞した様子が詳述される。MBFRについてはワルシャワ条約機構が1970年6月に「ブダペスト・メモランダム」を示し、中央ヨーロッパに駐留するアメリカとソ連の軍隊のみを削減するとの提案を行い、公式声明で初めて通常兵力の削減に言及した。西ドイツは、これが中部ヨーロッパ諸国自体の軍縮にいずれつながるのであれば受入可能という立場を示すが、NATO内は西ドイツの立場を支持する国と反対する国に二分してしまう。一方、1970年8月に西ドイツとソ連が「モスクワ条約」を締結し、武力行使の放棄や既存の国境線の不可侵性の尊重(=東ドイツの存在とオーデル=ナイセ線の事実上の承認)を確認し、西ドイツの東方政策は活発化した。その結果、西ドイツは東ドイツが多国間会議に自国と同格で参加することを受け入れられるようになったが、その前にベルリン問題の解決を決着させる必要があると考えた。そこでブラントはソ連に対し、ベルリン問題の解決をモスクワ条約批准の前提条件として求めた(この方針は「ユンクティム(抱き合わせ)」と呼ばれた)。ソ連と西ドイツはベルリン交渉の進展を望んだが、ベルリンの地位と西ベルリンへのアクセス権という二つの重大な争点を拙速に解決することを嫌った米英仏が慎重な姿勢を取り、ソ連も従来の立場を変更することができなかったので、ベルリン交渉は停滞してしまう。その結果、1970年12月のブリュッセルNATO外相会議は、MBFRであれ、会議のための一般的な問題であれ、多国間交渉に入るべきではなく、軍縮デタントよりも東ドイツとの二国間交渉やベルリン問題を重視すべきとの立場を取り、コミュニケもそうした態度の硬化を反映したものとなってしまった。
第五章では、イギリス、フランス、西ドイツがそれぞれヨーロッパ安全保障会議に関する立場を一致させていく様が描かれる。イギリスは、NATO諸国が徐々にヨーロッパ安保会議に前向きになっていく中で、MBFRも安保会議も否定するわけにはいかなくなったため、より悪弊が少ないと考えられた後者については理解を示す、という立場を取るようになった。フランスのポンピドゥ大統領は、かねてから多国間の安保会議は東西ブロックを固定化する効果を持ちうるとして反対していたが、やがて対ソ接近の必要性、デタント推進派の側近による説得、ブラントの東方政策への対抗心といった複数の理由から、ベルリン問題の解決をヨーロッパ安保会議開催の唯一の開催条件とするという立場を取るに至った。一方ブラントは、ベルリン交渉を加速させるべきとポンピドゥに働きかけた結果、ポンピドゥの怒りを買ってしまう。著者によれば、ブラントはポンピドゥの怒りを鎮めるために、ヨーロッパ経済通貨同盟の問題に関してフランスに譲歩するとともに、満足のいくベルリン交渉の妥結をヨーロッパ安保会議開催の唯一の条件とすべきというフランスの主張を受け入れた。こうしてイギリス、フランス、西ドイツは、ベルリン問題の解決が安保会議開催の唯一の前提条件であるとの点で立場を収斂させたのだった。
第六章は、ベルリン問題、MBFR、ヨーロッパ安保会議が複雑に絡み合った外交の複雑さがもっとも顕著となった局面を取り上げている。米ソは、キッシンジャーとドブルイニン駐米ソ連大使との間のいわゆる「バックチャンネル」を通じてベルリン問題を話し合っていたが、すぐに行き詰ってしまった。そこでブラントの側近バールは、「法律的な諸問題を脇において、プラグマティックな進展をもたらす方法」を見出すべきとの提案を出し、その後アメリカ、ソ連、西ドイツの政府代表で「三人組」を結成して、ベルリン問題の突破口を開いた。一方MBFRに関しては、これを警戒するイギリスが、安保会議でMBFR交渉の場について話し合い、そのあとで軍縮交渉を開始するという、両者をリンクする提案を行い、フランス、西ドイツ、ソ連がこれを受け入れる姿勢を示し、当初拒否したアメリカも徐々に関心を示すようになった。しかし、ソ連が1971年9月の西ドイツとの外相会議において、モスクワ条約が西ドイツ議会で批准されなければ、ベルリン最終議定書には署名しないという「逆・抱き合わせ」の立場を表明したことで状況は一変する。ソ連は、ベルリン協定のみが成立して、モスクワ条約が西ドイツ議会で否決されることを恐れたためにこのような行動をとったのだった。西ドイツ政府は、議会でモスクワ条約の批准を得るためには、東ドイツが参加することになる安保会議の多国間準備協議を開始しない方がよいと判断し、ベルリン最終議定書の調印の前にヨーロッパ安保会議の多国間準備協議を開始することに反対する方針を決めた。またアメリカは、安保会議に積極的ではなかったので、西ドイツに同調し、他国もそれに続いた。同時にアメリカは、MBFRの早期開始を望んでいたため、安保会議とMBFRの切り離しを主張した。その結果、安保会議とMBFRをリンクするイギリスの提案は、ここで事実上頓挫してしまうのだった。
第七章では、本書の目玉の一つとなるヨーロッパ政治協力(EPC)が安保会議の手続きに関する主要国の立場の収斂において果たした役割と、いわゆる人権条項の起源についての検証が行われる。CSCEの会議手続きに関しては、短い準備段階と長い三段階の本会議で構成すべきとするフランス提案と、長い準備段階と一回限りの短い外相会議を開催すべきとするアメリカ提案が出され、NATO諸国の意見も分かれた。EC六ヵ国による政治協議の枠組みであったEPCがこの問題を取り上げたものの、1971年中に意見を集約することはできなかった。しかし、やがてフランスが、本会議での実質的な交渉の場となる第二段階の事務レベル協議の指針となる作業指令文書(mandate)を、本会議第一段階の前に、多国間準備協議を開いて作成するとの提案を出すと、西ドイツが条件付きでこの提案を受け入れ、1972年11月のEPC外相会議はフランス提案の線で基本文書を採択した。ここで筆者は、EPCがCSCEの手続きの問題について、NATOとは異なる独自性を発揮した点を強調する。またNATO内では、「人・思想・情報の移動の自由」についての関係国の立場が割れていたが、西ドイツが人権を、国家間関係を規定する諸原則に関する宣言に含めるよう提案し、人権を一般的な形で提示することによって、米英などの強硬な立場をとる国々を間接的に説得しようとした。結局、人・思想・情報の移動の自由については、議題のタイトルに関する論争へと姿を変え、CSCEの準備交渉では「人の接触」という穏健な文言が採用されることになった。
第八章も、本書のもう一つの目玉ともいえる、MBFRとCSCEの開催形態をめぐって西欧諸国と米ソとの間で繰り広げられた攻防が中心に描かれる。とりわけクローズアップされるのが、CSCEを1973年6月末から9月末にかけて開催し、その後にMBFR交渉本会議を開催するという「密約」を米ソが交わしたという事実である。この「密約」は、ヨーロッパの現状を承認する短期間の会議を望むソ連と、CSCEを早々に終わらせてMBFRを早く開催したいアメリカの利害が一致したことによって生まれたものであった。この「密約」を嗅ぎつけた西欧諸国とカナダは、CSCE第二段階の事務レベル協議を米ソがMBFR交渉開始時期として当初設定した9月に敢えて開始して、CSCEとMBFRの連続開催案を潰し、ソ連がMBFR本会議の開始日を明確にしなければ、第一段階となる外相会議への公式な返答を行わないこととして、ソ連に圧力をかけた。その結果ブレジネフはMBFR本会議を73年10月30日から開始することに同意し、CSCEとMBFRは連続開催から並行開催へと切り替えられ、米ソの「密約」は葬られた。こうして西欧諸国とカナダは、多国間準備協議で「人・思想・情報の移動の自由」などの西側にとって重要な議題を、時間をかけて徹底的に議論する環境を手に入れたのだった。なお、CSCEにどこまで安全保障問題を含めるかについて、NATO諸国は異なる考えを持っていたが、最終的には軍隊の移動や軍事演習に関する事前通告といった信頼醸成措置に限ってCSCEでは扱われることになっていた。
エピローグでは、1973年7月3日から1975年8月1日まで開催されたCSCEを概観し、安全保障問題とドイツ問題、経済問題、人権問題とフォローアップ会議という、おおむねヘルシンキ最終議定書の各バスケットについて、その成果と著者の評価が簡潔にまとめられている。
結論では、CSCEをめぐる国際政治や外交に関する著者の分析が、おおむね四点に分けて披露される。まず一点目は、西欧諸国こそがヨーロッパの多国間デタントの主たる担い手であったと著者は指摘する。西ドイツのブラント政権が、ドイツ問題とベルリン問題に関する方針を大胆に転換して突破口を開いたことにより、ヨーロッパにおける多国間デタントが実現する必要条件が整えられた。著者によれば米ソは、ヨーロッパの多国間デタントをある程度管理できたものの、これが本格的に進展し始めると、完全にコントロールすることはできなかった。
第二に、ヨーロッパを二国間デタントから多国間デタントへと突き動かしたのは、1968年の学生運動であり、著者は当時の社会情勢がイギリスをはじめとする一部NATO諸国の対外政策に大きな影響を及ぼしたとの見方を示す。NATOがCSCEを受け入れていくにあたってカギとなったのは、1970年5月のローマ会議であった。アメリカ、フランス、西ドイツが依然として二国間デタントにこだわっていた中で、条件付きながらもCSCE開催へ向けて踏み出すことができたのは、イギリスのスチュワート外相や他の小国の政治家たちが、1968年の学生運動をみてデタントに前向きであることを学生や若い世代に示す必要を痛感したからであったと著者は指摘する。
第三に、CSCEの成功にとって重要な意味をもったのは、EPC内において形成された会議の形態に関する合意と、そこから生まれた主導権であったと著者は主張する。NATO諸国が会議の形態に関して足並みを揃えられない中、フランスが作業指令文書を作成する多国間準備協議に、外相会議・事務レベル協議・最終会議という三段階で構成されるCSCEの会議形態を提案し、EPC内でフランス案を中核とした合意が形成された。EPC諸国が主導権を発揮できたことにより、短期の会議で現状を承認するのではなく、時間をかけて実質的な取引を行うための交渉の枠組みを作り上げ、このような会議手続きをめぐる外交こそがCSCEを成功に導くうえで重要な役割を果たした。
最後に、著者はヘルシンキ最終議定書に盛り込まれた現状維持デタントは、ヨーロッパにおける政府間関係を安定化させたが、同時に経済・文化交流デタントと人権規範は、東側陣営を時間が経つにつれて根底から揺さぶり、これがヨーロッパ冷戦を終結させる重要な一因になったとの解釈を示している。著者によれば、ヨーロッパ冷戦の終結は、四つの要因が複合的にもたらした結果であった。第一に、ドイツ・ベルリン問題が暫定的に解決されたのを受けてCSCEが開催されることにより、ヘルシンキ最終議定書に人道的要素が盛り込まれ、CSCEの成功が経済・文化交流デタントが活性化した。第二に、ソ連・東欧諸国が安定と経済交流を望んだことで、人権問題を無視できなくなった。第三に、経済・文化交流デタントが東欧社会を変容させ、東欧諸国の政府を西欧諸国の借款を頼ることになった。第四に、人権や自由を求める人々が、経済・文化交流デタントのもたらしたきっかけをつかんだことで、ヨーロッパに構造変動を生み出した。これらの要因が相まってヨーロッパの分断が克服されたと著者は結ぶ。
3.評価・コメント
既存の研究も本書が掲げるCSCEに関する研究課題に取り組んできたが、一国の視点からの外交史であったり、CSCEをめぐる外交の一側面に光を照らしたりする断片的な国際関係史であったりするなど、射程の限定されたものがそのほとんどであったといえよう。
これに対して本書は、分析射程の幅の広さと分析対象の奥行きという点で、ヨーロッパ・デタントをめぐる国際政治史・外交研究として大きく踏み出すものであるといえる。まず分析の幅の広さという点で、著者は英独仏米の4ヵ国にも及ぶ第一次史料を駆使して、大国のみならず、西欧の中小国がさまざまな外交イニシアティヴにいかに反応したか、またそれら諸国の動向がいかに大国の方針に影響を与えたのかといった点まで綿密な検証を行っている。もちろん東側陣営内の国際政治も検証しなければ、厳密にはCSCEの全貌が解明されたとはいえないだろうが、東側諸国の史料の入手可能性に限界もあるであろうし、叙述や分析の複雑さが格段に増すといったことを考えれば、そこまで求めるのは無いものねだりといわざるをえないだろう。また奥行きという点でいえば、前述したように、少なくとも6つの外交上の争点を取り上げており、それらが複雑に絡み合っていた様子を鮮やかに描いている。
このような特徴に照らせば、本書はCSCEの開催決定をめぐる国際政治、あるいはヨーロッパ・デタントの多国間化を「面」で捉える、おそらく初の本格的な国際関係史といえるのではないだろうか。著者のいう「同盟の力学」とは、CSCEとMBFRの開催形態をめぐる「アメリカvs西欧・カナダ」、人・思想・情報の移動の自由をめぐる「英米蘭vs他のNATO諸国」、ヨーロッパ安保会議構想をめぐる「米仏西ドイツvs他のNATO諸国」、ドイツ・ベルリン問題をめぐる「ドイツvs NATO諸国」といった様々な構図が、西側陣営内で重層的に存在し、その中で複雑な多国間外交が展開された様を指しているものと評者は理解した。NATO各国が複雑な思惑に駆られて、デタントに関する立場を異にしながらも、外交を通じて利害を調整していく過程を描くことで、デタント期のNATOが決して一枚岩ではなかった事実を明らかにするとともに、国家間の緊張が相対的に低下している時代における同盟外交の難しさを指摘する重要な国際関係史の業績といえるだろう。
さて、ここで本書において示される論点につき、評者なりに考えさせられた点をいくつか挙げておきたい。第一に、第八章と結論に出てくる「管理できない多国間デタント」についてである。たしかにCSCEを短期とするか長期とするかという問題を、「米ソvs西欧諸国+カナダ」という構図で捉えることは可能であろうし、米ソが西欧諸国やカナダとは異なる考えをもって会議の運営を目論み、それを西欧諸国とカナダが阻んだのは事実である。CSCE開催当時から米ソ共謀論(superpower collusion)がささやかれていたし、本書はCSCEの早期終結に関する米ソ間の「密約」や、米ソの目指すCSCEの運営方法と西欧諸国とカナダが目指したそれとの間に大きな違いが存在していた事実を実証した。
しかし、評者のみるところ、少なくともアメリカに関する限り、ヨーロッパの多国間デタントを「管理できなかった」というよりも、「管理しなかった」と形容する方が適切なのではないかと感じた。西欧諸国とカナダが達成したのは、CSCEとMBFRの開催条件を連続開催から並行開催へと変更する、ということであった。これは米ソ両国の利益を損なうものではなく、むしろMBFR本会議の実現というアメリカの外交上の利益を実現し、CSCEを早期に閉幕させるための切り札をソ連から奪うものだった。つまり、アメリカがCSCEを軽視し、利益も害ももたらすものではないと考えたからこそ、西欧諸国とカナダはこの点に関して外交上のイニシアティヴを発揮しえたともいえる。換言すれば、西欧諸国とカナダのイニシアティヴが、アメリカの利益を損なうものであったとすれば、それがどこまで実現したかは分からない。要するに、西欧諸国とカナダは、アメリカの許容範囲内で行動していたのであり、アメリカの目的や根本的な利害を覆すような外交を繰り広げたわけではなかったといえよう。
この点は、CSCEをめぐる外交においてアメリカの果たした役割をどう評価するかという問題と表裏一体をなしている。アメリカに焦点をあてながらCSCE外交を分析するスナイダ―は、西欧諸国の対米不信感が根強かった事実を認めつつも、アメリカは、実質的には西欧諸国とソ連との仲介役のような役割を果たしていたとの見方を示している点は興味深い。(Snyder:266-7)
第二に、第二章・第三章と結論で示される、1968年の学生運動がヨーロッパの多国間デタントを突き動かす重要な要因であったとの著者の見方についてである。やや大雑把で乱暴なまとめ方になるが、著者は、西ドイツがドイツ問題・ベルリン問題に暫定的解決を与えることで、多国間安保会議を開催可能とする条件が整い、1968年の学生運動が多国間デタントに対する西側の伝統的な警戒心を取り払う効果を持ったのみならず、スチュワート英外相をはじめとする西欧諸国の政治家たちに多国間デタントの追求を必要とさせる要因になったとの見方を取っている、と評者は理解した。
評者も著者の見方に賛同するが、もし仮に1968年に学生運動が起こっていなければ、たとえドイツ問題・ベルリン問題が西ドイツによって暫定的に解決されていたとしても、CSCEは開催されなかったといえるのか、考えさせられる。西側が、ヨーロッパにおける多国間デタントをゼロから生み出したわけではないという点は、著者も重々承知であろうと思う。東側が多国間の現状維持デタントを切望していた事実自体が、西側を優位に立たせ、外交イニシアティヴを発揮する余地を生み出していたのは間違いない。CSCEをめぐる西側の外交はつまるところ、東側に現状維持デタントを与える見返りとして、西側が何を求めるか、そしてこの東西間の大取引をどのような枠組みの中で追求すれば西側の要求を最大限実現できるかを調整する過程にほかならなかった、といえよう。こうした外交攻勢をしかける機会が発生している事実を、ドイツ問題・ベルリン問題という政治的障害が取り払われた後にも、はたしてNATO諸国がみすみす閑却したといえるのかは、にわかに判じ難い(特にベルリン問題はCSCEの開催とも絡み合っていただけに、単純な反実仮想を控えなければならないことは評者も理解している)。しかし中ソ対立が激化し、米中接近が現実化していく中で、ソ連がヨーロッパ・デタントを一層強く希望しているとの戦略的観測が生まれれば、遅かれ早かれNATO諸国の中に、こうした状況を奇貨として、東側陣営内にくさびを打ち込むために多国間安保会議に応じるべしとの立場を取る国が登場してきた可能性も完全には否定しきれない。やはり東側が現状維持デタントを多国間ベースで望んでいたという根本条件も西側のCSCE外交全般に作用した点は、もっと強調されてもいいのではないかと感じた次第である。
最後に、いわゆる「ヘルシンキ効果」と経済交流デタントの評価についてである。本書の目玉の一つは、EPCが第三バスケットの実現を可能にするような会議形態を編み出して、それを米ソの思惑に対抗しながら、巧みな外交によって現実化したという歴史的事実の解明にある。著者はヨーロッパ・デタントに関する研究でいまや主流になったともいえる、第三バスケットの意義を重視する見方を取る一方、エピローグでは第二バスケットの重要性は低かったという評価を下している。
ところが、著者は結論で「ヘルシンキ効果」に触れる際に、経済交流デタントや東欧経済がいかに西側に依存するようになっていたかを度々指摘しており、「経済ファクター」がクローズアップされているとの印象を拭えない。経済交流デタントが冷戦の終結において重要な意味を持っていたにもかかわらず、著者がいうようにヘルシンキ第二バスケット(経済交流)のインパクトが微少だったとすれば、西側諸国が二国間ベースで進めた経済交流デタントが重要な意味をもったということになる。今後は、冷戦終結に至るソ連・東欧の社会変容において、二国間ベースの経済交流デタントが果たした役割やその影響が検証される必要があるだろう。
第三バスケットについては、たしかに東側がヘルシンキ最終議定書の第三バスケットを受諾したことにより、その後それがソ連・東欧諸国内の人権問題を批判する際の根拠を与え、これこそが東欧諸国の革命に結びついたという点にその意義を求めることは不可能ではない。むしろこうした解釈は、近年の冷戦の通史などに散見される。
しかし、ソ連・東欧諸国が反体制派の政治批判を抑え込めなくなったそもそもの背景は、重工業偏重の経済構造によって十分で多様な消費財を生産できず、東欧各国の政府が期待された経済的成果を挙げられなかったことにより、大多数の国民の間で不満が強まり、抑圧的な体制を維持するための基盤も揺らいでいったからだともいわれる。もしそうだったとすれば、次の二点が指摘可能であろう。第一に、第三バスケットに依拠した反体制派による体制批判の激化は、東欧諸国政府の弱体化ないし経済停滞の「結果」であって、その「原因」であるとは必ずしもいえないのではないか。第二に、CSCE第二バスケットの経済交流デタントのみならず、西側各国が進めていた二国間の経済交流デタントによって、たとえばハンガリーのように、西側諸国の借款などによって東欧諸国の政府が支えられていたという事実があったのだから、実は経済交流デタントは東欧諸国政府の延命を助け、東欧革命を先延ばしにする効果を持った可能性すらある。事実、経済相互援助会議(COMECON)は、当初ソ連が東欧を搾取する枠組みだったが、1960年代には東欧諸国がソ連に補助金を求める場へと転じていた(Hanhimaki:206)。西側による東欧諸国への借款供与や東西貿易などの経済交流デタントは、ソ連の「重荷」を減らす効果を持っていたともいえよう。
こうした意味で文化交流デタントは、東欧諸国政府の内部崩壊を最終局面で多少なりとも加速したかもしれないが、経済交流デタントについては、東欧の民主革命を先延ばしにした面もあったと考える余地が残されているといえよう。だとすれば、デタントないしヘルシンキ最終議定書が冷戦の終結に寄与したという評価には、一定の留保が付されうるのかもしれない。
ヨーロッパ・デタントと冷戦終結に関する今後の研究上の課題ということでは、経済交流デタントと文化交流デタントをまとめて評価するのではなく、それぞれのもたらした効果を分けて検証するとともに、さらに経済交流デタントについては、崩壊を促進した面と遅延した面の双方を慎重に検証する必要があるといえよう。ヨーロッパ・デタントが全体としてソ連・東欧諸国の政府の延命を図る効果をもち、冷戦の終結を遅延したといった解釈や評価がもし将来登場することがあれば、CSCEやその実現を図った外交に対する評価も変わってくるのかもしれない。ソ連・東欧諸国内部に関する詳細なデータに基づいた研究を待たねばならないが、この分野はまさしく冷戦の終結に関する研究のフロンティアであるといえよう。
以上は評者の浅薄な知識に基づいた批評であるが、本書はヨーロッパ・デタントの多国間化のプロセスと構造を描き出す、実証性の高い国際関係史の研究であることに変わりはない。ここまで複雑な同盟外交を、幅広く奥行きのある国際関係史としてまとめあげた著者の今後の研究に期待したい。
【参考文献】
Jussi M. Hanhimaki, “Détente in Europe, 1962-1975,” in Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad eds., The Cambridge History of the Cold War, Vol.II, Crises and Détente, Cambridge University Press, 2010, pp.198-218.
Sarah B. Snyder, “The United States, Western Europe, and the CSCE,” in Matthias Shultz and Thomas A. Schwartz eds., The Strained Alliance: U.S.-European Relations from Nixon to Carter, German Historical Institute, 2010, pp.257-75.
