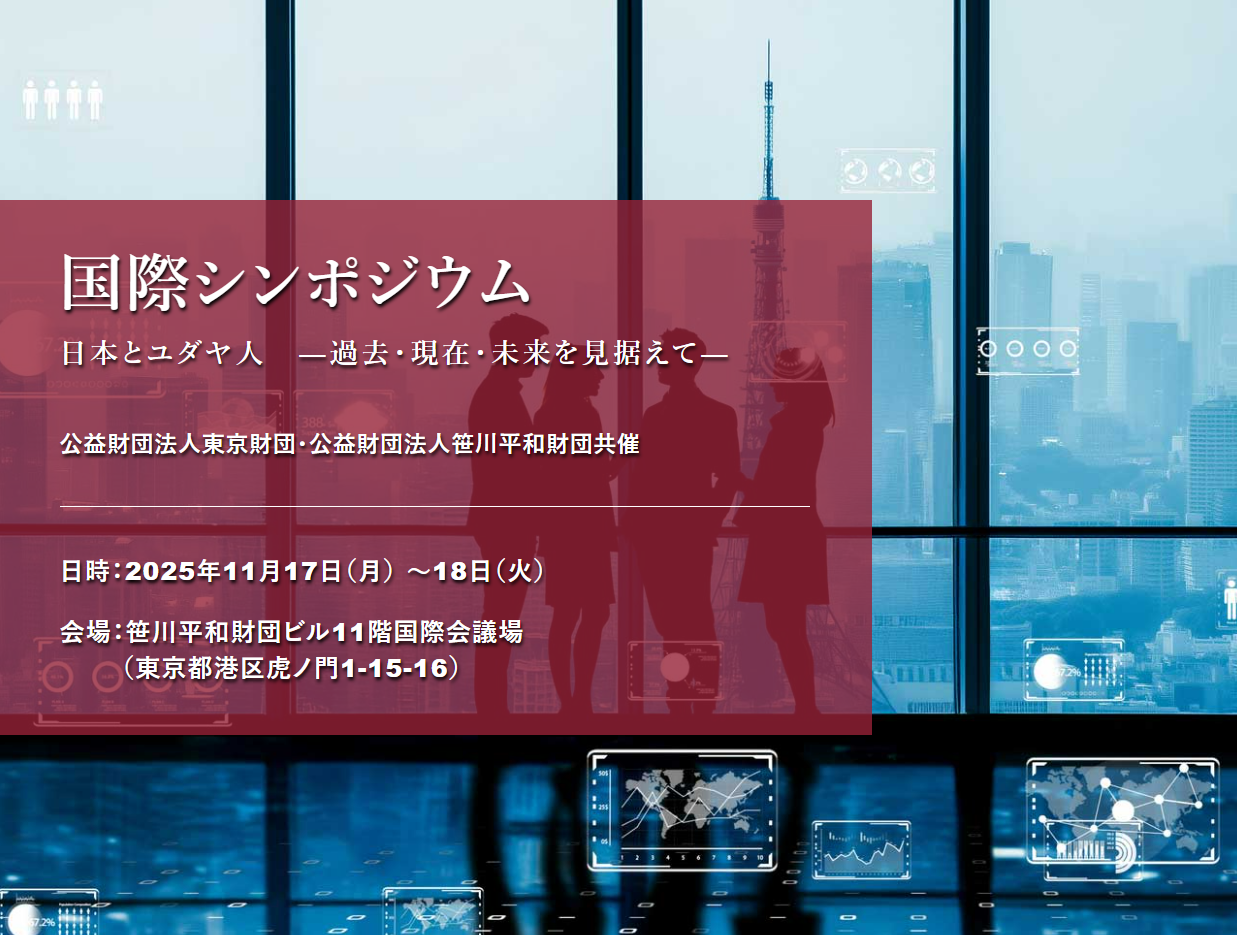
- レポート
【開催報告】国際シンポジウム「日本とユダヤ人―過去・現在・未来を見据えて―」
November 20, 2025
東京財団は、2025年11月17日(月)および18日(火)に、笹川平和財団ビル国際会議場にて、国際シンポジウム「日本とユダヤ人―過去・現在・未来を見据えて―」を、公益財団法人笹川平和財団と共催いたしました。ご多忙の中、ご参加いただいた皆様、ご登壇いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。
 シンポジウムの様子(事務局撮影)
シンポジウムの様子(事務局撮影)
1日目は当財団の中林美恵子理事長から開会挨拶として、本シンポジウムの開催に至った経緯を紹介するとともに、国内外からご出席いただいた登壇者や参加者の皆様への謝意を述べました。
続いて、来賓挨拶では、大西洋平氏(外務大臣政務官)より、現在、世界の様々な地域で紛争が続いている状況において、世界に平和と安定をもたらすべく、日本を含む国際社会が未来志向で考え行動していくことが重要であることをご示唆いただくとともに、アンドリュー・シアー氏(日本ユダヤ教団代表)より、ユニークな日・ユダヤ関係を取り上げる意義と重要性をご指摘いただきました。
基調講演ではメロン・メッツィーニ氏(ヘブライ大学名誉教授)をお迎えし、「なぜ日本に反ユダヤ主義がなかったのか?」をテーマに基調講演が行われました。メッツィーニ氏は、自身の父親が1年半ほど日本に住んでいたことをきっかけに日本への関心が生まれたと明かし、20世紀初めから現代に至るまで日本がユダヤ人に対してどのように向き合い、接してきたのかについて深く考察しました。そして、我が国に反ユダヤ主義が存在しなかった理由として、ユダヤ人の居住者数が少なく、我が国の一体性やアイデンティティを脅かす存在と見なされなかったこと、また反イスラエル思想を広めるイスラム教徒が我が国にはほとんどいなかったことなどを挙げ、最後に『今後、日本において反ユダヤ主義が外交のカードとならないことを願う』と述べ、講演を締めくくりました。
続いて行われたパネルディスカッションでは、「ユダヤ人に対する日本の態度:過去・現在・未来」をテーマに、石田訓夫氏(ヘブライ大学博士/元外務省外交史料館長)、丸山直起氏(明治学院大学名誉教授)、二シム・オトマズキン氏(ヘブライ大学人文学部長)、新居雄介氏(イスラエル国駐箚日本国特命全権大使)をお迎えしました。各登壇者の発表後には、ホロコーストが始まった1938~40年頃に我が国がユダヤ人の入国を受け入れた背景や、上海など海外での対応、我が国がドイツの強い要求にもかかわらず公平で人道的な対応を維持できた理由などについて活発な意見交換が行われました。我が国が世界で唯一、1938年12月に国策として制定した、ユダヤ人を差別しない方針を示す『猶太(ユダヤ)人対策要綱』が、ユダヤ人を保護する上で大変重要であったことを確認しました。
2日目には当財団の笹川陽平名誉会長から歓迎挨拶として、歴史的な文脈から我が国とユダヤ人の関係性に注目する重要性が紹介されました。その後、1日目の議論を踏まえて、「日本とユダヤ人―その関係性の実態に迫る―」をテーマに、パネルディスカッションが行われました。
前半では、水内龍太氏(前オーストリア共和国兼コソボ共和国駐箚日本国特命全権大使)、樋口隆一氏(明治学院大学名誉教授)、ロバート・D・エルドリッヂ氏(日本国際問題研究所シニアフェロー)による発表の後、当日急遽欠席となった白石仁章氏(外務省外交史料館外務事務官)の発表原稿が司会者に代読され、特に日本のユダヤ人政策形成の創始者ともいえる樋口季一郎や「命のビザ」の発行で知られる杉原千畝など、日本とユダヤ人の関係構築に貢献した日本人の話に、来場者は熱心に耳を傾けていました。
後半では、引き続き同テーマのもと、パメラ・ロトナー・サカモト氏(歴史家/プナホウ・スクール教諭)より、アメリカの視点から見た「命のビザ」について語られた後、石田訓夫氏(ヘブライ大学博士/元外務省外交史料館長)より、日本ではまだあまり知られていない、神戸の小辻節三博士や上海の犬塚惟重海軍大佐が果たした役割についての話がありました。次に、エドワード・N・ルトワック氏(歴史家/米国政府戦略アドバイザー)が樋口季一郎や杉原千畝のレガシーをこれからの日本にいかに戦略的に生かしていくかを考察した発表を行い、最後に閉会挨拶として、共催者である笹川平和財団の角南篤理事長より、本シンポジウムの意義を改めてご紹介いただくとともに、今後はこれまで以上に当財団と密接に連携・協力を進めていく決意が示され、2日間にわたるシンポジウムは幕を閉じました。
本シンポジウムを通じ、我が国における反ユダヤ主義の不在が、単なる偶然ではなく、文化的・宗教的背景、さらには日本人の価値観や世界観に根ざしたものであることが明らかになりました。また、「人道とは何か」「公平とは何か」といった根源的な問いを改めて考える貴重な機会となりました。参加者からは、「未来の共生社会のあり方を考えるうえで、非常に意義深い学びの機会となった」との声も寄せられました。
東京財団は、人口減少が進む中で我が国が抱える様々な社会課題を解決すべく、調査研究を展開しておりますが、このような活動を行う上で、過去の取り組みや歴史を振り返ることも重要と考えております。そのため、今後も東京財団では、国内外の政府機関や大学等研究機関との連携・協力をさらに強化してまいります。より一層のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
 登壇者の皆様(事務局撮影)
登壇者の皆様(事務局撮影)
特設ページはこちら
