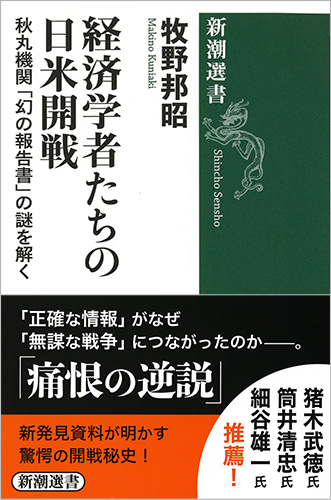 評者:村井 哲也(明治大学法学部非常勤講師)
評者:村井 哲也(明治大学法学部非常勤講師)
日米開戦研究の新境地
日米開戦をめぐる意思決定の謎は、現代でも大きな関心を集める一大トピックである。両国間の明らかな国力差にもかかわらず、なぜ無謀な意思決定はなされたのか。
この謎には、すでに歴史研究で膨大かつ詳細な蓄積があり、絶え間なく歴史小説やドキュメンタリー番組が世に送りだされている。くわえて、戦争責任など歴史認識問題に関わってくるだけに、繊細なバランス感覚が求められる。言い換えれば、本格的な新規参入を果たすには少々ハードルの高いトピックでもある。
本書は、日米開戦をめぐる国力評価をなした陸軍省戦争経済研究班―通称「秋丸機関」―に焦点を当てることで、このハードルを軽々と超えてみせている。日米開戦研究の新境地を拓く傑作と言ってよい。著者の貪欲かつ真摯な資料収集、説得的な論理構成、それらを展開していく絶妙な筆致は、各方面から高い評価を集めている。
通説では、秋丸機関の客観的かつ正確な国力評価にかかわらず、「愚か」な軍部が無謀な日米開戦に踏み切り、秋丸機関の報告書は軍部に都合が悪い機密扱いゆえ焼却された、とされてきた。だが著者は、軍部に批判的なはずの丸山眞男が戦前のエリート軍人たちを「よほど合理的だった」と高く評価していることに、まず注意を喚起する(3頁)。
起訴保釈中であったマルクス経済学者の東京帝大教授・有沢広巳らを秋丸機関にスカウトしてまで客観的かつ正確な国力評価を求めたのは、他ならぬ軍部であった。この疑問から著者は、経済史学者ならではの鋭い洞察で神話化した通説を覆しつつ、日米開戦をめぐる意思決定のスリリングな謎解きに耽溺していくのである。
目次
はじめに
第一章 満州国と秋丸機関
第二章 新体制運動の波紋
第三章 秋丸機関の活動
第四章 報告書は何を語り、どう受け止められたのか
第五章 なぜ開戦の決定が行われたのか
第六章 「正しい戦略」とは何だったのか
第七章 戦中から戦後へ
おわりに
本書の概要① ―秋丸機関の軌跡―
まず、本書前半の各章に沿って秋丸機関の軌跡を概観する。
第一章は、秋丸機関が創設された経緯が描かれる。秋丸次朗は、満州国の経済建設にあたり「関東軍の頭脳」と呼ばれた東京帝大経済学部卒のインテリ軍人であった。ノモンハンの惨敗や第二次世界大戦の勃発を受け、岩畔豪雄軍事課長から「経済謀略機関」の創設を依頼されたのは、陸軍省経理局兼軍務局課員として帰国した1939年9月のことである。
経済戦争を中心とする国家総力戦への対応が急がれるなか、満州国の資源開発の経験から秋丸は、自国勢力圏での自給能力こそが国力評価の基準であると看破する(25-27頁)。後の「抗戦力」に繋がる認識である。1940年1月に秋丸機関は創設され、各省の革新官僚や満鉄調査部の精鋭、有沢はじめ多分野の学者がスカウトされ5月に陣容は整った。
第二章は、大日本帝国憲法における意思決定不全を克服する試みであった近衛新体制が秋丸機関に与えた影響を指摘している。「持たざる国」日本の経済力を超えた日中戦争の軍事費負担によって、国家目的に沿った統制経済は必至とされた。そのための運動である経済新体制の司令塔こそ秋丸機関であり、世間もそのようにみなしていく。
しかし、右翼、議会、財界の強い反発で1941年4月に近衛新体制の政治的な挫折が明白となった。これは2つの点で転機となる。第1に、「アカ」批判で有沢は表向き解嘱を余儀なくされるなど秋丸機関は憲兵監視下に置かれた。第2に、憲法上の意思決定不全が継続されたことで、日米開戦という「重大な意思決定」をなす基盤が残された(53頁)。
第三章は、『班報』の解読により1940年夏から本格化した秋丸機関の活動と認識が分析される。目を引くのは、日本経済の脆弱性と英米への輸入依存という悲観的な見通しを明確に立てていたことである。ただし、これは他機関も指摘した予想通りの内容であり、陸軍から批判もなかった。1941年前半まで、こうした国力の限界は正確に認識されていた。
「アカ」批判による企画院事件で主要メンバーが検挙され全体の研究が遅延するなか、有沢と秋丸は中間報告『経済戦争の本義』を1941年3月に著す。そこで最重要の概念であり後に焦点となったのは、敵の戦争経済の「抗戦力」をどれだけ破壊できるかでなく、自国の戦争経済への「抗戦力」をどれだけ守れるかにあった(74-77頁)。
第四章は、1941年7月に作成された報告書を解読していく本書の白眉である。まず英米分析は、日米の経済力格差の認識で一致しながら、有沢はアメリカへの長期抗戦力の不可能を強調し、秋丸は英米間の輸送力の弱点を挙げ短期抗戦力(2年)の可能性を匂わせていた。両者の微妙な認識の違いは、より悲観的なドイツ分析で明らかとなる。
ドイツによる大西洋での英米船舶撃沈を渇望する日本にとり、独ソ戦の長期化による激しい疲弊は最大の懸念であった。ここで促される日本の選択は、対ソ参戦していたずらに消耗する「北進」でなく南方資源を獲得する「南進」である。そして、以上の分析は、当時の雑誌や新聞で開陳されていた常識の範囲であり機密でも何でもなかった(103-109頁)。
筆者はこう通説を覆したうえで、報告書の核心部分に迫る。秋丸は、陸軍省経理局兼軍務局の課員であった。報告書は、「北進」を唱える陸軍参謀本部を牽制し、「南進」を唱える「軍務局の意向に沿う」性格を帯びたものだったのである(126-130頁)。
とはいえ報告書は、悲観的な見通しを正面からとらえた客観的かつ正確な国力判断でもあった。これが、どのようにして「愚か」な開戦決定をもたらしたのであろうか。
本書の概要② ―日米開戦の意思決定をめぐって―
続いて、本書後半の各章に沿って日米開戦の意思決定の内実や秋丸機関の顛末を概観する。
第五章は、最新の理論を駆使して日米開戦の謎に迫る。行動経済学によるプロスペクト理論では、損失発生が確実な場合にリスク愛好的な意思決定がなされやすいとされる。つまり、報告書で指摘された高い確率での長期抗戦力の不可能は、むしろ同時に指摘された低い確率での短期抗戦力に賭けさせる結果をもたらしたのであった。
集団心理学による集団意思決定では、極端なリスキーシフトである集団極化が起りやすいとされる。これは、スペインのフランコのように強力なリーダーが存在する場合でなく、統帥権が独立して首相が弱体な大日本帝国憲法で格好の条件を提供するものであった。
だが、理論以上に重要と思われるのは、アメリカの経済制裁が大々的に報道され、「不当な圧力」として国民世論が対米強硬論で沸騰したという箇所である(163-164頁)。こうして、客観的かつ正確な国力判断が広く認知されながらリスキーシフトは加速されたのである。
第六章は、秋丸機関の戦略への評価を試みている。そもそも戦略で解決できる問題でなかった、と著者は指摘する。日独両国は共通の目標も戦略もなく、互いにないものねだり のまま個々に戦い個々に敗れたからである。秋丸機関も、日本の抗戦力を過大評価しアメリカの抗戦力を過小評価していた。
それでは、秋丸機関に参加した経済学者はいったい何ができたのであろうか。著者は、時間稼ぎで国際環境の変化を待つ「レトリック」が必要だったという。ネガティブな現実を突きつけるよりポジティブな3年後への抗戦力プランを示せば、リスキーシフトを防げたはずだったというのである(202-204頁)。
第七章は、秋丸機関の顛末を描いている。開戦前後のゾルゲ事件や満鉄調査部事件は、もともと「アカ」批判を受けていた秋丸機関への警戒心を増し、ついに1942年末に解散へと追いやった。しかし秋丸機関のメンバーらは、停戦後の米英ソの離間を図るというポジティブなレトリックを編みだし、終戦工作へ一定の寄与を果たしていく(222-223頁)。
有沢は戦後、吉田茂首相の私的諮問機関で、戦時の抗戦力測定の経験から経済の拡大再生産を図る傾斜生産方式を唱えた。しかし有沢の真意は、その政策効果でなく、そこからGHQの信用を得て復興に必要な重油輸入を得るというレトリックにあった。秋丸機関の失敗の経験から、戦後復興へ一定の寄与を果たしたのである(234-235頁)。
「おわりに」で著者は、現代にも通じる普遍的な課題を示している。自らも経済学者として、日米開戦という重い意思決定において「経済学者には何ができたのだろうか」と、改めて自問自答するのである(239-240頁)。
容易に答えが出るはずもない。しかし著者は、歴史を学ぶ意味は、そこから現代への教訓を読み取ることであるとする。そして、本書がエビデンスとヴィジョン、そしてレトリックを使って、より良い選択をするための考える機会となることを願うのである。
評価:優れた歴史研究リテラシー
本書の概要を踏まえ、その評価を試みたい。前述した通り、日米開戦研究の新境地を拓く本書は各方面から高い評価を集めている。ここでは、既存の評価との重複は避け、主に歴史研究における資料解釈はどうあるべきか、という根源的な視点から評価を試みたい。
本書が高水準の歴史研究を示しえたのは、著者が近年に急進展するデータベース化とデジタル化を貪欲に駆使したことにある(70-71、87-88、238頁)。この歴史研究の変化の波に乗ったことで、さらに資料を俯瞰的に相対化する著者の真摯な姿勢がさらに際立ったように思われる。
これまでの歴史研究では、特定のコネクションを持つ研究者ないし研究集団が特定の資料へのアクセスを独占しがちであった。もちろん、提供者との信頼関係や発見努力の報いとして必然のことではある。他方で、アクセス独占が公平な資料解釈を阻み、発見努力による思い入れの深さから資料解釈に偏りをもたらすことが多々あることも否めない。
著者は、秋丸機関報告書の発見に多大な努力を費やしながら、こうした歴史研究の落し穴に陥っていない。当時の新聞・雑誌を渉猟することで秋丸機関の分析内容が同時代的に常識であったことを突きとめ、そこから報告書を俯瞰的に相対化していった。
日米開戦研究には膨大かつ詳細な蓄積がありながら、多くの歴史研究者が盲点を衝かれる新視点が本書に満載された背景には、このような資料解釈でこそ勝負するという真摯な姿勢がある。それだけではない。資料の俯瞰的な相対化には、当然ながら「行間を読む」力量が問われる。その源泉は、著者の幅広い学際性にある。
まず、経済史研究者としての著者の手堅い力量が前提である。日米開戦は、経済戦争を中心とする国家総力戦の時代の真っただ中にあった。その時代に醸しだされた資料を読み解くには、経済史への専門知識が欠かせない。ゆえに著者は、政治史をはじめとする歴史研究者が読み解きがたい「行間」を自由自在に行き来した。
同時に、政治史をはじめとする歴史研究の膨大かつ詳細な蓄積も読み解かねばならない。国家総力戦における経済的な「抗戦力」という概念が持つ意味を読み込んだうえで、日米開戦の政治的な文脈を浮かび上がらせた場面は、その最たるものであろう。著者は、これらを的確に消化したうえで、経済史研究との架橋を果たす力量を示している。
本書は、貪欲かつ真摯な資料収集、公平かつ俯瞰的な資料解釈、そして専門性を横断する学際性を備えている。すなわち、多くの研究者がお手本とすべき、多くの読者が学ぶべき「歴史研究リテラシーの書」としてこそ、評価され直すべきであろう。
論点:政治権力と専門家のディレンマ
本書に若干の違和感もある。それを指摘しつつ、現代にも通じる普遍的な課題を抽出したい。
違和感を覚えたのは、本書後半で頻出する「レトリック」の必要性についてである。もちろん、秋丸機関の顛末話やブレーン集団の戦略論として、その趣旨は理解できる。有沢たち経済学者たちは、レトリックの不足を心から悔いていたかもしれない。
とはいえ著者は、日米開戦を阻止するレトリックについて、「必ずしもエビデンスに基づく必要はなく、極端な場合、事実や数字を捏造しても良かっただろう」(203頁)とまで踏み込んでいる。このレトリックの危険性への無自覚さは、さすがに勇み足であろう。
そもそも、秋丸機関の客観的かつ正確な国力評価という本書の分析視覚そのものが揺らぎかねない。しかも、秋丸機関は軍務局の意向に沿って報告書で「南進」を促すという、やや際どいレトリックを駆使している。それは結果として日米開戦に格好の口実を与え、レトリック不足というより、レトリックが策に溺れてしまったと言えなくもない。
もっとも、この勇み足は些末な問題にすぎない。本書が暗示する普遍的な課題こそ掘り下げていくべきであろう。全ての専門家にとって、自らの専門性と信念を現実の意思決定に反映させるべく政治権力へ接近するリスクは不可避である。時に、政治権力の意向を忖度して献策内容にレトリックを駆使することは不可欠であろう。潔癖症では何も変わらない。
一方で、政治権力への接近とレトリックの駆使が進むにつれ、客観的かつ正確であったはずのエビデンスは政治性を帯び、専門家の正統性(信頼性)は失われていく。実際にそのようなケースは、古今東西を問わず無数に存在する。時に、政治権力への接近と専門家の正統性はトレード・オフの関係に陥らざるを得ないからである。
このディレンマに対峙して困難なバランスを取ることは、全ての学者、ジャーナリスト、あるいは政治権力と接する機会の多い官僚にとっても普遍的な課題である。そう考えれば、著者によるレトリックの勇み足は、「経済学者に何ができたのであろうか」と自問自答する姿勢が、それだけ本気だったことの表れなのかもしれない。
その危険性に自覚的ならば、レトリックをめぐる言説は歴史研究と政治研究に新たな土壌をもたらすように思われる。筆者がその成功例とした終戦工作や傾斜生産方式と失敗例とした秋丸機関との分水嶺は、果たしてどこにあるのか。専門家たちは、どのようなディレンマに葛藤してきたのか。逆に政治権力の側は、専門家にどのように対峙してきたのか。
また、第六章で著者が、レトリックで日米開戦を回避できた可能性に言及しつつ、「もちろん硬化している国民世論をどう説得するか」という問題は残る、とさりげなく指摘した箇所は実に重要である(203頁)。専門家のレトリックは、世論を矯正する存在なのか、操作する存在なのか。近年のメディア史研究やポピュリズム研究と共振する部分は多いであろう。
以上のように本書は、優れた歴史リテラシーの書でありながら、現代への教訓となる普遍的な課題を満載している。きっと多くの読者が、我が身に置きかえて振りかえりたくなるに違いない。本書が現れたことを喜びつつ、著者のさらなる研究の発展を期待したい。
