
東京都立大学法学部教授
詫摩佳代
新型コロナウイルスを巡っては「アフターコロナ」という言葉が定着してきた。その流行やそれへの対応が我々の社会や政治、経済を大きく変えるという認識がその前提にはある。新型コロナウイルスに限らず、感染症の流行は、時に社会や政治を大きく変えてきた。ちょうど100年前に流行したスペイン風邪もその一つであろう。第一次世界大戦の兵士の波に乗って流行し、スペイン国王やウィルソン米大統領、マハトマ・ガンディーなど多くの著名人も罹患した。社会を麻痺させ、戦況に影響を与え、また国境を越える保健協力を進展させる契機となった。
それから1世紀を経た現在、我々は再び感染症と闘っている。スペイン風邪をきっかけに発展してきた保健協力の枠組みは今、大きな試練に晒されている。そもそも国際的な保健協力はなぜ、どのように発展してきたのか。今後、どのような方向に進んでいくのだろうか。歴史を振り返りつつ考えていきたい。
| ・第一次世界大戦と保健協力 ・アメリカのイニシアティブ ・国際保健協力の改革の行方 ・次なるパンデミックにいかに備えるか |
第一次世界大戦と保健協力
1918年にアメリカが第一次世界大戦に参戦すると、アメリカで発生した新型のインフルエンザ(後のスペイン風邪)は、兵士や船の移動とともに世界全体へと広がった。1919年1月に始まったパリ講和会議でも、ウィルソン大統領をはじめとするアメリカ代表団員が罹患、この時までに世界人口の約1/3が感染、約5000万人が亡くなったとされる。
同時期に流行したのはスペイン風邪だけではなかった。戦時中にはマラリアも流行したし、ロシアでは発疹チフスも流行した。特にチフスは兵士や難民の移動、ロシア革命や内戦から逃れる人の波に乗って、大戦後も東欧で広く感染が続いた。以上のような経験は、既存の保健協力の限界を露呈し、国際協力の発展を促すこととなった。この時までに1903年に締約された国際衛生協定とそれを監督する国際公衆衛生事務局が存在していたが、その対象はコレラ、ペスト、黄熱病の情報収集・分配機能に限定され、大規模な感染症流行への機動力は備えていなかった。ポーランドは赤十字と国際公衆衛生事務局に支援を依頼したが、支援に足りるだけの資金や人材を用意できなかったのだ。設立されたばかりの国際連盟はその規約第23条で疾病の予防及び撲滅を機能としていたこともあり、感染症委員会を設置、ポーランドに派遣して状況の改善に大きく貢献した。その後、感染症委員会の活動は国際的に大きく評価され、1923年秋に国際連盟保健機関(LNHO)が設立された。
ちなみにスペイン風邪やチフスの流行は、国境を越える保健協力のみならず、各国の保健システムを見直す契機ともなった。ヨーロッパの多くの国では公共のヘルスケアシステムが整備され、また保健省の地位改善の契機ともなったのだ。
アメリカのイニシアティブ
アメリカは国際連盟に加盟しなかったが、非公式な形で戦間期の保健協力に関与した。アメリカのロックフェラー財団は国際連盟に多くの資金を投じたし、アメリカの医学者たちも国際連盟保健機関の官僚たちとの連携を保った。当時のアメリカでは革新主義の影響もあり、疾病を予防し健康を維持するためには、行動様式の変化や保健システムの整備が必要だという見方が盛んであった。連盟保健機関はその影響を強く受け、感染症情報の集約拠点としての機能を向上させることに加え、アジアでの衛生設備改善や専門家のインターンといった事業も手掛けた。
アメリカは第二次世界大戦中も国際連盟保健機関と協力しつつ、連合国陣営の感染症管理に尽力、その経験から世界保健機関(WHO)設立を主導した。国境をこえる感染症には国境を越える枠組みが必要という認識に加え、感染症や食糧など機能別の協力関係を地道に積み重ねることが、戦後のリベラルな秩序の基盤になるだろうという期待もそのイニシアティブの背後にはあった。
戦後においても、例えば天然痘の撲滅やポリオの抑制などの主要な功績は、アメリカをはじめとする先進国の資金と医薬品等の資材に大きく依拠してきた。他方、アメリカはその圧倒的な資金力をテコに、保健協力をアメリカに都合良く維持する、あるいは変更させるということをしばしば行ってきた。例えばパレスチナ解放機構(PLO)が1989年に正式加盟を申請した際、アメリカは分担金の支払いを停止すると発表、当時の事務局長はアメリカからの支払いが停止されれば困るとして、アラファト議長に申請を取り下げるよう直訴した経緯もある。このほかにも、WHOが発表した必須医薬品リストや、糖分の摂取量に関する勧告を出した際にも、米国内の製薬会社や砂糖協会らとともに、WHOに対して分担金の支払い停止をちらつかせて撤回を迫ることもあった。
国際保健協力の改革の行方
戦前から長きに渡って保健協力を支えてきたアメリカにとって、そこに割り込むかのような中国を黙って見ていられないというのが本音だろう。中国は近年、WHO事務局長を一帯一路ハイレベル保健会合に招いたり、中国製の医薬品の活用に関する協定をWHOと締結したり、保健協力に熱心に取り組んできた。しかし中国のWHOに対する影響力とは、アメリカのそれとは比べものにならない。WHOの歳入は加盟国の分担金と拠出金からなるが、アメリカはいずれも多くを拠出してきた。2019年度の歳入のうち、アメリカは14.67%を占め首位、それにビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団(9.76%)、GAVI Alliance(8.39%)、イギリス(7.9%)らがそれに続く。中国はなんと全体の0.21%を占めるに過ぎない。トランプ大統領によるWHOへの拠出金停止の発表はそのような中で行われた(2020年4月14日、ホワイトハウスにて)。アメリカは一見WHOを突き放しているように見えるが、実際にはその手綱を放したわけではなく、むしろ締めることで自身の思うように変えようと試みているにすぎない。
それではその改革とはどのようなものになるのだろうか。第一は感染症対応枠組みの強化である。感染症が発生した際には、国際保健規約に則り、各国がそれぞれ水際対策や国内の感染状況を把握し、WHOに報告することが求められるが、中国を含め世界の約7割の国がそのような能力に欠いているとされる。ポンペオ国務長官は新型コロナウイルスの発生源を調べるべく、中国に調査官の立ち入りを認めるよう要請している。アメリカと並んでオーストラリアも、各国の自発的な申告に依拠している現体制に疑問を呈し、WHOに発生国の同意なく当該国に立ち入り、感染症の流行状況について調査できる権限を与えようという改革案を提示している。米豪の提案に中国は猛反発しているが、今後何らかの強制的な措置がアメリカの主導で確立される可能性は高いだろう。
第二はWHOの能力不足を補うような改革である。そもそも、近年では感染症の流行が世界経済、政治に大規模に影響を及ぼすため、WHOの手に追えない事態が目立つ。エイズについては国連合同エイズ計画(UNAIDS)という新たな組織が作られ、エボラ出血熱の時には国連エボラ緊急対応ミッションという暫定組織が設立された。グローバル化社会の大規模な感染症に対しては、資金や人材に限りあるWHOが単独で対処するには重荷すぎる感もある。WHOという機軸を残しつつも、世界規模の危機に立ち向かうための、多様なアクターとの連携体制の確立も急務となろう。
WHO事務局長ポストも大きな争点となるだろう。これだけ国際的な信頼を失えばテドロス事務局長の続投は難しい。事務局長はWHO執行理事会が絞り込んだ候補を世界保健総会(WHA)で投票して決定されるわけだが、米中がそれぞれ次期事務局長候補を立て、激しい選挙戦が繰り広げられると予想される。
改革の第四は台湾に関するものとなろう。台湾は2008-2016年まで世界保健総会にオブザーバーとして参加していたが、独立志向を強める蔡英文総統が就任して以来、中国の圧力により完全にWHOから締め出された。コロナを巡っては、日米らの強い希望もあり、中国は台湾の専門家が個人の資格でWHOの専門家会合に参加することを渋々認めた。その後もアメリカは台湾のWHO参加を推しており、アメリカの圧力次第では、中国は例えば台湾のオブザーバー参加を認めるなど、妥協を余儀なくされるであろう。
次なるパンデミックにいかに備えるか
他方、以上の提案が実行され、定着するか否かは予断を許さない。WHOの改革にはWHO憲章や感染症対応のための国際保健規約の改正が必要であり、加盟国の一定数以上の賛成が必要だからである。また、たとえそのような手続きを通過したとしても、それを持続させるには加盟国の政治的意図が不可欠である。アメリカが提案する改革に対し、中国が反発する可能性は高く、国際保健協力の舞台で米中の争いが続くことが予測される。しかし保健協力の主体は米中だけではない。フランスや日本といった多くの国も、WHOの機能や加盟国の対応能力を高める必要性を認識しており、改革の推進力になりうる。またWHO側には、冷戦期のWHOが米ソに対して行なっていたように、対立する米中双方への細やかな対応が求められるのだろう。時代の変化とともに、保健協力のあり方や必要な機能は更新される必要がある。それを実行に移すのは容易ではないが、多様なアクターの利害関係を一つの目標―感染症から人類を守る―に向けてすり合わせるためのリーダーシップと知恵が今、求められている。
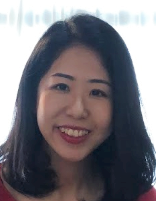 詫摩佳代(たくま かよ)
詫摩佳代(たくま かよ)
1981年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程単位取得退学。博士(学術)。著書に『国際政治のなかの国際保健事業』(ミネルヴァ書房、2014)、『人類と病』(中公新書、2020)、共著に『新しい地政学』(東洋経済新報社、2020)など。
