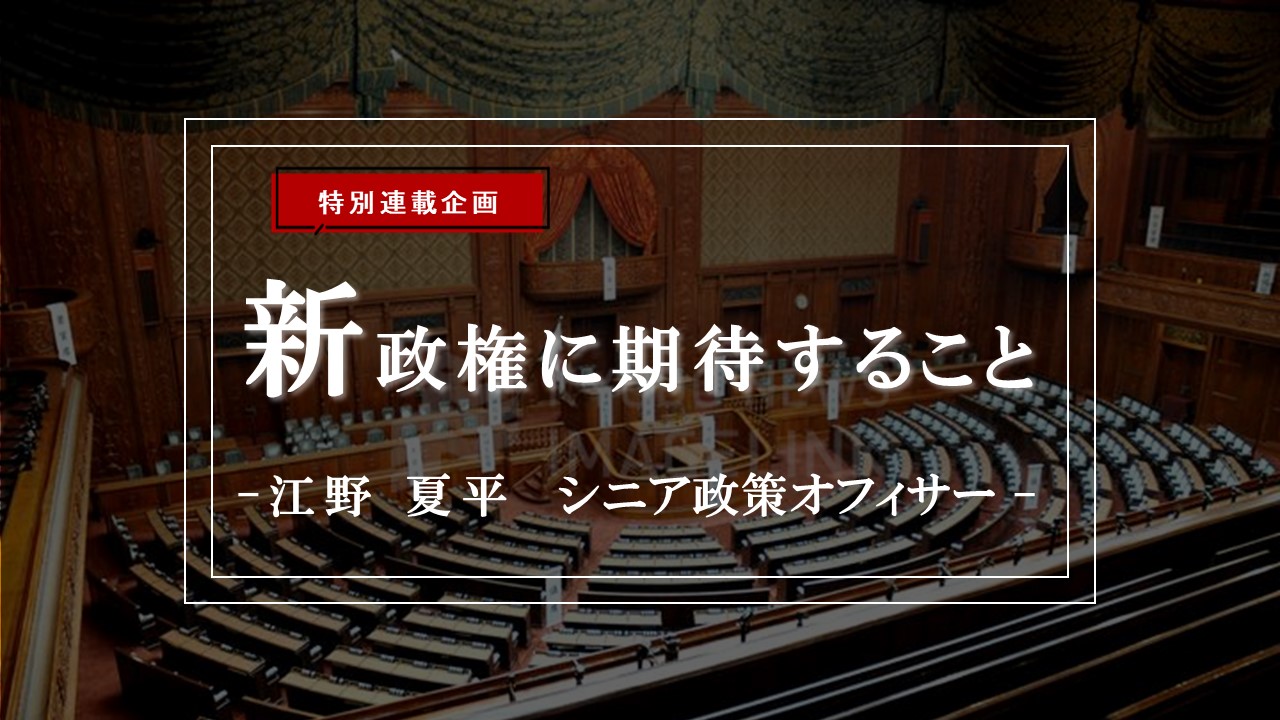
- Review
【特集】新政権発足に寄せて―政策論争の再興と政治報道の転換― 政局から政策へ 政治とメディアが変わる時
October 23, 2025
2025年10月21日に開催された第219回臨時国会で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されました。新政権の発足に寄せて、東京財団の政策プロデューサーと常勤研究員が、「これから期待すること」について各専門分野から論じます。
高市早苗氏を首班とする自民党と日本維新の会の連立政権が発足し、安定多数にはとどかないものの、自民党と日本維新の会を合わせて衆議院の過半数を確保したことは、日本政治の新たな局面を示す出来事となった。両党は理念のすべてを共有しているわけではないが、行政改革、地方分権、教育再生といった具体的な政策課題を軸に協調を図る姿勢を明確にしている。それは、従来の「政権を取ることを目的とする政治」から、「政策を実現する政治」への転換を象徴している。日本の政治は、いまようやく「数の論理」や「権力の維持」を超え、何を、どのように実現するかを問う段階へと踏み出した。
この変化は、政治だけでなく、報道の現場にも確実に広がっている。これまでの日本の政治報道は、「どの政党が政権を担うのか」「どの派閥が主導権を握るのか」「連立の枠組みはどう変化するのか」といった政局や人事に焦点を当ててきた。そこには人間ドラマがあり、視聴者や読者の関心を引きつける要素があると考えられてきた。結果として、政治の本質的課題が脇に追いやられ、表層的な動きばかりが繰り返し報じられる状況が長く続いた。その背景には、報道の軸そのものの歪みがあった。派閥の駆け引きや人事予測を中心に据える方が、視聴率や購読数を確保しやすいとの判断が優先され、政策論争は「難解で伝わりにくい」「堅苦しく地味」とみなされて取り上げられる機会が減っていった。メディアは、国民の関心がどこにあり、どの程度まで政策的な理解が可能なのかを十分に把握せず、複雑な課題を丁寧に解きほぐして伝える努力よりも、即時性とわかりやすさを重視する構成へと傾いた。その結果、報道は「伝える」よりも「見せる」ことを目的化し、政治の本質から次第に距離を置くようになっていったのである。
だが、いま政治と報道が、ともに転換期を迎えている。高市新総裁誕生後に生じた一時的な政治空白は、政治家とメディアにとって立ち止まり、自らの役割を見つめ直す貴重な時間となった。この空白は単なる停滞ではなく、政治が政策の中身を、メディアがその伝え方を再点検する「熟考の時間」であった。いま、国民の関心が政局や人事よりも、生活をどう良くできるかという政策提案の内容と実現性へと移りつつあるとの認識が、報道現場に広がっている。
政治の焦点が「誰が」から「何を」に移る中で、各党の政策論争も具体性を増している。象徴的なのが、国民民主党が提案した「年収の壁」引き上げ政策である。社会保障制度の構造的制約を是正し、働く意欲を損なわずに可処分所得を増やすことを狙うこの政策は、低所得層支援を超え、中間層をも包含する生活支援策として注目を集めた。与野党を超えて「手取りを増やす経済」という共通課題が共有されつつある点に、政治の質的変化が表れている。対立のための対立ではなく、政策の成果を国民の前で比較し合う「政策論争型政治」への移行が鮮明になっている。
一方で、高市政権が掲げる「科学技術立国」も、政策の重心が変化していることを象徴している。研究開発やイノベーション投資を成長の基盤に据え、経済の自律的な競争力を高めるとともに、「分配なくして成長なし」との立場から税制や社会保障を通じて格差を是正する。給付付き税額控除や社会保険料負担の軽減といった施策は、「成長と分配の両立」を掲げる実践的経済政策の一環であり、理念ではなく結果を問う政治の姿勢を体現している。
こうした政治の変化は、報道の姿勢にも明確な変化をもたらしている。従来、政治報道は派閥や人事の動向を追い、権力構図を分析することに重点を置いていたが、連立政権発足以降は、物価対策、社会保障制度改革、地方財政の健全化など、生活に直結する課題が報道の中心に据えられるようになった。NHK「日曜討論」や民放各局の情報番組でも、閣僚や党首が政策の実現可能性や財源の裏付けを問われる機会が増えており、理念やスローガンではなく、実行力や持続性といった具体的指標に基づく議論が行われている。
視聴者にとっても、「どの政党が何をどこまで実現できるのか」という政策遂行力の差が、政権選択を判断する上での重要な基準になりつつある。報道が政策比較を行うことは、単に政治を評価する材料を提供するだけでなく、政策を育てる行為でもある。メディアが政策形成の一端を担い、政治と国民をつなぐ「検証者」として機能し始めたともいえる。
この報道姿勢の変化を支えているのが、国民意識の成熟である。SNSや動画配信サービスなどの普及により、国民は自ら情報を取捨選択し、政策の妥当性を主体的に判断するようになった。メディアはもはや「解説者」ではなく、「検証者」としての責務を問われている。派閥や人事への関心は薄れ、物価、賃金、年金、社会保障など、生活に直結する課題への注目が高まっている。政治を評価する基準は、政党名や政治家の顔ではなく、政策の内容と実現性へと移り、「それが本当に自分たちの生活を改善するのか」という実感が政治を見る新しい軸となっている。
こうした国民の変化に応じて、メディアも自らの存在意義を問い直している。政治を「見せる」報道から、「共に考える」報道へ。単に権力を監視するだけでなく、政策を検証し、時に育てていく視点が求められている。制度の欠陥を暴くだけで終わるのではなく、より良い制度設計の可能性を示し、政治に建設的な刺激を与えること——それこそが、民主主義社会における報道の使命といえるだろう。
政治空白は本来、望ましい状況ではない。だが、その時間を「熟考の機会」として政策議論の深化につなげられるかどうかは、政治とメディアの姿勢にかかっている。この期間は停滞ではなく、政治家・メディア・国民が政策を見直し、学び直す契機となった。偶発的に生じたこの経験を一過性に終わらせず、政治文化として定着させられるかが問われている。
政治の本質は、派閥の均衡でも顔ぶれの刷新でもない。国民が「生活が確かに良くなった」と実感できる成果こそが、政治の正統性の根拠であろう。メディアは、批判にとどまらず政策を育てる視点を持ち、制度や仕組みの課題を指摘するだけでなく、より良い方向性を示す報道へと進化することが求められている。
政治とメディアが互いに緊張関係を保ちながらも、国民の生活を豊かにするという目的を共有するとき、日本の政治と報道は停滞を超え、次の段階へと進むことができるだろう。政策論争の再興は、政治と報道がともに成熟へ向かうための出発点にすぎない。
