
鶴岡路人
主任研究員
英国は1月31日の英国時間23時(ブリュッセル時間24時)をもって、EUを離脱する。2016年6月23日の国民投票で離脱派が勝利してから、約3年7ヶ月である。長くて短い期間だっただろうか。
離脱日は当初2019年3月29日とされた。それに向けて2018年11月には当時のメイ政権とEUとの間で離脱協定が合意されたものの、英議会は同協定を繰り返し否決した。そのため、英国はEUに対して離脱期日の延期を求めることになり、結局3度にわたって延期され、2020年1月31日になった。離脱の実現を目前に控え、連載最後となる今回は、Brexitとは何だったのか、そして何をもたらすのかを改めて考えることにしたい。
何だったのか
Brexitはやはり偶然だった。どちらに転んでもおかしくなかった。この点は何度でも繰り返す必要がある。
離脱という現実を前にすれば、それが必然だった、あるいは運命だったと考える方が頭の整理はつきやすいかもしれない。残留派にとっても諦めがつく。グローバル化やEU統合の恩恵を実感できずに、取り残されたと感じる労働者の不満、移民増加への不安、ブリュッセルという遠いところで政策決定が行われることへの反発など、離脱票の背景にはさまざま指摘することが可能である。しかし、それらが不可避的に離脱をもたらした十分条件だったとはいい難い。
今回の離脱は、偶然が幾重にも連続した結果だと理解する方が現実に則している。第1に、残留か離脱かを問う国民投票の実施自体が偶然の産物だった。キャメロン首相の国民投票実施提案は保守党内の離脱派を抑えるための方策だったし、2015年総選挙で単独政権にならなければ政府の政策にはならなかった。第2に、2016年6月23日の国民投票結果も、どちらに転んでもおかしくなかった。無数にあった要因のうち、いくつかでも違えば、異なる結果になっていただろう。国民投票で、18歳から24歳の約73%が残留を支持した事実は重い。
第3に、2019年12月12日の総選挙である。ジョンソン首相率いる保守党は議席数に関する限り大勝した。しかし、前回、「Brexitカウントダウン(21)」で触れたように、保守党の得票率は微増(1.2ポイント)に過ぎず、英国民がジョンソン政権下でのBrexitを突如として熱狂的に支持したのではない。世論は「変わらなかった」のである。それでも保守党大勝となったのは、残留派の分裂と小選挙区制度ゆえである。
つまり、Brexitへの賛否については国内が真っ二つに割れたままなのだが、少なくとも3つの大きな偶然を経て、英国はEUから離脱することになった。
離脱派にとってのBrexitは、「主権を取り戻す」行為だった。しかし、主権を観念的・象徴的なものとしてではなく、英国の国家としての影響力という観点でとらえれば、EUからの離脱は大きなマイナスである。
経済面に関して、離脱派の一部からは、「EUの足かせから自由になり、世界に羽ばたく英国」という離脱後の展望が聞かれる。ジョンソンも「離脱の果実」という表現を使う。しかし、離脱によってマクロ経済にプラスの影響がもたらされるとする経済分析は皆無に等しい。
離脱交渉を振り返れば、経済的損失をいかに小さくできるのかが問われてきたとも、あるいは、それでも重要だったのは経済的考慮ではなく政治的考慮だったともいえる。立場によって異なるロジックに基づき、異なる景色がみえていたのが、Brexitのプロセスだった。
それゆえに、Brexitをめぐって英国内の対立は激化し、政治は混迷を極めたのである。つまり、離脱派・残留派双方の納得できる解決策は存在しなかった。あるいは、より正確にいえば、メイ政権もジョンソン政権も、真の意味で双方の声に応える努力をしなかったということでもある。
メイ首相は「離脱は離脱(Brexit means Brexit)」と唱え、ジョンソン首相は「離脱に決着をつける(get Brexit done)」と連呼した。国民投票結果は離脱票が約52%、残留票が約48%だったが、最初から48%の国民は無視されたに等しい。それでは国はまとまりようがない。
2019年12月の選挙により、EUとの離脱協定が英議会で承認される政治的状況は出現したものの、Brexitをめぐる国内の利害関係や意見の対立という基本的構図には、何の変化もないのである。
英国との離脱交渉におけるEUの姿勢に関しては、物、人、資本、サービスの自由移動に基づく単一市場の不可分性を強調し、「いいところ取り」は許さないなど、厳しい姿勢を貫いたイメージがあるかもしれない。実態としては正しい理解だが、EU側にとっても初めての経験であり、試行錯誤だった。このプロセスにおいて、「EU27」(英国以外のEU加盟国)の結束が維持可能か否かについては、当初、懸念の声が少なくなかったことも忘れてはならない。
それでも結束することができたのは、離脱交渉に関する限り、精算金や英国在住のEU市民の権利保護など、目的が明確だったうえに、EU27の将来をかけたものだったからである。ただし、EU27にとっても、離脱交渉で期待できるのは利益ではなく、損害をいかに小さくできるかが課題だった。その意味で、勝者のいない交渉が、英国のEU離脱過程だった。
何をもたらすのか
勝者がいない交渉は、1月31日の離脱後も続くことになる。2月から本格化するのは、FTA(自由貿易協定)を含むEU・英国間の将来の関係を構築するための交渉である。これまでの離脱交渉よりも数段困難であるといわれる。
そもそも、何を目指すのかについても、EUと英国の間でコンセンサスがあるわけではない。ジョンソン政権は野心的なFTAだといいつつ、2020年末までの移行期間を本当に延長しないとすれば、包括的なFTAで妥結にまで至るのは、現実的に考えてほぼ不可能である。期日を優先するのであれば、物品貿易を中心とする限定的なFTAにならざるを得ない。
そしてこれは世界で初めて、貿易を自由にするためではなく、不自由にするためのFTA交渉になる。自由貿易の原則が挑戦を受け、統合ではなく分裂に進む今日の世界を象徴しているのかもしれない。
これまで加盟国の増加(拡大)を続けてきたEUにとって、Brexitは、加盟国を失う初めての経験となる。欧州統合にとっての象徴的な曲がり角になるのだろう。EU28カ国のなかでの英国は、GDP(国内総生産)で約15%、人口で約13%を占める存在だったが、同国が離脱することの影響はそうした数値以上のものになる。経済面では、金融やサービス分野での英国の存在は大きかったし、外交・安全保障においては、フランスと並ぶ欧州の中心的アクターだった。そんな英国がEUから離脱するのである。EU内での、英仏独という大国間のバランスも崩れる。
それゆえに、EU27の間にはEUの弱体化への危機感が存在し、特にEUの対外関係(EU外交)の強化が模索されている。欧州の「戦略的自律性(strategic autonomy)」や、「地政学的な欧州委員会(geopolitical European Commission)」といった議論が盛んになるのは、そうした文脈である。
しかも、「小さくなるEU」が漕ぎ出す海はまさに荒波なのである。欧州大陸では地政学的脅威としてのロシアが復活し、その積極的な行動はシリアなどの中東にも及ぶ。米国とイランとの対立の激化は、欧州の無力さを改めて露呈する結果になっている。
加えて、米中関係も欧州への影響が小さくない。米中対立の激化も懸念せざるを得ないが、米中の「手打ち」も、欧州に悪影響を及ぼす懸念が小さくない。さらに、米欧関係自体も、いわゆる「関税戦争」の懸念が再燃している状況にある。中国との第一段階の合意ができたために、欧州がトランプ政権の次なる標的になるという見立てである。
これまでのEU統合は、経済統合を通じて、域内で疑似的なグローバル化を進めることで、規模の経済の恩恵を享受しつつ、EUという大きな船を造ることによって、世界の荒波に対処してきたのである。この観点では、加盟国は多ければ多いほどよく、英国のような欧州の大国が抜けることのダメージは計り知れない。
そうした状況に置かれたEUがどこに向かうのかは、予断を許さない。先述の「戦略的自律」のような方向に進むのか。それはEUの「内向き化」を意味するのか。あるいは(ないしそれと同時に)、ロシアや中国といった諸国への接近を図るのか。それとも米国との関係修復に本腰を入れるのか。フォン・デア・ライエン委員長率いる欧州委員会の方向性はまだみえない。いずれにしても、EUの弱体化と漂流を防ぐことが喫緊の課題になる。
英国にとってのEUからの離脱は、世界の荒波に一人で漕ぎ出すようなものである。「主権を取り戻す」との離脱派の掛け声とは裏腹に、達成されたのは「孤独」だったという批判は根強い。国際問題に関するEU内での協調もこれまでのようにはいかない。EU・英国間にいかなる協力枠組みが構築されたとしても、EUにおける議論を英国が自らリードするようなことは、もはやできない。
気候変動問題やイランへの対処、自由貿易の原則を含む多国間主義などに関して、英国の基本的立場は、米国よりも常にEUに近かった。短期的にも、次世代携帯通信5Gへの中国企業ファーウェイの参入の是非をめぐる問題やデジタル課税など、トランプ政権との間での懸案が、すでに待ち構えている。米国とのFTAに関しても、医薬品市場の開放や食品安全性など、難題が少なくない。英国は、米欧間の架け橋を自任してきたが、今後は(特にトランプ政権下では)米欧の間で引き裂かれる機会が増えそうである。
Brexit後しばらくは、EUにとっても英国にとっても、勝手の違いに戸惑うことが少なくないかもしれない。Brexitによる経済的損失も、具現化するのはこれからである。また、FTA交渉においては、とげとげしいやりとりも予想される。それでも、経済的なショックはいずれ乗り越えられるはずであり、より重要なのは、政治面を含めた欧州としての一体性が維持できるか否かであろう。
* * *
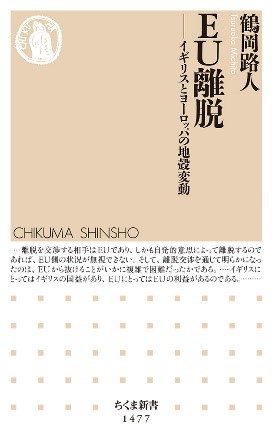
本連載の内容をもとに、大幅な加筆・修正・再構成を行った書籍、鶴岡路人著『EU離脱――イギリスとヨーロッパの地殻変動』(ちくま新書)が2020年2月5日に刊行されます。
【Brexitカウントダウン】連載一覧はこちら

