
| ヤングリーダー奨学基金プログラムは、日本財団が1987年に将来の世界を担うリーダーの育成を目指して立ち上げ、1997年からは東京財団が運営を行っている、世界の大学の人文社会科学分野の大学院生を対象に奨学金を給付する奨学制度。日本を含む世界44か国の69大学・大学連合に各々100万米ドルの基金を寄贈し、17,000名 を超える奨学生(Sylffフェロー)を輩出してきた。Sylffフェローは卒業後、外相や中央銀行総裁などを務めたり、学術研究、ビジネス、非営利セクターなど様々な分野の第一線で活躍している |
医療現場における事故や過失は、患者に深刻な影響を及ぼすだけでなく、医療従事者にも精神的な負担をもたらす。こうした「医療被害」に対し、より共感的かつ制度的に持続可能な対応を模索するSylffフェローがいる。オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学准教授のジェニファー・シュルツ氏は、医療社会学、法学、公衆衛生の知見を融合させ、患者と医療者双方にとってより良い解決策を提案する。
シュルツ氏はニュージーランド・カンタベリー大学の修士課程在籍中の2000年に、東京財団が運営するSylff奨学金を受給した。以来、政府機関や大学での研究・教育活動を通じて、医療被害に関する制度改革や教育の充実に取り組んできた。
2025年10月、神戸大学との共同研究を進めるために来日した際、東京財団のSylff Association事務局を訪問。これまでの研究活動や今後の展望について、直接話を聞く機会を得た。
医療事故の「隠れた代償」に光を当てる
「医療事故は、米国では死因の第3位、オーストラリアでは第2位に位置づけられています」とシュルツ氏は語る。手術ミスや過剰投薬など、日常的な診療の中にも様々なリスクが潜んでいる。
しかし、被害を受けた患者が法的手段に訴える場合、裁判は時間がかかり、費用も高く、精神的な負担が大きい。さらに、医療従事者側も「第二の被害者」となり得る。「謝罪したくても、それが過失の認定と受け取られる可能性があるため、裁判では言えないことが多い」と指摘する。
こうした課題に対し、シュルツ氏は「コミュニケーションによる紛争解決プログラム(CRP)」という、過失の有無にかかわらず医療事故に対応する非訴訟型モデルを提唱している。CRPは、医療機関が事故を開示し、調査・説明・謝罪・補償を行うことで、患者との間に率直で誠実、かつ共感的なコミュニケーションを築くことを目的としている。従来の「否認と防御」型の対立から脱却し、患者中心の安全文化への転換を図る枠組みであり、医療の質と信頼性の向上にも寄与する制度である。
個人の体験談が政策を動かす
シュルツ氏の研究は、統計に頼るだけでなく「体験の共有」にも重きを置いている。ある15歳の少女が病院で過剰投薬を受け、心身に深刻な影響を受けた事例を取り上げた論文では、彼女の回復と成長の過程が描かれている。この少女は、シュルツ氏が医療被害後の解決プロセスの改善を目的とした研究(2018〜19年のSylff Leadership Initiatives助成による)でインタビューを行った患者の一人である。
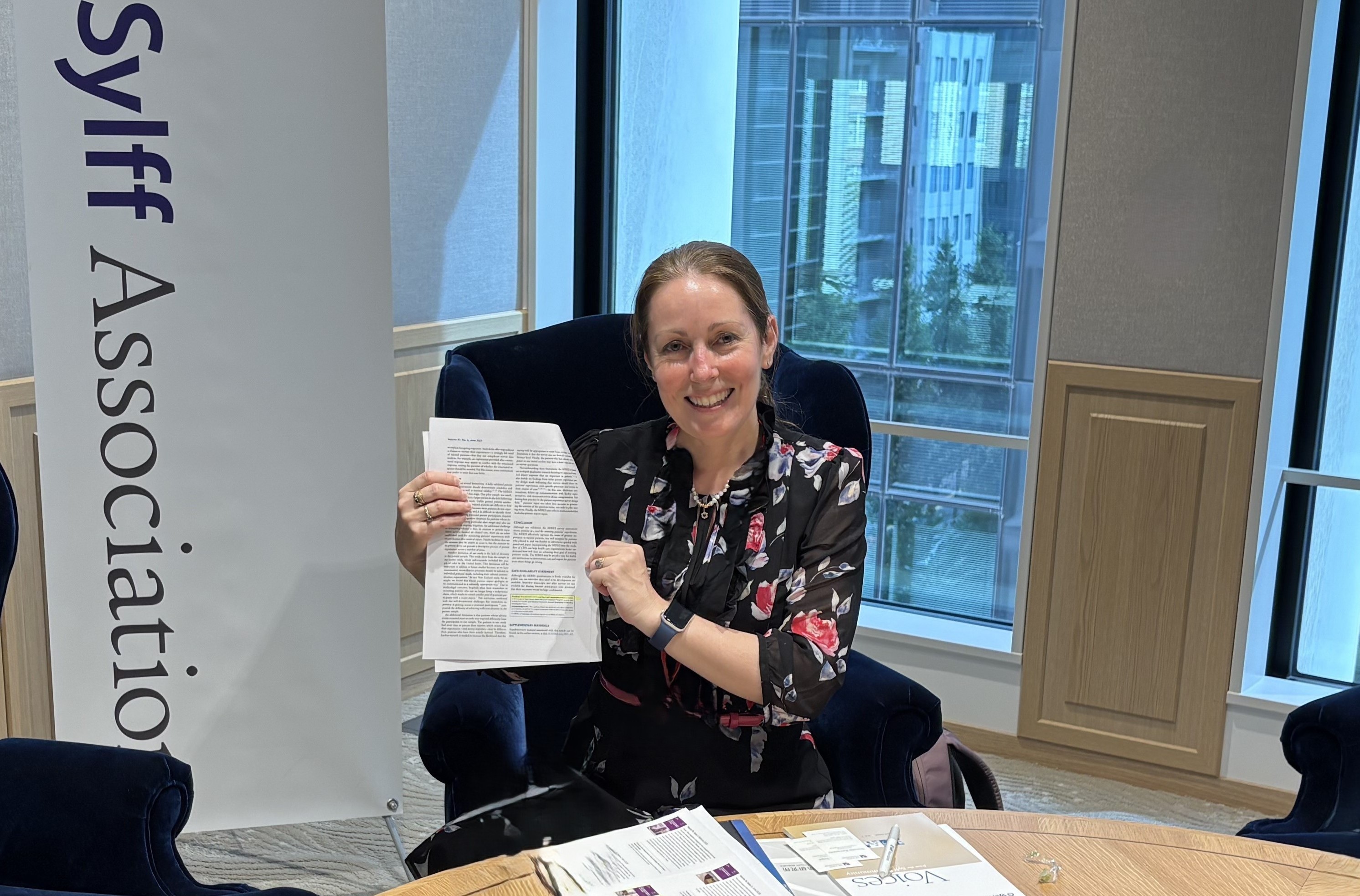 その後もシュルツ氏は彼女との関係を保ち続け、4件の研究に協力してもらうなど、継続的な交流を続けてきた。少女は精神的な困難を乗り越え、大学を卒業し、現在では医師の助手として医療現場に立っている。自身が経験した医療被害を糧に、同じような境遇にある人々を支えたいという強い思いから、医療の道を選んだのである。
その後もシュルツ氏は彼女との関係を保ち続け、4件の研究に協力してもらうなど、継続的な交流を続けてきた。少女は精神的な困難を乗り越え、大学を卒業し、現在では医師の助手として医療現場に立っている。自身が経験した医療被害を糧に、同じような境遇にある人々を支えたいという強い思いから、医療の道を選んだのである。
シュルツ氏はまた、ニュージーランド政府での勤務時には、複数国の検視官制度を比較する調査を実施。100件以上のインタビューを通じて、制度改善の必要性を明らかにし、2016年にはその成果をまとめた書籍を出版した。検視官(coroner)は、死因究明のために検死審問を行い、将来の同様の死亡事故を防ぐための勧告を行うことがあるが、その勧告を社会的な変化につなげる仕組みに不備があることをシュルツ氏は浮き彫りにし、ニュージーランドにおける法制度改革を促す契機を作った。「政治家が動いたのは、統計ではなく、患者の声に心を動かされたからです」と強調する。
現在は、人工知能(AI)による医療被害にも関心を寄せている。診察記録の自動作成やロボット手術など、AI技術の導入が進む一方で、誤記録や操作ミスによる新たなリスクが生じている。「新しい技術は大きな可能性を秘めていますが、同時にリスクを理解し、対策を講じる必要もあります」と警鐘を鳴らす。
教育と人文学への情熱
大学を離れ、政策立案に携わっていた時期もあるが、教育と若い世代との対話にこそ情熱を感じる、とシュルツ氏は語る。2018年には、ニューサウスウェールズ大学の1年生から、最も感動を与えた教員として「Inspiring Teacher Award」を贈られた。学生たちは彼女を「並外れた教師」「毎回の授業に情熱とエネルギーを惜しみなく注ぐ人物」「進路に影響を与えてくれた完璧なメンター」と称賛している。
教育者としての姿勢は彼女の研究にも通底しており、定量的・科学的な研究を「骨格」に、人文学を「肉」に例え、「人文学は、数字が人々にとって何を意味するのかを理解するための基盤である」と強調する。近年、世界的に人文学分野への予算が削減される傾向にあることを憂慮しており、共感力や批判的思考を育む教育の重要性を訴えている。
自身の娘が科学者になることを夢見ている一方で、シュルツ氏は娘にも人文学の素養を身につけてほしいと願っている。科学的知識と人文学的視点の両方を持つことで、技術の進歩が人間社会に与える影響をより深く理解し、より良い未来を築く力になると考えているからである。
 シュルツ氏の活動は、研究成果が実社会に影響を与える好例であり、制度改革や教育の現場においても大きな波及効果を生み出している。東京財団はSylff奨学金事業を通じて、こうした社会課題に対して共感を持って取り組む人材を支援しており、今回の来訪インタビューを通じて、彼女の取り組みの深さと広がりを、事務局としても改めて実感することができた。(文責:河本 望)
シュルツ氏の活動は、研究成果が実社会に影響を与える好例であり、制度改革や教育の現場においても大きな波及効果を生み出している。東京財団はSylff奨学金事業を通じて、こうした社会課題に対して共感を持って取り組む人材を支援しており、今回の来訪インタビューを通じて、彼女の取り組みの深さと広がりを、事務局としても改めて実感することができた。(文責:河本 望)
▼Sylff Association公式ウェブサイトのオリジナル記事(英語)はこちら
Impact through Empathy in Redressing Medical Harm: Sylff@Tokyo
▼ヤングリーダー奨学基金プログラム(Sylff Association)の詳細はこちら

