評者:細谷雄一(慶應義塾大学法学部准教授)
本書の概要
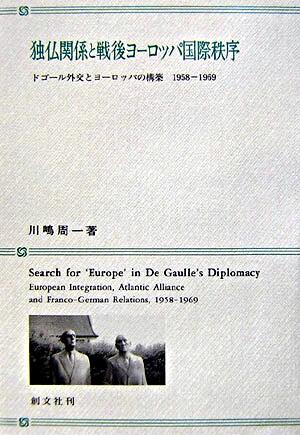 本書は、1958年から1969年までのフランスのドゴール外交を中心にして、独仏関係と「ヨーロッパ構築」としての国際秩序の展開を論じる研究書である。フランスおよびドイツの広範な一次史料のみならず、アメリカやイギリスの史料も用いた画期的な国際政治史研究であり、また、ドゴール外交を検証する日本語ではじめての研究書でもある。ドゴール外交を軸とした伝統的な外交史的手法と、近年顕著に発展しつつあるヨーロッパ統合史的手法を組み合わせて、冷戦という国際政治構造の中に位置づけるという、きわめてスケールの大きな構図の研究として仕上がっている。最近では、川島真・服部龍二編『東アジア国際政治史』(名古屋大学出版会)において、はじめて本格的な東アジア国際政治史の通史が描かれた。また、遠藤乾編『ヨーロッパ統合史』(名古屋大学出版会、近刊予定)では、日本語ではじめて戦後ヨーロッパの歴史を、政治・経済・安全保障・文化などの多面的な要素を総合的に捉えて、「統合史」としてその全体像を描いている。このように、近年の新しい傾向として、外交史を一国の内政と外交を総合するという視点のみならず、多数国間の相互作用として立体的な「空間」を描く潮流が見られるようになった。本書もまた、そのような流れの中に位置づけることができる。
本書は、1958年から1969年までのフランスのドゴール外交を中心にして、独仏関係と「ヨーロッパ構築」としての国際秩序の展開を論じる研究書である。フランスおよびドイツの広範な一次史料のみならず、アメリカやイギリスの史料も用いた画期的な国際政治史研究であり、また、ドゴール外交を検証する日本語ではじめての研究書でもある。ドゴール外交を軸とした伝統的な外交史的手法と、近年顕著に発展しつつあるヨーロッパ統合史的手法を組み合わせて、冷戦という国際政治構造の中に位置づけるという、きわめてスケールの大きな構図の研究として仕上がっている。最近では、川島真・服部龍二編『東アジア国際政治史』(名古屋大学出版会)において、はじめて本格的な東アジア国際政治史の通史が描かれた。また、遠藤乾編『ヨーロッパ統合史』(名古屋大学出版会、近刊予定)では、日本語ではじめて戦後ヨーロッパの歴史を、政治・経済・安全保障・文化などの多面的な要素を総合的に捉えて、「統合史」としてその全体像を描いている。このように、近年の新しい傾向として、外交史を一国の内政と外交を総合するという視点のみならず、多数国間の相互作用として立体的な「空間」を描く潮流が見られるようになった。本書もまた、そのような流れの中に位置づけることができる。
本書の目次は、以下の通りである。
序章 戦後ヨーロッパ国際関係史の再構築
第1部 「大構想」の実現を目指して 1958-1963:ドゴール=アデナウアー時代
第1章 アングロサクソン、アルジェリア、世界政策
第2章 政治同盟交渉
第3章 米仏二つの大構想と西ドイツ外交
第4章 エリゼ条約の成立
第2部「大構想」後のヨーロッパ国際政治の危機とその克服 1963-1969:デタントと共同市場
第5章 ドゴール外交の「頂点」
第6章 ヨーロッパ・デタント
第7章 ヨーロッパ統合の危機
第8章 ヨーロッパ共同体の定着
終章 統合されたヨーロッパと多極化された世界
第1部では、1958年のドゴール政権成立と、同年9月のドゴール覚書による西側同盟再編案、すなわち英米仏三国による「三頭制改革」成立を目指した「大構想」について検討している。その「大構想」が、アイゼンハワー米大統領とマクミラン英首相に拒絶された一つの帰結が、1963年1月の独仏間のエリゼ条約成立であった。その間の、アルジェリア問題や、フーシェプラン、ベルリン危機や、MLFとしての核管理問題などをめぐり、ドゴールが中心となり米欧間で大きな摩擦が見られた経緯を詳細に検討している。
第2部では、自らの「大構想」が挫折した後に、自主外交を展開してデタントを目指す外交過程が、1963年から1969年までの期間に光を当てて論じている。ドゴールがソ連との緊張緩和の中で世界の多極化を目指す一方、その後背でヨーロッパ共同体が危機を乗り越えて着実に権限を増し進化していく様子が描かれる。
このようにして極めて複雑で、多層的な1960年代のヨーロッパ国際政治を、ドゴールという一人の政治指導者を中心として、独仏関係とヨーロッパ統合、冷戦という枠組みの中にそれを位置づけるのが本書の特徴である。冷戦の起源としての1940年代や、緊張が高まる1950年代、デタントの進む1970年代や冷戦終結へ向かう1980年代と比べると、「1960年代」は描くのが極めて難しい、過渡期としての時代である。他方で「静かなプロセス」としての「秩序変容」が進んだ1960年代を把握することは、冷戦体制の確立から、世界の多極化、さらには冷戦終結に向かっていく大きな転換点を理解することにも繋がる。そのような難しい課題を、多数国にまたがる豊富な史料を効果的に使用することで、見事に描ききったのが、本書の意義といえる。
本書の評価
本書は、1960年代の「より広義な意味でヨーロッパという『空間』」を歴史的再検討することを目的として、フランスのドゴール外交を軸として、独仏関係をその中核に位置づけて、ヨーロッパ国際秩序を描く国際政治史研究である。
著者は、戦後のヨーロッパ秩序を、「本質的に多層的で、かつ米欧関係に深く規定された存在である」と位置づける。従来においては、フランスやイギリス、ドイツといった、個別的な各国外交史と、現在のEUに至るヨーロッパ統合史、そしてNATOの歴史が、切り離されて論じられることが多かった。しかし本書はそれらを「多層秩序」という視点から捉え直して、それらを総体的に論じることではじめて、戦後ヨーロッパ国際秩序の全体像が把握できると語る。それは、「ヨーロッパ構築(Construction europ & eacute; enne)」の歴史でもあった。そのような新しい視座から、戦後ヨーロッパを総合的に捉える視座は、意義深いものといえる。
そして「この六〇年代のヨーロッパ国際政治の主役」は「フランス大統領ドゴールであった」。それでは、ドゴールは外交において、何を望んでいたのか。著者によれば、「ドゴールが望むのは、アメリカからの『離反』ではなく、アメリカから『自立』し、統合された軍事力をフランスの自由な指揮下に置きつつ、独自の核戦力によってフランス防衛に当たることであった。」さらに、ドゴールは、東側諸国との「緊張緩和、友好・協調、提携」を求め、「世界が米ソ冷戦構造から脱却する最初の扉を開けたのである。」ドゴールが自らの「自主外交」によって、秩序再編を求めたことが、1970年代のデタント、さらには1980年代の冷戦終結に至る新しい潮流の契機をもたらしたと言えるかもしれない。しかしその後ドゴール外交は、「外交の硬直化」が見られるようになり、行き詰まりを迎える。「『アメリカからの自立』という外交目標がドグマ化した時、彼の外交はダイナミズムを失ったのである」からだ。
また著者は、独仏友好関係を「戦後和解」としてロマンティックに語るのではなくて、豊富な史料に基づいて、極めて冷徹に描いている。それは信頼の置ける記述といえる。つまり、「独仏関係は真の意味での枢軸とはなりえないとドゴールが自覚的に考えていたからではなかろうか」と著者は論じる。というのも、独仏関係とは、「根本的にはフランスが優位となる不均衡状態」にあり、「ドゴールからすれば、フランスの利益に沿うように西独を動かすための手段でしかなかった」からだ。本書は、従来の印象論的な独仏友好関係のイメージを、学術研究の水準に上昇させる上で、重要な位置を占めるであろう。
本書でもう一つ描いて欲しかった点は、フランス外交の特質を抽出する作業である。ドゴールという「ユニーク」な指導者に振り回されるフランス外交は、しかしながら、その後のフランスの一つの外交路線を構築することになる。現在に至るまで、「ドゴール主義」として論じられるフランス外交の一つの潮流が、どのような特質を持ち、どのような遺産を残したのかがより体系的に論じられれば、さらに本書の価値は増したのではないか。また「ヨーロッパ構築」という言葉で語られるこの時代のヨーロッパ秩序が、一体いかなる実態であったのか、より具体的な記述で、ヨーロッパ統合とNATO、冷戦を包括する視座が描かれていれば親切であっただろう。
高坂正堯はその著書、『現代の国際政治』(講談社学術文庫)において、1960年代におけるドゴール外交を「自立性への試み」という大きな文脈の中に位置づけている。よく知られているように、ドゴールはその回顧録を、「フランスは偉大さなくしてはフランスたりえない」という言葉から始めている。フランス外交史の大家であるパリ政治学院教授モーリス・ヴァイスは、「偉大さ(Granduer)」という言葉を書名に付したドゴール外交の研究書の中で、しかしながら慎重な計算を尽くしたドゴール外交を高く評価しながら描いている。しかしその「偉大さ」という言葉では説明し得ない、フランス外交が抱える複雑な問題や戦略を丁寧に描いた本書は、日本においてドゴール外交を語る一つの古典的地位を得ることになるのではないか。












