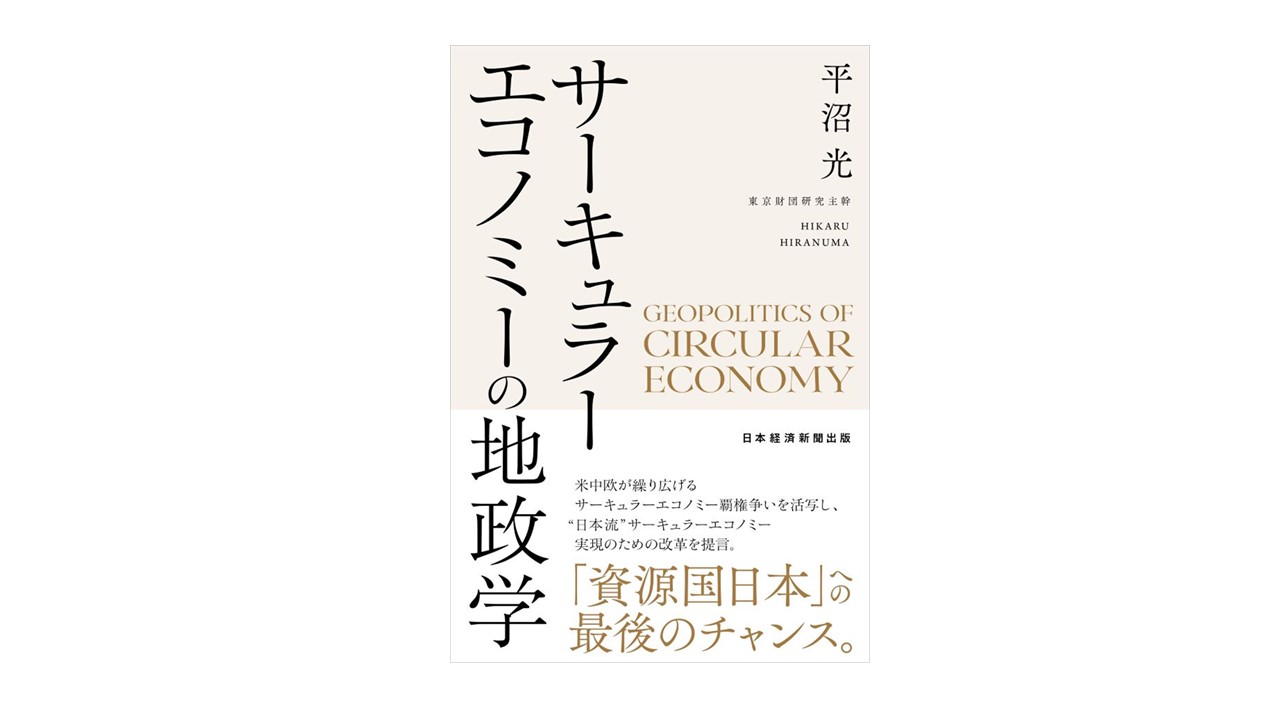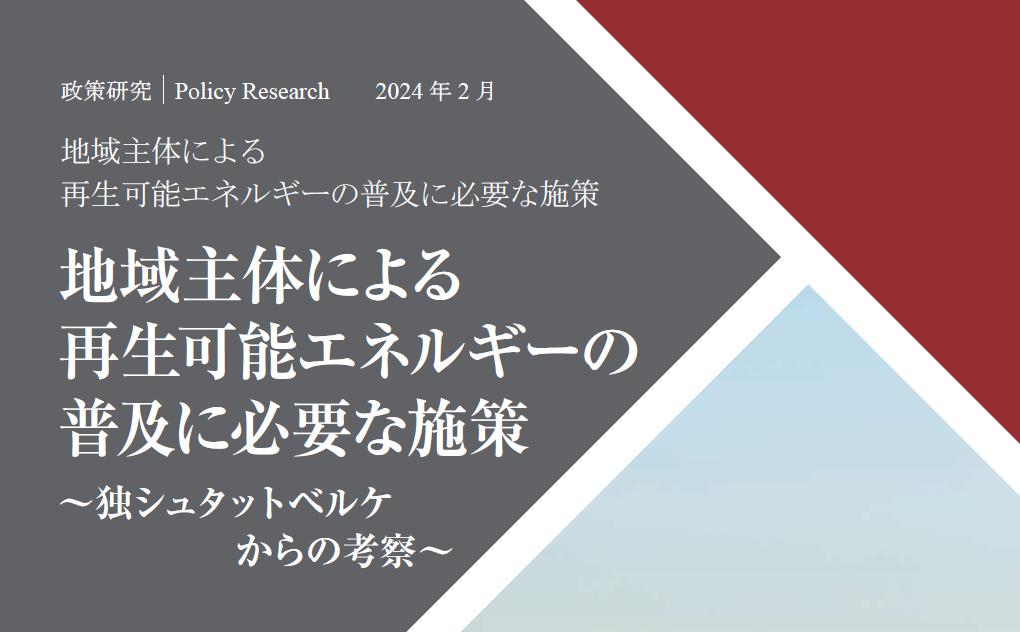- Review
【特集】新政権に期待すること―レアアース政策の失敗から学べ~日本のグランドデザインを描かずに政策のパッチワークをするのはもうやめよう~
November 17, 2025
2025年10月21日に開催された第219回臨時国会で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されました。新政権の発足に寄せて、東京財団の政策プロデューサーと常勤研究員が、「これから期待すること」について各専門分野から論じます。
|
目指すべき日本の姿(グランドデザイン)を具体的に描くことの重要さ |
目指すべき日本の姿(グランドデザイン)を具体的に描くことの重要さ
2025年10月21日、衆参両議院の本会議にて、自由民主党(以下、自民党)の高市早苗総裁が第104代首相に指名された。高市政権の誕生である。
10月24日に行われた高市首相の所信表明演説では、「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済をつくる。そして、日本列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。」という意気込みが冒頭で述べられるとともに、その後は物価高対策や食料安全保障、エネルギー安全保障、人口政策、憲法改正などの個別の政策についての考え方が述べられた。
一方、日本を具体的にどのような国へとこれから導いていくのかという肝心の日本の全体像、すなわち将来の日本の姿となるグランドデザインは残念ながら十分に語られることなかった。もちろん個別の政策の方針を示す必要はあるが、個別の政策はあくまで日本のグランドデザインを実現するための手段であり、日本のグランドデザインを示さなければ個別の政策も意味をなさないだろう。
例えば人口政策では、日本の人口減少を食い止めることを前提とした国の姿と、人口減少をしても国が成り立つ姿を描くのでは打つべき個別の政策はまるで違うものになるだろう。
エネルギー政策においても、現在の第7次エネルギー基本計画では、「再生可能エネルギーと原子力を共に最大限活用していくことが極めて重要」という方針が示されているが、周知のとおり再生可能エネルギー(以下、再エネ)は地域に由来する地域分散型のエネルギーである。一方、原子力は主に沿岸域に大規模な発電設備を設置して発電を行う大規模集中型のエネルギーである。第7次エネルギー基本計画では再エネと原子力を共に最大限活用していくとしているが、地域分散型と大規模集中型という特徴の異なる2種類のエネルギーをどのようにしてエネルギーシステムの中で共存させるのか、日本のエネルギーシステムのグランドデザインを描かなければ再エネと原子力がバッティングして共倒れになってしまう危険性がある。
高市政権誕生に先立ち、10月20日に公表された自民党と日本維新の会による連立政権合意書では、「戦後最も厳しく複雑な国際安全保障環境・・・」と記されているように、かつてない混迷の時代だからこそ日本が目指す姿となるグランドデザインを具体的に描き、それを実現する施策としての個別政策を示すことが重要だ。グランドデザインを描かずに個別の政策を進めると、それこそ課題ごとに国民受けする政策をパッチワークのようにちりばめたポピュリズム政治になりかねない。
グランドデザイン無きゆえに失敗したレアアース政策
実際、日本はグランドデザインを描かなかったが故に数々の失敗を繰り返してきている。例えば、昨今の米中貿易戦争により注目されているレアアース問題があるが、レアアースの供給を中国に依存しているという問題はなにも今始まったものではない。2010年9月には、沖縄県尖閣諸島沖で起きた海上保安庁の巡視船と違法操業の中国漁船の衝突事件をきっかけに、中国が実質的なレアアースの輸出禁止を実施したことで世界中がレアアースショックに陥ったことは記憶にあるだろう。
当時日本は対策として、2010年10月に経済産業省が総額1,000億円の補正予算による「レアアース総合対策」を取りまとめ、①供給源の多元化、②レアアース削減と代替技術の開発、そして、③リサイクルの促進に取り組むという個別の政策を示したが、残念ながらこれらの政策は中途半端に終わっている。
レアアースショックの顛末は、中国によるレアアースの輸出規制は協定違反であるという世界貿易機関(WTO)の勧告が下されたことにより、中国が輸出制限の撤廃を行うという終幕となった。その結果、中国産レアアースが再び市場で安価に調達できるようになったことで、いつのまにやら個別の対策も疎かになって中国依存のリスクを解決しないまま今日に至っているという、まさに「のど元過ぎればなんとやら」の結末になっているのだ。
そして、昨今の米中貿易戦争で中国が再びレアアースの輸出規制を交渉カードとして切ってきたことで世界的な混乱が起こり、またもや日本はうろたえているという、まるでデジャヴを見るような情けない事態になっている。
もし、レアアースショックを教訓として資源の海外依存は重大なリスクであることを深刻に受け止め、2010年当時から省資源化とリサイクル資源をはじめとする国産資源の活用により、「海外の資源に依存しない自立する国家」とすることを将来の日本のグランドデザインとして描き、継続して取り組んでいたらどうであっただろうか。
レアアースのリサイクル技術については、2012年4月17日に自動車メーカーのHondaと日本重化学工業株式会社が共同で、自社製品の使用済み部品からレアアースをリサイクルプラントの量産工程で抽出するプロセスを世界で初めて確立したことを公表[1]しているなど、日本はレアアースリサイクルの高い技術力を持っていることが当時からわかっていた。
また、2013年3月21日には、独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)と東京大学大学院工学系研究科などが、2013年1月に実施した南鳥島周辺の海底海洋調査の結果、超高濃度のレアアースを含む堆積物「レアアース泥」を発見したことを公表しており、国産資源としてのレアアースの存在が明らかになっていた[2]。
2010年のレアアースショック当時から「海外の資源に依存しない自立する国家」を将来の日本のグランドデザインとして描き、レアアースリサイクル技術の社会実装と国産資源であるレアアース泥の商業化に継続して取り組んでいれば、十数年たった今ごろはレアアースの国産資源化が進展し、レアアースの中国依存は大きく解消されていたことが考えられる。
そればかりか、レアアースの国産資源化は外交面においても強力なカードとなっただろう。レアアースを絡めた米中貿易戦争の睨み合いはまだまだ目を離すことができないが、もし日本がアメリカに対してレアアースを中国に代わり供給できるという提案ができたら、様々な日米交渉における日本外交の切り札とすることができただろう[3]。
残念ながらこれらは「たられば」の話であり、グランドデザインを描かなかったがゆえに失敗したことが悔やまれる。
日本のグランドデザインを具体的に示せ
グランドデザインを描かなかったが故に起きた失敗は、レアアース政策だけではない。高市政権が立ち上げた日本成長戦略本部が11月4日に公表した新政権肝いりの17項目の戦略分野にはグリーントランスフォーメーション(GX)が盛り込まれているが、GXも今に始まった話ではない。
GXは化石燃料に依存した経済構造を、再エネをはじめとするクリーンエネルギーを中心とした社会へと転換し、気候変動問題への対応と経済成長を両立させることを目指す取り組みである。化石燃料依存の解消といえば、1970年代に中東でおきた第4次中東戦争とイラン革命が招いた2度の石油ショックが思い浮かぶ。
石油ショックにより海外の化石燃料依存の危険性を思い知った日本は、石油を代替するエネルギーとして、国産の資源である再エネの重要性を認識し、「サンシャイン計画」の開始(1974年)や「石油代替エネルギー法」の制定(1980年)など、国産のクリーンエネルギーの活用に舵を切る政策を矢継ぎ早に打ち出している。2度の石油ショックにより打ち出されたこうした政策は、現在のGXとその趣旨は一致しており、1970年代にすでにGXの動きはあったのである。
しかし、残念ながらその動きは不発に終わり、今日に至るまで海外の化石燃料に依存し続けるという構造は変わらず、新政権になった今でもGXを戦略分野に盛り込まなければならない状況にある。
もし、1970年代の石油ショック当時から「海外の資源に依存しない自立する国家」を将来の日本のグランドデザインとして描き、再エネをはじめとする国産のクリーンエネルギーの活用に継続して取り組んでいれば、五十数年たった今ごろは世界トップのクリーンエネルギー大国として日本は目覚ましい成長を遂げていたのではないだろうか。
過去を悔やんでもしようがないが、日本のグランドデザインを描かなかったがために犯してしまった失敗はこの他にもいくつもある。こうした過ちを繰り返さないためにも、新政権には、目指すべき日本の全体像となるグランドデザインを具体的に示すことを期待したい。グランドデザインなくして個別の政策をパッチワークのようにちりばめることはあってはならない。
<お知らせ>
筆者がプロジェクトリーダーを務める「資源エネルギー循環型社会の構築」研究プロジェクト(2025年10月~)では、日本を人口減少下でも持続可能な社会とするため、国産資源を主力として活用し、それを循環利用していくことで海外の資源に依存しない自立した国家とする「資源・エネルギー循環型社会」を将来の日本のグランドデザインとして描く研究を実施している。研究成果を随時発信していくので、そちらもぜひ注目していただきたい。
[1] Hondaニュースリリース「使用済み部品に含まれるレアアースの再利用について」2012年4月17日 https://global.honda/jp/news/2012/c120417.html
[2] 独立行政法人海洋研究開発機構、東京大学大学院工学系研究科プレスリリース「南鳥島周辺における超高濃度レアアース泥の発見とその分布概要(南鳥島調査航海について)」2013年3月21日 https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/archive/2013/20130321.pdf
[3] 産経新聞出版『愛する祖国へⅡ』笹川陽平 令和6年11月20日