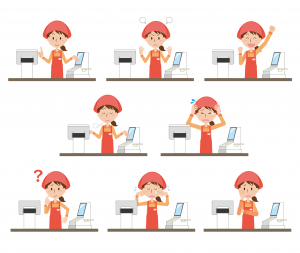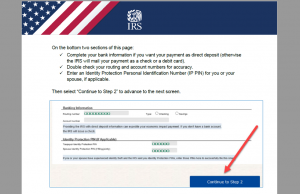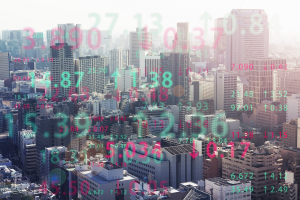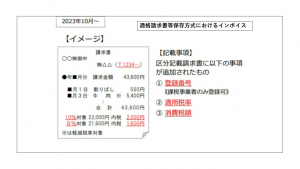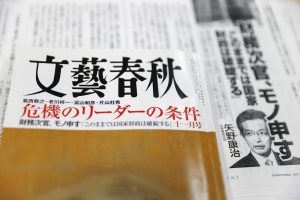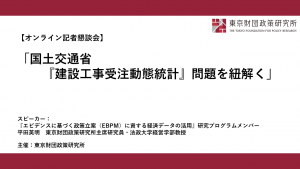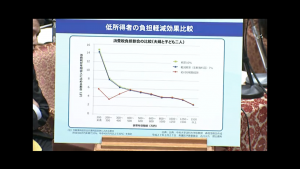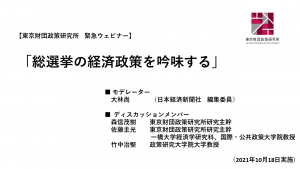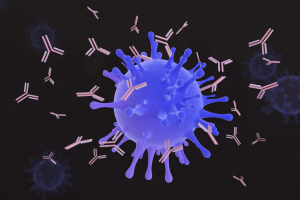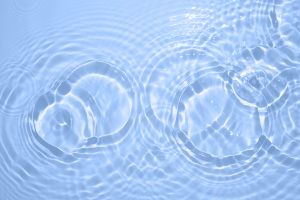R-2023-087
| ・4月のマイナス金利解除が標準シナリオに ・日銀の意図的な「出遅れ」戦略 ・マイナス金利解除後はある程度速やかに利上げか |
4月のマイナス金利解除が標準シナリオに
金融市場では、一部に昨年12月か今年1月にもマイナス金利解除との見方があったが、結局、日銀が動くことはなかった。その一方で、1月の「展望レポート」に「2%の物価目標に向けた見通しが実現する確度が高まってきている」旨の記述が加えられたこともあり、市場関係者の間では今春のマイナス金利解除が標準シナリオとなってきた。これは、従来からの筆者の見立てと一致するものである。フォワード・ガイダンスを重視する植田総裁は、現在の「必要があれば、躊躇(ちゅうちょ)なく追加的な金融緩和措置を講ずる」という、次回の政策変更は追加的な金融緩和だとする現行のフォワード・ガイダンスを3月の金融政策決定会合で変更した上で、26年度までの物価見通しを示す4月の会合でマイナス金利解除に踏み切る可能性が高い[1]。
消費者物価の上昇率だけなら、既に20ヶ月余り2%超が続いている[2]。それでも、日銀がこの春まで政策変更を待つのは、今春の賃上げの実現を確認したいからだろう。昨年12月のReviewでも指摘したように[3]、賃上げより物価上昇が先行すると、実質賃金が低下して(日本の実質賃金は20か月連続で前年比マイナスになっている)個人消費に悪影響を与え、企業も値上げに慎重になり、結果的に物価上昇が持続しないリスクがあるからだ。米国などでも、インフレ急進期には実質賃金がマイナスとなったが、この時期をコロナからの経済活動正常化とこの間に蓄積された過剰貯蓄でしのいだ。現在は、賃金上昇が続く一方で、インフレ率が落ち着くにつれて実質賃金がプラスに転じ、堅調な個人消費を支えている。日本でも同じシナリオの実現を期待しているに違いない。
そのためには、昨年に続いて今年も高めの賃上げが実現することが不可欠だ。今年の春闘を巡る情勢をみると、連合が賃上げ目標を昨年の「5%程度」から「5%以上」に高めた一方、7%や10%といった高めの賃上げを口にする有力企業経営者も少なくない。これらを踏まえれば、今年の春闘賃上げ率は昨年実績(厚生労働省調べで3.60%)を上回ることはほぼ確実であり、4%台に乗る可能性も十分にあると筆者は考えている[4]。それでも、日銀はこの事実を数字で確認できる3~4月まで政策変更を待つ構えであり、これは意図的に「出遅れ」(behind the curve)戦略を採っていると言うことができる。
日銀の意図的な「出遅れ」戦略
この戦略は通常の金融政策の運営の考え方とは異なる。金融政策は財政政策などと比べて政策の実行から効果の発現までのタイム・ラグが長いため、通常は景気や物価の動きを先読みして(forward lookingに)政策決定を行うことが望ましいと考えられている。実際、米国の連邦準備理事会(FRB)も日銀も3か月に1度、やや長めの経済見通しを公表しているが、それもこうした考えに基づくものである[5]。それでも敢えて日銀がbehind the curve戦略を採っているのには、大きく2つの理由がある。
その第1は、過去四半世紀の間に試みられた金融引き締め方向の政策変更、すなわち2000年のゼロ金利解除(速水総裁時代)、および2006年の量的緩和解除とそれに続く2回の利上げ(福井総裁時代)がいずれも「失敗」だったと受け止められていることだ。確かに、日本経済はその後景気後退局面を迎えるが、それには日本サイドの小幅な金融政策の変更よりも、2000年のITバブル崩壊、2007年の住宅バブル崩壊(とそれに続くリーマン・ブラザーズ破綻を含む金融危機)という2度の米国サイドでのバブル崩壊の影響の方がはるかに大きかったというのが常識的な見方である[6]。だが、仮にそうした「不運」があったとしても、この2度の「失敗」が景気後退の深刻化、デフレの長期化、さらには黒田前総裁の下での(副作用も覚悟した)大胆な金融緩和の実験などにつながっていったことは否定できない。そう考えると、最初の失敗時に日銀審議委員を務めていた植田総裁が「3度目の失敗は許されない」、「ようやく巡ってきたデフレ脱却のチャンスを逃してはならない」と考えるのは十分理解できよう。
第2の理由は、上記とも密接に関連するが、植田氏が総裁就任以前から「金融正常化が遅すぎるリスクより、早過ぎるリスクの方が大きい」と繰り返し述べてきたことである。一昨年末から昨年初めに消費者物価上昇率が一時4%超に達したのは、日銀の想定を上回っていたとみられ(政府による電気・ガス料金への補助金支給がなければ4%台はもっと長続きしただろう)、足もとの為替相場(本稿執筆時点で1ドル=140円台後半)は大方の予想より相当な円安水準にある。結果として、実質賃金がまだ前年比マイナスを続けているのは前述の通りだ。それでも、一時前年比2桁近くに達した欧米のインフレ率と比べれば、随分控えめなものだったし、エネルギー価格の低下などもあって、日本のインフレ率もピークアウトしつつある。日銀の慎重姿勢で金融正常化が遅れ気味となっていることのコストはさほど大きくなかったと判断される[7]。
マイナス金利解除後はある程度速やかに利上げか
以上のように、日銀の意図的なbehind the curve戦略は比較的うまくいっているようにみえるが、難しいのはマイナス金利解除の後ではないか。と言うのも、民間エコノミストには物価に関する弱気の見方が根強く、金融市場ではマイナス金利解除後もしばらくの間、ゼロ金利に近い状態が続くとの見方が多いからだ。実際、過去1~2年間、日銀の物価見通しは物価上昇圧力を大幅に過少評価してきたが、民間の物価見通しは日銀よりもさらに低いのが通例だった[8]。しかし、賃金・物価据え置きノルムが変化しつつある今、「どうせ物価は上がらない」という思い込みも徐々に変わりつつある。いずれにしても、日銀がbehind the curve戦略を続けてきたことが、こうした物価、金利上昇を過小評価する見方を強めてしまった可能性がある。
だが、今春にもマイナス金利解除が実行されるならば、それは日銀が2%のインフレが安定的に持続すると判断したことを意味する。そうであれば理論的には、金利水準は中立金利、すなわち2%+自然利子率(景気に中立的な実質利子率)に向けて上昇していくことになる。もちろん、自然利子率の推計は極めて難しいため、かなりの幅を持って考える必要があるが、自然利子率が若干のマイナスであったとしても[9]、中立金利がゼロ近傍ということはないだろう。そう考えると、マイナス金利解除の後、当面は3か月ごとに0.25%程度の利上げを続け、金利が0.5~1.0%に達した所で実体経済への影響を確認するという流れが自然のように思える。その場合、市場予想との食い違いが混乱を招くことのないように、日銀には周到なコミュニケーション戦略が求められる。
[1] マイナス金利解除に先立って、長期金利を狭い範囲に固定するイールドカーブ・コントロール(YCC)は、植田総裁の下で昨年7月、10月と2度にわたって弾力化されており、10年金利の上限1.0%が「目処」となったことで既に形骸化が進んでいる。しかし、毎回の政策公表文には「10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう」と明記されており、マイナス金利解除時にはこの部分を変更する必要がある。具体的にどのような表現にするかは定かでないが、長期金利の変動に十分な柔軟性を与えるものとなろう。
ただし、巨額の国債残高を抱える日本では、長期金利の急騰リスクを無視することはできない。管理通貨制のように、長期金利が急騰した際には介入の余地を残す仕組みとしてYCCが維持される可能性はあろう。
[2] 今年1月の東京都区部の消費者物価指数(除く生鮮食品、中旬速報値)は前年比+1.6%であったため、全国ベースでも1月には2%割れとなる可能性がある。ただ、2月には、これまで政府が実施してきた電気・ガス料金への補助による物価抑制効果が一巡するため、再度2%超となることが確実視されている。
[3] 拙稿Review 2%物価が実現しつつある理由 | 研究プログラム | 東京財団政策研究所 (tkfd.or.jp)を参照。
[4] 1月のESPフォーキャスト調査によると、民間エコノミストの春闘賃上げ率の予想は平均3.85%と昨年の実績(3.60%)をわずかに上回る程度だが、昨年1月時点の同調査の平均値は2.85%と実績(3.60%)を大きく下回っていた。
[5] FRBの経済見通しを示すものがSEP(Summary of Economic Projections)であり、日銀の経済見通しは『経済・物価情勢の展望』(通称「展望レポート」)に掲載されている。ともに機関としてのFRBないし日銀の見通しではなく、会議参加者個人の見通しという扱いになっているが、両者の大きな違いはSEPには先行きに政策金利の見通しも公表される(会議参加者の見通しが点で示されるため、ドット・チャートなどと呼ばれる)一方、「展望レポート」には政策金利の見通しはない点である。
[6]また 2000年当時の日本サイドの問題について言えば、1997~98年の金融危機後も不良債権処理が十分に進まず、金融システムの大きな弱点を抱えていたことが大幅な株価下落などにつながった。
[7] さらに言えば、市場は長い時間をかけて金融正常化を織り込んできたため、懸念されていた金融緩和の「出口」における市場の混乱リスクは低下していると言えよう。実際、黒田総裁時代の末期と比べて長期金利のvolatilityは大幅に低下しているうえ、マイナス金利解除が近いというコンセンサスとYCCの形骸化にもかかわらず、本稿執筆時点で10年国債利回りは0.7%台と危機的な状況とは程遠い。
[8] 日銀はこのところ物価上昇要因を輸入物価上昇が国内物価上昇につながる「第1の力」と、国内の賃金と物価の好循環を示す「第2の力」に分けて説明しているが、日銀も、それ以上に民間は「第1の力」を強調し過ぎているのではないかと感じる。輸入物価のピークは一昨年の秋だったから、過去1年間に「第1の力」が強まったという説明には無理がある。この間の物価の上振れは、サービス価格上昇が示す「第2の力」か、企業の価格決定力(pricing power)が強まった結果、輸入コストの転嫁が予想以上に進んだか、いずれかのはずである。筆者は、pricing powerの強化まで持続性に乏しい「第1の力」で理解するのは不適切だと考える。
[9] 昨年4月のIMF世界経済見通し(World Economic Outlook)の第2章には、主要国の自然利子率の推計が示されていた。グラフから見たところ、日本の自然利子率はごく小幅のマイナス(-0.2~0.3%程度?)と推計されていたようである。







































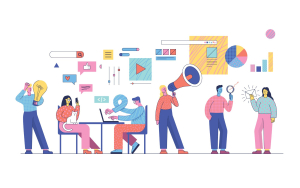

















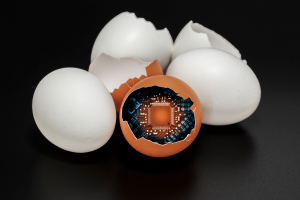















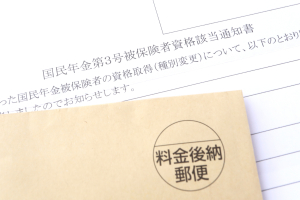
















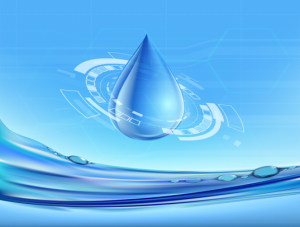

































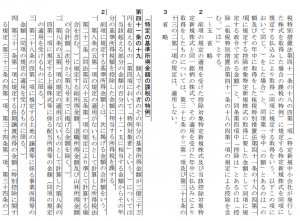






























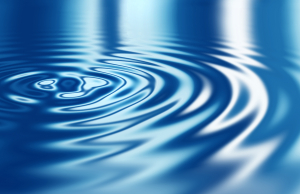

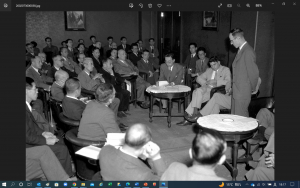


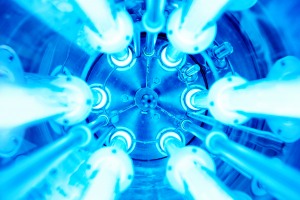

















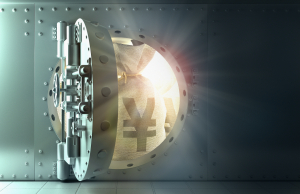



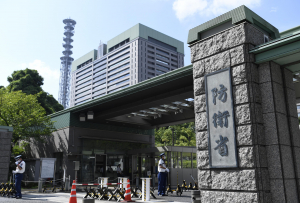





_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)













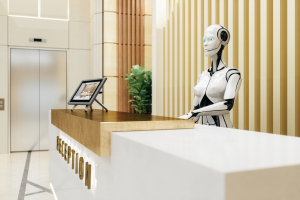







_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)