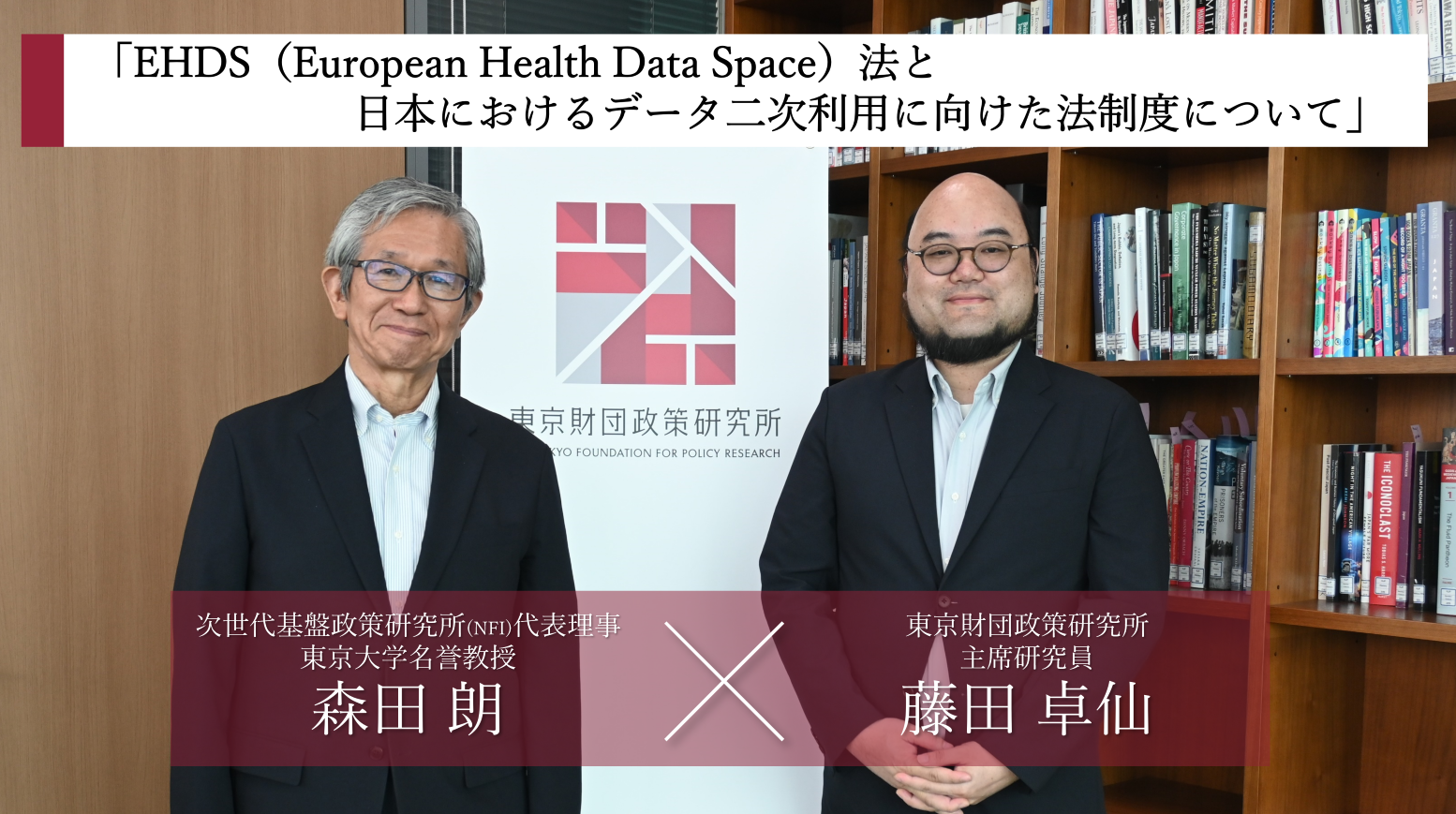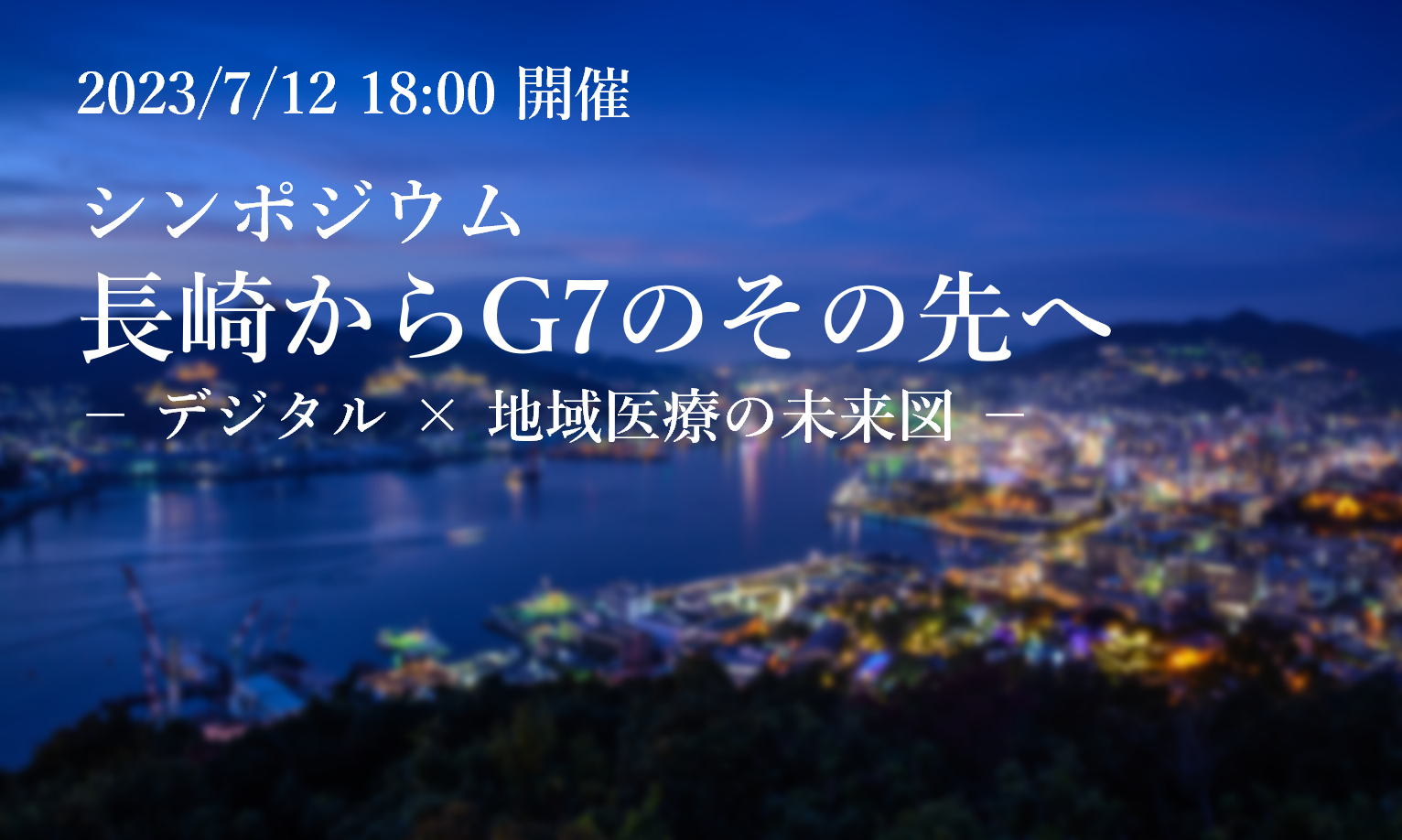このレビューのポイント
医療DXの進展に伴い、AMEDが推進する予防・健康づくりのための学会指針や、生成AI、PHR(Personal Health Record)等の各種ツール・サービスに関するガイドラインが整備されつつある。こうした基本的にボトムアップで作成される指針やガイドラインは、トップダウンによる個別の法的規制を補完し、技術革新の社会実装を加速させる点で大きな意義を持つ。しかし、従来の医療臨床の枠を超えた形での社会実装を進めるにあたり、いくつかの重要な論点が存在する。
|
1. 共同規制としてのルール形成の必要性 |
1.共同規制としてのルール形成の必要性
地域での実装を広く行うとともに、個別の状況や技術の進展に応じた医療DXの実現には、トップダウン型の規制とボトムアップ型のガイドラインが融合した形の「共同規制」[1]の仕組みが望ましい。トップダウン型の法律・規制は一定の統一性を確保するものの、技術革新のスピードに追いつかない場合が多い。一方、ボトムアップ型の指針やガイドラインは、現場の課題や技術発展の実態を踏まえて調整が可能であり、迅速かつ実効性のある制度設計を可能にする。
特に、実際、医学・医療の多くの分野においてはガイドラインが機能している。東京財団政策研究所が実施する研究プログラム「地域に根ざした医療DXの実装に向けた人材開発に関する政策研究」[2]においても、持続可能な医療システムの実現を目指し、医療DXの実装における政策的課題を検討するにあたり、トップダウンでの法整備のみでなく、ボトムアップでの地方発のルール形成に着目をしている。
2.医療DXに関連する主要ガイドライン
従来、日本においては、行政からの通知・通達中心でのルール運用がなされてきた。これにより、迅速な対応が可能な一方で、透明性や一貫性の確保が課題となることがあった。しかし、近年では共同規制の枠組みが注目を集め、法規制(ハードロー)と各種ガイドライン(ソフトロー)の融合が重要となっている。
EUのEHDS(European Health Data Space)法[3]やAI法[4]では、法律によるガバナンスのみならず、民間主導での標準化を活用・推進する共同規制の側面を持つ。日本においても、このようなモデルを参考にし、柔軟なルール形成を行うべきである。
特に日本の医療DXを推進するうえで重要なガイドラインとして、例えば以下のものが挙げられる。
-
オンライン診療等に関するガイドライン:
厚生労働省が策定した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」等[5]や、日本遠隔医療学会による「CPAPオンライン診療の手引き」[6]、日本外科学会による「遠隔手術ガイドライン」[7]その他各関連学会による診療関連ガイドラインや、⽇本医学会連合による「オンライン診療の初診に関する提言」[8]等により、安全で適切なオンライン診療の普及を促進するための基準が示されている。
-
PHRに関するガイドライン:
経済産業省が策定した「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」[9]や、PHR普及推進協議会・PHRサービス事業協会「民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン」[10]がある。これらは、個人の健康情報の適切な管理とPHRを活用したサービスを促進するための基準を示している。
-
予防・健康づくりに関する関連学会指針:
AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)の「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」の一環として、高血圧、糖尿病、腎臓病、女性の健康等の領域に関連し、各専門学会が策定し、2025年度中に7学会のものが公開される予定である[11]。これらの指針は、従来の臨床医学のガイドラインの形式でエビデンスに基づいた推奨度を示すものであるが、広範なデジタルツールの活用も含めた内容となっている。
-
生成AIに関するガイドライン:
総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン」[12]や、日本デジタルヘルスアライアンス(JaDHA)による「生成AIの医療応用に関するガイドライン」[13]などがあり、生成AIの適正な医療分野への応用に関する枠組みが整備されつつある[14]。
-
医学系研究に関する倫理指針:
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等、研究に関する倫理的なルールが厚生労働省他から示されており[15]、医学研究における倫理的基準やデータ管理の枠組みを示している。個人データ管理に関しては、原則として個人情報保護法のルールに対する上乗せとなっており、また治験等の場合には、薬機法や臨床研究法等の法的なルールに関する指針が示されている。
-
医薬品・医療機器開発に関するガイドライン:
PMDA(医薬品医療機器総合機構)による各種ガイドライン[16]が存在しており、医薬品や医療機器の研究・開発・承認プロセスを規定している。その他、医療機器開発に関するガイドライン[17]、AIを用いたものも含めた医療機器や医療機器プログラム(SaMD)[18]の評価に関しても基準が示されている。
-
医療分野の個人情報に関するガイドライン:
個人情報保護委員会・厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」[19]があり、患者情報の適正な取り扱いと管理についてのルールを提供している。また医療分野のセキュリティに関してはいわゆる3省2ガイドラインがある[20][21]。
-
その他ガイドライン:
上述のものの他、医療分野における広告のガイドライン[22]、経産省によるヘルスケアサービスガイドライン[23]、スマートシティ[24]等他領域DXに関するガイドライン等様々なガイドラインが関わる。
3.ガイドラインの意味合いとアジャイル・ガバナンス
共同規制の観点から、ガイドラインは公的規制と民間の自主規制を調和させる役割を担っている。AIに関する規制の議論においても、EU的な包括的ハードローによる規制ではなく、事業者の自主規制をベースとした共同規制の仕組みが提案されている[25]。
行政庁が提示するガイドラインは、行政法学的には、一種の行政規則もしくは、「行政指導」「命令」の一形態に位置づけられ、法的拘束力を有する場合も有さない場合もある[26]。例えば、厚労省が作成するガイドラインは、企業や医療機関が適切な運用を行うための指針として機能し、法的義務とは異なるが、他の規制の存在も相まって実質的に遵守が求められるケースが多い。また、行政庁ではなく、民間が提示するガイドラインは単なる自主基準として、拘束力を有さないのが通常であるが、個人情報保護法上の認定個人情報保護団体による個人情報保護指針[27]のように一定の法的な位置づけがなされているものもある。
一方、医学的なガイドラインは、エビデンスに基づいた最適な医療実践を促進するための指標であり、診療の標準化や医療の質向上を目的とする。これらは法的強制力を持たないものの、医療訴訟などでは医療の「標準的な手順」として参照されることが多く、実質的な影響力を持つ。なお、診療ガイドラインに関しては、国際的なルールに従って作成されており[28]、内容に関しても一定の科学的なエビデンスが求められている。上述の「予防・健康づくりに関する関連学会指針」もこのルールに従って作成されたものであるため、デジタルツールの活用に関して現時点では科学的なエビデンスが不足していることもあり、必ずしも事業者や一般市民にとってわかりやすいとは限らない部分も存在している。
また、医療DXの分野では技術革新が急速に進むため、「アジャイル・ガバナンス」[29]の考え方も重要である。アジャイル・ガバナンスとは、ステークホルダーの関与を促しながら、状況に応じてルールを適宜見直し、適応可能な規制を維持する枠組みを指す。医療においては、一方で機微性が高い情報を取り扱い、生命・身体に重大な影響を及ぼしうる領域であるため、ハードローによる厳格なルールが求められるが、同時に新しい技術の迅速な取り込みも望まれる領域である。そこで、こうしたアプローチにより、医療DXに関する規制が硬直化せず、技術革新と整合性を持ったルール形成が可能となる。
4.提言
本稿で検討したように、日本における医療DXの推進には、行政主導の規制と民間主導の標準化を組み合わせた共同規制が不可欠である。さらに、ルールのデジタル化を進め、生成AIを活用することで、多数のガイドラインの把握とアップデートの効率化を図る仕組みが求められる。加えて、地域ごとの個別事情を反映するボトムアップでのルール化・実装と、共通の標準を浸透させるトップダウンでの法・システム整備の双方向の取り組みを行う必要がある。具体的には以下のような取り組みを行うべきである。
(1)共同規制の枠組み強化とデジタル化の推進
まず、共同規制の枠組みを強化し、デジタル化を推進することが重要である。法的規制と民間の標準化のバランスをとり、持続可能な医療DXの基盤を構築し、EUのEHDS法やAI法の事例を参考に、日本に適した規制・標準化の枠組みを確立することが求められる。特に、医療分野におけるガイドライン自体のデジタル化を推進し、電子化されたルールを生成AIが解析し、関係者に最適な情報を提供できる環境を整備することで、ガバナンスの効率性と透明性を向上させるべきである。
ガイドラインなどのルールのデジタル化は、アジャイル・ガバナンスの実践にも資する。変化する技術環境に適応しながら、ルールの柔軟な見直しを可能にする仕組みを確立することが不可欠である。ステークホルダーが定期的に意見を交換し、規制と標準の調整を図るフォーラムを設置し、生成AIを活用してデータ分析を通じたルール改定の自動化と継続的な最適化を行うことが推奨される。
(2)多様な立場の関係者が協働する仕組みの構築
(1)の多様なステークホルダーの関与に際しては、政府、民間企業、医療機関、学術機関、患者会を含む市民団体など、様々な立場の関係者が協働する仕組みを構築する必要がある。診療ガイドラインは通常専門家である学会を中心に作成されるが、その内容や社会実装に関しては、透明性の高いルール形成プロセスを推進し、実効性のある医療DXの実現を目指し、AIを活用したガイドラインのモニタリングと評価システムを確立し、適切な関与を支援することが求められる。
(3)双方向アプローチによる全国的な医療DXの一貫性の担保
さらに、地域の実情を踏まえたボトムアップ型のルール化・実装を進め、地域に応じた最適な医療DXを推進しつつ、全国レベルもしくは国際的な標準化を進めるトップダウン型の法整備・システム整備を並行して進めることで、全国的な医療DXの一貫性を担保することが重要である。双方向のアプローチを通じて、地域ごとの柔軟性と全国的な統一性を両立させることが、持続可能な医療DXの実現に向けた鍵となる。
5.まとめ
本稿では、医療DXの推進における共同規制の重要性について検討した。従来、日本では行政の通知・通達を中心としたルール運用が行われてきたが、近年では民間主導のガイドライン策定が進み、政府と民間の協力による柔軟なルール形成が求められている。欧州のEHDS法やAI法が示すように、法的規制と民間の標準化を組み合わせた共同規制の枠組みは、技術革新と適応性を確保するための有効な手段となる。
アジャイル・ガバナンスの概念を活用し、ステークホルダーの適切な関与を促進することで、医療DXにおけるガバナンスの柔軟性と透明性を高めることができる。医療分野における個人情報保護、生成AIの適用、オンライン診療、医薬品・医療機器の開発など、各領域で適切なガイドラインの整備と継続的な見直しが必要である。
今後、日本においても欧州の事例を参考にしながら、法規制と民間の標準化を適切に組み合わせた共同規制の枠組みを確立し、医療DXの円滑な推進を図ることが求められる。
参考文献
[1]生貝直人『情報社会と共同規制: インターネット政策の国際比較制度研究』勁草書房、2011年
[2] 東京財団政策研究所「地域に根ざした医療DXの実装に向けた人材開発に関する政策研究」
[3] European Commission, "European Health Data Space (EHDS)"
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2024-INIT/en/pdf
[4] European Commission, "Artificial Intelligence Act (AI Act)"
https://artificialintelligenceact.eu/the-act/
[5] 厚生労働省「オンライン診療について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
[6] CPAPオンライン診療の手引き | JTTA|一般社団法人 日本遠隔医療学会https://telemed-telecare.jp/?p=1144
[8] オンライン診療の初診に関する提言を掲載しました。 | 一般社団法人日本医学会連合
[9] 経済産業省「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」
PHR(Personal Health Record)(METI/経済産業省)
[10] 「民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン(第3版)」及び追補を公表致しました(2024年6月28日) – 一般社団法人PHR普及推進協議会(PHRC)
「民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン(第3版)」を発出しました – PHRサービス事業協会
[11] 医学会発「指針」とは? | E-LIFEヘルスケアナビ | ヘルスケアサービス事業者・利用者向け情報サイト
[12] 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」
AI事業者ガイドライン(第1.0版)(METI/経済産業省)
[13] JaDHA「ヘルスケア事業者のための生成AI活用ガイド」第2.0版
https://jadha.jp/news/news20250207.html
[14] 東京財団政策研究所レビュー「生成AIの医療分野での活用に向けた3つの提言」
[15] 厚生労働省「研究に関する指針について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
[16] ガイダンス・ガイドライン | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
[17] 策定されたガイダンス(ガイドライン)紹介とダウンロード | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
[19] 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス |個人情報保護委員会
[20] 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)|厚生労働省
[21] 医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン(METI/経済産業省)
[22] 医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省
[23]「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」について(METI/経済産業省)
[24] 総務省「スマートシティ セキュリティガイドライン (第 3.0 版)」
[25] AI戦略会議 AI制度研究会 中間とりまとめ(案)
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/13kai/shiryou2.pdf
[26] 株式会社 NTT データ経営研究所「国の行政機関が公表したガイドライン等の実態把握のための調査研究 報告書」
[29]「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」報告書を取りまとめました (METI/経済産業省)