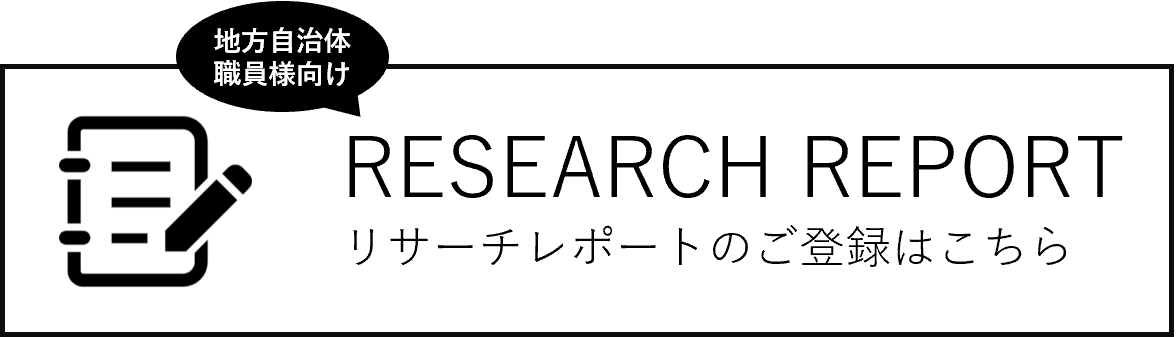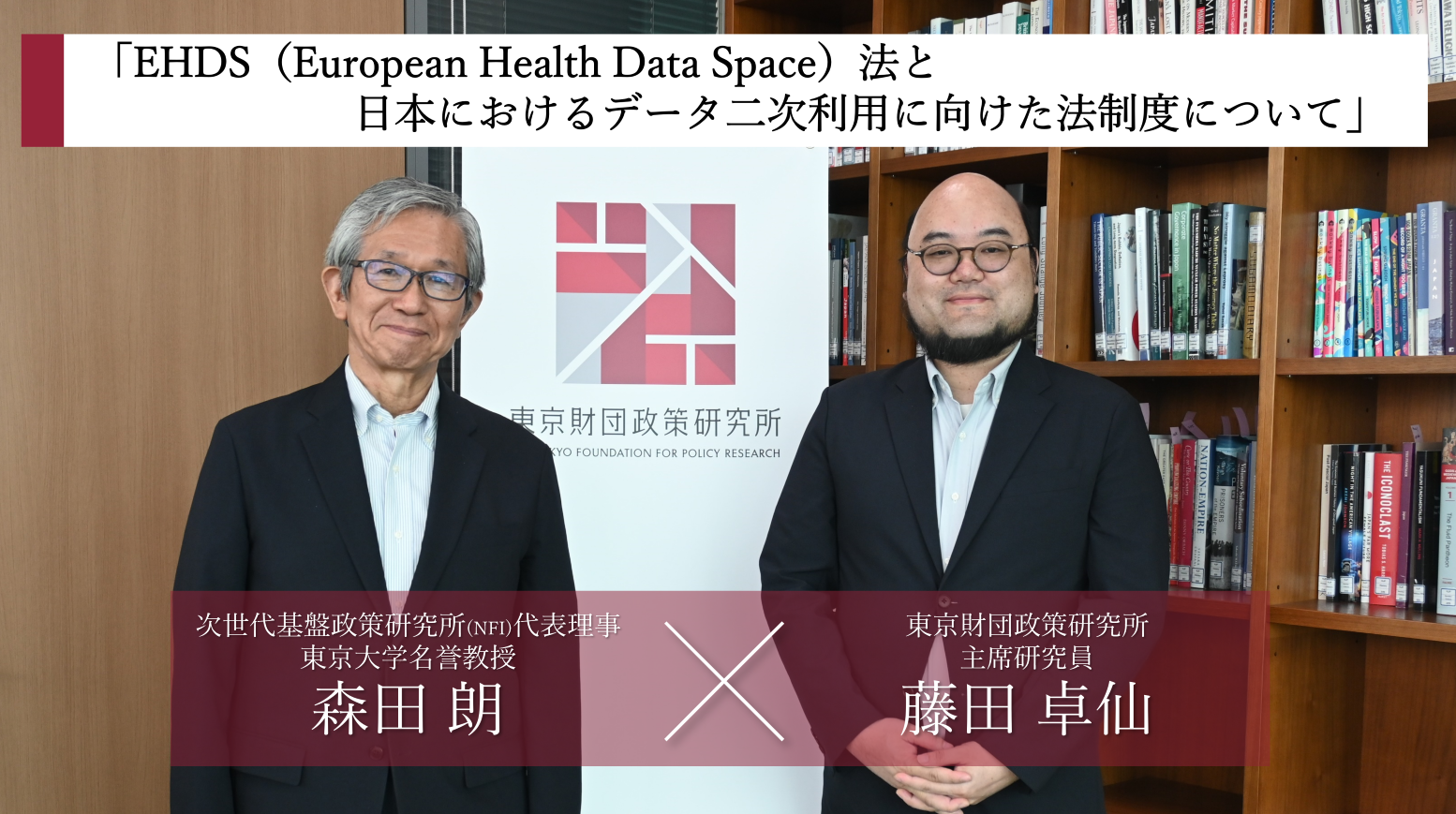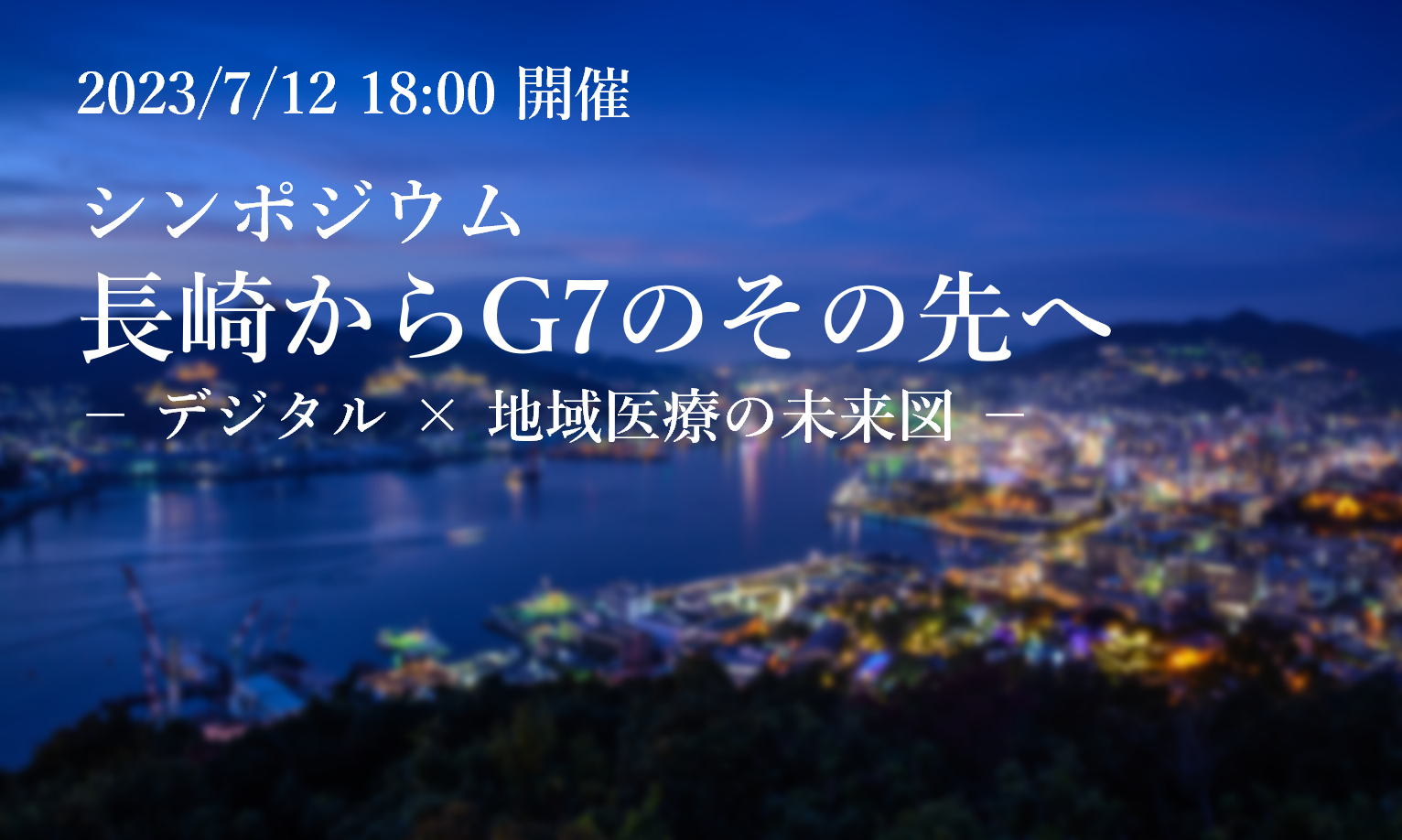先日、出張先でタクシーに乗った時のこと。運転手から質問をされた。
「行先までのルート、何かご指定はありますか?」
たまにこういうことを聞かれることがある。プロの運転手におまかせしたいところであるが、もしかして運転手歴が浅いのかもしれない。
この時の出来事を、最近の医療の事件でふと思い出した。
2025年9月9日に福岡地裁が下した判決[1]に、医療界から批判が起きている[2] [3]。
九州大学病院で2018年にバイパス手術を受けた後に脳梗塞を発症して意識障害となり、そのまま寝たきりになって2024年に亡くなった男性とその家族が、術式が適切でなかったなどとして約4500万円の損害賠償を求めたのに対して、「医師に(術式の)説明義務違反があった」と原告の主張を一部認め、九州大学に約160万円の支払いを命じたとのことである。
なぜ、この判決文に批判が寄せられているのか。詳しい事実や裁判所による判断は判決文自体を読まないとわからないが、報道によると、
主な争点は、人工心肺を使って心停止させて実施した「オンポンプ手術」と呼ばれる術式の是非。人工心肺を使わない「オフポンプ手術」という術式もあるが、判決は、異なるメリットとリスクのある二つの術式に関する説明義務を果たしたとは認められず、リスクを踏まえた上で手術を受けるか否かを患者が自ら決める、自己決定権を侵害したと結論づけた。一方、どちらの術式を選択すべきかについて明確な基準はなく、手術自体は問題なかったと判断した。(出典:朝日新聞)
とのことであるが、医学的には適切な治療を行ったにもかかわらず、損害賠償請求が認められたこと、今回説明義務が果たされなかったとされる「オフポンプ手術」は手術が行われた2018年には「オンポンプ手術」に勝らないとするエビデンス[4] [5]がすでに出されていたことから、どのような説明をすれば説明義務違反にならないのかがわからない、といったことから批判が起きている。
本事案以前にも、医療行為に関する医師の説明義務違反が問われたケースはこれまでにも多く存在する。1970年代頃までは、手術等の医的侵襲行為に対し患者の承諾(同意)があるか否かは、違法性阻却事由、つまり「説明・同意がない医療行為は違法」である点で議論されていた。その後、インフォームド・コンセントの概念や患者の自己決定権といった考え方が強まり、現在に至るまで、患者の自己決定権尊重という趣旨から説明義務違反が問われることが主流となった。すなわち、医師によるパターナリスティック(父権主義的)な医療行為が許容されていた時代から、「説明内容に関する医師の裁量権は、患者の自己決定権に優先するものではない」との考え方に変化してきたといえる[6]。例えば、宗教的理由による輸血拒否の事案(最三小判平成12年2月29日)[7]は(エホバの証人の信者である患者が無輸血の意思を示していたにもかかわらず医師が輸血を行い、医師側の説明義務違反が認められ50万円の慰謝料支払いが命じられたケース)や、未確立療法に関する医師の説明義務の事案(最三小判平成13年11月27日)[8](当時標準治療ではなかった乳房温存療法について、患者が強く関心を示している場合には医師はその適応可能性や実施医療機関を説明すべきと判示した乳がん手術のケース)は、こうした考え方に則ったものと解すこともできる。
また、帝王切開術による分娩を強く希望していた夫婦に経膣分娩を勧めた医師の説明についての損害賠償についての平成17年の最高裁の判決(最一小判平成17年9月8日)[9]は、医師の説明義務の内容を考える上で重要である。同判決では、
以上の諸点に照らすと,帝王切開術を希望するという上告人らの申出には医学的知見に照らし相応の理由があったということができるから,被上告人医師は,これに配慮し,上告人らに対し,分娩誘発を開始するまでの間に,胎児のできるだけ新しい推定体重,胎位その他の骨盤位の場合における分娩方法の選択に当たっての重要な判断要素となる事項を挙げて,経膣分娩によるとの方針が相当であるとする理由について具体的に説明するとともに,帝王切開術は移行までに一定の時間を要するから,移行することが相当でないと判断される緊急の事態も生じ得ることなどを告げ,その後,陣痛促進剤の点滴投与を始めるまでには,胎児が複殿位であることも告げて,上告人らが胎児の最新の状態を認識し,経膣分娩の場合の危険性を具体的に理解した上で,被上告人医師の下で経膣分娩を受け入れるか否かについて判断する機会を与えるべき義務があったというべきである。ところが,被上告人医師は,上告人らに対し,一般的な経膣分娩の危険性について一応の説明はしたものの,胎児の最新の状態とこれらに基づく経膣分娩の選択理由を十分に説明しなかった上 ,もし分娩中に何か起こったらすぐにでも帝王切開術に移れるのだから心配はないなどと異常事態が生じた場合の経膣分娩から帝王切開術への移行について誤解を与えるような説明をしたというのであるから,被上告人医師の上記説明は,上記義務を尽くしたものということはできない。
とされた。詳細な解説は他[10]に譲るが、経膣分娩と帝王切開の選択肢がある中で、帝王切開を本人が希望していたにもかかわらず、それに反して経膣分娩がとられ、出生児の死亡という不幸な結果に終わったという事案であり、それがこの判示に繋がっているものと考えられる。
今回の九州の事案において、本人の希望がどうであったかはわからないが、たとえ科学的なエビデンスとして劣った(より結果が期待できない)手法を本人が希望していた場合であっても、その希望に則さない手法がとられ、結果が悪かった場合に、一定の損害賠償(慰謝料相当)を認めるということであったとするならば、裁判所の判断は、これまでの裁判例に照らすと一般的なもののように思われる。
医師はどのような場合に、どこまで説明すればいいのだろうか。2001年の最高裁判決(未確立療法に関する医師の説明義務の事案)においては、「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するにあたっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り患者に対し、①当該疾患の診断(病名・病状)、②実施予定の手術の内容、③手術に付随する危険性、④他に選択可能な治療方法があればその内容と利害得失、⑤予後等について説明する義務がある」とされ、それは未確立療法に対しても、①少なからぬ医療機関において実施されており、②相当数の実施例があり、③これを実施した医師の間で積極的な評価もされている治療法について、④患者が当該治療法(術式)の適応である可能性があり、かつ、患者が当該治療法(術式)の自己への適応の有無、実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合には行うべきとされた。
では、過去の実施例はあるものの、現在は積極的な評価がなされなくなってきている(紹介するほうがかえって害であるとする意見もある)治療法に関してはどうなのか。もし仮に、そうしたものまで説明しなければならないとなると、医師にとっての負担が大きくなりすぎないか。
前回のレビュー[11]において、生成AIを用いたチャットボットによる医療相談について述べた。生成AIに相談することで、患者としてはより多くの選択肢が与えられ、より適切な自己決定ができるかもしれない。しかし、生成AIが勧める内容のすべてに関して医師は十分な説明が可能であろうか。
冒頭のタクシーの話に戻る。
タクシーの運転手は1つの道しか提示せず、その道で良いと私も言った。
正直、目的地に早く着いて安ければ何だって良い。
だが、その道はGoogle Mapが最適としてスマホで示していた道ではなかった。
結果として、予測された時間より遅く到着することとなり、その後の予定にも遅刻してしまった。仮に運転手が別の道も選択肢として提示していたとしても、お勧めの方でお任せしますと言っていただろうし、仕方ないか、とその時は思った。
しかし、運転手にはっきりと「Google先生はこの道がよいと言っています」と主張すべきではなかったか。どうせ間に合わないならバスに乗っていたのに、とその時のタクシー代がもったいなかったといまだに根に持っているからこのような文を書いているわけである。
たかがちょっとの時間とお金のことでもそうなのだから、医療において、結果が思わしくなかった時の無念は如何ばかりか。そう思うと同時に、では医師としての最善を尽くすとは、事前の説明も含めてどこまでのことが求められるのだろうか、とも思う。
分野が何であろうと、プロの判断を信頼し、結果がどうであれ諦めがつく、というのは今どきは難しいこととなっていくのであろうか。
参考文献
[1] 心臓手術前の患者へ「説明義務果たさず」九州大病院に賠償命じる判決 [福岡県]:朝日新聞
[2] https://togetter.com/li/2601063
[3] 医療技術に問題なし、でも敗訴〜九州大学病院の心臓手術判決が波紋〜|とある地方都市の某外科医
[4] On-Pump versus Off-Pump Coronary-Artery Bypass Surgery | New England Journal of Medicine
[5] Effects of Off-Pump and On-Pump Coronary-Artery Bypass Grafting at 1 Year | New England Journal of Medicine
[6] No.163/裁判例にみる‟医療者のインフォームド・コンセント” その3 3.医療訴訟で問題となる医師の説明義務 | 弁護士法人ふくざき法律事務所
[7] 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
[8] 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
[9] 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
[10] 例えば、分娩方法に関する説明義務違反と機会の喪失 | 有斐閣Online
[11] 生成AIに医療相談は今どこまでできるのか | 研究プログラム | 東京財団