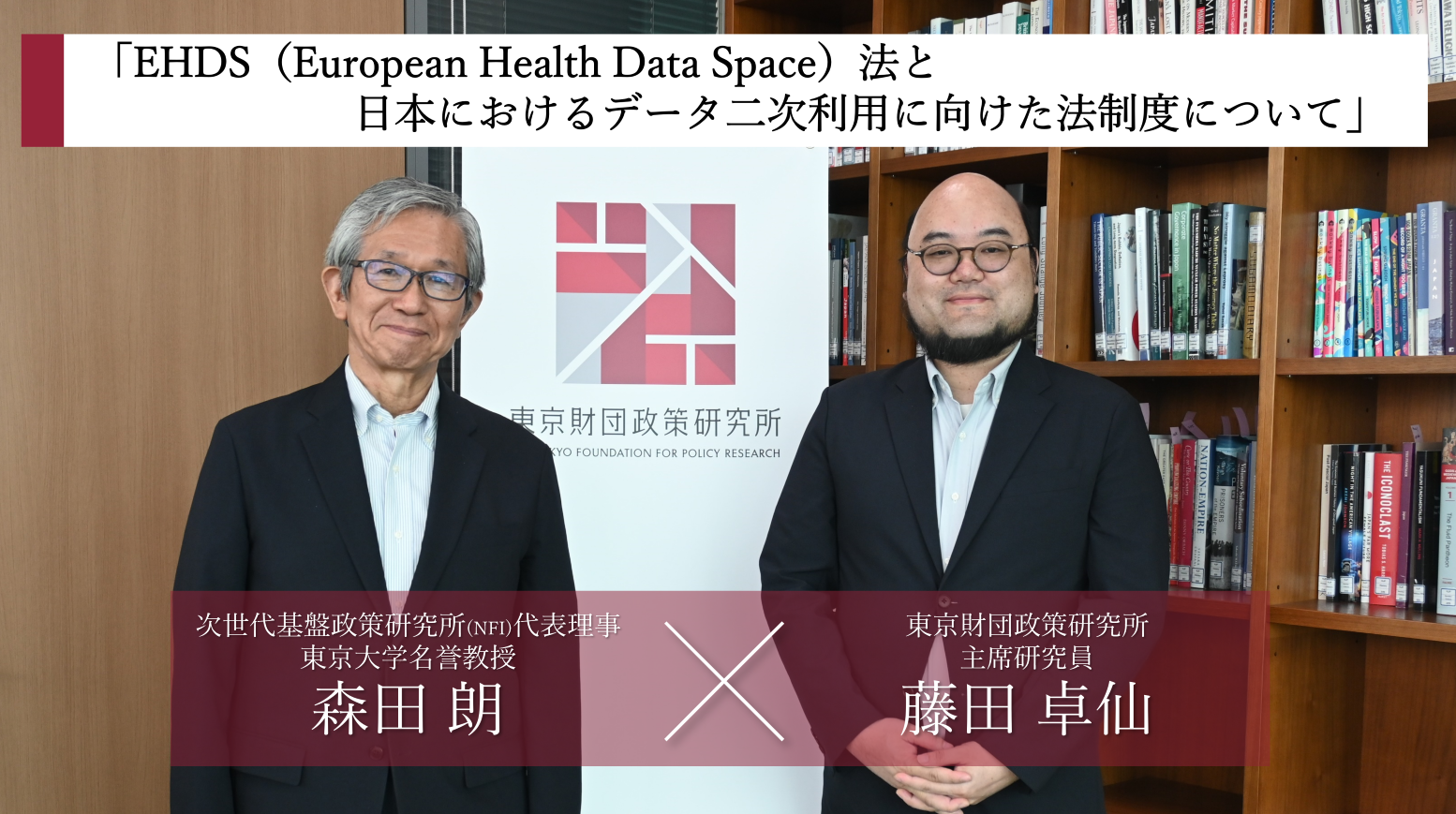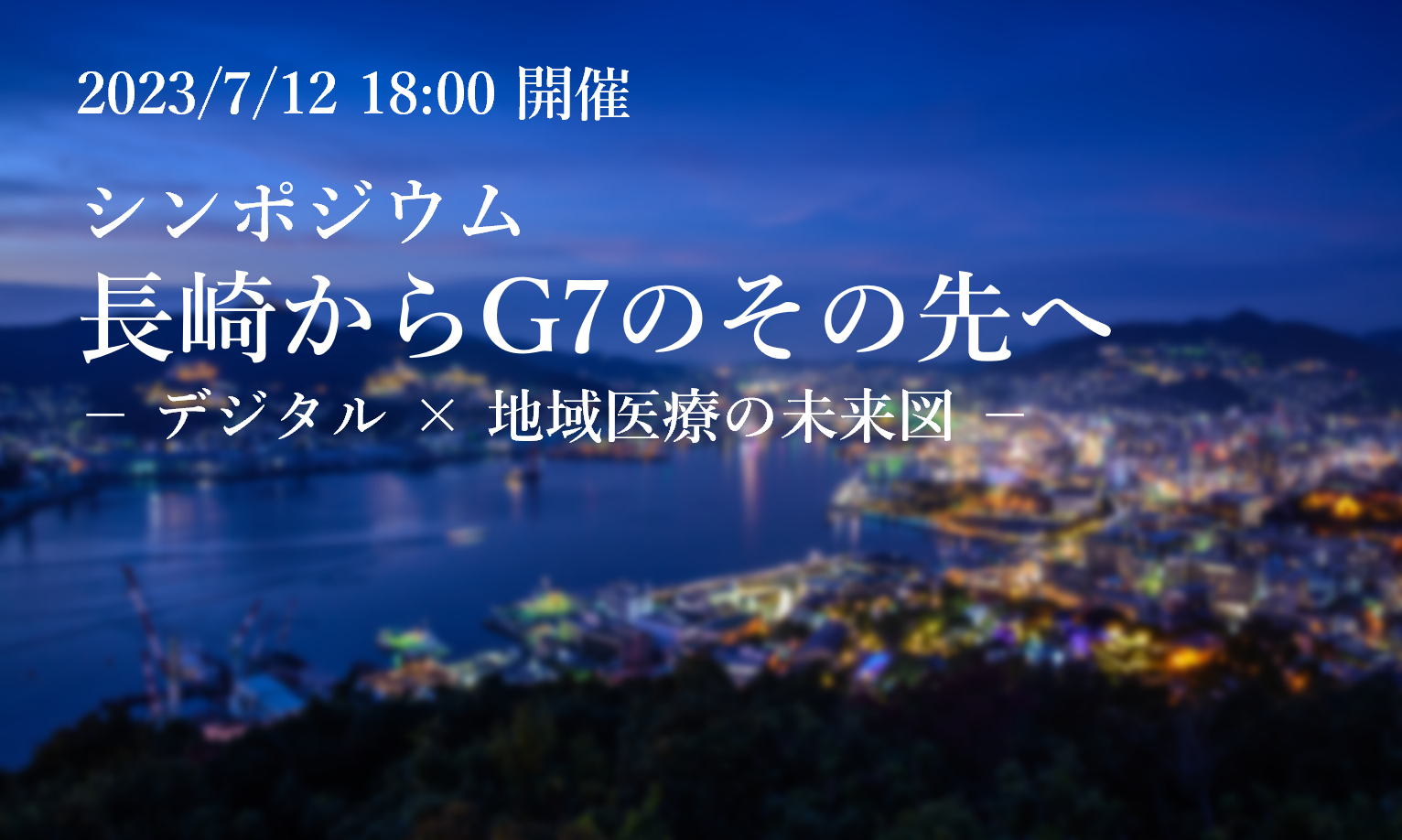- Review
【特集】新政権に期待すること―人口減少社会における社会保障政策:どこまでDXが進められるか
November 11, 2025
2025年10月21日に開催された第219回臨時国会で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されました。新政権の発足に寄せて、東京財団の政策プロデューサーと常勤研究員が、「これから期待すること」について各専門分野から論じます。
|
医師出身デジタル大臣・副大臣への期待 |
自由民主党(自民党)の高市早苗総裁が第104代首相に選出されたことは、様々な意見があるが、初の女性首相であるという点ではまず歓迎すべきことである。さらに、小野田紀美氏を経済安全保障担当大臣に起用したことも、多様性の観点からは注目に値する。
社会保障政策の観点からは、高市首相は、超少子高齢化に対応するため給付と負担の在り方を議論する「国民会議」の設置を表明し、「税と社会保障の一体改革(給付付き税額控除の制度設計を含む)を超党派で検討する」「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しや、電子カルテを含む医療機関の電子化、データヘルス等を通じた効率的で質の高い医療の実現等について、迅速に検討を進める」[1]としている。
上野賢一郎厚生労働大臣に関しては、旧自治省出身でありながら、自民党の税制調査会幹事や財務金融部会長などを務めてきたが、今回初入閣であり厚生行政に関しては未知数のところがある。連立先の日本維新の会が、社会保障制度改革に関しては重要論点としており、上野大臣も就任会見で「いわゆる医療法に関する三党合意書、また、骨太方針に関する三党合意書に記載されている医療制度改革の具体的な制度設計を令和7年度中に実現する、社会保障全体の改革を推進することで、現役世代の保険料率の上昇を止めて引き下げていくことを目指す」[2]としている。
片山さつき財務大臣に関しては、「税と社会保障の一体改革、特に社会保険料負担で苦しむ中低所得者対策としての給付付き税額控除の制度設計に着手すること」、「デジタルを活用したEBPM(筆者注:Evidence-Based Policy Making)を推進し、効果的な予算配分、予算執行につなげること」[3]としている点が注目に値する。EBPMは、これまで定性的に語られがちだった社会保障制度の議論を、よりデータ駆動で透明性の高いものへと転換する鍵である。
医師出身デジタル大臣・副大臣への期待
高市政権で最も注目しているのは、デジタル大臣・副大臣である。松本尚デジタル大臣、今枝宗一郎デジタル副大臣はともに医師である。そのため、厚生労働省(厚労省)とデジタル庁の連携が強化され、医療DXの推進がなされるのではないかと期待する。松本大臣は、日本医科大学の教授として、救急医学・災害医学を専門とし、ドクターヘリの推進をしたことで知られ、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』[4]の医療監修も行っている。一方で、デジタルに関しては、救急医療におけるデジタル活用の経験はあるものの、過去にデジタル大臣を務めた平井卓也氏や平将明氏ほどは必ずしも明るくないようである。しかし、それがむしろ良いように思われる。というのは、現在、医療DXの推進の壁の一つとなっているものに、高齢化している医療従事者のデジタルリテラシーの低さがあるからである。
医療DXの重要性に関しては、他稿[5]でも述べてきたところであるが、医師を含めた国民的な理解を得るにはまだ至っていない。今枝副大臣は若手であるが、「医療・ヘルスケア産業の新時代を創る議員の会」(ヘルステック推進議連)をリードし、オンライン診療解禁やPersonal Health Record (PHR)推進の制度整備を進めてきており、医療DXに関しては知見を有している。「デジタル化については、『誰一人取り残さない』をモットーに、人口減少の中でも一人ひとりの生産性と暮らしの質を高める社会の実現に全力を尽くす」[6]としているが、松本大臣との連携により、医療従事者の理解の向上と、医療DXの実装が加速することに大いに期待する。
社会保障全般へのDX展開
加えて、デジタル庁は医療にとどまらず、介護、福祉、年金、子育てといった社会保障全般のデジタル基盤整備に関与している。介護分野では、ケアプランのデータ連携を可能とする介護情報基盤の整備を支援し、自治体システム標準化と併せて、効率的かつ質の高いサービス提供を目指している。子育て分野では、こども家庭庁との連携の下、母子保健や予防接種情報を含む「こども政策DX」においてPublic Medical Hub(PMH)の導入が進められており、子どもと家族に関する支援をデータに基づき提供するための基盤づくりが始まっている。
これらの社会保障DX施策は、松本大臣のリーダーシップの下、実務を担う今枝副大臣や川崎ひでと大臣政務官(NTTドコモ出身)らとともに省庁横断的に展開されつつある。特に今枝副大臣はPHRの推進にも取り組んでおり、医療・健康情報を本人が一元管理できる未来像に向けて具体策を推進している。
また、オンライン診療の恒久化と普及も医療DXの重要な柱である。新型コロナ禍を契機に初診からのオンライン診療が解禁され、今後は慢性疾患や高齢者医療をはじめとする分野での活用が期待されている。これにより、地理的・身体的制約を抱える患者へのアクセスが改善され、医療機会の平等性が高まるとともに、医療機関側の業務効率化にもつながる。デジタル庁はこの分野におけるガイドライン策定やシステム安全性の確保、自治体との連携強化を進めており、オンライン診療のインフラ整備は着実に前進している。
デジタル人材育成とEBPMの推進
これらの取り組みに加えて、医療DXを現場に定着させるには、デジタル人材の育成と確保が不可欠である。高齢化が進む医療現場では、ITに不慣れなスタッフも多く、技術導入を円滑に進めるための支援体制が求められている。現在、厚労省とデジタル庁は、医療・介護施設におけるデジタル人材(ITパートナー、デジタル推進支援員など)の配置を進めるとともに、全国医療機関向けにDX研修パッケージを提供している。今後、地域医療を担う中小規模の診療所や介護施設にも対応できるよう、地域単位での支援人材の育成・派遣モデルの構築が求められる。
こうした取り組みのベースには、EBPMの視点が重要となる。電子カルテの相互運用性、オンライン診療の効果、PHRの利活用状況といった各種施策の成果や課題を定量的に評価し、それに基づいた改善サイクルを回すことが求められる。ただし、エビデンス活用に関しては、一定のバイアスが生じやすいことにも留意すべきであろう[7]。ともあれ、デジタル庁は、医療・福祉分野におけるEBPM推進のため、関係省庁と連携してデータ標準化や匿名加工情報の利活用ガイドライン整備を進めており、今後は地方自治体レベルでもデータに基づく政策形成能力の底上げが期待される。
さらに、年金情報や介護情報などがマイナポータル上で閲覧できるようになるなど、行政サービスのワンストップ化も加速している。今後は、出生から高齢期まで、ライフステージ全体における社会保障サービスがマイナンバーを軸にシームレスにつながる社会の実現が期待される。
財源問題と持続可能性の確保
一方で、このような社会保障DXの推進には、相応の初期投資が必要となる。電子カルテの標準化、医療情報ネットワークの構築、デジタル人材の育成など、短期的には財政負担が増加する可能性がある。しかし、中長期的には医療の効率化や重複検査の削減、適切な予防医療の推進により、社会保障費の抑制効果が期待できる。
片山財務大臣が掲げるEBPMに基づく予算配分は、こうしたDX投資の費用対効果を可視化し、国民の理解を得る上で重要な役割を果たすだろう。特に、デジタル化による医療費削減効果を定量的に示すことができれば、必要な予算措置への合意形成も進みやすくなる。
また、給付付き税額控除の導入は、社会保険料負担の逆進性を緩和し、現役世代の可処分所得を増やす効果が期待される。これにより、少子化対策や消費の活性化にもつながる可能性がある。DXと税制改革を組み合わせた総合的な社会保障改革こそが、人口減少社会における持続可能性の鍵となる。
地方自治体の役割と地域格差の是正
そのため、社会保障DXの実装において、地方自治体の役割は極めて重要である。医療・介護サービスの多くは地域で提供されており、自治体がデジタル基盤を整備し、住民サービスに活用できるかどうかが成否を分ける。
現在、自治体間でデジタル化の進捗には大きな格差がある。財政力や人材確保の面で優位な都市部の自治体は先進的な取り組みを進める一方、人口減少が著しい地方の小規模自治体では、システム導入や人材育成に苦慮している。政府は自治体システムの標準化を進めているが、単なる技術的統一にとどまらず、地方への財政支援や人材派遣、先進事例の横展開など、実効性のある支援策が求められる。
特に、過疎地域においては、オンライン診療や遠隔医療が医療アクセスを確保する重要な手段となる。デジタル庁と総務省、厚労省が連携し、高速通信インフラの整備と医療DXを一体的に推進することで、地理的不利を克服し、全国どこでも質の高い医療を受けられる環境を実現すべきである。
国際的視点とデータ連携の未来
さらに、医療DXにおいては、国際的な動向にも目を向ける必要がある。エストニアやデンマークなど、デジタル先進国では既に全国民の医療情報が電子化され、EHDS(European Health Data Space)構想を中心に、国境を越えたデータ共有も進んでいる。日本も、こうした先進事例から学びつつ、独自の医療制度や文化に適合したシステムを構築していくべきである。
また、グローバルなAI開発競争の中で、日本の医療データは貴重な資源となりうる。個人情報保護と利活用のバランスを取りながら、匿名加工された医療ビッグデータを研究開発に活用し、日本発の医療イノベーションを創出することも重要な視点である。
結びに代えて
このように、高市政権下においては、社会保障政策そのものの改革と、それを下支えするデジタル基盤の整備が並行して進められている。デジタル庁が単なる技術部門ではなく、制度設計に深く関与するパートナーとして位置付けられる中、医師出身の松本大臣の現場感覚と政策遂行力、そしてそれを補佐するチーム体制が、日本の社会保障制度を人口減少時代にふさわしい持続可能な形へと進化させる鍵となるであろう。
人口減少と超高齢化という構造的課題に直面する日本にとって、デジタル技術は単なる効率化の道具ではなく、社会保障制度を次世代に引き継ぐための不可欠な基盤である。技術導入の過程では、デジタルデバイド(情報格差)への配慮や、医療従事者・国民の理解促進など、克服すべき課題も多い。しかし、誰一人取り残されないというビジョンの下、着実に改革を進めることができれば、日本は世界に先駆けて、デジタル技術と人間中心の医療・福祉が調和した社会モデルを示すことができるはずである。
東京財団では、「AIデータ利活用社会の実現」に向けた新規プロジェクトを開始した[8]。国内での医療DXの取り組みのみならず、国際的なデータ活用やAI活用の推進に向けて、今後も検討を深めたい。
[1] https://www.jimin.jp/news/policy/211670.html
[2] https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00861.html
[3] https://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2025b/20251022-1.html
[4] https://www.fujitv.co.jp/codeblue1st/index.html
[5] https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4453
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4717
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4755
[6]https://www.instagram.com/reel/DQHPNMJDKAp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==