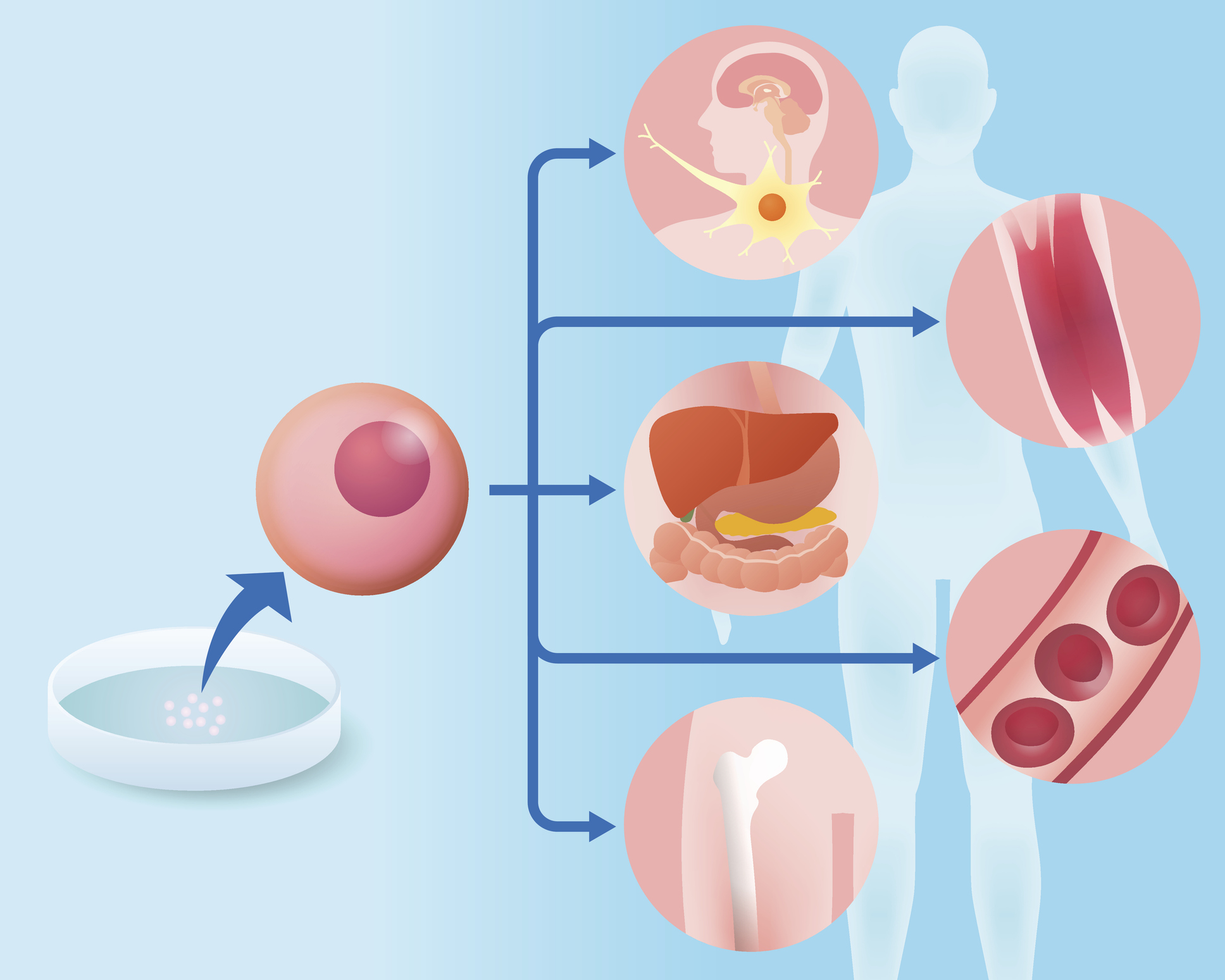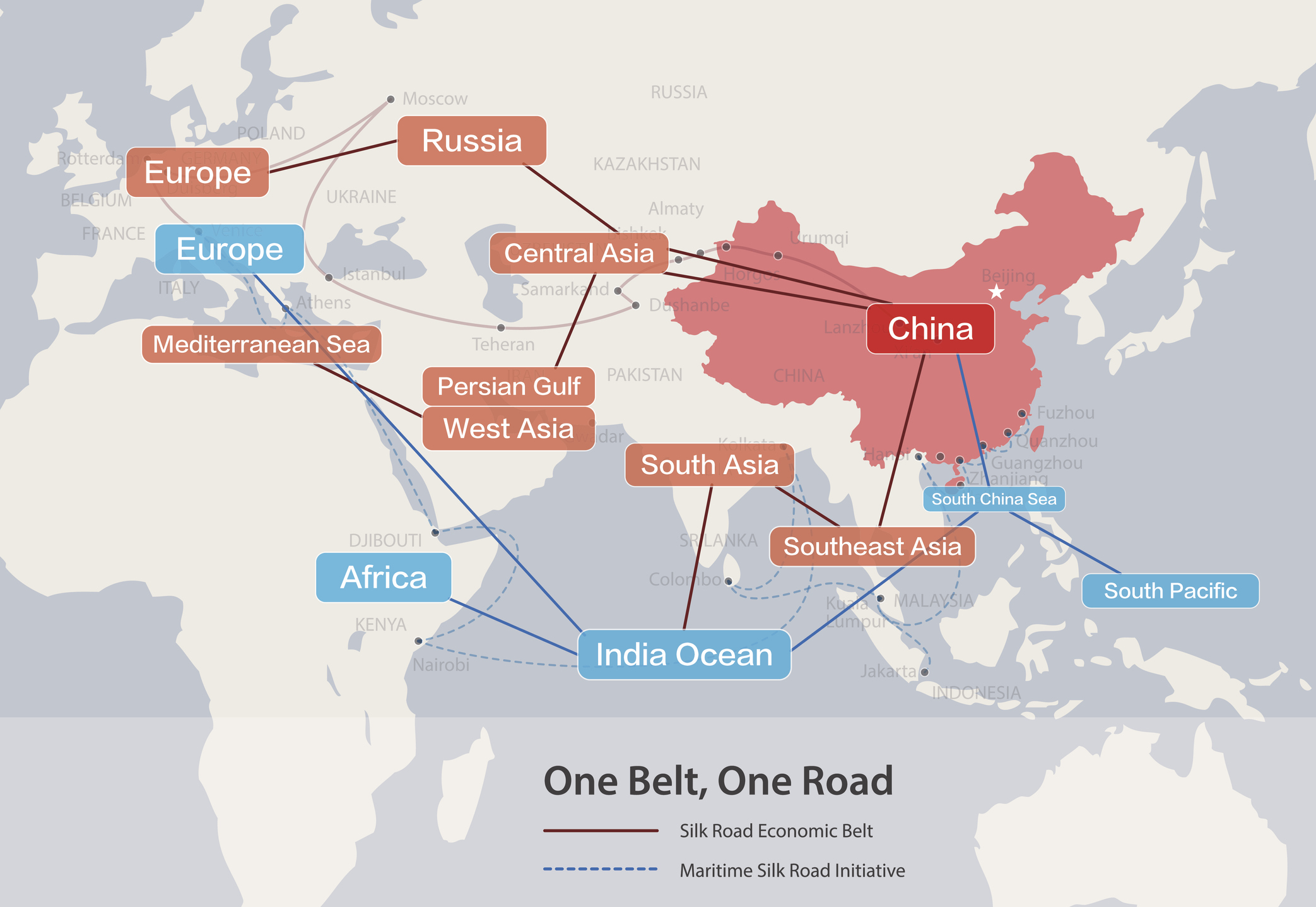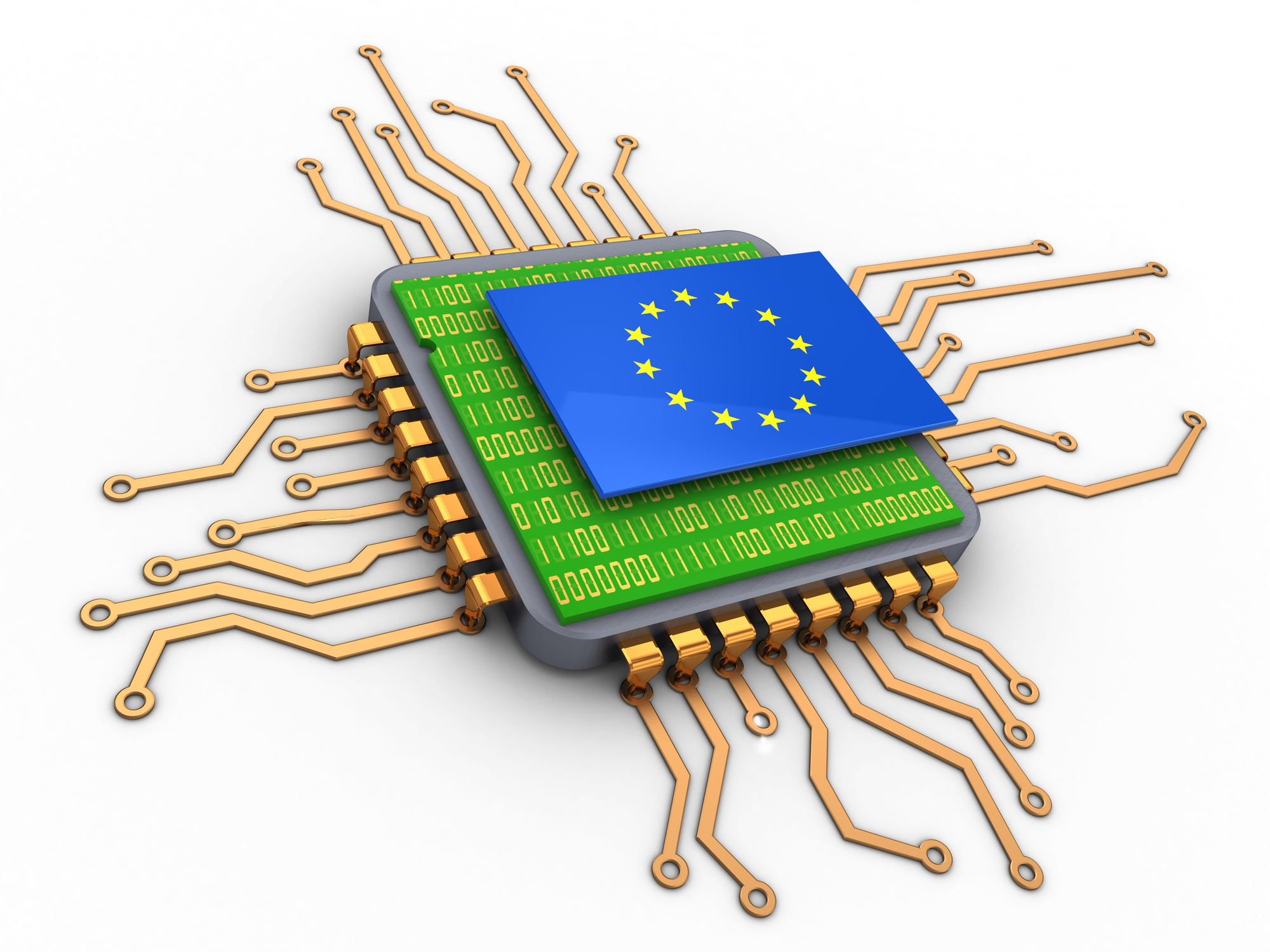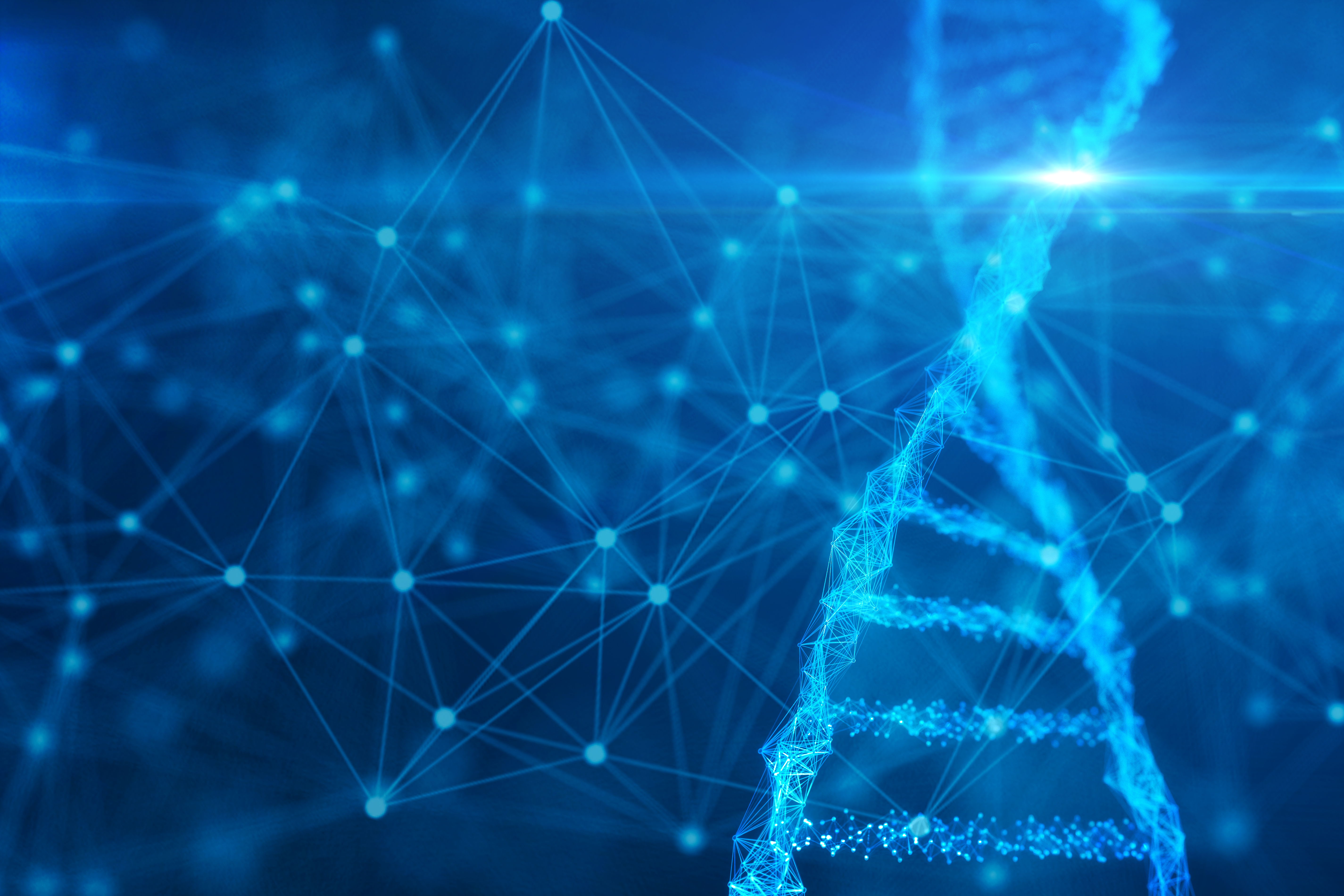R-2023-018
| ・はじめに 1.がん免疫治療薬「オプジーボ」に対する緊急薬価改定の概要と問い 2.緊急薬価改定に至る政策過程 3.考察 ・おわりに |
はじめに
新興科学技術は、従来の製品・サービスでは満たすことができなかった価値の提供を可能とする。ライフサイエンス分野では、新薬の開発により従来治療が困難であった疾患の治療が可能となり、再生医療等製品のように失われた機能や組織を再生させうる技術さえ登場しつつある。こうした新たな革新的な技術の登場は、アンメットニーズに応えるものであるがゆえに極めて高い価値を有すると同時に、非常に「高価」な価格設定となるのが一般的である。自由な競争市場ではない政策的に仕切られた市場において、こうした高価な製品・サービスの価格をどのように制御・調節するかは、科学技術政策の結果を受容し、あるいは制度化していくうえで極めて重要な課題である。
わが国において取り扱われる医薬品・医療機器・再生医療等製品は、その大部分が保険適用の対象となっている。これらの製品・サービスの価格は中央社会保険医療協議会(中医協)における検討を中心として、公定価格として政策的にコントロールされており、薬事とは異なる製品価格に対する実質的な規制として機能しているといえる。一方で、国民健康保険制度は保険料負担のみで完結しておらず、実際には4割程度を税によって賄っているのが実態である。それゆえに高額医薬品や再生医療等製品のような高額な製品に対する価格コントロールには、医療政策を所管する厚生労働省のみならず、財政当局による関与、すなわち財政的な統制という側面が強く観察される。
本稿では、こうした高額な製品・サービスに関する財政統制の事例として、がん免疫治療薬「オプジーボ」に対する緊急薬価改定の政策過程を概観したうえで、その制度的な公正性について考察することで、わが国における予見可能性の低い制度環境が企業にとって「レギュラトリーリスク」となりうることを指摘する。
1.がん免疫治療薬「オプジーボ」に対する緊急薬価改定の概要と問い
2016(平成28)年10月6日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)薬価専門部会において、小野薬品工業株式会社の抗PD-1抗体薬「オプジーボ®(二ボルマブ)」の緊急薬価引き下げが了承された。その後、11月16日に開かれた中医協総会ではあらためて薬価の50%引き下げが提案され、最終的にこれが了承されることとなった。このオプジーボに対する緊急薬価引き下げをめぐっては、特に手続き的な観点において極めて「異例」の対応がみられたことから多くの波紋を呼んだことは記憶に新しい。
2020(令和2)年度までは、薬価は原則として2年に1度の診療報酬改定に合わせて見直しが行われることが慣例であった[1]。ところが、オプジーボに対する薬価引き下げはこうした定期の改定の一環として実施されたものではなく、文字通りオプジーボのみを対象として緊急に実施された異例の価格改定のプロセスであった。中医協の了承を受け、2017(平成29)年2月に特例拡大再算定として薬価収載当初の価格から50%引き下げられたことを皮切りに、2018(平成30)年4月には用法用量変化再算定等として23.8%の引き下げ、同年11月にはさらに37.5%の引き下げがなされるなど、毎年のように薬価の急速な引き下げが進められたことで、現在のオプジーボの価格は当初の収載価格の5分の1程度の水準に至っている。
こうした短期間での価格の引き下げが繰り返された背景には、オプジーボの価格が極めて高額であることに加え、いわゆる適用拡大(効果・効能の追加や用法・用量の拡大)によって対象患者数が飛躍的に増大したことに伴い、大幅に財政的な負荷が増大することが予想されたことが直接の要因として挙げられる。実際の薬価改定のロジックは「当初の想定を超え、大幅に市場が拡大」したことを受け、市場拡大再算定の特例要件[2]に該当することから定められた算式に従って引き下げを行うというものであった。薬価改定の対象は、「ア 平成27年10月から平成28年3月に効能追加等されたもの」「イ 平成28年度の予想年間販売額が1000億円を、かつ予想販売額の10倍を超え」のものとされたが、実際にこれに該当する製品はオプジーボのみであり、実質的には「決め打ち」というべき対象設定であったといえる[3]。
ここでの問いは、大きく次の3点に集約される。第一に、なぜ通常の診療報酬改定ではなく、臨時改定による薬価引き下げというプロセスがとられることになったのか、その経緯と理由である。第二に、緊急薬価引き下げの妥当性およびその根拠は何かである。第三に、緊急薬価引き下げが、日本の医薬品開発・医療機器開発におけるイノベーションにもたらす影響についてである。以下では、これらの点を念頭に価格変更に至った政策過程について確認する。
2.緊急薬価改定に至る政策過程
2.1. 外部によるアジェンダセッティングとフレーミング
オプジーボをめぐる価格の高さと財政的な負荷の大きさの問題を指摘し、薬価改定の必要性をアジェンダとしてフレーミングしたのは、中医協をはじめとする厚生労働省内のプロセスではなかった。2016年4月4日に開催された財政制度等審議会(財政審)財政制度分科会においてヒアリング対象として招かれた日本赤十字社医療センター化学療法科部長の國頭英夫がオプジーボの財政的負荷についての問題提起を行ったことが直接的な端緒となっている。國頭は、オプジーボが年に3500万円もかかる薬(体重60キロの患者が1年間に26回使用することを想定)であり、肺癌患者推定13万人のうち少なく見積もって5万人に対して提供した場合に当時の薬剤費の20%近くに相当する1兆7500億円がコストとして生じることを指摘したうえで、オプジーボをはじめとする高額医薬品に対する価格コントロールが必要であることを主張した[4]。また、同会議の委員である土居丈朗(慶應義塾大学経済学部教授)が國頭の主張に同意するとしたうえで、医薬品の高額化等に伴って医療費が増加することを抑制する手段として薬の使用対象を制限する「ガイドラインを定めるというやり方」も有効なのではないかという提案を行っている。この提案が、実際にその後の使用制限を通じた価格抑制の根拠として求められる「最適使用推進ガイドライン(GL)」へとつながることになる[5]。
2.2. ステークホルダーによるフォローと内部化
財政審分科会の開催後には日本医師会がすぐさま反応し、4月6日に開かれた定例記者会見において「高額な薬剤が保険収載されることは、持続可能な保険財政の観点から考えれば、医薬品の費用の適正化を進めざるを得ない」として基本的に財政審での議論を肯定しながらも、価格決定のイニシアティブはあくまで中医協にあることを主張した[6]。
また、4月13日に開催された中医協総会では、診療側・支払側の双方から高額な医薬品について、効能・効果が追加され対象患者数が増加した場合には、期中でも薬価改定をすべきであること、薬事承認された効能・効果の一部だけを保険適用するルールも考慮すべきとする意見が提示され、薬価制度の根本的な見直しが必要ではないかとの指摘がなされるなど、財政審に概ね同調する流れとなった[7]。こうした中医協総会での議論を踏まえ、その後は「高額な医薬品の薬価算定ルール」に関するルールメイキングのあり方が焦点となるなど、財政審分科会によって設定されたアジェンダを受ける形で、中医協を舞台に緊急薬価改定に向けて議論が進んでいく形となった。7月27日に開催された中医協総会では「高額な薬剤への対応方針として、2年に1回の薬価改定における再算定以外の方法の検討を検討することに加えて、当面の対応として①「オプジーボに係る特例的な対応」の検討、②「最適使用推進のための取り扱い」の検討という方向性が示されている[8]。前者は手続きとしての緊急薬価改定をどのように正当化するか、後者は前述の土居らによる指摘を受け高額医薬品の過剰な使用を回避するためのガイドライン(使用が最適と考えられる患者の選択基準等)の整備を保険制度上どのように位置付けるかについてである。
このように、財政審分科会によってフレーミングされたアジェンダに従って、中医協においてもオプジーボをターゲットとした緊急薬価改定に向けてそのプロセスと手段のリーズニングが模索されることとなった[9]。一方で、引き下げ率をめぐっては、その算定根拠とされる市場拡大再算定の特例要件に該当する情報の不足もあり、機械的な算定が困難なことから大きな課題となった。
2.3. 経済財政諮問会議による政治的なイニシアティブ
その後、中医協および事務局においてガイドラインの具体化、引き下げ幅についての検討が進められたが、これまでに積み上げられてきた慣習を翻すような急な事情変更に対する正当化は容易ではなく、やや議論が硬直したまま推移することになる。そうしたなか、大きく事態が進むことになるのは、10月14日に開催された経済財政諮問会議の場である。ここでは、民間議員である高橋進、伊藤元重、榊原定征、新浪剛史らによってオプジーボの薬価引き下げを行う必要性が指摘されることとなった。特に、新浪は「現在検討されているオプジーボの下げ幅は最大で25%と伺っているが、50%以上下がっても然るべきだと思う…(中略)…2年に1回というルールづくりではなくて、期中の再算定もできるというルールづくりをしっかりやるべき」と述べるなど、引き下げ幅をめぐって調整が続く中で50%引き下げが適当という引き下げ率に関する具体的な言及を行っている点が着目される[10]。こうした経済財政諮問会議における民間議員による指摘を受け、安倍晋三首相(当時)が「高額薬剤について対応策を具体化してもらいたい」と関係大臣に指示を行ったほか、塩崎厚労相が「国民負担軽減の観点から、薬価改定の年ではなくても緊急引き下げを実施する」と説明するに至った[11]。これにより、市場拡大再算定の特例要件の該当性にかかわらず、50%引き下げという方向性が決定的なものとなった。
このように経済財政諮問会議において「50%引き下げ」が妥当であるという見解が示されたことが、オプジーボの緊急薬価改定に関する一つの帰結を導くことになった。特に着目されるのは、「50%引き下げ」の妥当性については必ずしも具体的な議論や検討、あるいは算定要件に照らした妥当性の検証等が十分に行われないままに、その結論のみが政治的に決定された点であろう。
表 オプジーボの緊急薬価過程に関する主な出来事
|
年月 |
内容 |
|
2016年4月 |
財政制度等審議会財政制度分科会による問題提起 |
|
2016年4月 |
中医協総会および費用対効果評価専門部会においてオプジーボが取り上げられる |
|
2016年7月 |
中医協総会において「最適使用促進ガイドライン」(厚労省医薬・生活衛生局)について了承 |
|
2016年8月 |
中医協薬価専門部会において「緊急薬価引き下げ」が提案される |
|
2016年9月 |
中医協薬価専門部会において製薬業界に対するヒアリングが実施され反対意見が示される |
|
2016年10月 |
経済財政諮問会議民間議員が50%引き下げを要求 |
|
同 |
首相が厚生労働大臣をはじめとする関係大臣に引き下げを指示 |
3.考察
3.1.外的な統制の背景
オプジーボをめぐる緊急薬価改定の政策過程をみると、診療報酬や薬価の改定が厚生労働省における自律的なプロセスとして完結しているわけではないことをあらためて認識させられる。社会保障財政はそのボリューム、伸び率ともに際立った特徴を有するがゆえに、他の政策領域以上に強力な財政統制を受けることになる。財政審や経済財政諮問会議といった財政志向の会議体からの影響力、さらにこれらと連動した政治的イニシアティブが強く機能した様子がうかがわれる。
また、中医協における意思決定そのものが、そのオペレーションの多くが様々な慣習に依拠しており法的なサポートが弱いため、とりわけ政治的なイニシアティブに対抗するような制度的な基盤を持ち合わせていない。(特に製薬・医療機器業界において)意外と正確に認識されていない点として、中医協自体に価格決定権はなく、厚生労働大臣に求められて答申を行うことがその基本的な機能とした諮問機関にすぎない[12]。そのため、薬価は最終的に必ず政治的にオーソライズされることになる。そのため、中医協における意思決定は、行政組織における稟議のような垂直的意思決定プロセスではなく、あくまで答申のための合議の積み重ねにすぎず、ときとして政治的な決定がこうしたプロセスに対して優位となりうる。実際、オプジーボの価格改定をめぐっては、2016年度の当初から財政当局によってオプジーボに対する薬価改定の必要性がフレーミングされたうえで、経済財政諮問会議をはじめとする政治的なイニシアティブがそれを後押しする形となったことで、落としどころが決定的となったといえる。
また、薬価の調節という観点では、基本的に2年に1回の薬価改定により一様に価格を低減させる手法のみしか持ち合わせておらず、高額医薬品のような財政的負荷の著しい製品に関する「価格抑制」「価格再調整」といったメリハリの利いた価格コントロールの仕組みを持ち合わせておらず、他の価格調節の手段を選択する余地がなかったことも課題として指摘できる。
以下では、本事例から得られるインプリケーションとして、特に制度的な公正性の観点から3つの点について課題を指摘したい。
3.2.事後法的な対応
さかのぼれば、2015(平成27)年12月にオプジーボに対する適用拡大(肺がん効能追加)を認めたのも厚生労働省および中医協であり、本来であればその時点で対象患者数が飛躍的に増大することは予見できたはずである。それに伴い薬剤費が急激に増大し財政的な負荷が大きくなることは想像に難くなかったはずであるが、厚生労働省は財政当局による外部からの統制が進む前に、自らオプジーボをはじめとする高額医薬品等に対する価格の抑制や制御について自律的にルール形成を行うことができなかったように見受けられる。オプジーボは、国産の画期的新薬ということで新薬創出加算の加算率を変更するなどの制度改正を行ってまで保険適用を行った製品であったこと、また期中改定という例外的な取り扱いを正統化することなど、終始対応に苦慮した様子がうかがわれる。
しかしながら、財政的な負荷が大きくなることが外的に指摘されたからといって、事後的に新たなルールを設定して当該製品の公定価格を切り下げるというのはやや乱暴な印象を受ける。というのも、保険適用を申請する側の企業からすれば、何ら手続き的に違法性や瑕疵があるものではなく、少なくとも形式的にはあらかじめ定められた手続きにのっとって申請を行い、保険適用(および適用拡大)を受けただけである。緊急薬価改定はあらかじめ定められたルールにのっとって実行されたものではなく、事後的に争点化され文字通り「特例的」な対応が行われたものである。
また、最適使用ガイドラインの策定についても該当する特定の製品を念頭に、その使用を制限するために事後的に用意された手段であり、事後法的な側面を多分に有する。いわば「後出しじゃんけん」ともいうべきこうした対応は、薬価をめぐる制度運用が極めて予見性の低いなかで営まれていることを如実に表している。公定価格という仕組みが、薬事とは異なる価格面での実質的な規制としての性格を有している以上、こうした予見性の低い制度運用についてはその公正性が問われる。
3.3.曖昧な根拠づけ
通常の薬価改定は、改定前に行われる薬価調査で把握された市場実勢価格をもとに行われる。一方で、オプジーボに対する薬価引き下げにあたっては、通常の薬価調査を実施する余裕がないことから、厚生労働省が独自に推計した値を用いながらオプジーボの年間販売額を算出し、その結果として特例再算定の対象となる1500億円の基準を超える(1516億円)と整理された。
小野薬品公表の予想販売額÷流通経費×消費税(1.08)×乖離率+適応拡大分X円=1516億円+X円[13]
厚生労働省はこの算定式のうちの「乖離率」を3.45%と設定して推計を行った。乖離率を3.45%とした理由は、2015年度薬価調査における「その他の腫瘍用薬(注射薬)」の平均乖離率6.9%の「2分の1」(新薬創出加算の対象であることを考慮)であると説明されているが、この「2分の1」の妥当性は極めて不明瞭であり、実際に11月16日に開催された中医協総会においても複数の委員から「2分の1」の妥当性に対して疑義が提示されている。それに対する厚生労働省の担当者(薬剤管理官)は「保守的に厳しく見積もりをするべきであると考えまして」「平均乖離率の6.9%に対して2分の1を掛ける明確な根拠はないということです」「やはり厳しく見積もった上でという観点を入れたいことから2分の1にした」と回答するにとどまり、「2分の1」に関する明確なエビデンスを示すことはなかった。最終的には、合理的な説明を欠いたまま「今回限りの式」ということで了承されるに至っている[14]。
このように、実際には50%引き下げという結論ありきで、年間販売額の推計が1500億円を超えるように「乖離率」を調整したと言われても仕方がないような形で根拠づけがなされており、その判断の妥当性に大いに疑問が残る結果となった。
3.4.イノベーションへの影響
期中における価格改定および50%の引き下げのいずれについても、後付けでの根拠づけを求められたことからわかるように、何らかの制度的裏付けのもとに、然るべき手続きにのっとり価格改定が試みられたわけではない。既に述べたように、むしろ価格引き下げありきで議論が推移しており、公正性の面で疑問が残る。
実際に適用拡大を了承したのも中医協であり、了承した時点においては価格再算定について明示されていない以上、メーカーにとっては先々価格引き下げを受けるのは定期的な価格改定のタイミングであると予想するのは合理的な行動といえる。その点でいえば、オプジーボの緊急薬価引き下げは「予見可能性」を大きく損なうものであるといえる。公定価格が設定されている以上、企業の収益はその価格に直接依存しており、価格の改定はいわば企業の利益そのものを直接的に操縦する形となるため、その決定には高い予見可能性と公正なプロセス、そして透明性が求められる。
企業の側が悪意を持って適用拡大によって瞬間的な利益の最大化を狙ったのではないかとする意見も考えうるが、仮に、万が一そうであったとしても企業が現行制度から予測される範囲内で利益の最大化を目指して行動するのは当然のことであり、制度的な欠陥があったことを企業側の責任に転じることは誤りであると考える[15]。その点において、適用拡大をめぐって企業側に手続き上の瑕疵があったとは言えないだろう。また、現在の毎年改定の仕組みとは異なり、当時は2年に1度の改定を通例としており、特例的に特定の製品のみを対象とした薬価改定を期中に行うことを企業側に予見させることはできなかったであろうと思われる。
実際、これらの点については、2016年9月14日に開かれた中医協薬価専門部会での製薬業界に対する聞き取りにおいて、①企業は2年に1度の薬価改定を前提に経営を行っていること、②これまで存在しないルールを突然導入することは容認できないこと、③イノベーションを阻害する可能性があることに対して強い疑問と批判が呈されている[16]。すなわち、たとえオプジーボをめぐる特例的な取り扱いであったとしても、いったんこうした例外的な価格改定を行うことそのものが制度的な予見性を低下させ、日本における研究開発と上市に対する意欲を削ぐことにつながるという指摘である。特徴的なのは、こうした企業側の見解は、緊急薬価改定の方向性が既に決定された後に聴取されており、議論の方向性を検討する過程においては参照するような機会が(少なくとも公式には)設けられていない点である。政策変更の影響を直接的に受ける当事者の声はもちろん、関係する業界などのステークホルダーの意見が考慮されないままに、規制側の論理だけで強引なルール変更や解釈の変更を推し進めることは、規制内容に積極的に従うどころか、被規制主体側の規制主体に対する信頼感や規制手段・規制内容に対する納得感を失わせ、モラルハザードを誘発する可能性さえある。
おわりに
本件において、財政的な観点から何らかの手段で早急にオプジーボに対する価格抑制を行う必要性があったことは論を待たない。しかしながら、価格抑制の方向性とその手段の決定に至るプロセスについてはその公正性があらためて問い直されるべきであろう。
実際の価格改定をめぐる政策過程においては、政策変更の影響を受ける企業や業界の見解がきちんと聴取されることもなく、また議会における議論や検討がなされていないなかで、一企業の利益を左右するような特例的な価格改定の方向性が決定されている。薬価改定は特定の企業の利益に直接的な影響を与えるものでありながら、法改正などの政治的な調整コストの大きいプロセスを必要としない、行政のプロセスのみで変更できてしまう仕組みである。その点、政府の側には、公定価格という制度を通じて企業の経営に直結する利益、損失についての一定の操縦可能性が存在していると言えよう。そうであるからこそ、政府の対応には高い公正性や予見可能性が求められるのであり、あらかじめ定められたルール以外の方法でプレイヤーの行動を統制するようなことは決してあってはならない。
イノベーションに向けてプレイヤーの積極的な行動を誘発しようと考えるのであれば、透明性のあるプロセスのもとでつくられたルールに基づいて、いかに予見可能性を高めていくのかが追求されるべきであり、オプジーボの事例はそれとは逆行するような事案であったといえる。こうした制度的な公正性が保証されない限り、日本の市場における規制環境は企業にとっては文字通りレギュラトリーリスクにしかならないのである。
[1] 2021年度以降は診療報酬改定のない年にも薬価改定が行われるようになっている。
[2] 市場拡大再算定の特例要件では、①年間販売額が1000億円を超え1500億円以下、かつ予想販売額の1.5倍以上の場合に最大25%引き下げ、②年間販売額が1500億円を超え、かつ予想販売額の1.3倍以上である場合に最大50%引き下げを行う、とされていた。
[3] 内閣府経済財政諮問会議社会保障ワーキング・グループ資料https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/291018/sankou1-5.pdf(2023年1月30日アクセス)
[4] 國頭英夫「がん治療のコスト考察; 特に肺癌の最新治療について」2016年4月4日(財政制度等審議会財政制度分科会提出資料)なお、審議会事務局を務める担当主計官は國頭に対するヒアリングを実施する意図として「政策論の在り方として、このような医療の高度化をどのように取り込んでいくか、その上でいかに医療保険制度の持続性を確保していくのかという観点から、どのように改革を行っていくかということを議論していただく時の、1つの視点としてお話しいただければ」と述べている。
[5] 財政制度等審議会財政制度分科会「議事録」平成28年4月4日https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10319762/www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/proceedings/zaiseia280404.html(2023年1月30日アクセス)
[6]日医on-line(5月5日プレスリリース)
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/004339.html(2023年1月30日アクセス)
[7] 中央社会保険医療協議会総会(第330回)議事録https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125926.html(2023年1月30日アクセス)
[8]中央社会保険医療協議会 総会(第334回)「高額な薬剤への対応について(案)」 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130983.html(2023年1月30日アクセス)
[9] なお、4月27日に開催された中医協費用対効果専門部会では、営業利益率の加算率が最も高いことを理由にオプジーボを費用対効果評価の試行的導入における対象品目として選定している。
[10] 内閣府「経済財政諮問会議 議事要旨」(平成28年10月14日)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1014/shidai.pdf(2023年1月30日アクセス)
高橋は「オプジーボは肺がんへの適用拡大に伴い、患者数が新薬収載時の想定の32倍以上へと大幅に拡大している。薬価の大胆な引き下げ、効能追加などに伴う期中の再算定ルールの明確化が不可欠である」としたほか、伊藤は「日本の価格設定に柔軟性がない、機動性がない」ことを指摘した。また、榊原は「オプジーボは、早期に大胆な引下げを行う必要がある。そして、平成30年の薬価改定においても、必要に応じて、更なる適正化を図る必要がある。また、今回のケースのような、効能・効果の追加などに伴う期中の再算定の在り方についてのルールを、きっちりと見直す必要がある」と述べている。
[11] 「オプジーボ、『50%以上の引き下げ』求める声も」 https://www.m3.com/news/open/iryoishin/467681
[12] 厚生労働大臣に価格決定権があり(健康保険法76条)、その価格改定の際は厚生労働大臣は中医協に諮問しなければならない(同82条)とされている。
[13] Answers News「オプジーボ 根拠乏しい「50%引き下げ」…17年2月に緊急薬価改定」http://answers.ten-navi.com/pharmanews/8141/
[14] 中央社会保険医療協議会総会(第339回)議事録https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153024.html(2023年1月30日アクセス)なお、委員からは乖離率を「3分の1」として計算すると1497億円になり、25%引き下げが妥当という結論になることが示唆されている。
[15] この点は、ふるさと納税における新制度(指定制度)による大阪府泉佐野市を指定しない旨の総務省の決定を違法とした判例に類似する性質を有していると考えられる。令和2年(行ヒ)第68号 不指定取消請求事件 令和2年6月30日第三小法廷判決
[16] 業界団体からの意見聴取では、以下のような意見が提示された。「企業は2年に1回の薬価改定を前提に経営を行っており、期中改定ありきの議論にくみすることはできない」「これまでにないルールを突然導入し、適用することは到底容認できない」(多田正世:大日本住友製薬社長、日本製薬団体連合会会長)、「イノベーションを阻害するだけでなく、医療の現場や流通段階で不要な混乱が生じることも懸念される」「革新的な医薬品の薬価を期中に引き下げる制度を導入すべきではない」(梅田一郎:ファイザー社長、米国研究製薬工業協会・在日執行委員会副委員長)、「(現行の2年おきの価格改定が)適切に機能している」(カーステン・ブルン会長:バイエル薬品社長、欧州製薬団体連合会)
出所:中央社会保険医療協議会薬価専門部会「第118回議事録(2016年9月14日) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147619.html(2023年1月30日アクセス)