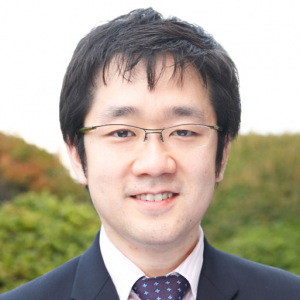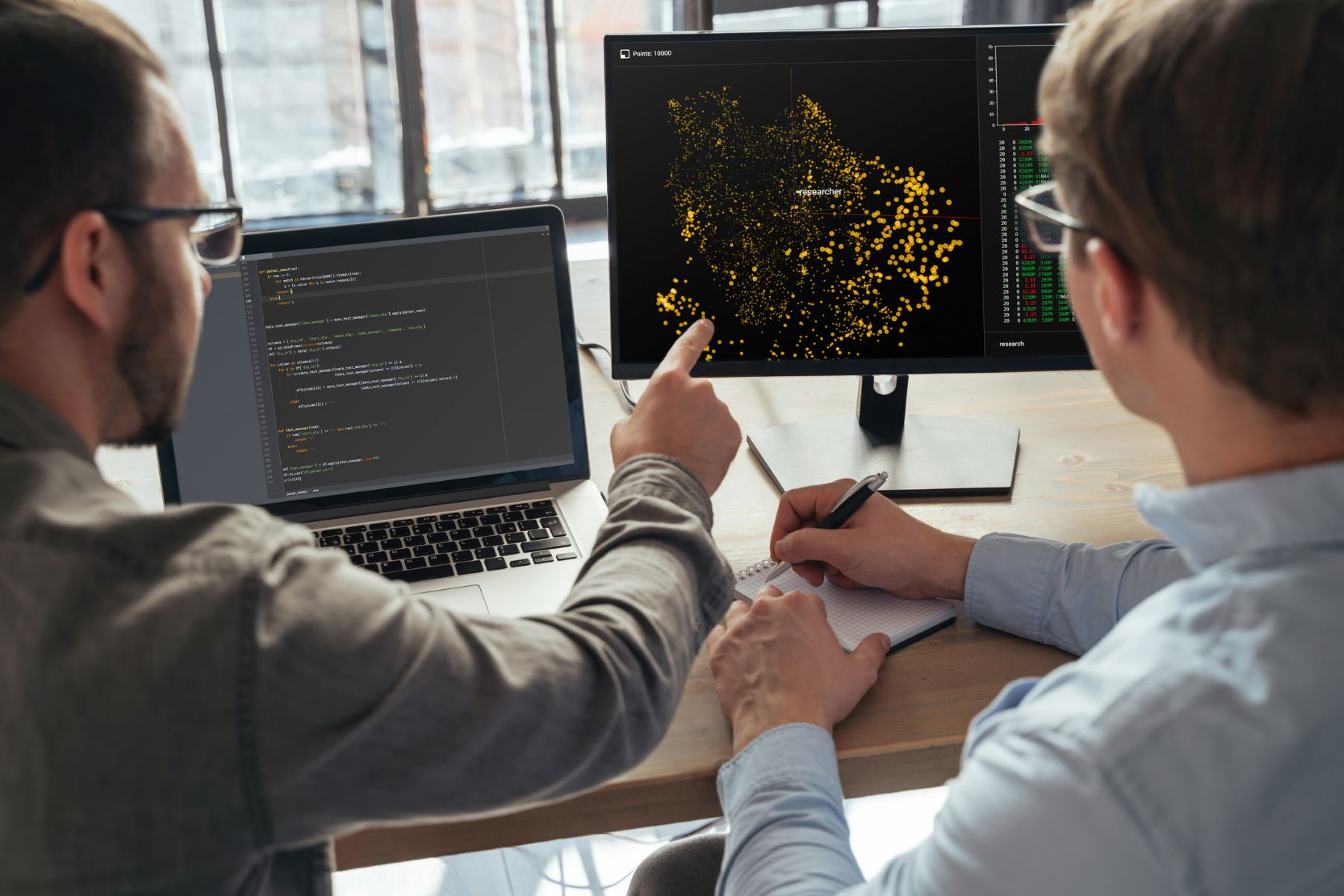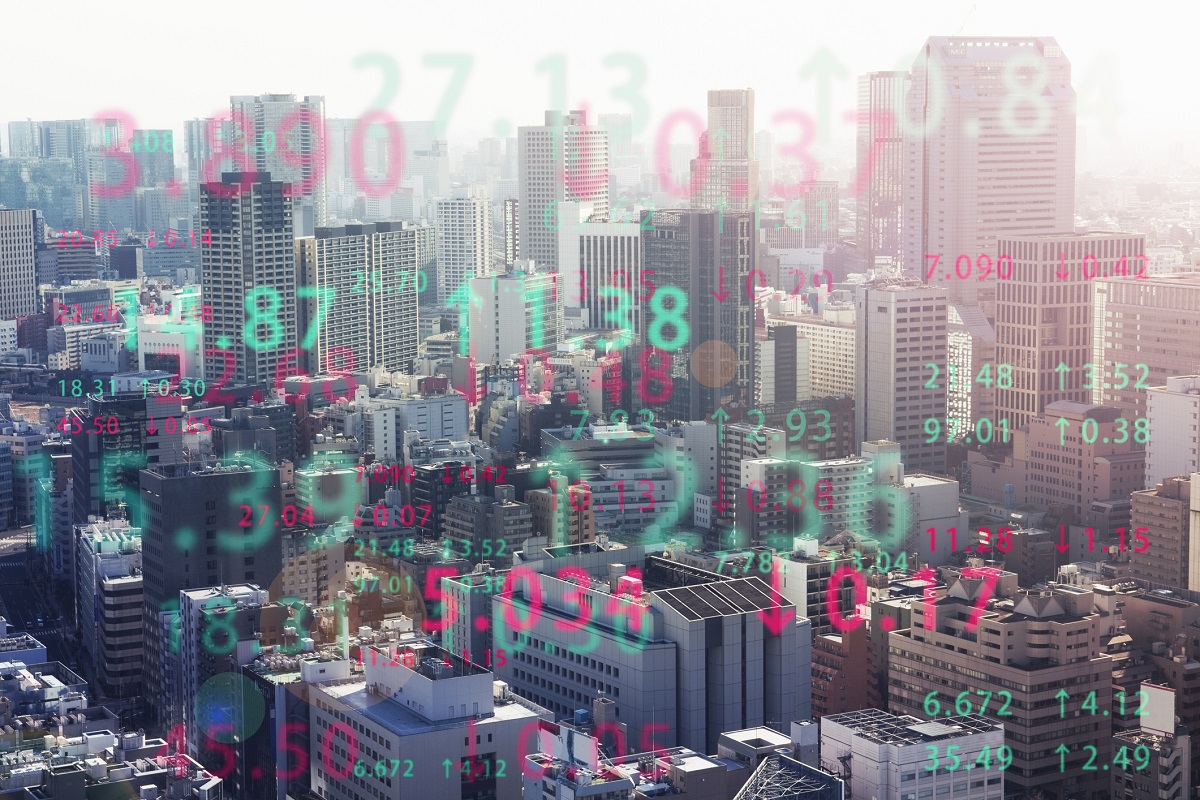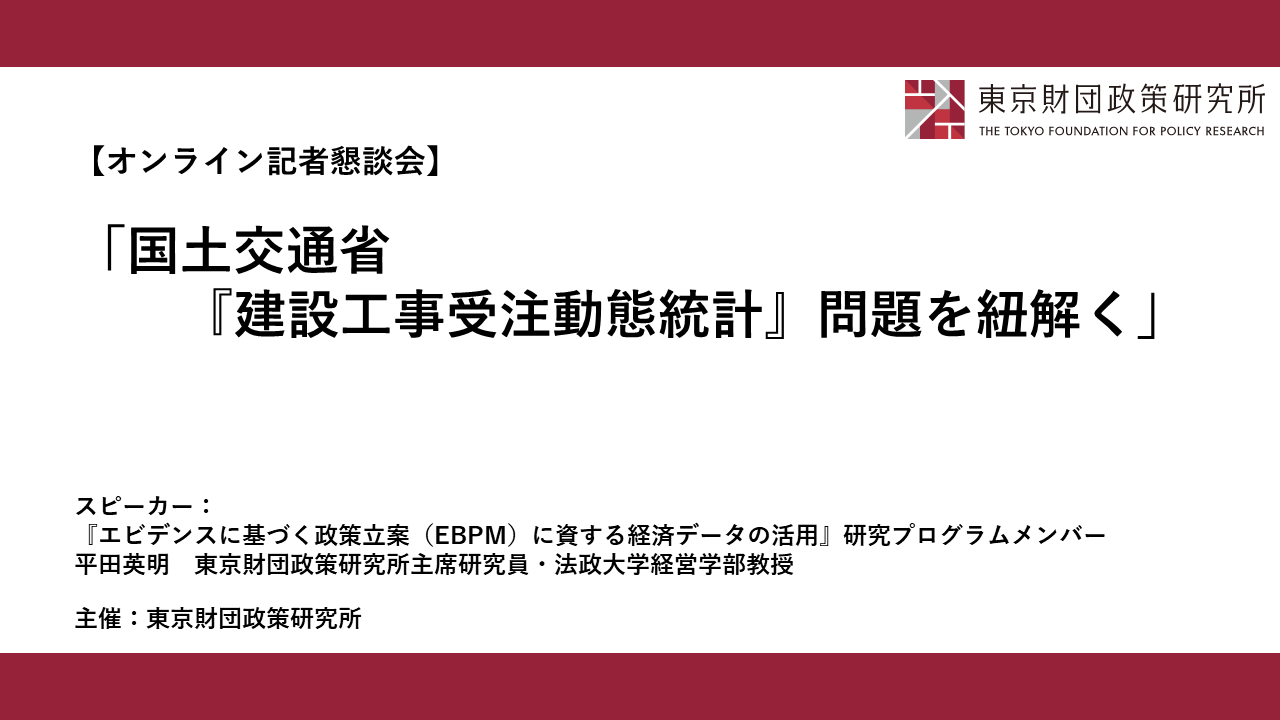東京財団政策研究所「リアルタイムデータ等研究会」メンバー
法政大学経営学部教授
はじめに
ふるさと納税の本来の目的は、故郷や地方を思う気持ちや地域貢献を寄附という形で表すことである。たしかに、ふるさと納税は個人住民税の寄附金税制の1つであり、「寄附」という位置づけであるが、実際のところは純粋な寄附目的でふるさと納税の額が過去5年ほどで急増したわけではない。詳細は平田(2018)に譲るが、最も肝となるのは、①(控除の上限を下回る)寄附額については、居住する自治体に本来は行う納税を回避できて所得控除の対象となる、②寄附先の他自治体から何らかの返礼品を受け取ることができる、以上2点の組み合わせである。結果的に、かなり極端な「節税」ができることが人気の秘訣と考えられる。ふるさと納税をして貰った自治体が納税者宛てに用意する返礼品はふるさと納税に必ず付けなければいけないものではない。しかし、ふるさと納税額の一定分(=返礼率。現在は寄附金の3割が上限)が返礼品として戻ってくるのであれば、納税者にとっては魅力的であろう。
ふるさと納税の議論について賛否が混在するが、議論を冷静に分析すると、賛否の根っこにはそれを論じる立場の違いがある。本稿では経済主体別にそれを整理した上で、本質的な意味でふるさと納税の果たしている役割を明らかにし、同等の政策を行うならばもっと効率的な方法があることを論じる。なお、本稿は筆者の研究室の学生達による2論文(鈴木麻世・我妻沢麻・八木湧大・後藤菜月「ふるさと納税の決定要因」2018年10月、我妻沢麻・八木湧大・安達美穂・井桁知洋「ふるさと納税の功罪〜自治体間格差とふるさと納税の決定要因〜」2019年10月[1])にその多くを依拠している。
経済主体別にみたふるさと納税の影響
ふるさと納税の影響を理解するに際し、流出の影響と流入の影響を区別して考えることが肝要だ。流出とは、居住自治体以外の自治体(以下「他自治体」)へ寄附が行われていることにより、居住自治体が本来受け入れるはずであった納税分を失うことを意味する。流入とはその逆で、他自治体から居住自治体へ行われる寄附である。
家計
実は、家計にとってふるさと納税は諸手を挙げて歓迎の政策とは必ずしもいえない。なぜなら、他自治体へ寄附をするということは、返礼品が貰えるという正の影響があると同時に、居住自治体への納税額が減るという負の影響もあるためである。結果として、居住自治体から本来受けるはずであったところの行政サービスを受けられなくなる。この負の影響をより大きく受けやすいのは高所得層よりも低所得層になる。財政の所得再分配機能を踏まえれば自明であろう。更に言えば、高所得者になるほど控除の上限が高まり、ふるさと納税をするインセンティブが高まりやすいことも、低所得層の受ける影響を大きくする[2]。
次に、流入に目を移そう。居住自治体の家計にとって、流入に対しては何も影響を与えることは出来ないが、流入額次第では大きな影響を受ける。もしも流入額>流出額であれば、単純計算で、居住自治体への納税額が減るという負の影響が帳消しとなるだけでなく、追加的な行政サービスを享受できることになるかもしれない。逆に、流入額<流出額であれば、居住自治体への納税額が減るという負の影響は流入額分だけ弱まるが、本来よりも受けられる行政サービスは減ってしまう。
企業
企業の立場からみると、多くの場合で直接的な影響は限定的である。ただし、流入について返礼品に選定された物品やサービスを生産・供給する企業となった場合、話は別となる。自社の製品が返礼品として選ばれることで、収入は増えることになる。
自治体
自治体の立場から考えると、流入額は自治体の歳入となるが、流入総額のうち実際に自治体にどのくらいのお金が残るかはまちまちである。大きい部分で言えば、返礼率30%、ポータルサイトへの掲載コストに10%、決済関係の手数料で数%が差し引かれる。ここで、ポータルサイトとは、返礼品の情宣を行う民間のオンラインサイトである。また、返礼に関しては、個別企業に偏るという問題はあるが、地元産業の振興につながるという経済効果もある点は注意を要する。
流出は本来期待されている税収を減らす。ただし、地方交付税交付金を受けている自治体の場合、流出額の75%が国からの地方交付税交付金によって補填される。これは、流入額の大小とは関係なく補填される。しかし、地方交付税交付金の対象となっていない自治体の場合は、補填は行われない。一部の地方交付税交付金対象外の都市部の自治体がふるさと納税に不満を表明するのは、この補填がない中で、高所得層がふるさと納税を積極的に活用する結果、大きな流出に直面するためである。
さて、整理をすると、ふるさと納税の自治体への影響を把握するには、①ふるさと納税による流入(税収増)、②他自治体への流出(税収減)、③地方交付税交付金による補填の3つを捉える必要がある[3]。2018年度の場合、1739市区町村のうち地方交付税交付金を受けている1639市区町村についてみると、①と②で既に黒字となっている自治体数は1366(83%)、③のおかげで黒字に転じる自治体は141(9%)となる。③をうけても赤字の自治体は132となっており、92%の自治体はふるさと納税に関して黒字となっている。なお、地方交付税交付金を受けていない場合、黒字自治体の割合は33%にとどまる。
政府
政府(国)にとっては、ふるさと納税に関連して、地方交付税交付金の歳出が発生する。年々ふるさと納税の受入額及び受入件数は増加しており、政府の負担も増加傾向にある(細かいが、納税者がワンストップ特例制度を利用しない場合は所得税も控除され、その分の国税が減る)。ただし、ふるさと納税制度を通じて地方創生に財政支出をしているとみなすこともできる。
結局何がおきているのか
以上、各主体別に概観した通り、同じ経済主体の中でもふるさと納税からうける影響は異なる。では、結局、この結果、何がおきていると考えればよいのだろうか。
第一に、寄附という名目でありながら、実質的には節税手段として機能し、特に高所得層がその恩恵を得る仕組みとなっているということである。近年、とくに高所得層は増税に直面してきていることを踏まえると、やや穿った見方をすれば、ふるさと納税は不満のガス抜き的な効果をもたらしたと評価してもよいのかもしれない。
第二に、ふるさと納税が実質的な意味で農水産業やそれに関連する産業の割合の多い自治体への補助金のような役割を果たしているということである。ふるさと納税の返礼品は原則として地場産品とするという規制がある中で、雑貨・工芸品や宿泊券等に比べると、生鮮食品や加工食品が返礼品の人気ランキングを独占している(株式会社Insight Tech, 2019)。また、農水産業が盛んな地域はふるさと納税で黒字となるケースが多いことがデータからも確認できる。
第三に、ラフに言えば、ふるさと納税は都市部から地方への所得移転となっているということである。これは、地方創生という観点でいえば、思惑通りだということになる。地方交付税交付金を無視すると、8割程度の自治体(主に地方)がふるさと納税で黒字、残り2割が赤字(主に都市部)ということは、(あくまで単純な平均値での議論となるが)ふるさと納税という枠に限って考えると、赤字自治体1団体あたりで4つの黒字自治体の黒字を支えているという構図になっている。
第四に、交付金無しでも既にふるさと納税に関して黒字の自治体に、更に国が交付金を支払っている状況が8割以上存在しているということである。これは、ふるさと納税に関する地方交付税交付金は、流入額と独立に決まってくる(流出額にのみ応じて決まる)ため発生する。仕組み上致し方のないこととはいえ、このような仕組みが、返礼率の上限規制が導入される以前の時期に、返礼率を少しでも高めて流入額を増やそうというインセンティブを各自治体に与えた。
さて、以上のようなことをもっとシンプルに実現できないのだろうか。ふるさと納税には地方の宣伝効果が一定程度あるため、その点はふるさと納税独自の魅力といえる。しかし、それ以外については、(適切かどうかの議論は別として技術的には)補助金や減税でもっとシンプルかつ低コストで同等の経済効果を実現することができる。むしろ、ポータルサイトや決済業者という地方創生とは関係の薄い民間企業を徒に利してしまうという問題を改善できるだろう。
昨年6月以降、過度な競争を防ぐ目的から、返礼率を3割以下とする規制が導入された。これに関連して話題となった泉佐野市は、この規制導入前の2018年度に全国のふるさと納税の1割のシェアを集めた。これは泉佐野市の返礼率が他自治体に比べて著しく高かったためである。今後はこのようなメカニズムは働かないため、泉佐野市のような突出した寄附額を集める自治体は減ることが予想される。総務省によるふるさと納税の位置付けは、①納税者が寄附先を選択でき、②地元など関心のある自治体の力となることができ、③自治体間の競争を促すことができる、というものである。今後、納税者の関心を引きつけ、適正な自治体間競争に繋がる要素が何になるのか、単に人気の食品というのではなく本源的な地方の魅力を反映した納税の仕組みが実現できるのか、様々な問題を抱えて今後も制度は継続していく。
参考文献
株式会社Insight Tech(2019)「「ふるさと納税」に関する実態調査」2019年12月13日
平田英明(2018)「ふるさと納税で大きい、ポータルサイトの存在」朝日新聞社『論座』2018年12月20日
[1] https://hirataseminar.wixsite.com/hirata-seminar/research
[2] 例えば、総務省によれば、共働き+子1人(高校生)の家計の場合、年収が300万円ならば1.9万円、1000万円ならば16.6万円までのふるさと納税が全額(自己負担額2000円を除く)控除の対象になる。
[3] この段落の自治体数の結果は、井桁知洋氏・安達美穂氏の計算に基づく。
 平田 英明 法政大学経営学部 教授
平田 英明 法政大学経営学部 教授
1974年東京都生まれ。96年慶応義塾大学経済学部卒業、日本銀行入行。調査統計局、金融市場局でエコノミストとして従事。2005年法政大学経営学部専任講師、12年より現職。IMF(国際通貨基金)コンサルタント、日本経済研究センター研究員などを歴任。経済学博士(米ブランダイス大学大学院)。