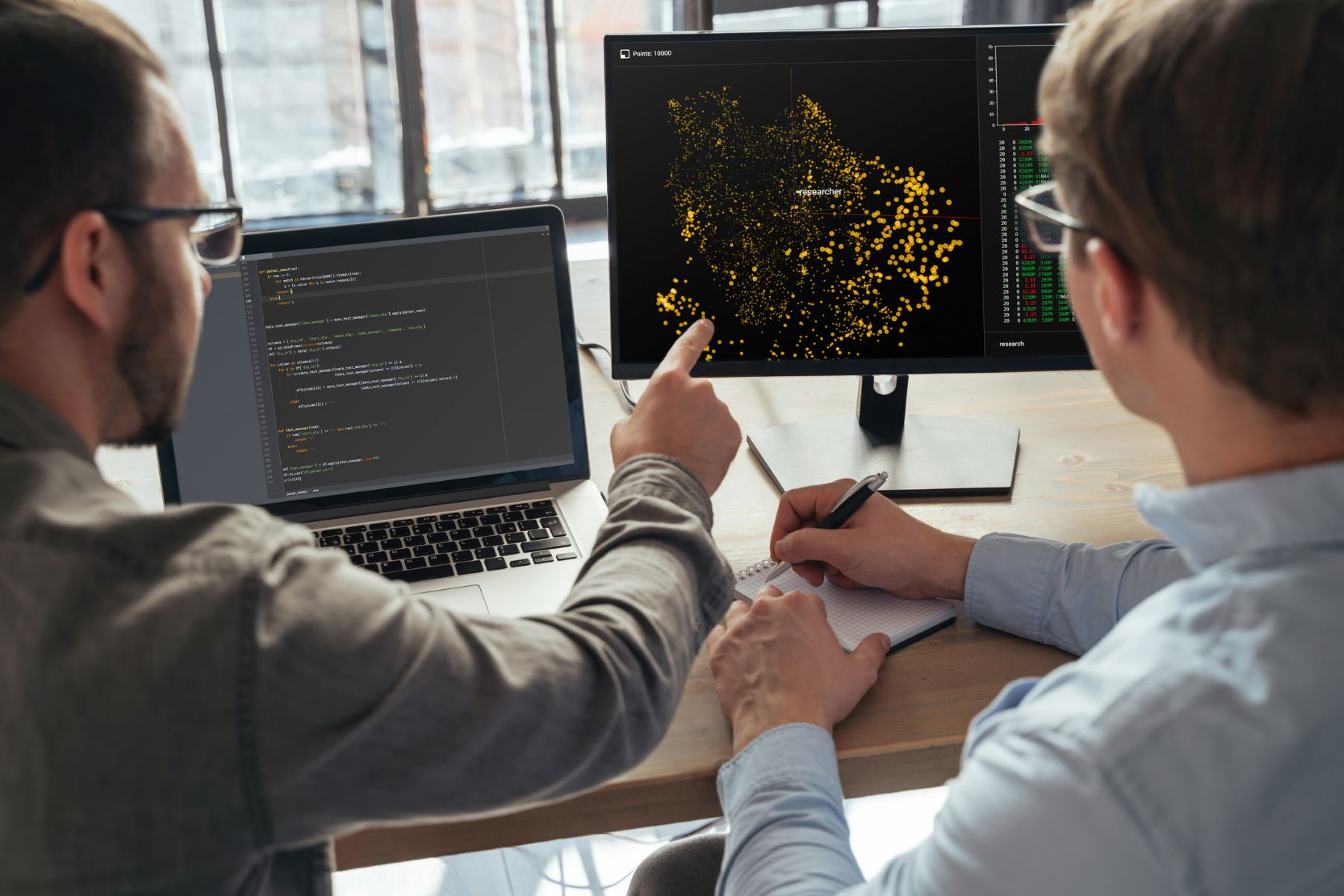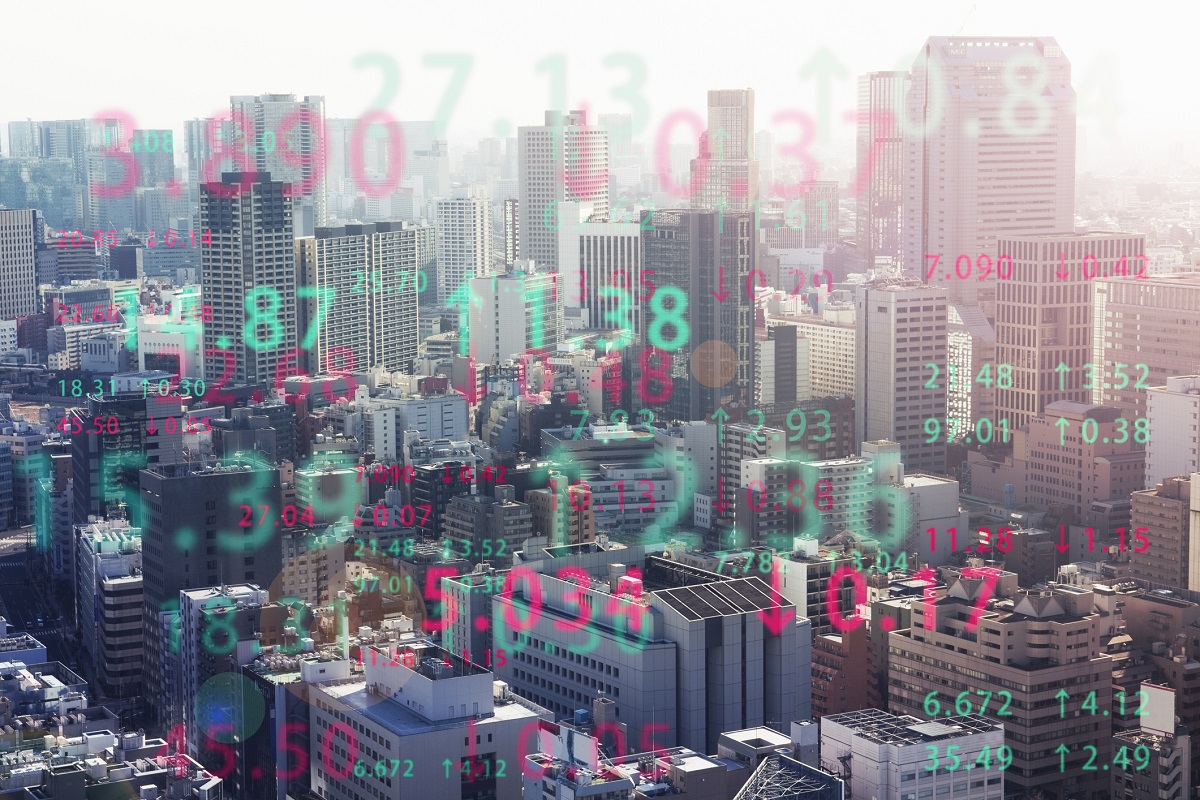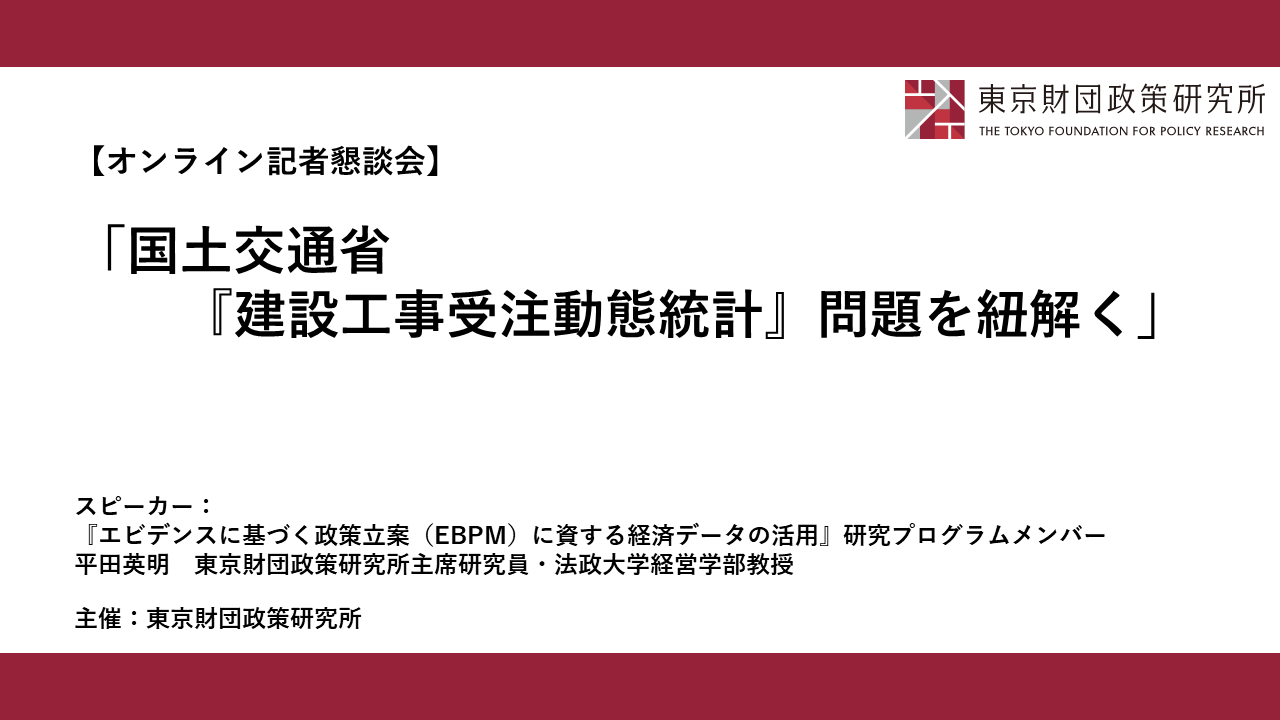R-2022-014
2%目標は、いつ、どこから来たのか
前号、前々号では、「岸田政権のもとでの成長戦略によって経済成長率はどの程度上昇すると見込まれるのか。わからないとすれば、なぜか、何をすべきか」といった問題意識のもと、成長政策がその主たる政策目的である生産性に対して与える効果をきちんと計測できない、その結果、より生産性の高い経済の実現に向けた政策の検証、議論が進みにくい、という我が国の成長政策の課題を論じてきた[1]。
こうした問題意識を持つに至った背景には、「実質2%を上回る成長」といった、この10年間実現されてこなかったにもかかわらず、変わることのない日本の成長目標がある。
3回目となる今号では、こうした問題意識の始まりに立ち返り、そもそも、2%といった成長目標が、いつ、どういった考えのもとで登場したのかを振り返ってみたい。翻って、現在において、我が国の実態に即した相応しい目標と言えるのかを考える。
|
・新しくて古い2%成長という相場観 |
新しくて古い2%成長という相場観
前号では、2022年1月に公表された、我が国の中長期的な経済財政の姿を展望する政府の試算(「中長期の経済財政に関する試算」)の中で、2%目標が「実現可能」と評価されていること、その一方で、目標の実現に向けた具体的な道筋、根拠が見られないことを議論した。
そもそも、現在の様式での試算が最初に登場したのは2002年1月であり、この2002年1月試算は、経済財政諮問会議における成長政策を含む中長期的な経済財政運営(「構造改革と経済財政の中期展望」)の審議のための参考資料として公表された[2]。「構造改革と経済財政の中期展望」以降の取組と2%目標の関係については後に触れていくが、実は、この「構造改革と経済財政の中期展望」は、2001年の中央省庁再編を機に幕を閉じた「経済計画」を引き継ぐものであったという点から話を始めたい[3]。
「経済計画」は、戦後、約半世紀にわたって策定されてきた我が国の中長期の経済政策運営の中心をなすものと言えるが、中長期的な成長目標のルーツを辿るという今号での議論の機会を活かし、まず、この「経済計画」について、簡単に触れてみたい。「経済計画」は、1955年に最初の計画が策定され、1999年に最後の計画が策定されるまでの間に、計14本策定されてきた。いずれの計画も、実現可能な望ましい経済社会の姿に関する展望を明らかにする、そうした経済社会の実現に向けて政府が中長期的に行うべき経済運営の基本方針を定めるとともに重点となる政策目標、政策手段を明らかにする、そして、家計や企業の活動のガイドラインを示すといった、一言で言うと、その時代の国の包括的なビジョンを示す役割を担ってきた。その中には、おそらく最も有名である高度成長期に策定された「国民所得倍増計画」も含まれる。
このように「経済計画」はビジョンを示すものであり、その中では、将来展望と政策目標が掲げられる一方で、展望される経済社会の姿を具体的に描くという観点から将来的な経済成長率の見込みや複数のシナリオに基づくシミュレーション結果が示されることはあれど、現在のように目指すべき目標として成長率が設定されることはなかった。例えば、最後の計画となった「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(1999年7月5日)では、参考として2010年頃までの中長期的な実質成長率が2%程度と展望されることが報告されていたが、それは、計画が描くあるべき経済社会の中で想定される経済成長の姿であった。なお、その成長の姿については、「1%程度の資本の寄与、若干のマイナスの労働の寄与、1%強の技術進歩の寄与の合計で」という想定であった[4]。もちろん、1999年当時のこの2%という将来展望が現在の2%目標に繋がっているわけではないが、その一方で、10年どころか20年以上も前から、2000年代以降の日本経済について、“相場観”として2%といった経済成長率が共有されていたことを示唆しているのかもしれない。
さて、この「経済計画」(正確には、計画を策定してきた経済審議会)については、その役割を終える際に、「経済審議会活動の総括的評価と新しい体制での経済政策運営への期待」(2000年12月)と題し、これまでの活動の評価とともに、その役割を引き継ぐ将来の政策運営に対して、つまり、経済財政諮問会議のもとでの現行の政策運営の在り方について助言を行っている。それを見ると、半世紀にわたり「経済計画」が担ってきたビジョン作りについては、「国民へ強く訴える力をもったビジョンの作成」が必要とあり、「ビジョンの作成側で国民が求めていることを感じ取る努力を行うとともに、ビジョンの受け手が具体的なイメージを描きやすいように、可能な場合には数値等を用いてビジョンの意味するところを表現すること」、「政策目標や目指すべき将来像を実現するための戦略性を持った政策を策定し、それを着実に実行していくことによりビジョンに対する国民の信頼を得ること」といった具体的な提言があった。現行の成長政策では、目標の実現に向けた具体的な道筋、根拠が見られないことを議論してきたが、10年間実現されてこなかった2%目標の実現を目指すのであれば、今こそ、こうした提言を活かすべき時であるかもしれない。岸田政権のもとでの成長政策のビジョンはどの程度国民の信頼を得られていると言えるだろうか。
2%目標の登場:期待されるものから、目指すものへ
期待されるもの
中央省庁再編後の2002年時点に話を戻すと、現行様式での最初の試算を示した「構造改革と経済財政の中期展望」は、「経済計画」の中長期的なビジョン作りという役割を引き継ぐとともに、財政、社会保障に関する持続可能性への懸念が高まる中で、経済財政諮問会議のもと、文字通り経済と財政の整合的な姿を描くという観点から策定されたものであった。加えて、機動的な政策を可能とする観点から短期と中長期の政策運営の一体性が意識される中、その時々の最新の経済状況を反映し、2005年度にかけて毎年度改定が重ねられたが、その中で2%目標が設定されることはなかった。
こうした中、2%成長が次に登場したのは、「構造改革と経済財政の中期展望」を引き継ぎ、2006年度、2007年度に策定された「日本経済の進路と戦略」においてであった。この中では、日本経済を「長い停滞のトンネルをようやく抜け出した」と評価し(もちろん、その後に生じるリーマンショックについては知る由もない)、今後は「負の遺産を取り除くための改革ではなく、新しい可能性を切り拓くための改革」に取り組むといったビジョンが示された。そして、そうした取組により、「今後5年間のうちに2%程度あるいはそれをかなり上回る実質成長率が視野に入ることが期待される」といった見方が示されたのである。
目指すべき目標として設定されたものではないが、期待されるものとして、「2%程度あるいはそれをかなり上回る」と、今を知る我々からみると強気な見方が示されていた。その理由としては2つの点が考えられる。1つは、当時は景気拡張期の最中にあり、そうした中で実現された高い成長率をもとに見込みが立てられたことである。実際、景気拡張期以降の2002年度~2005年度における実質GDP成長率の平均は1.9%(当時)であった。2つ目は、この当時、与党内で繰り広げられた財政再建に向けた政策論争の影響を受けたことである。財政再建に向け増税をも視野に入れる財政再建派に対し、経済成長を頼りに財政再建を実現するとした上げ潮派は、歳出削減に加え、増税ではなく、成長政策と金融政策を組み合わせることで、4%の名目GDP成長率を目指していた。
目指すもの
その後、リーマンショックを受け、こうした政策論争はリセットされ、経済環境の変化を踏まえた次なる議論が行われることとなったが、そうした中で、いつ、2%目標が設定されたのかを見ると、これが、アベノミクス以前の2010年6月試算であった。
2010年当時、リーマンショックからの持ち直し後の経済の中長期的な姿を展望する中で、当時の成長政策を取りまとめた「新成長戦略」(2010年6月18日)において、「2020 年度までの年平均で、名目3%、実質2%を上回る経済成長を目指す」とされた。初めて目指すものとして位置づけられたわけだが、その実現可能性については、「過去10年の低成長等を考慮すれば、これらの目標の達成には困難を伴うと考えられるが、政策努力の目標と位置付け、全力で取り組む」とされていた。2010年6月試算の中では、こうした目標が達成された場合の“シナリオ”として、現在の試算と同様に、全要素生産性(TFP)上昇率に強めの仮定[5]を置く結果、潜在成長率が足もと(2009年度)の0.6%から2020年度には2.3%に増加していく姿が示された[6]。
「実質2%を上回る成長」といった我が国の成長目標は、これ以降、今に至るまで続いているのである。
2%目標を維持する意味
なぜ、目標は2%であったのだろうか。今号の最後に、2%目標が設定された当時の議論を振り返ってみたい。
なぜ、目標は2%だったのか
2010年当時、2%の成長目標は、政策の失敗による低成長と評価した過去(2010年時点において、過去10年間の実質成長率、潜在成長率は1%程度と評価されていた)からの“復活”といった議論のもと、過去10年間の実績値プラス1%として、設定された。
失敗をして1%成長であったのだとすれば、上手く政策を行うことにより2%の成長も可能であると考えたのかもしれない(少なくとも、リーマンショック前に見られたように、高い成長率が実現されていたわけでも、上げ潮派的な議論があったわけでもない)。こうした当時の評価の是非は別として、実際、政府は、当時、政策努力を行わない場合の将来的な潜在成長率として、0.8%程度を見込んでいたのである。
では、2022年時点において、2010年から2020年にかけての潜在成長率の動きを見ると、何がわかるであろうか。2010年当時に期待していたように、政策努力により、この10年間の平均的な成長率は2%を上回ったのであろうか。答えは、既に前々号でも確認したように、否である。
2022年時点で見ると、2011年度から2020年度までの間の(もしくは、コロナ禍以前の2019年度までで見ても)平均的な潜在成長率は、TFP上昇率の低迷を背景に、0.8%程度であった[7]。こうした結果は、2010年当時の評価に従えば、政策努力を怠った結果となるが、前々号で述べた通り、この10年間、様々な分野で生産性の向上に向けた取組が行われてきたわけであり、必ずしも成長政策の失敗を意味するものとは考えていない。むしろ、この結果を素直に見れば、成長政策の効果(政策努力)の賜物として、1%弱程度の潜在成長率が実現された、と解釈するほうが自然であるかもしれない[8]。
こうした点を踏まえると、2010年当時と比較を行うことで、同じ2%目標ではあるが、現在においては、その意味合いが異なることに気づく。すなわち、2010年当時は、政策努力がない場合の潜在成長率を1%程度と評価し、その結果、政策努力により成長率を1%引き上げることで、2%目標を実現すると考えていた。
しかし、実際には、2010年以降の10年間の成長率は、様々な政策努力を行ってきたのにもかかわらず1%の成長にとどまったのである。政策努力を怠ったわけではなく、努力を重ねる中で実現された成長率が1%であったとすると、2%目標の実現のためには、これまでと同等の努力を維持することに加え、さらに、もう1%の成長を生む取組が必要となる。政策努力なくして1%成長が実現される場合(結果を見れば誤った評価であったが)の2%目標と、努力しても1%成長しか実現されない場合の2%目標では、後者の方が、その実現に向けたハードルが高い。
2022年6月に入り、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(2022年6月7日)や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(2022年6月7日)といった岸田政権のもとでの成長政策を含む経済財政運営の基本方針が示された。次号では、2%目標が設定された2010年当時における経済環境の評価や政策的な根拠などに関する議論を振り返りつつ、現在の議論との比較を行うことを通じて、現在において、引き続き、2%といった成長目標を維持する是非を考えてみたい[9]。
(「10年変わることのない日本の成長目標の意味を改めて考える(4)」に続く)
[1]過去、生産性が十分に上昇してこなかった背景・理由を定量的な根拠をもとに評価・分析することができない、また、将来についても、成長政策の効果を見積もることができない、といった成長政策の課題、難しさについては、前号までの議論を参照されたい。
[2]内閣府からこれまで公表されてきた全ての試算については、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」に関するウェブページで見ることができる。
[3]前川(2022)では、「経済計画」の終焉について、「1955年の「経済自立五ヶ年計画」から14本の経済計画が作られ、日本の戦後復興、高度経済成長、石油危機後の安定成長等に大きな役割を果たしたが、東西冷戦の終結等の世界情勢の大きな変化を背景に、市場と競争の力の強まりや、経済の主体としての民間の役割の強まり等から、経済計画という政策手法は役割を終えたという認識が高まり、2001年の中央省庁改革とともに、経済計画は策定されないことになった」と議論されている。
前川守, 2022. 経済財政諮問会議の理念と歩み:司令塔としての経済財政諮問会議(1). 内閣府経済社会総合研究所『Economic & Social Research』No.36 2022年春号, 11-14.
[4]参考までに、2010年度の潜在成長率の実績値を見ると、0%近傍であり、資本の寄与が▲0.2%、労働の寄与が▲0.5%、全要素生産性(TFP: Total Factor Productivity)の寄与が0.8%となっている。
[5]具体的には、2009年度の0.3%程度から2020年度にかけて1.9%程度まで上昇と、10年間に1.6%程度の増加を仮定。参考までに、2022年1月試算を見ると、2020年度の0.4%程度から2025年度にかけて1.3%程度まで上昇と、5年間に0.9%程度の増加と仮定されている。
[6]なお、2010年6月試算では、別のシナリオとして、経済成長を慎重な前提のもとに試算するシナリオ(2020年度の潜在成長率が1.0%程度)を設け、財政状況の評価には、この慎重シナリオがメインシナリオとして用いられていた。財政状況の評価はより慎重(prudent)に行うもの、といった当時の政策スタンスが窺える。
[7]実質GDP成長率を見ても、2011年度から2019年度までの間の平均的な成長率は0.8%程度となっている。
[8]繰り返しになるが、成長政策の課題は、こうした成長政策の効果(政策努力)をきちんと計測できず、TFPの低迷を背景に潜在成長率が上昇していないことが、実態として生産性が上昇していないことを表わしているのかといった基本的な問いへの答えすら判然としない中、政策の検証、議論が進みにくいことにある。例えば、同じ2009年度の潜在成長率について見ると、2010年6月試算では0.6%、2022年1月試算では▲0.1%となっている。この10年の間に、推計に用いる基礎統計の改定や推計手法の変更等により、両者ともに実績値であるにもかかわらず大きく改定されていることを見ても、その計測に困難が伴われることがわかる。
[9]2%目標について、いわゆる「骨太の方針2022」では、「骨太の方針2021」で記載されていた「デフレ脱却・経済再生に取り組み、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長、600兆円経済の早期実現を目指す」といった記述が見られない。こうした点についても、意味があるのであればその真意を読み解いていきたい。