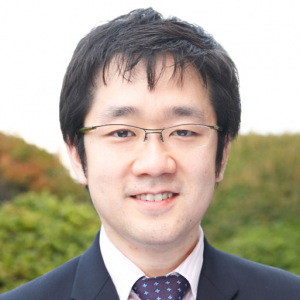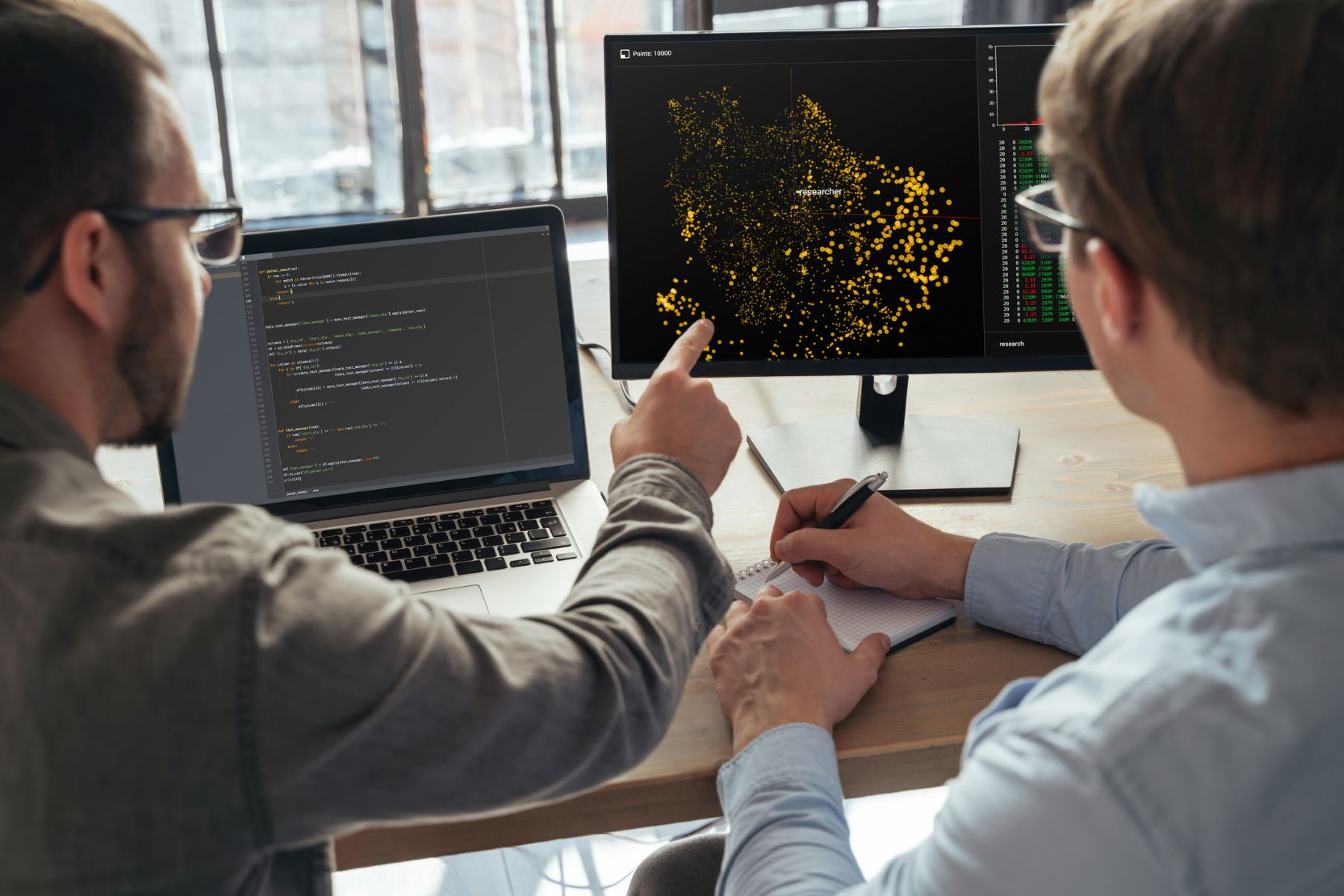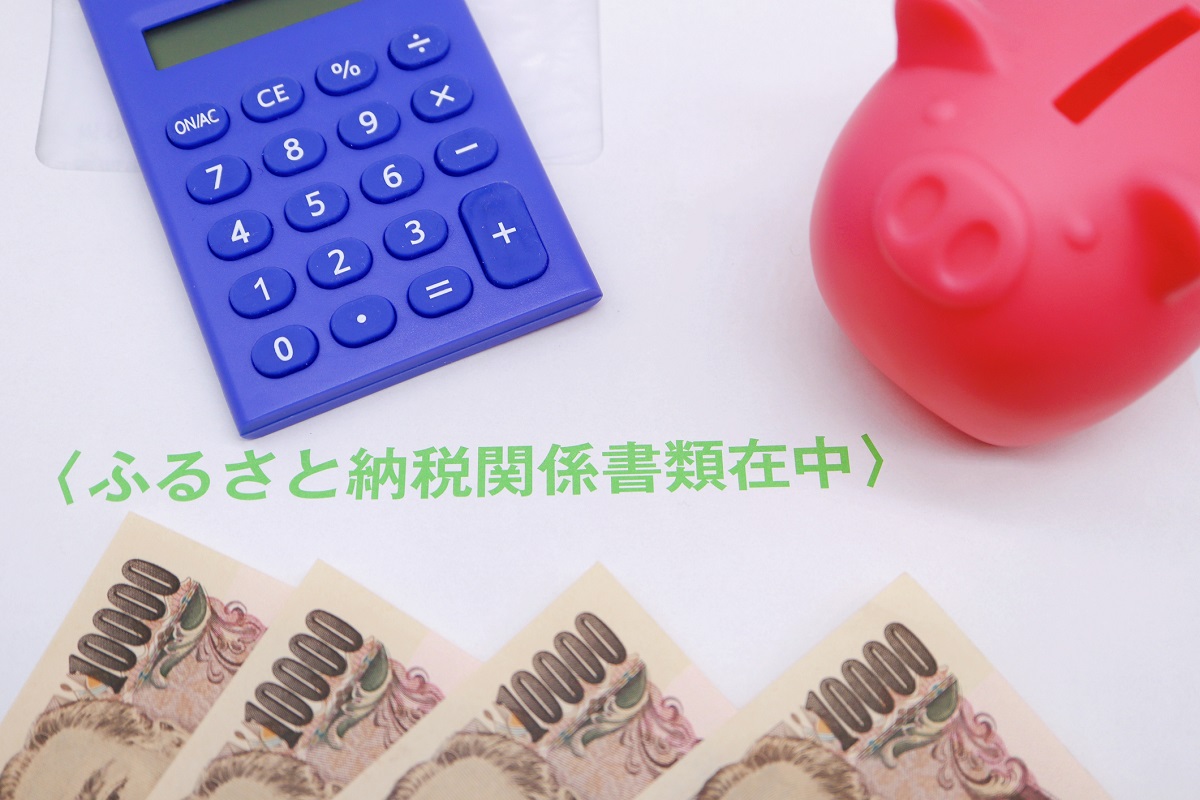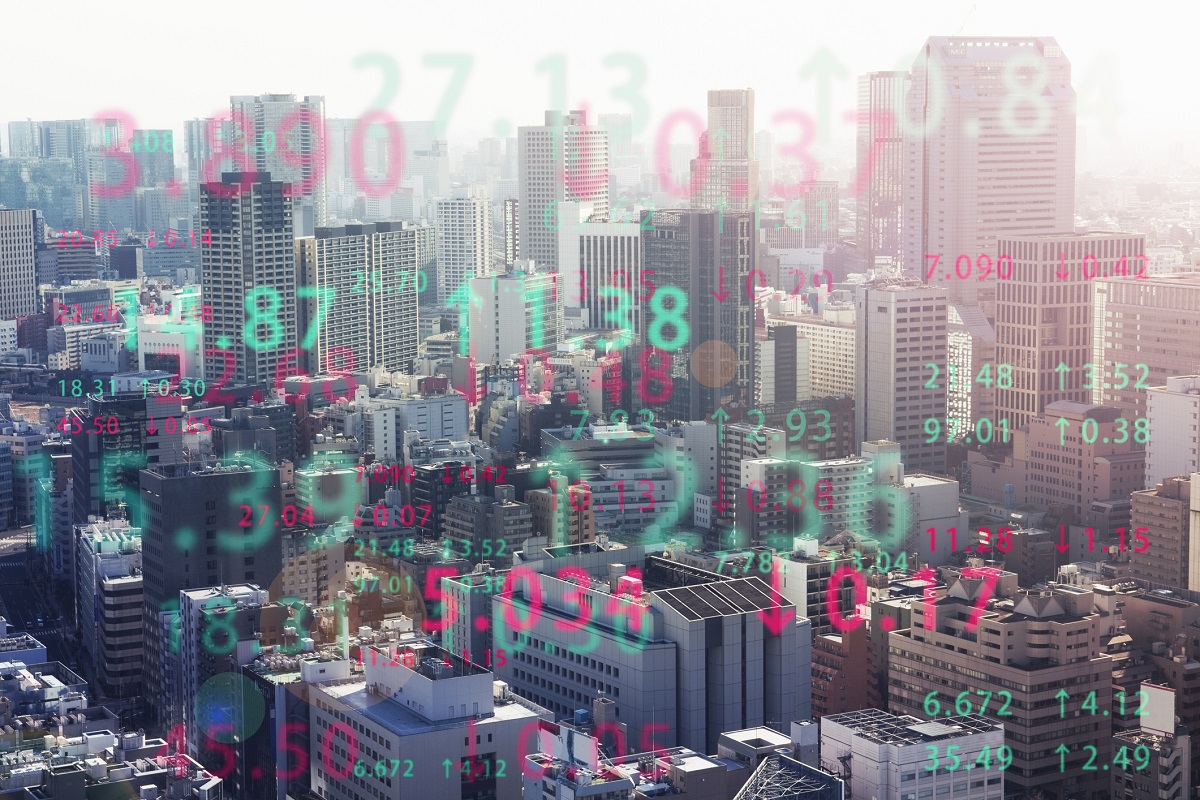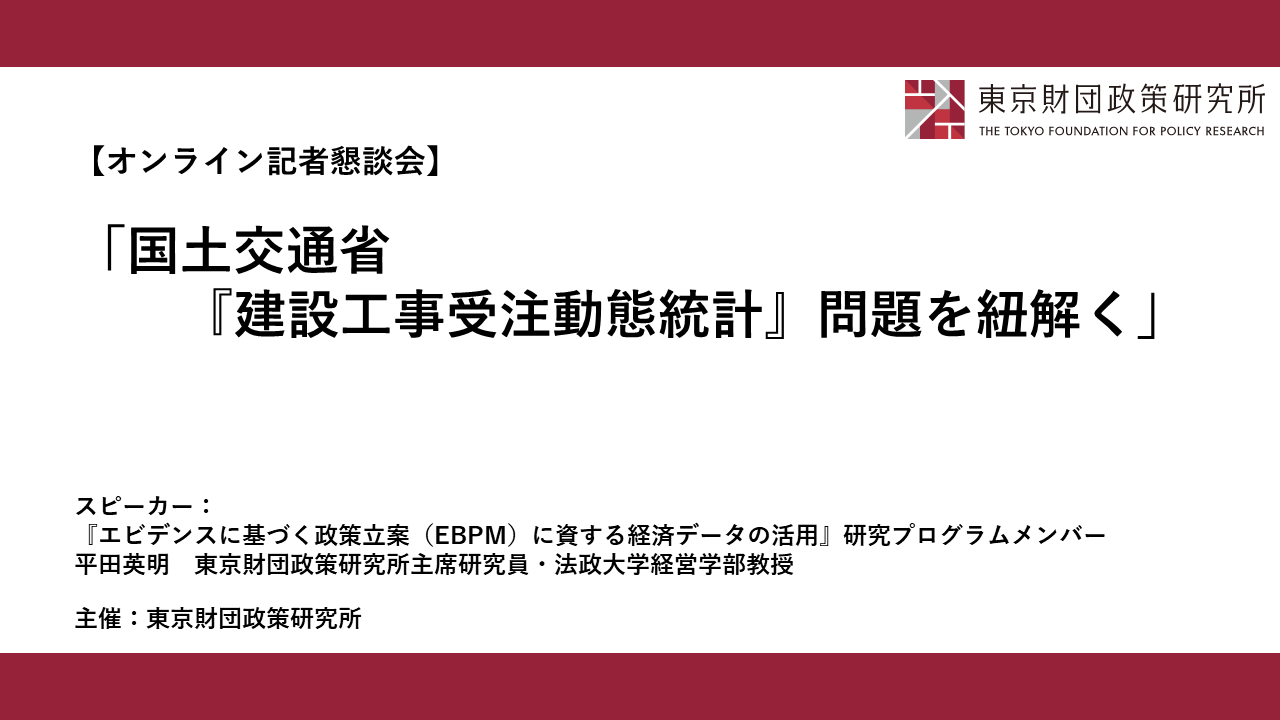R-2024-107
本稿は、東京財団政策研究所にて複数の自治体にご参加いただいた第2回ふるさと納税意見交換会(2024年12月20日)での知見を踏まえた内容となっている。記して感謝したい。
|
1.はじめに |
1.はじめに
2024年12月、例年どおり、ふるさと納税の広告がテレビやインターネット上に溢れた。ふるさと納税の市場規模は、2023年には1.1兆円を超える規模となり、引き続き2桁の成長が続いている。このモメンタムを考慮すれば、広告が大量に打たれるのは当たり前なのかもしれない。その原資がもとはといえば税金であったとしても。
ふるさと納税はすべてのプレイヤーにとって経済余剰が増える(≓すべてのプレイヤーが得をする)仕組みではなく、勝者と敗者が必ず存在する「ゲーム」となっている。そして、このゲームは毎年のようにルールが少しずつ変わり、敗者が翌年には少しでも勝者に追いつけるように、そして勝者は勝者としての地位を少しでも確固たるものにするように努力をし続ける必要がある。このゲームが厄介なのは、不参加のつもりが結局は強制的に参加させられていて、その場合は自動的に敗者になってしまう点だ。結果的に、ゲームに与するしかなくなり、囚人のジレンマに陥ってしまう仕組みとなっている。これは、地域間競争が底辺への競争に繋がる典型的な一例といえる。
さて、2025年は3つの理由からゲームを取り巻く環境が大きく変わり得る年となりそうだ[1]。第一の理由は、隠れ返礼品とも呼ばれる仲介サイトによるポイント付与が本年10月以降に廃止されるルール変更である。第二の理由は、いわゆる「103万円の壁」問題に関係するものである。第三の理由は、2024年末にふるさと納税の市場に参入したアマゾンの存在である。
本稿では、第一の理由を中心に今後のふるさと納税の動向について展望し、第三の理由については次稿以降で触れていく[2]。
2.ゲームに巻き込まれる住民税争奪戦のプレイヤーにとっての経済効果
前述のとおり、ふるさと納税には経済面での勝者と敗者が存在する。そして、期せずしてゲームに参加させられる。どういう意味か、プレイヤー別に見ていこう。
納税者(家計)
家計について考えてみると、ゲームの参加者、つまりふるさと納税(の寄付)を行う納税者(以下、寄付者)の場合、返礼品を獲得することができ、行わない納税者は返礼品を獲得できない。そして行うにせよ、行わないにせよ、居住する自治体から流出した住民税分だけ地元の自治体からの行政サービスは受けられなくなる[3]、[4] 。
つまり、寄付者は、返礼品というメリットと行政サービスを失うデメリットの差分を手にする。実際にこの差分が正か負かの計算は容易ではないが、毎年、ふるさと納税を行う人数が増えているという事実は、これが正だと認識するケースが多いことを示唆する。
そして、ふるさと納税の増加は「当該自治体の会費」とも呼ばれる住民税の減少に直結するため、ふるさと納税に与せず、住民税をフルに払っている納税者もゲームに巻き込まれてデメリットだけを享受させられる[5]。そして、翌年以降はゲームに参加する納税者が増加していくことになる。
自治体(市区町村や都道府県)
自治体について考えてみると、ふるさと納税の寄付が多く流入すればするほど自治体は潤う(勝者)。そして、流出すれば流出するほど財政的に厳しい状況に追い込まれる(敗者)。この場合も、動学的に考えると、ゲームに参加して少しでも流入額を増やそうとする自治体は年々増加していくと考えられる[6]。
敗者の典型例は、ふるさと納税の趣旨に鑑みて、返礼品付きのふるさと納税の流入を自粛している東京都や東京23区の1つである練馬区のような自治体である[7]。彼らは、いわばガードをせずにひたすらパンチを打ち込まれるボクサーのように、流入はゼロでひたすら流出のみに直面する[8]。しかし、特にこの数年、川崎市や世田谷区や新宿区のような都市部の自治体も、毎年の流出増に耐えかねて流入を増やす方向に致し方なく舵を取り始めるケース、つまりゲームに本格参入するケースも増えている。
ふるさと納税の場合、本来は住民税であった部分が寄付に回ったとしても、実際には各種の経費を除くと自治体の歳入は約半分になるという点が問題とされてきた。しかし、2019年にふるさと納税の経費上限を納税額の半分とするルール(いわゆる5割ルール)が導入された。2023年10月以降にさらにルールが厳格化したこともあり、もはや半分が溶け出すことを所与として、各自治体が行動をするようになっている。つまり、とにかく寄付総額を増やせば、結果的に自治体に入るお金も増えるという考え方が定着してきており、わが国の大半の自治体が住民税の争奪戦に巻き込まれる構図となっている[9]。
仲介サイト
仲介サイトビジネスは、デジタル・プラットフォーマーと呼ばれるビジネスの一種である。これは、返礼品について、需要側である寄付者と供給側である自治体をマッチングする仕組みであり、現在、数十の仲介サイトがあるとみられる[10]。サイト構築等について大きな初期費用を要するが、顧客を取り込めれば、毎年のふるさと納税を通じて、長期的に利益を生み出すことができる。ただし、仲介サイトは市場への参入と退出(つまり、撤退)がかなり活発な競争の厳しい世界であり、ここにも勝者と敗者が存在する。
仲介サイトビジネスに限定して考えてみると、納税者や自治体のように期せずしてゲームに参加させられるといったメカニズムはない。しかし、ポイント経済圏の一部としての仲介サイトビジネスという観点で考えると、ふるさと納税を通じて自社のポイント経済圏に家計を取り込みたい企業にとっては、1,000万人の利用者が存在する同市場に参入しないわけにはいかないという側面がある。
ふるさと納税のマクロ経済効果
以上のとおり、ふるさと納税によって、多くの経済主体が直接・間接にその影響を受ける[11]。その中で、マクロ経済的な効果を考える場合、各種の研究では産業連関表を使いながら、生産誘発や雇用誘発効果を推計するケースが多く、1~4兆円程度の経済効果があると報告されている[12]、[13]。
分析手法そのものは定石どおりのものであり、その点に異を唱えるつもりはない。しかし、筆者は、これらの推計が仮定している状況が現実を十分に反映したものではないことから、経済効果を過大評価していると考えている。そもそも、どんなにふるさと納税の寄付総額が増えたところで、日本における税収が増えるわけではなく、住民税が国内自治体間で行き来するだけである。そこから、返礼品に関連して、公共事業のようなかたちで民間部門(返礼品の生産、仲介サイトビジネス、運送等々)に半分程の資金が流れるため、これらの返礼品関連のビジネス活動を通じた経済効果はたしかに生まれる。先行研究もここから生じる経済効果を推計している。だが、人気の返礼品と呼ばれる米やトイレットペーパーを返礼品として受け取った家計が、従来どおりにそれらを消費し続けるとは考えにくい。つまり、ふるさと納税の返礼品の多くは食品等の生活必需品であり、家計はその分の消費を減らす代替が生じるケースが多いと考えるのが自然であろう。すると、効果はかなりの程度、相殺されるはずである[14]。
3.仲介サイトによるポイント規制の意味するところ
経済学者的な視点からは、経済政策としてのふるさと納税によるマクロ的なインパクトに関心がいく。しかし、当事者である自治体からすれば、ミクロ的なインパクト、すなわち自分の自治体にどれだけふるさと納税を呼び込めるか、について関心が集中する。この鍵になるのが返礼率である。そして、ポイントは形を変えた返礼品という性格を有する。以下では、時系列で経緯を確認してみよう(表1参照)。
表1 ふるさと納税に関する主な規制と規模
| 2015年 |
控除上限(所得税及び個人住民税から全額控除されるふるさと納税額の年間上限)の二倍化、ワンストップ特例の導入 |
0.17兆円 |
| 2017年 |
返礼率を3割以下とすることを総務省が自治体に要請(4月) |
0.36兆円 |
| 2018年 |
総務大臣による返礼率等に関する規制の表明(9月) |
0.51兆円 |
| 2019年 |
3割ルール、旧5割ルール、地場産品ルールの導入(6月) |
0.49兆円 |
| 2023年 |
5割ルール厳格化の発表(6月) 厳格化した5割ルールの導入(10月) |
1.12兆円 |
| 2024年 |
2025年10月以降のポイント付与禁止の発表(6月) |
- |
| 2025年 |
ポイント付与禁止(10月) |
- |
資料:総務省自治税務局市町村税課(2024)「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)」
注:規模は地方自治体が個人から受領したふるさと納税の寄附金。
ふるさと納税は、「地方団体が地域の実情に即した行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うもの(総務省による「地方税の原則」より引用)」という住民税の基本を敢えて満たさない仕組みとして導入されている。しかし、返礼率=0、すなわち返礼品のない時代のふるさと納税は非常に低調であった。無論、仲介サイトも彼らの発行するポイントも存在しなかった。
ふるさと納税拡大の起爆剤となったのは返礼品であり、寄付に占める返礼品の価値、すなわち返礼率が注目を集めるようになった。それとともに仲介サイトビジネスも始まった。2010年代前半には返礼率に関するルールがなく、各自治体が返礼率を上げる競争を繰り広げた中で、地方税財政を司る総務省から自治体に対して2019年に返礼率を3割以下とする厳格なルール(3割ルール)が設定された。このルールにより、各自治体の設定する返礼率は3割になると見込まれ、これで自治体間の返礼率に関するイコール・フッティングが実現すると思われた。
しかし、自治体からすれば返礼率を高くして寄付額を増やせるのであれば、それに越したことはない。仲介サイトも少しでも自分のサイトを通じたふるさと納税を呼び込みたい。この思惑の一致は、自治体の返礼品に加えて、仲介サイトが(換金性の高い)ポイントを寄付者に付与することで、実質的に3割を超える返礼率を実現することにつながった。仲介サイトの収入は基本的に自治体からの手数料に拠るため、仲介サイトの付与するポイントは、形を変えた返礼品と見なせる。仲介サイトは民間企業であるため、総務省の規制の対象とはならないことを見透かした戦略だったとみることもできる。
3割ルールと同時に設定されたのが、ふるさと納税の経費上限を納税額の半分とする5割ルールであったが、ルールの抜け穴を突いて、実際には多くの自治体が5割を超える経費を計上していた(平田, 2024)。物価が上昇する中で、この手法は返礼率3割を維持していくための裏技的な役割を果たしていた面もあるとみられる。問題視した総務省は2023年10月から厳格化した新5割ルールを導入した[15]。
経費には、自治体から仲介サイトに支払われる代金も含まれ、新5割ルールは総務省から仲介サイトへの間接的なコスト削減要求的な意味合いがあったと考えられる。しかし、実際には仲介サイトが自治体に要求する経費を引き下げたといった話は聞かれなかった。これは、プラットフォーマーとしての市場支配力・交渉力を(特に大手の)仲介サイトが有するためである。
このような中で、2024年6月に総務省から仲介サイトによるふるさと納税の寄付者へのポイント付与を2025年10月から認めない旨の新ルールが示された(より正確には、ポイントを付与する仲介サイトを自治体が利用することを総務省は認めない、とした)。これにより、5年越しでようやく真の意味での3割ルールが実現するとみられている。
4.ポイント規制は何をもたらすのか
一部の報道等では、総務省によるポイント規制によって、ふるさと納税が大きく減るとの懸念が示されている。しかし、ふるさと納税の成長率の鈍化はあれども、成長がマイナスに転じる可能性は極めて低いと考えられる。なぜならば、ふるさと納税は引き続き寄付金控除の対象であり、3割ルールに基づく返礼品が得られるという寄付者にとってのメリットは不変なためである。
J.D. パワー社による2023年の仲介サイト利用者調査によると、寄付者に選択される仲介サイトについていくつかの興味深い特徴がみえてくる。第一に、前年の満足度が高いと、寄付者は同じ仲介サイトを通じて同じ返礼品を再び選びやすい。第二に、寄付者はポイントのプログラムが魅力的な仲介サイトを利用したがる。第三に、手間の煩雑化を避けるために、寄付者は単一の仲介サイトを継続して使いたいと考えており、返礼品を幅広く掲載しているサイトを選好する。整理すると、魅力的な返礼品を取り揃え、ポイントを多く出す仲介サイトは寄付者にリピートされやすい。
このような寄付者の意識を踏まえると、本年10月以降、仲介サイトによるポイント付与がなくなることにより、各サイトがこれまでロックインしてきた寄付者の流動化が進む可能性がある[16]。有り体にいえば、ポイントの切れ目が縁の切れ目となり、他仲介サイトへの乗り換えが生じるかもしれない。そして、これまで以上に、魅力的な返礼品を擁する自治体から事業を引き受け、寄付者を引きつける返礼品を提供していくことが仲介サイトの生き残りの鍵となってく。
5.まとめにかえて
(ポイント経済圏の一部としてではなく、ふるさと納税のビジネスに限って考えてみると、)仲介サイトの利益の源泉は住民税、つまり自治体の歳入である。では、本年10月以降、仲介サイトから要求される経費が下がり、自治体が手にできる歳入は増えるのだろうか。
確かにポイント付与分の経費を仲介サイトが要求しないならば、そうなるだろう。しかし、そのようなシナリオは楽観的すぎるかもしれない。ポイントレスの時代になると、これまでのロックイン効果を除けば、サイトの返礼品の品揃えや使いやすさといった非価格的な要因によって、仲介サイト間の差別化が行われることになるだろう。すると、これらの要因に強みを持つ集客力の高い大手仲介サイトへの選択と集中が進む可能性が高い。これに対し、中堅中小の仲介サイトは手数料を下げて自治体との契約を維持しようとするかもしれない。しかし、前述のとおり(特に大手仲介サイトの)プラットフォーマーとしての市場支配力・交渉力を踏まえると、単純に手数料が下がるかどうかは不透明である[17]。ただし、昨年末に新規参入をしたアマゾンのビジネスモデルはこの構造に風穴を開ける可能性がある(詳しくは次稿で論じる)。
いずれにしても、本年9月末までは、各仲介サイト間の激しいポイント合戦が繰り広げられるだろう。そのため、9月末にかけて、駆け込み的な需要が生じることは必定とみてよい。
ところで、ポイント禁止によるふるさと納税の市場規模低下の可能性は低いと上述したが、ふるさと納税の規模を確実に押し下げる要因について最後に触れておきたい。それは、冒頭で指摘したふるさと納税というゲームを取り巻く環境が大きく変わり得る2つ目の理由として取り上げた政策変更、すなわち国民の関心も高い「103万円の壁」の見直しに伴う基礎控除の引き上げである。現状では、どのような形で決着するかがわからず、はっきりとしたことはいえないが、標準的なサラリーマン層の1人当たりの寄付額上限は、数千円~数万円下がると見込まれる[18]。
寄付額上限の押し下げの理由は以下のとおりである。所得控除の1つである基礎控除の引き上げが実現すると、課税所得(=課税対象となる所得=収入-必要経費-所得控除)が減る。税率が不変であれば、課税所得の減少に伴い減税となる。一方、ふるさと納税は寄付の一種として控除の対象となるものの、控除対象となる寄付額には、課税所得に応じた上限が設定されている。このため、基礎控除↑→課税所得↓→ふるさと納税の寄付額上限↓となり、昨年よりもふるさと納税をできる上限が下がることになる[19]。
[1] これまでの大きな転換期としては、表1の通り、大きな制度変更があった2015年、2019年が挙げられる。
[2] 本稿の内容は、ふるさと納税の仕組みについての基本的な内容を所与としたものである。基本的な部分については、拙著東京財団政策研究所Review「歪み続けるふるさと納税(1)制度の変遷と生じた問題」、「歪み続けるふるさと納税(2)民間事業者の功罪」、「歪み続けるふるさと納税(3)ふるさと納税の資金フローと都市部自治体の苦悩」を参照されたい。なお、第二の理由については、本稿の最後で少し触れる。
[3] ただし、地方交付税交付金を交付される自治体は流出分の75%が国より補填される(不交付団体は一切補填されない)。地方交付税交付金の原資は所得税や法人税などの国税である。ふるさと納税の規模が増えるにつれて交付金は増えていくため、国税を通じて家計や企業がそれを負担していることになる。
[4] 結果的に、ふるさと納税をした者も敗者になるという可能性もある。
[5] ふるさと納税の事務手続きの手間を考えて不参加の場合は、単純に損をしているともいえない。
[6] 流入については自治体の努力次第で増やすこともできるが、流出についてはいくら自治体が努力しても防ぐことは難しいという非対称性がある。
[7] 練馬区は、2024年度の予算編成で、区民のふるさと納税による住民税の50億円を上回る流出故の財源不足を補うために、積み立ててきた基金を取り崩す必要性が生じている旨を公表している(札内僚「「ふるさと納税は廃止すべき」前川燿男・東京都練馬区長」『日経グローカル』2024年9月16日)。今後、このような動きが都市部自治体で増えることが懸念されている。
[8] 企業版のふるさと納税では、東京都、東京23区、川崎市などは、寄付を受け入れることが認められていない。
[9] その証拠に、各自治体のふるさと納税担当の部署では、寄付の受け入れ目標額が明示されることが一般化している。
[10] 仲介サイトは、いずれも民間企業であり、自治体と契約を結んでビジネスを行う。大手4社と呼ばれるさとふる、ふるさとチョイス、ふるなび、楽天ふるさと納税のシェアは9割を超えるといわれる(柴田秀並「「じつは…」アマゾンのふるさと納税、自治体が明かす寄付者メリット」『朝日新聞』2024年12月19日)。
[11] ふるさと納税には、寄付者が税金の使途を指定できたり、地方の特産品を知る機会を得られたり、といった特徴もある。
[12] 例えば、株式会社ふるさと納税総合研究所「2023年度ふるさと納税の経済効果」2024年11月2日、同「令和4年度ふるさと納税の経済効果」2023年10月18日、参照。
[13] 地域経済への効果を検証した小川光・田村なつみ・深澤映司(2024)「ふるさと納税の受入れが地域経済に及ぼす影響―影響の非線型性に着目した実証分析―」CREI Working Paper No. 25によると、少なくとも個人の課税所得と個人住民税(所得割)の税収については、ふるさと納税依存度が大きい自治体ほど、ふるさと納税の純受入額(受入額-流出額)が増えるほど、個人の課税所得と個人住民税(所得割)の税収の増加するものの、増加のインパクトは逓減するという。
[14] 近年のふるさと納税の増加は高所得層よりも中所得層で伸びており、インフレ下では返礼品として生活必需品の需要が強い傾向が観察されている。
[15] 折からの物価上昇傾向に伴う諸経費の増加を踏まえて本ルールを満たすため、自治体が返礼率を3割未満に設定するケースも増えている。
[16] 実際、仲介サイト間のポイント還元の消耗戦となっていた側面もあるため、ポイント禁止に対して、好意的な評価を示している仲介サイトも少なくない。
[17] 仮に経費を下げたとしても、自治体が返礼率を上限の3割にするかもしれない。返礼率を上げることで失う分を、寄付額の増加分で相殺できるのであれば、自治体としては合理的な判断といえる。
[18] 全額控除されることにこだわらなければ、上限を超えた寄付は妨げられるものではない。
[19] ふるさと納税の寄付金控除額は、所得税と住民税から行われる(確定申告の場合)。住民税については基本分と特例分に区分される。控除上限は、所得税については総所得金額等の40%、住民税(基本分)については総所得金額等の30%、住民税(特例分)については住民税所得割額(=多くの人にとっては、課税対象所得の10%)の20%となっている。