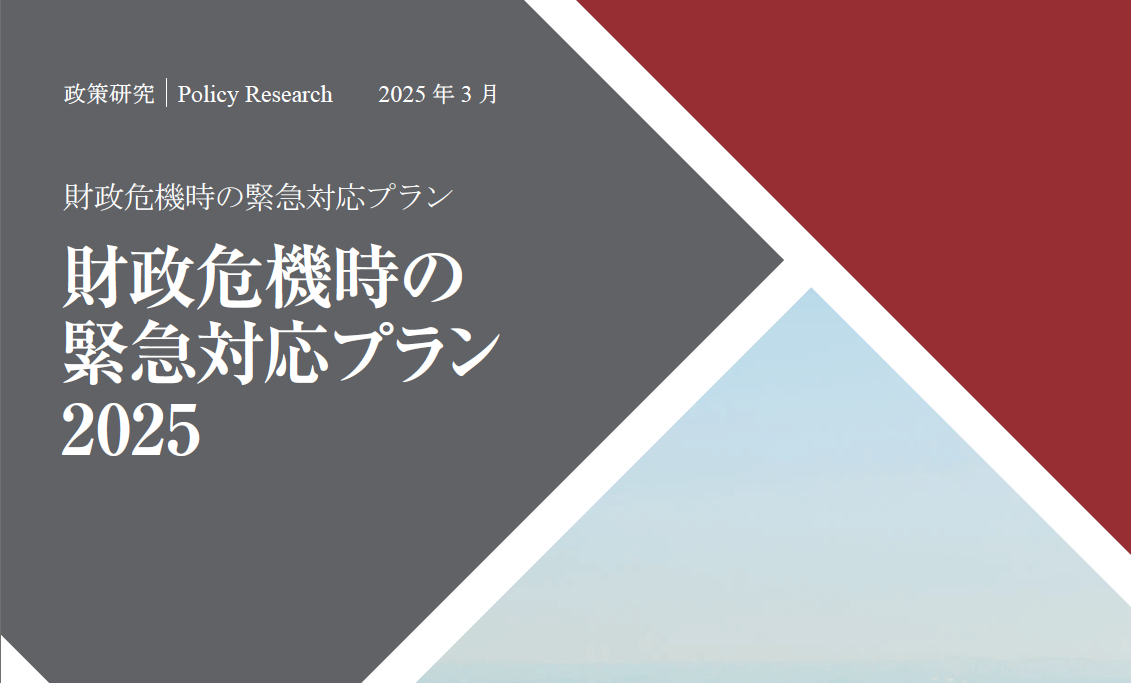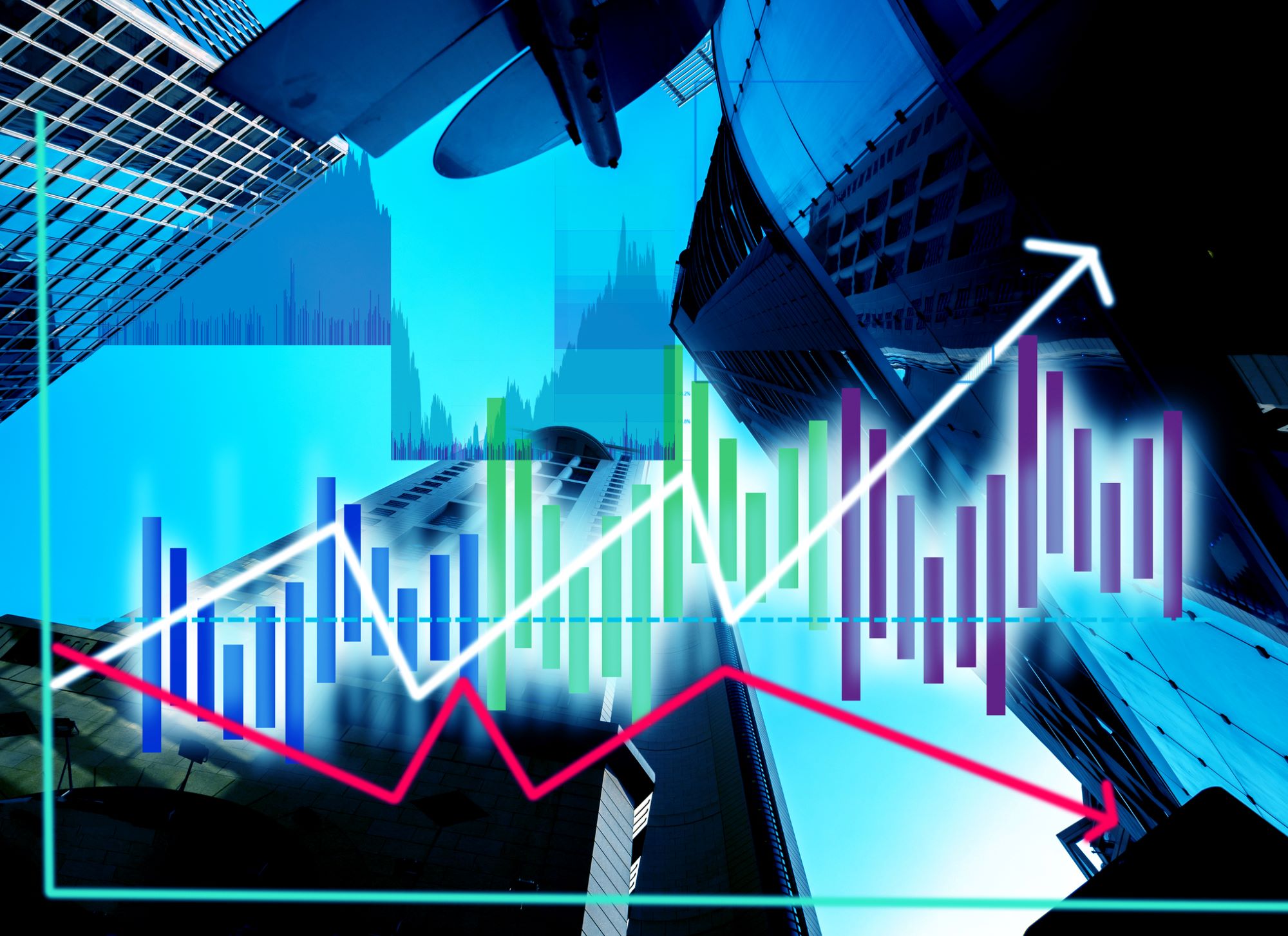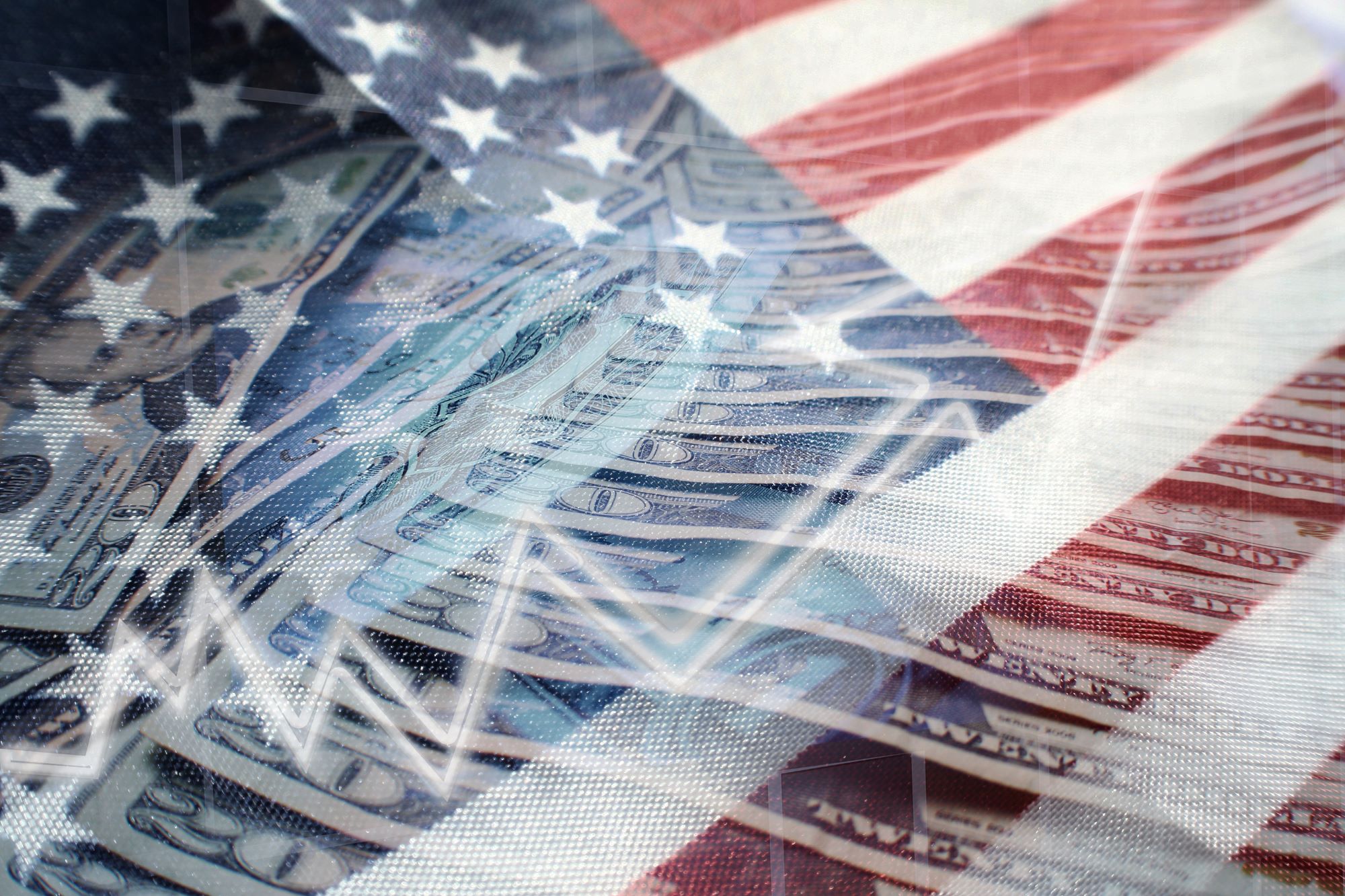- Review
【特集】新政権に期待すること―議員定数削減:実施するならば、社会構造と国民意識に整合的な選挙制度改革を
November 20, 2025
2025年10月21日に開催された第219回臨時国会で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されました。新政権の発足に寄せて、東京財団の政策プロデューサーと常勤研究員が、「これから期待すること」について各専門分野から論じます。
1.はじめに
2025年10月の自由民主党(以下、自民党)総裁選後に公明党が連立政権を離脱し、新たに日本維新の会(以下、維新)が閣外協力の形で高市早苗政権に加わった。閣外協力の条件の「目玉」となったのは、議員定数の1割削減である。
内外の重要な政策課題が山積する中、定数削減問題が国民にとっての喫緊な課題だとは思えないが、政党や議員にとっては一大事である。連立政権合意書にも明記された以上、臨時国会や来年の通常国会での最大の焦点の一つとなり、膨大な政治エネルギーが注がれることになろう。議員定数削減の問題は、高市政権の高支持率で噂される早期解散の誘因にも制約にもなりうるため、今後の政治・経済動向にも大きな影響を与える。
なお、議員定数削減自体に反対する動きは、日本共産党、れいわ新撰組など一部に留まる。立憲民主党や国民民主党は過去に定数削減を主張していた。公明党も定数削減自体には理解を示している。各種世論調査でも有権者の多くは定数削減を支持している。そのため、問題の焦点は、定数削減のための手続のあり方と、定数削減の内容—とりわけ小選挙区と比例区との比率をどうするか—である。
2.手続面の問題
手続については、議員の定数削減など選挙制度関連の法案を、通常の議決ルールで決めて良いのかという問題がある。通常の法律改正と同じ扱いなのであれば、衆参で過半数を握った政権与党は、公職選挙法改正を通じて、自らに有利な選挙制度に転換させることが法律上は可能だ。小選挙区比例代表並立制を採る日本の例で言えば、相対的に小選挙区に強い政党が、小選挙区比率を大幅に引き上げることなどである。
ただし、これは過半数を握る政党にとって利益相反的な状況であり、法的には許されても、手続的な正統性には疑問が生じうる。そのため他国では、選挙制度改革に際して、ニュージーランドのように通常の法案より厳しい要件を課したり、国民投票や与野党間の合意を慣例的に求める場合もある。また、多くの国では憲法が選挙制度の主要部分を規定しており、その改革には(法律改正より通常は厳格な)憲法改正の手続が必要となる。
高市首相も11月4日の所信表明演説で、議員定数削減については各党各会派の幅広い合意が必要であると述べている。これは、手続面で通常の法案とは異なる配慮が必要であるとの認識を示したものと言えよう。また、自民党や維新の議員を含む超党派議員連盟は、三権分立の観点からも、議員定数削減については衆議院議長の下の「選挙制度に関する協議会」で議論を進めるよう衆議院議長に申し入れた。他方、維新の藤田文武共同代表は、定数削減は自民・維新の両党の合意だけで実現できるとし、それが潰されたら解散すればいいと述べている[1]。
3.内容面の問題
議員定数削減問題は、政党・議員にとっては死活問題ともなるため、膨大な政治エネルギーの投入が必要となる。新政権の優先的な政策課題とすべきかには大いに疑問は残るが、自民・維新の連立合意を実現するために不可避であるならば、この際、内容面での徹底した検討を求めたい。小選挙区・比例区の比重変化にまで踏み込んだ議員定数削減は、今後の日本政治のあり方に大きな影響を及ぼしうるからだ。
現行制度導入時の反省
現行の小選挙区と比例選挙区を併用した小選挙区比例代表並立制は、1994年の政治改革関連法案により採用された。並立型の選挙制度は世界的にもよく見られるが、日本の場合は、小選挙区制の比重が非常に大きいことが特徴的である[2]。
この選挙制度改革は、その後の日本政治やそれによって象られる日本経済・社会に大きな影響を与えてきた。ただ、自民党の総裁として選挙制度改革の与野党合意を取りまとめた河野洋平氏が「当時の想定と大変な差があった」と述べるなど[3]、改革時の目的が実現しているかについて、さらには改革時の目的自体についての批判的な見方は多い。
当時の政策論争を顧みると、小選挙区制の導入こそが「政治とカネ」の問題の抜本解決となる、政策本位の政党間競争を実現させる、など、いわば「小選挙区制バラ色論」が席巻していた。有力政治家、そのブレーンとされる政治学者や経済学者の一部、さらにメディアや財界人などがそうした過度に単純化された「バラ色論」を主導していた。他方で、政治の現場からの草の根の声の採り入れ、エビデンスに基づく分析、各国の最新状況を踏まえた先端的な知見の活用など、地道な検討は不足していた。
今回、小選挙区と比例区との比重の大幅な改変が行われるとすれば、1994年に導入された現行選挙制度の初めての大規模改革となる。これに踏み込むならば、自民・維新両党の政治妥協や政治戦術の手段として実施するのは、手続的にも内容的にも適切ではない。
内容面では、小選挙区と比例区との比重を変えることがどのような影響を与えるかなどにつき、今回こそエビデンスに基づいた分析を徹底して行い、それをベースに与野党合意を形成していくべきであろう。手続的には、専門家や市民を含む第三者委員会などを設置し、そこでの検討をベースに与野党間の合意を図るなどの工夫が必要となる。
小選挙区制と比例選挙区制
内容面での焦点となるのは、小選挙区と比例区の配分比率についてである。議員定数削減の早期実現を強く唱える維新は、議員定数の1割削減を比例区の定数削減によって実施することで、スピーディな対応が可能になるとする。こうした対応が実現すれば、小選挙区の比重がすでに大きい日本の選挙制度が、さらに小選挙区寄りになることを意味する。
小選挙区制、比例代表制にはそれぞれ長短があり、ここでそれを詳細に論じることはしない。ただ、1994年の選挙制度改革以前から、世界的な潮流は、比例代表制あるいは比例代表制を組み入れた並立制(混合型)への移行であった。その要因は、比例代表制の方が民意を反映しやすいといった点に加えて、社会構造や人々の価値観が多様化、多元化する時代に、比例代表制がより適合しやすいという判断もある。
小選挙区制は二大政党制につながりやすいという傾向は広く観察されてきた[4]。1994年の選挙制度改革の主導者たちの目線も政権交代が可能な二大政党制の実現であり、それが小選挙区制の比重の高い現行の選挙制度導入につながった。
政治学者のシュタイン・ロッカン(Stein Rokkan)らはかつて、西欧の政党システム(例 二大政党制や多党制のあり方)は西欧の社会的亀裂(social cleavage)に沿って生成し、凍結されたと指摘した。これに対して日本の場合は、1994年の上からの改革によって、二大政党制の方向に強引に誘導されたという印象を受ける。
2009年に民主党政権が誕生するなど、当初は1994年の選挙制度改革のもくろみ通り、日本でも二大政党制の方向に進むように思えた。しかし、民主党政権の迷走により、その後は自民党の一人勝ちが続いた。そして、2024年の衆院選、2025年の参院選の結果、衆参で与党は過半数の議席の確保ができず、現在は多党制の状態が生じている。
「資本家vs労働者」といった一元的な対立軸で政治競争が行われる国や時代では、小選挙区制やそれによって導かれる二大政党制は社会的亀裂と適合する場合も多い。しかし、価値観の多様化、政治的対立軸の多元化が進む時代において、1994年の選挙制度改革は、果たして日本社会の構造・文化や国民意識と整合的な改革だったのか、そうした検討は行われたのか、という疑問は残る。
選挙制度改革がその後の政治・経済・社会に与えた大きな影響を考えれば、少なくとも十分な検討はなされるべきだった。現在、少数政党が相対的に不利な現行選挙制度の下で多党制の状態が生じていることは、上からの選挙制度改革で抑えつけられた国民や社会の切実な声にも思える。
今回、1994年以来の大改革が実施されるのであれば、前回の反省に鑑み、選挙制度と日本の社会構造や国民意識の整合性について、現場から積み上げた検討を徹底的に行うべきである。
小選挙制度比例代表並立制の副産物:ゾンビ議員の絶滅を
日本の小選挙区比例代表並立制は、思わぬ副産物も生み出した。小選挙区で落選した候補者が比例区で復活当選するいわゆる「ゾンビ議員」の大量発生である。
小選挙区と比例区との重複立候補が広がる中、多くの候補者にとり、比例区は小選挙区の敗者復活戦の場となっている。これでは、比例区の存在意義が有権者に認識されるはずがない。比例区がゾンビ議員の温床となるのであれば、比例区の定数を減らし小選挙区の比重を上げるべきという議論も正当化されよう。
ただ、ゾンビ議員を排除するために比例区の定数を減らす必要性はない。重複立候補を公職選挙法で規制すれば良いだけである。あるいは、公職選挙法で復活当選のハードルを非常に厳しく設定するなどの方式も法的に可能である。
ゾンビ議員の排除は、選挙を通じた競争による新陳代謝を促進するためにも必要である。特に自民党は、第2次安倍政権以降の衆院選で圧勝を続ける中、小選挙区立候補者の大半が、比例区の復活当選を含めれば当選するという事態が長く続いた。これでは新陳代謝は進まず、自民党の地力の低下にもつながった可能性がある。
議員定数削減を通じて大規模な選挙制度改革を行うのであれば、大量のゾンビ議員の発生など前回改革で生じた問題点をどうするかについても、検討すべきである。
4.結び
繰り返しになるが、議員定数削減問題が、高市新政権にとって優先順位が高い課題であるかは疑問である。「政治とカネ」の問題と絡めて議員定数削減の必要性を唱える者もいるが、「政治とカネ」の問題へのより直接的な対応策はいくらでも考えられる。また、財政面での「身を切る改革」という視点で見ても、議員定数を削減するよりは、議員の歳費や調査研究広報滞在費などの削減を優先するべきであろう。日本の議員数は人口比で見ると国際的にはむしろ少ない部類に入る一方で、議員歳費水準は円安の影響で平均的な水準に近づきつつあるとはいえ、依然として相対的には高いからである。
ただ、自民・維新の連立維持のために議員定数削減問題に莫大な政治資本を投下するのであれば、この機会を生かした有意義な選挙制度改革を行うべきである。上からの頭でっかちな改革ではなく、日本の社会構造や文化や国民意識を踏まえた丁寧な改革が、与野党の幅広い合意の下で実施されていくことを望みたい。
[1] 『維新・藤田共同代表、定数削減実現しなければ「解散したら」…立民・野田代表「あまりに乱暴」と批判』。読売新聞2025年11月8日。https://www.yomiuri.co.jp/politics/20251108-OYT1T50070/
[2] この時の改革する側の視点については、小沢一郎 1993.『日本改造計画』講談社.などが詳しい。
[3] 「河野洋平氏『想定と大変な差あった』 30年前の政治改革振り返る」。朝日新聞2023年6月19日。https://digital.asahi.com/articles/ASR6M6QW3R6HUTFK036.html
[4] ただ、小選挙区制が二大政党制に直結するという理解は単純化されすぎている。より厳密にはCox, G. 1997. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral System. Cambridge University Press. など。