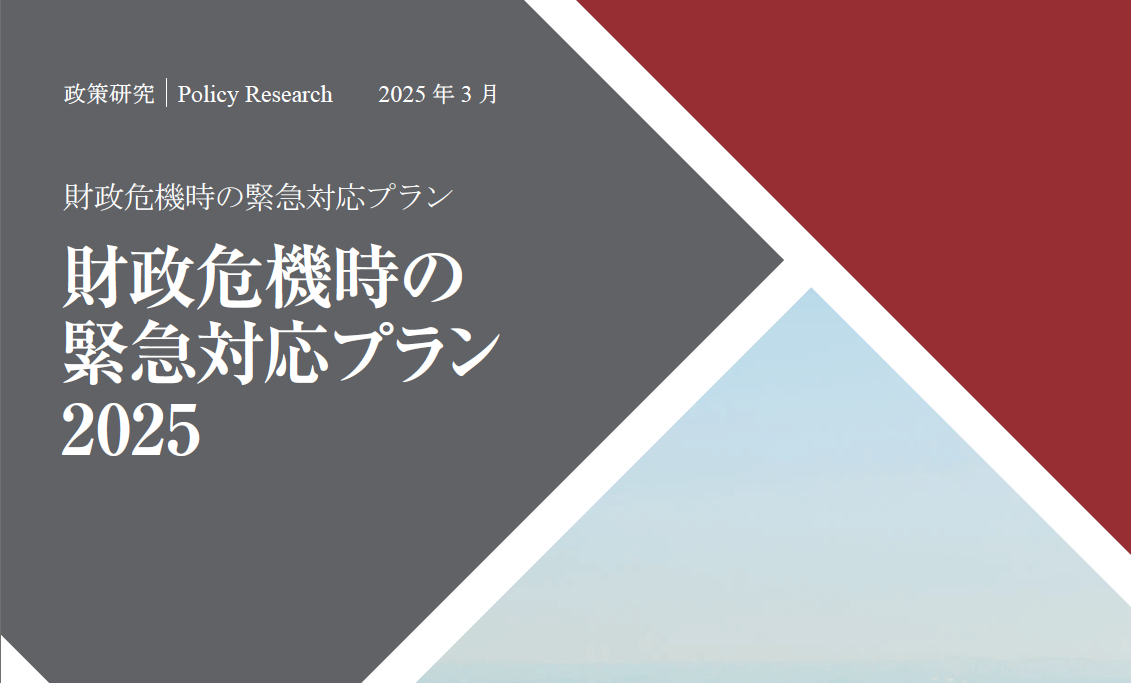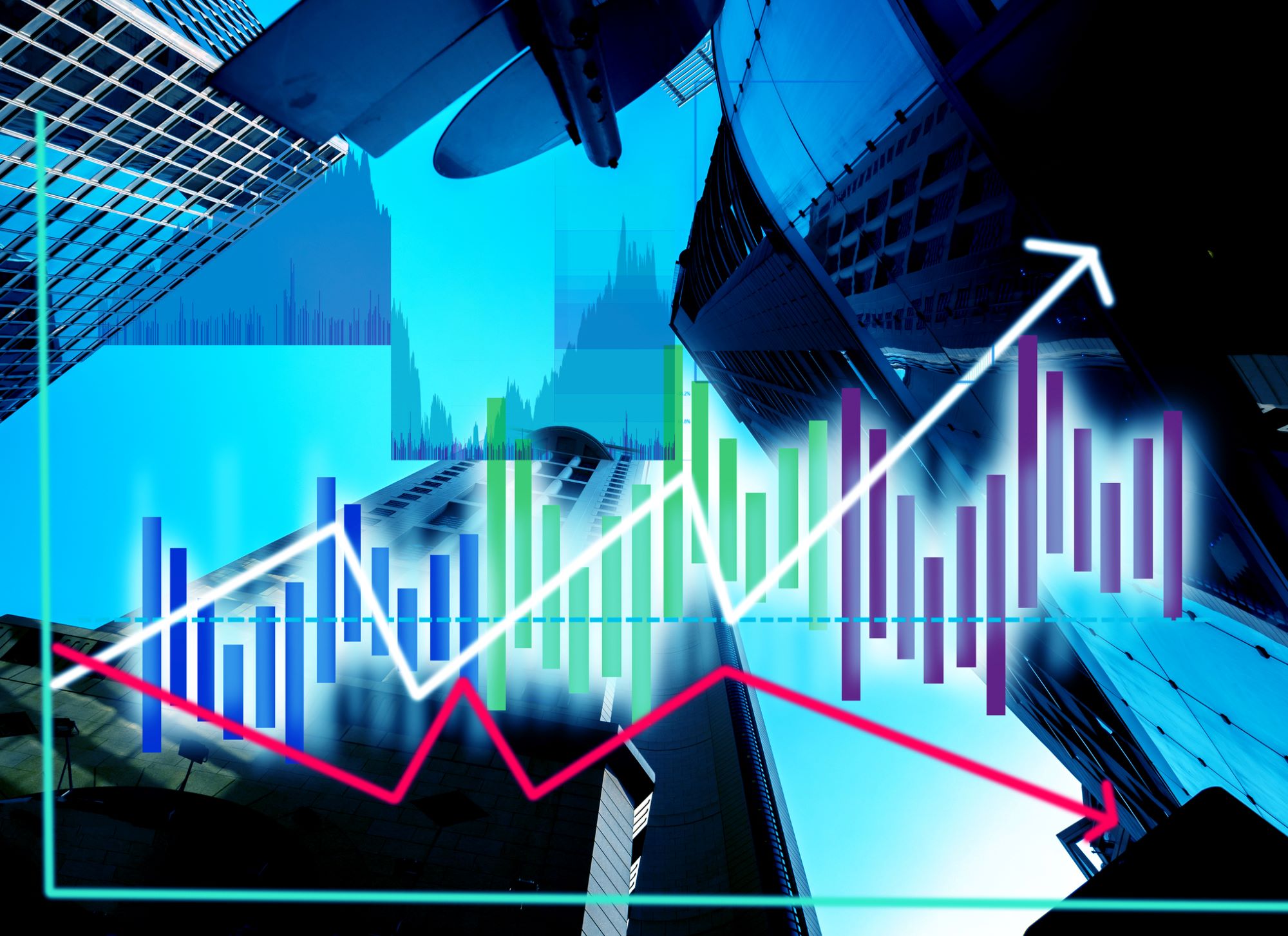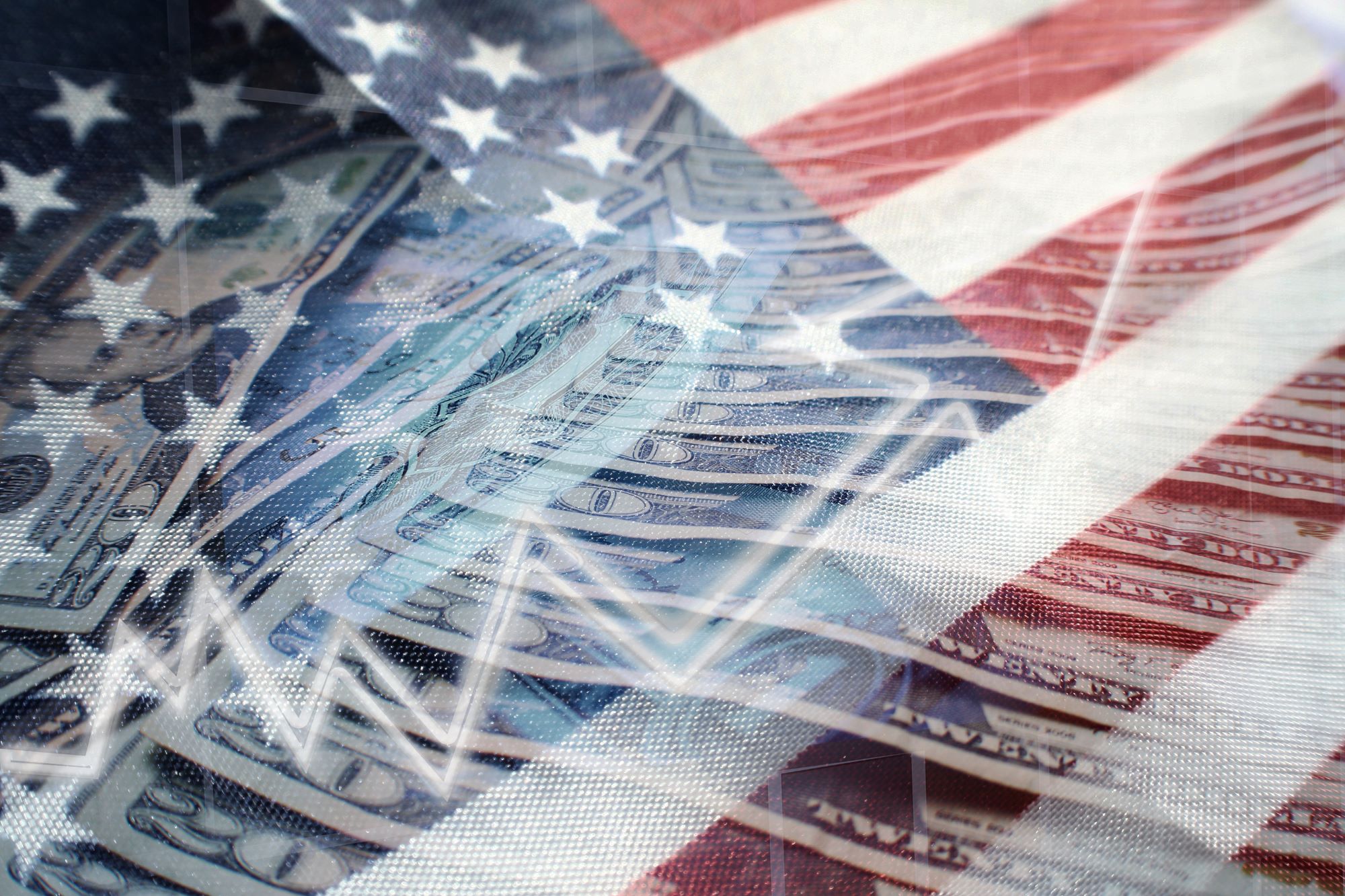R-2024-070
|
少数与党体制の発足 |
少数与党体制の発足
10月の衆議院議員総選挙で自民・公明両党は過半数の議席を確保できず、政権は維持したものの少数与党の座に転じた。自公両党のみで法案や予算案を衆議院で通せない状況の下、自公政権は主要野党(立憲民主党、日本維新の会、国民民主党)との協調を余儀なくされている。
石破茂政権は、当初は主要野党のうち国民民主党との協調を基軸に政権運営を進める方向性を打ち出していたが、補正予算案では維新と協調した。国民民主党も維新も自公政権との連立を否定しているため、政策ごとの協調となる。今後は幅広い分野で政策協調が模索されると考えられるが、現時点までで最も注目を集めたのは、「年収103万円の壁」に象徴される財政拡張的な政策を巡っての協調のあり方だ。11月22日に閣議決定された総合経済対策について、国民民主党は「103万円の壁」の見直しとガソリン減税の方向性が示されたとして、自公両党と国民民主党との三党合意が成立した。さらに12月11日には、国民民主党の方向性に沿う内容の合意書に三党の幹事長が署名した。維新は、「教育無償化」についての自公両党との協議枠組みの設置を条件に、補正予算案の賛成に合意した。
 (画像提供:共同通信)
(画像提供:共同通信)
「年収103万円の壁」などに関し合意書を交わし、撮影に応じる
(左から)国民民主党の榛葉幹事長、自民党の森山幹事長、公明党の西田幹事長=11日午後、国会
財政拡張策の合意争点化とバラマキ競争
9月の自民党総裁選や10月の衆院選を見ても、財政拡張的な方向性への異論、あるいは財政再建策を正面から打ち出す政党や候補者はほぼ皆無だった。そういう意味で、現在の日本において、財政拡張的な経済政策は、米国政治学者ドナルド・ストークス氏(1963)の言う「合意争点(valence issue)」と化しているようにも思える。
合意争点とは、大半の有権者の間で、その争点に対する賛否について概ねコンセンサスがある争点を指す。典型例としてはストークス氏自身が指摘した政治腐敗など政治倫理問題が挙げられる。政治腐敗を正していくべきという点では、おそらく日本を含めどの国の有権者の間でも概ねコンセンサスがあるからだ。合意争点に対比されるのは「対立争点(position issue)」であり、有権者の間で激しいイデオロギー対立があるような争点を指す。対立争点の典型例としては、日本では憲法(改正)問題が挙げられよう。他、たとえば米国では銃規制問題や中絶問題などがある。
合意争点であれば一見、政治的な合意や政党間の協調は容易に思えるかもしれない。実際、政党や候補者が合意争点での対策の是非で対立することは少ない。たとえば典型的な合意争点である政治倫理問題において、どの国にも、政治腐敗是正のための対策の必要性を否定する主要政党や候補者はまずいない。対策を否定すれば、有権者の支持を失うだけだからである。
ただ、以前のReviewでも述べたように(加藤 2022)、合意争点でも政策対立は生じる。その典型が、政党が有権者の支持を得るために、より強力な措置の提案を競い合うようなケースである。一方の政党の提案に対してもう一方の政党が「手ぬるい」「不十分」と批判し、より強力な措置を提案し合うエスカレーション競争である。財政拡張的な経済政策の文脈で言えば、矢野康治元財務次官(2021)の言う「バラマキ合戦」となろう。政治倫理問題で言えば、昨年の自民党の「裏金問題」に端を発した自民党内や与野党の動きも一例と言える。
合意争点でこうしたエスカレーション競争が生じると、実際に講じられる対策は往々にして、適切なレベルを超えた過剰なものとなる。財政拡張的なエスカレーション競争は、多額の公的債務を抱え、さらに少子高齢化が急速に進む日本において、特に深刻な懸念となる。
拒否権プレーヤーと財政膨張
冒頭で述べた10月の衆院選後の政党状況も、財政膨張に拍車をかける可能性がある。
自公政権が国民民主党との政策協調をベースとしている状況においては、国民民主党は自公政権の予算案、法案などに拒否権(veto power)(Tsebelis 1995)を持つ。自公政権が維新など国民民主党以外の主要野党との協調も模索する場合でも、その主要野党は拒否権を持つ。
政治的な拒否権プレーヤーと財政の関係についてはいくつかの研究がなされてきたが、実証的には概ね、政治的な分権化や拒否権プレーヤーの増加は、財政規律を弱め公的債務を増加させるという結果となっている(e.g., Crivelli et al. 2016; Hallerberg & Basinger 1998)。拒否権プレーヤーの研究とも重なるが、連立政権と財政の関係についての過去の研究においても、連立政権はより多くの公的債務を積み上げるという関係性が、概ね示されてきた(e.g., Persson & Tabellini 2003)。
実際、衆院選後、拒否権を握る国民民主党が、補正予算案などを人質に自公政権に財政拡張的な政策の実現を求め世論にアピールするという状況が続き、国民民主党の政党支持率は大きく上昇してきた。
対応の方向性
9月の自民党総裁選、10月の衆院選でも見られた財政拡張的な経済政策の合意争点化、さらに、衆院選結果により強力な拒否権プレーヤーが誕生したことは、上記の理論・実証研究が示唆するように、日本の財政状況をさらに悪化させていく可能性がある。すでにその兆候も見られる。
無論、超低金利下では財政赤字はむしろ経済的には望ましいといった研究や議論も存在する[1]。そこへの一部の政治的支持があるのは理解できるとしても、財政拡張策が合意争点化し、あらゆる主要政党が「バラマキ合戦」を競い合っている日本の政治状況はさすがに行きすぎであろう[2]。他の先進民主主義国家でも公的債務は拡大傾向にはあるものの、たとえばフランスとドイツでは、この11月と12月に相次いで、財政再建策を巡った激しい政党対立が政権を大きく揺るがした。財政拡張策と財政緊縮策との伝統的なせめぎ合いは、両国において少なくとも依然として大きな「対立争点」なのである。
私たちは現在、研究プログラム「財政危機時の緊急対応プラン」において危機の予兆時での意思決定や合意のあり方などにつき、現状に合わせた検討を進めている。以下では2つの考えられる大まかな方向性に簡単に触れたい。1つは合意争点の対立争点化である。もう1つは、拒否権プレーヤーを包含する与野党(超党派)合意の可能性である。
 (画像提供:共同通信)
(画像提供:共同通信)
会談に臨む(右から)野田佳彦首相、自民党の谷垣禎一総裁、公明党の山口那津男代表=2012(平成24)年8月8日夜、国会
方向性1:主要政党と国民との間のギャップの埋め方
すでに述べたように、10月の衆院選とその後の政治動向を見る限り、今の日本では、主要政党間では財政拡張への「合意」があるように見える。それが政党間の財政拡張のエスカレーション競争につながっている。ただ、主権者である有権者の間でそこに真の「合意」があるかは疑問である。私たちが2022年に東京財団で行ったアンケート調査では、有権者の多くはむしろ今の日本の財政状況に深い懸念を示し、財政再建の必要性を認識していた(加藤・前田 2023)。同アンケートで有権者の40%は財政赤字が「大きな問題」、25%は「ある程度問題」と考えており、大きな財政赤字を伴っている現在の財政拡張策に国民全般が「合意」している状況とは考えられない。
財政拡張的な経済政策についての有権者と主要政党の間にギャップが生じている大きな要因の一つは、政府や政党と国民との間の財政社会保障問題についてのコミュニケーションのあり方だと考えられる。この点については、別の研究を進めてきたため、本稿では踏み込まない(関連する政策提言として、佐藤他 2023など)。ただ、政府—国民間のコミュニケーションのあり方、議題設定の立て方、政策ツールの組みあわせ方などを工夫することで、財政拡張的な経済政策は対立争点と転化しうる。それにより、過剰なエスカレーション競争(バラマキ合戦)ではなく、日本の将来像を見据えたより長期の財政社会保障のあり方、財源論と組み合わせた賢い支出(ワイズスペンディング)のあり方などについて、与野党間の地に足をつけた政策「対立」が可能となるかもしれない。
方向性2:政党間合意の必要性とそのあり方
ただ当面は、財政拡張策について主要政党間で「合意」がなされている現況は変わらないだろう。10月の衆院選で強力な拒否権プレーヤーが誕生したことにより、財政拡張策を競い合うエスカレーション競争がさらに加熱しがちな状態となっている。合意争点における一方向への暴走は、日本に限らず多くの国で起こってきた。
過去に、財政を巡るエスカレーション競争を適切なレベルで留めるために有効だったのは、与野党間の協調(合意)あるいは超党派の試みである。一方の政党のみが財政再建を打ち出しても、対立政党が財政拡張を打ち出すと、政治的に押されて財政拡張にエスカレートしていくケースが多いからである[3]。たとえば米国では、レーガン政権時に超党派で制定された財政収支均衡法(グラム・ラドマン・ホリングス法)が有名だが、現在に至るまで多くの超党派による財政均衡の試みが行われてきた。連立政権の文脈においても、政党間での合意の存在は、一定の条件の下で、連立政権による財政膨張の影響を消し去る効果があることが実証されている(Back et al. 2017)。
日本の財政社会保障に関連した与野党間の協調の例としては、民主党政権末期(2012年)に民主党・自民党・公明党の間で成立した社会保障と税の一体改革に関する三党合意が挙げられる。この三党合意については、その後に誕生した自民党政権により消費増税時期が数度にわたり延期されるなど、紆余曲折を経る。当時の民主党議員の中には、自公政権によって合意が反古にされたと感じている者も多い。ただ、消費税や財務省に対して強い反発があったとされる安倍晋三首相の下で、曲がりなりにも二度にわたる消費増税が実現したのは、やはりこの三党合意の功績であろう。
10月の衆院選によって少数与党政権が誕生したことによる財政面での懸念について述べてきたが、与党政権が主要野党と協調していく必要性が生じたことは、財政拡張エスカレーション競争に歯止めをかける新たな与野党合意という面ではプラスにも働きうる。ただ、国民民主党や維新を一本釣りするような形での与野党合意では、エスカレーション競争は止まらない。やはり2012年の三党合意のように、財政社会保障について一部の野党だけでなく主要野党の大半が参加する与野党合意を実現することが必要となる。
2012年の三党合意は、民主党政権の支持率が低迷し、次の選挙での自公政権の復活がかなりの確実で予想されるなど、与野党間合意が得られやすい特殊な事情が重なる中で行われた。現況、財政社会保障について主要野党すべてが参加する与野党合意を実現することは容易ではないが、経済・財政状況が悪化し危機の予兆が顕れる段階などでは、そうした気運が高まる可能性はあるかもしれない。各党のリーダーの強い意志も重要となる。
合意のためには、国民に信頼される第三者機関などで研究者らが整理・分析したデータや推計を基に議論の共有基盤を確立し、財政社会保障の持続可能性について、ある程度共通の認識を与野党間で確立していくといった試みも今から必要となろう。55年体制下で発展した「国対政治」に代わる与野党間の新たな協調メカニズムの醸成も必要だ。持続可能性に疑義のある財政拡張競争で競い合うのではなく、持続可能な対等の基盤(土俵)を「合意」で設定した上で、与野党が将来の日本のあり方について知恵を出し合い存分に競い合うというのが、本来のあるべき民主主義的「対立」の姿のはずだ。
参考文献
Back, H., W. C. Muller, and B. Nyblade. 2017. “Multiparty Government and Economic Policy-making.” Public Choice. 170(1-2). Pp. 33-62. Springer.
Blanchard, O. 2022. Fiscal Policy under Low Interest Rates. Cambridge, MA: MIT Press.
Crivelli E., S, Gupta, C. Mulas-Grandos, and C. Correa-Caro. 2016. “Fragmented Politics and Public Debt.” IMF Working Paper 16/190. International Monetary Fund (IMF).
Hallerberg, M. and S. Basinger 1998. “Internationalization and Changes in Tax Policy in OECD Countries: The Importance of Domestic Veto Players.” Comparative Political Studies. 31: Pp.321-52.
加藤創太 2022.「求められるのは合意ではなく対立:増税・財政緊縮についての国民意識」東京財団政策研究所Review.
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3956
加藤創太、前田幸男 2023.「経済教室 財政・社会保障制度改革の視点 消費背増税前に歳出削減を」日本経済新聞4月3日。
Persson, T. and Tabellini, G. 2003. The economic effect of constitutions. Cambridge, MA: MIT Press.
佐藤主光、大竹文雄、加藤創太、小林慶一郎、前田幸男 2023.「政策提言(研究プログラム『多様な国民に受け入れられる財政再建・社会保障制度改革の在り方』)」東京財団政策研究所Review.
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4476
Stokes, D. E. 1963. “Spatial Models of Party Competition.” American Political Science Review 57-2. Pp. 372-373.
Tsebelis, G. 1995. “Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism, and Multipartyism.” British Journal of Political Science 25: Pp. 289-326.
矢野康治 2021.「財務次官、モノ申す このままでは国家財政は破綻する」文藝春秋11月号。
[1] 財政赤字や公的債務を問題視しないMMT理論(現代貨幣理論)がよく知られているが、最近ではBlanchard(2022)などより精緻な議論も展開されている。
[2] 東京財団政策研究所が2022年終わりに日本の経済学者へ行ったアンケートでは、44%が財政赤字が「大変な問題」と答え、42%が「ある程度問題」と答えた(加藤 2023)。一方、財政問題が「あまり問題ではない」は6%、「全く問題ではない」は0.7%に過ぎない。現時点では、MMT理論的な考えは日本の経済学者の大半には支持されていないと言えよう。
[3] こうした状況を「囚人のジレンマ」に陥っていると指摘する者もいるが、合意争点における各プレーヤーの協調のインセンティブは、政治・経済状況に強く依存する。