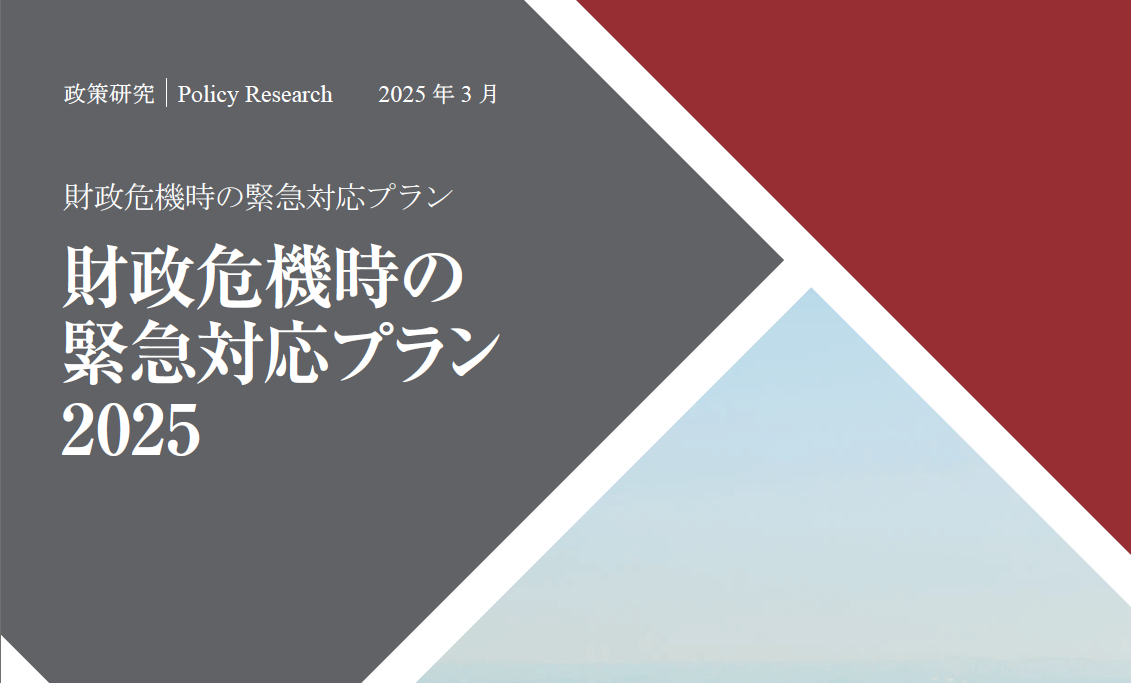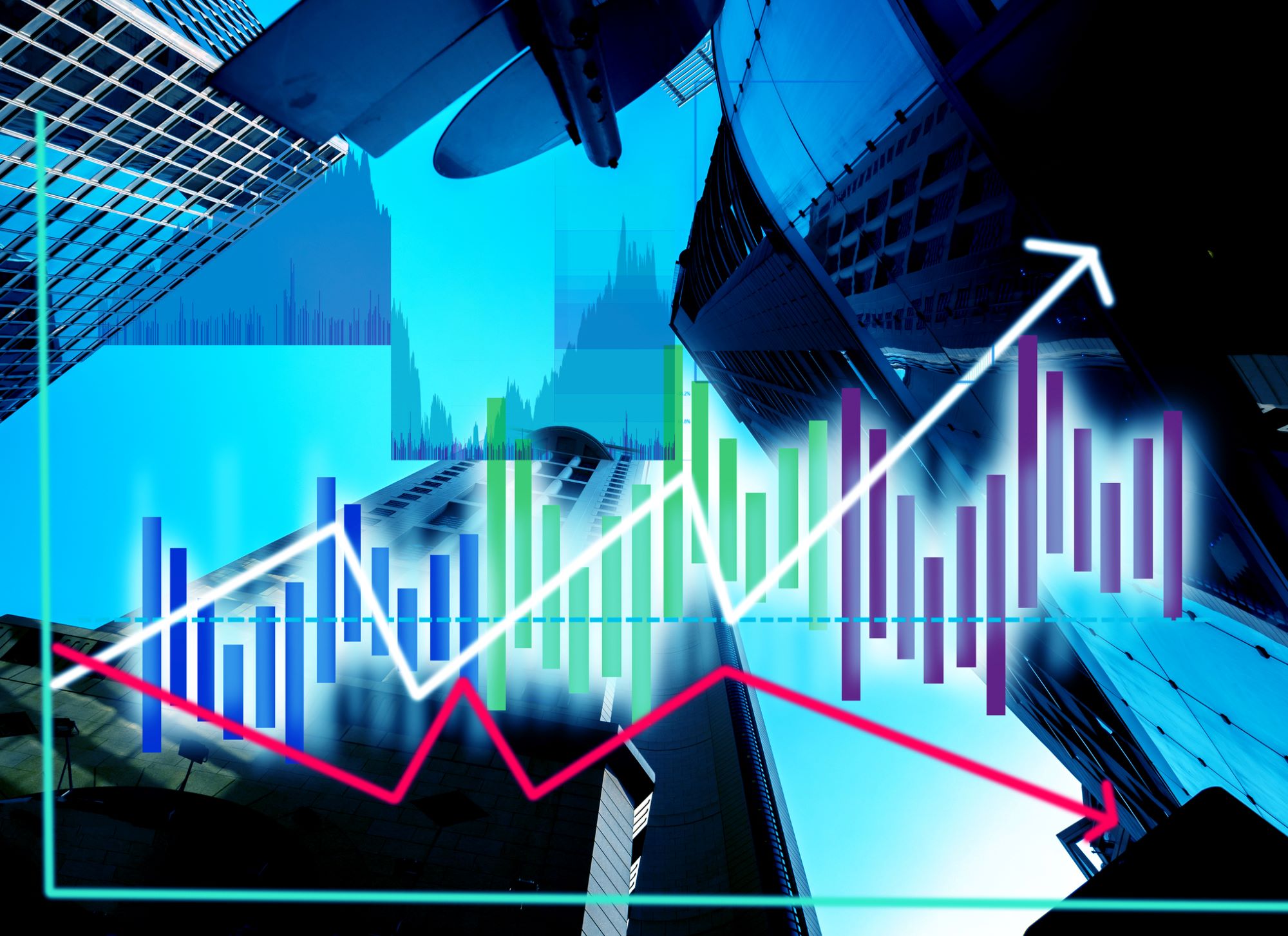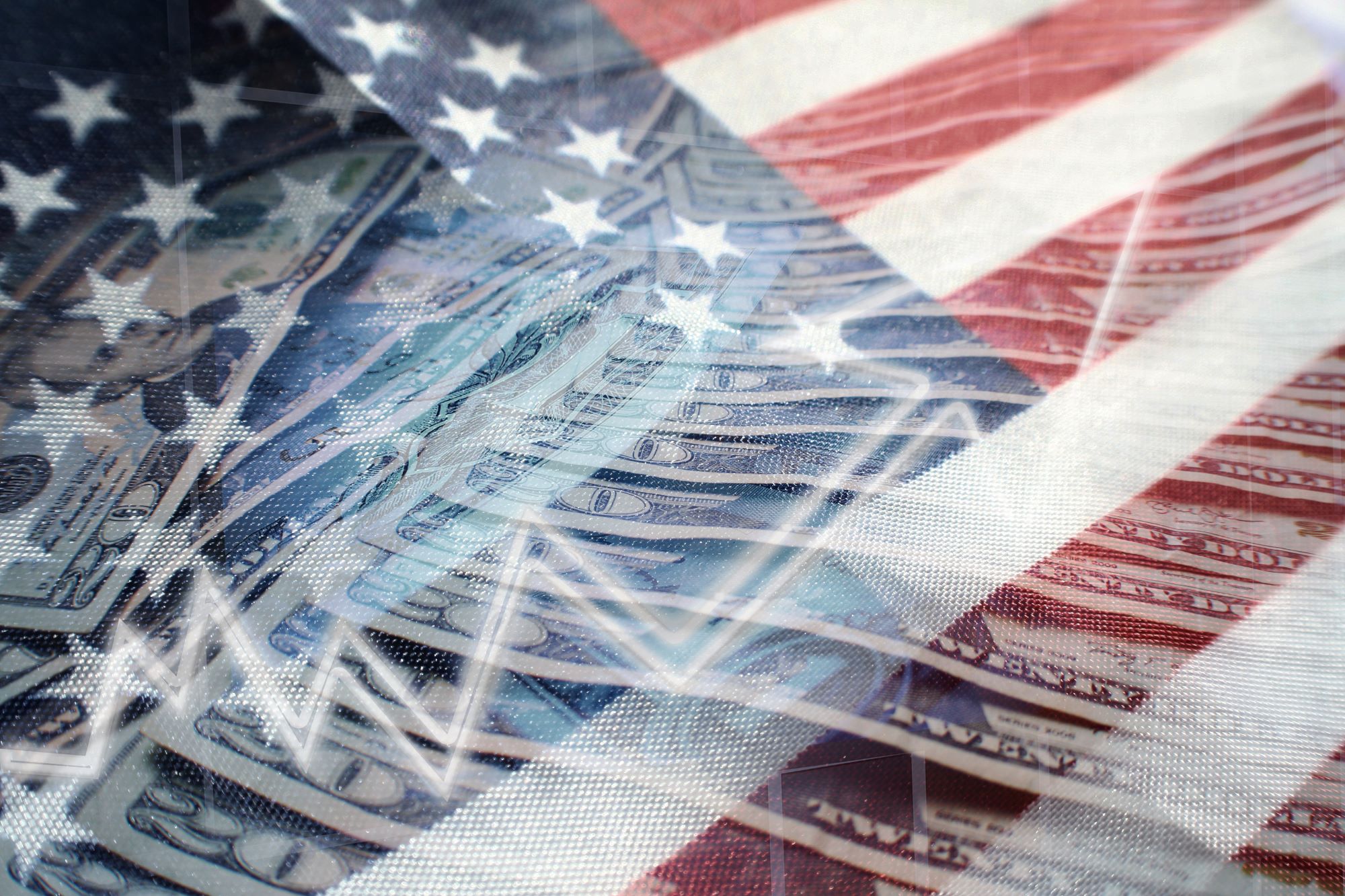X-2025-057
第27回参議院議員通常選挙が2025年7月に行われます。今回の選挙の注目ポイントはどこにあるのでしょうか。東京財団の研究員とシニア政策オフィサーが、各専門分野における争点について論じます。
|
物価対策としての「バラマキ合戦」 |
物価対策としての「バラマキ合戦」
7月20日に実施される参院選では、各種の世論調査を見る限り、物価対策が最大の政策争点になりそうである。たとえば6月末の日本経済新聞の調査では、優先的に処理してほしい政策課題として物価対策を挙げた回答者が48%で最も多く、他を大きく引き離している。
与野党から様々な物価対策が公約として打ち出されているが、その内容は財政拡張政策の競い合いだ。よりストレートな物言いをすれば「バラマキ合戦」(矢野 2021)である。選挙前に政権や政党が財政拡張やバラマキに走るのは民主主義国家において決して珍しい現象ではない。しかし、インフレ下であらゆる与野党がその方向に同時に走っている現状は、他国と比べても特異に思える。
たとえば、昨年財政問題で政治が大きく動いたドイツやフランスでも、与野党すべてが拡張の一方向に突っ走ったわけではなく、伝統的な財政拡張派と財政緊縮派の激しい対立があった。また、米国でもトランプ政権の大規模減税案などを巡り、議会内では与野党間、与党(共和党)内でのせめぎ合いが繰り広げられている。
さらに、日本の厳しい財政状況、今後予想される少子高齢化の一層の進展、インフレ対策として財政拡張策より財政引き締め策が通常は有効とされてきたこと、などを考え合わせれば、物価対策の名の下で財政拡張一色の日本の政治状況の特異さは際立つ。
財政問題の合意争点化
以前に当財団の論考で指摘したように(加藤 2022)、近年の日本では、主要政党間において、今回の物価対策を含め経済財政問題が、財政拡張的な方向で「合意争点(valence issue)」化しているように思える。
合意争点は、米政治学者のドナルド・ストークスによって提唱された概念で、その争点に対する賛否について概ねコンセンサスがある争点を指す(Stokes 1963)。各国で典型例としてよく挙げられるのは、政治倫理問題である。どの時代のどの国でも大半の有権者は政治腐敗に批判的だからだ。
合意争点に対比されるのは「対立争点(position issue)」であり、激しいイデオロギー対立があるような争点を指す。典型例としては、日本の憲法改正問題などがある。今回の参院選の争点で言えば、選択的夫婦別姓制度などもその一例だ。
合意争点と言えば聞こえは良いが、政党間の対立が生じるのは対立争点だけでない。合意争点でも政党間の激しい対立は起こる。たとえば、一方の政党の提案に対してもう一方の政党が「手ぬるい」「不十分」と批判し、より強力な措置を競い合うようなエスカレーション型の対立である。まさに昨年の衆院選以降の日本における、与野党間での「バラマキ合戦」的な状況だ。主要政党が軒並み財政拡張の方向性で「合意」している現状では、与野党間の対立が激しくなるほど財政は拡張方向に流れやすくなる。
こうした財政問題の合意争点化は、今回の参院選での政策論争の矮小化にもつながっている。選挙を間近に控え、物価対策のあり方などを巡り政党間での論争が活発に行われている。お互いの公約が「バラマキ」だと批判し合う状況も見られるが、そこで激しく争われているのは、消費減税か給付かといった財政拡張的な政策間の優劣である。いずれも物価対策の面から見れば、インフレをさらに悪化させるリスクもある対策だ。他方で、財政規律の実現や、生産性向上に向けた供給サイドの抜本的な構造改革など、全くの別方向から物価対策に切り込むような政策を正面から具体的に提示する政党は見当たらない。
バラマキ合戦にどう歯止めをかけるか―超党派合意の気運
今回の参院選での与党の苦戦が事前調査で伝えられているが、結果がどう出るにせよ、衆議院での少数与党体制は当面続く。少数与党体制は国会審議を実質化するなどプラスの面もあるが、財政拡張に向けて与野党が「合意」している現況では、財政拡張のエスカレーション競争を過熱化させてしまう。そのため、今回の参院選で与党が過半数を割るような事態になれば、エスカレーションはさらに進む可能性がある。
ではどうすれば良いか。私は以前から参院選後に超党派での合意を模索すべきと主張してきたが、参院選での政策論戦を見る限り、その要請はさらに高まっていると考える。
合意争点下での過剰なエスカレーション競争を抑制するために有効と考えられるのは、与野党間でいったん休戦協定を結ぶことである。財政拡張競争が進む中で1つの政党や政治家だけが財政規律を打ち出しても、財政拡張を唱え続ける他の政党や議員に党内外の選挙で打ち負かされる可能性が高い。少なくとも多くの議員はそう認識している。SNSでも集中砲火を浴びる。そのため、与野党が伯仲している現況では、与野党間でいわゆる休戦協定を結ばない限り、物価対策をはじめとする各種政策において、なかなか財政拡張のエスカレーションは止まらない。
休戦協定を結んだ上で、超党派の枠組みで、持続可能な財政、社会保障の中長期の見通しなどについて、一定の合意を得ることが有益だ。そうした試みは過去にも行われてきた。たとえば米国では、超党派での財政均衡の試みが何度も行われてきた。日本でも民主党政権末期の2012年に、民主党・自民党・公明党間で社会保障と税の一体改革に関する「三党合意」が成立した。この三党合意がなければ、その後の自民党政権下で、世論の反発の強い消費増税が二度にわたって実現することはなかったと思われる。
世界最大のヘッジファンドの創業者として知られるレイ・ダリオは、米国でも財政問題が大きな焦点となる中、7月1日のXへの投稿で「財政赤字・債務という爆弾の問題は、超党派的な合意で決定される税収増と歳出削減の組み合わせがなければ、持続可能な形で対処することはできない(筆者訳)」と指摘している[1]。
日本においても、最近になって超党派合意の気運が急速に高まりつつある。6月29日の記者会見において、石破茂首相は社会保障制度改革について超党派で議論する会議体を設ける必要があると発言した。これに対して立憲民主党の野田佳彦代表も協力的な反応を返した。野田代表は2012年の「三党合意」当時の首相でもある。このような現状を受けて、水面下では参院選後を見据えた超党派の動きは既に始まっている。
超党派合意は、単に政党間の合意だけでなく、幅広い国民の支持を得なければ維持できない。そのためにも、昨年来の少数与党体制の下で進められてきたような、密室での政党間の駆け引きでの合意は模索すべきではない。10年先、20年先の見通しをベースとする合意が求められている。石破首相が設置を示唆した超党派的な会議体には、政治家や経済財政の専門家や財界人といった「いつもの」メンバーだけでなく、地域・生活・職場など現場の声、SNS上のインフルエンサーの声などを取り入れていく、言わば国民会議的な仕掛けが必要となろう。
参院選とその後に向けて
衆議院に比べて、参議院は議員の任期は6年間と長く、任期途中での解散もない。存在意義が問われがちな参議院が独自性を発揮する意味でも、参院選においては本来、短期的な対策だけでなく、中長期の日本のあり方に踏み込んだ政策論争が期待されていたはずだ。
しかし、最大争点となっている物価対策に関する論戦は、目先のバラマキ競争に矮小化されている観がある。有権者にとっての選択肢は狭められているかも知れないが、世界的に財政問題への懸念が増幅し、日本の金利も上昇傾向にある中、少子高齢化が進む日本に時間の猶予はさほどない。
参院選後には、バラマキ競争的な状況への有効な対応策となりうる超党派的な取り組みの気運も生じつつある。今回の参院選においては、各種物価対策によって得られる短期的な受益だけでなく、中長期的な受益と負担も見極めた判断が有権者にも求められよう。
<参考文献>
加藤創太 2022.「求められるのは合意ではなく対立〜増税・財政緊縮についての国民意識」東京財団Review.
Stokes, D. E. 1963. “Spatial Models of Party Competition.” American Political Science Review 57-2. Pp. 368-377.
矢野康治 2021.「財務次官、モノ申す『このままでは国家財政は破綻する』」文藝春秋11月号。
[1] @RayDalio, 2025年7月1日(2025年7月2日確認)。