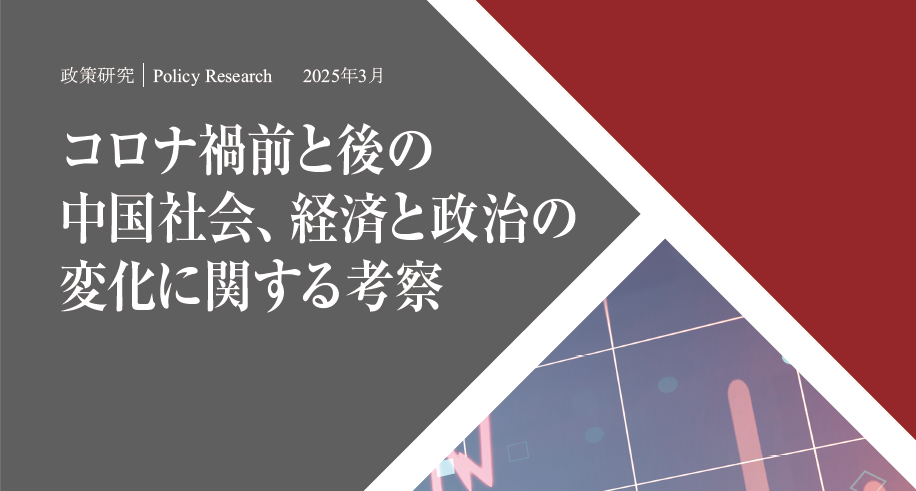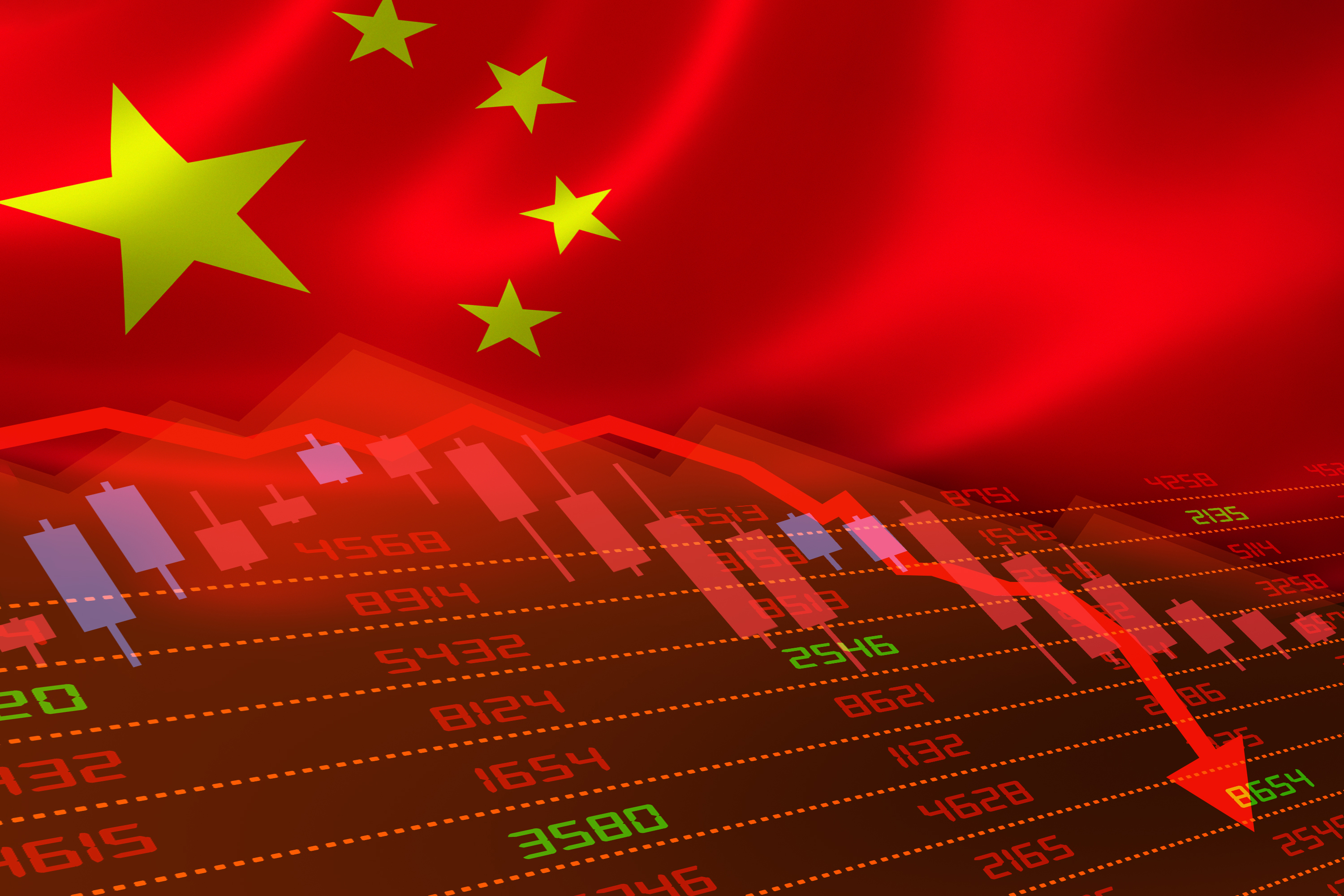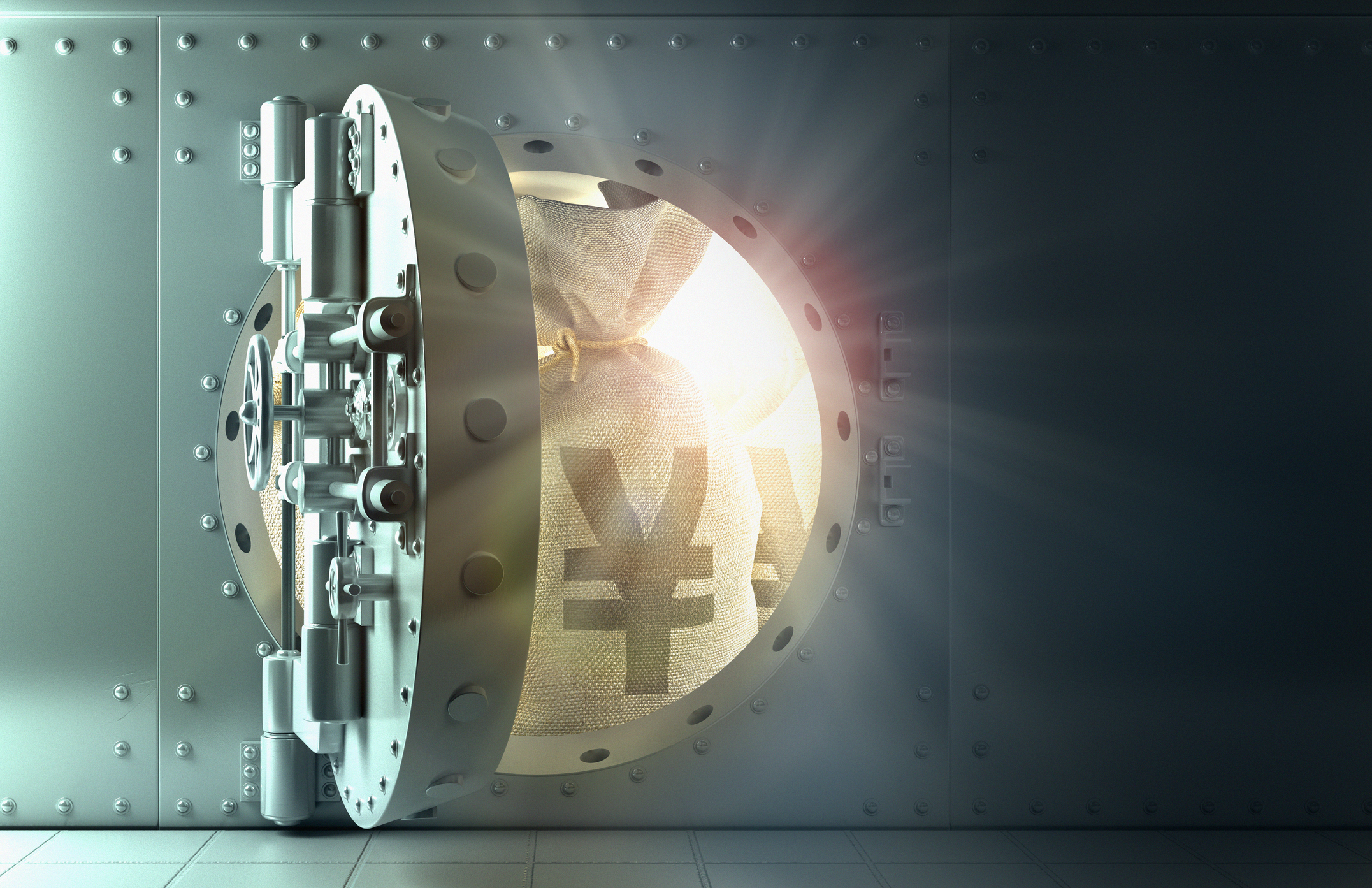- Review
【特集】新政権に期待すること―日中関係悪化に見え隠れする東アジア域内の覇権争いの行方
November 26, 2025
2025年10月21日に開催された第219回臨時国会で首相指名選挙が行われ、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されました。新政権の発足に寄せて、東京財団の政策プロデューサーと常勤研究員が、「これから期待すること」について各専門分野から論じます。
|
日中関係の悪化は避けられないものか |
先日、韓国で開かれたアジア太平洋経済協力(APEC)の際に日中首脳会談が行われ、そのとき、日中両国の首脳が戦略的互恵関係を包括的に推進するという方向性を改めて確認したことを日中両国政府は発表した。しかし、そこから一か月も経たないうちに、日中関係は急転直下し、急速に悪化している。そのきっかけは、前述の日中首脳会談後に行われた高市早苗首相と台湾代表の林信義氏との挨拶の様子および二人の記念写真が高市首相のXに投稿されたことに加え、国会での台湾有事に関する高市首相の答弁だったとみられている。
実は、日中首脳会談のとき、両国間でもう一つ問題になったことがあった。それは高市首相が習近平主席に香港や新疆ウイグル自治区などの人権問題について深刻な懸念を示したことである。これらの諸問題は中国の文脈を踏まえれば、いずれも外国首脳に言われたくないタブーである。言い換えれば、高市首相の発言は中国のレッドラインを踏んでしまったということである。
韓国で行われた日中首脳会談について中国中央電視台(CCTV)は習近平主席の発言を肉付けして報じたが、高市首相の発言内容について一切触れていない。中国国営の新華社通信は日中首脳会談について全く報じていない。逆に、高市首相の国会答弁について、中国国内の各メディアは新華社通信の報道をもとに、日本に対して一斉に批判している。特に中国の駐大阪総領事がX(旧Twitter)に暴言とも受け取れる記事(その言葉の引用はここで省くことにする)を投稿したことも事態の悪化に拍車をかけた。問題は、このつばぜり合いだけでは済まず、中国政府が日本への渡航・留学を慎重に考え直すよう呼び掛ける状況となっている。その上、11月19日になって、中国政府は日本からの水産物輸入を再び停止すると宣告した。日中関係はどこまで悪化するのだろうか。なぜ、高市首相の国会答弁はここまで中国政府を激怒させたのだろうか。
日中関係の悪化は避けられないものか
前述の問いの答えは、残念ながら答えはイエスであり、日中関係の悪化は避けられないと考えるべきである。これまでの日中友好はある意味では、まぼろしであり、価値観の違いは根底にあることを無視することはできない。中国経済の発展が遅れていた時代、中国政府は低姿勢で日本に学ぼうとしていた。今は、日中両国の経済力が逆転した。中国人の眼には日本が入らなくなってしまった。
もう一つの変化は中国の国力強化による急速な拡張路線への転換である。これはいわゆる従来の中国脅威論と合致するものである。中国の経済発展と国力強化が世界にとって脅威となることが従来から指摘されている。ただし、中国の経済力は公式経済統計を精査すれば、かなり過大評価されている可能性がある。すなわち、現下の拡張路線は必ずしも実際の経済成長に支えられているものではないかもしれない。脅威となるかどうかはその国の外交政策と戦略次第である。
冷静に中国経済と中国社会を考察してみよう。いわゆるコロナ禍(2020-22年)は中国経済のみならず、世界経済に深刻なダメージを与えた。習近平主席が自ら指揮し、実施した都市封鎖(ロックダウン)のゼロコロナ政策は、中国経済と中国社会に深い傷跡を残した。2023年にコロナ禍が収束したことを受けて、中国経済はV字型回復をすると思われていたが、結果的にL字型成長になり、減速を続けている。
中国経済の減速を表すのは実質GDP伸び率だけでなく、若者(16-24歳)の失業率の高止まりも挙げられる。しかも、経済が上昇傾向にあるときと違って、下降傾向にあるとき、低所得層の所得は大きく落ち込む傾向が強まり、所得格差が普段よりも拡大しやすくなる。それを受けて不満が高まり、社会不安が深刻化しやすい。
では、社会不安が増幅するなかで、なぜ中国政府は日本に対して態度を硬化させているのだろうか。中国政府の文脈から考えれば、高市首相はいくつかのレッドラインを踏んでしまった。一つは香港や新疆ウイグル自治区などの人権問題を習近平主席に面と向かって指摘したことである。もう一つは、習近平主席は台湾が中国の核心的利益といつも主張しているのに、高市首相は台湾有事について、集団的自衛権を適用させる可能性を明言したからである。これをきっかけに日中関係は出口のない袋小路に入ってしまったのである。このように考えれば、習近平主席が高市首相の答弁を看過できないことは理解できないことではない。しかし、高市首相は自らの発言を撤回できない。ただでさえ少数与党であるため、もし高市首相はこの発言を撤回したら、保守層からの支持を失ってしまい、政権が一気に不安定化してしまう。結論的にいえば、日中関係の悪化は避けられるものではなく、予想以上にエスカレートし、長期化する可能性が高い。
中国の台頭と強国復権の夢
戦後の冷戦期、世界情勢は米ソの覇権争いが基本的な構図だった。そのとき、日本は安全保障を日米同盟に委ねた。中国はソ連と協力して、いわゆる米国帝国主義に対抗した。1953年、スターリンが死去した後、中ソ関係に徐々に亀裂が走った。原因はソ連でフルシチョフがスターリン批判に走ったことに加え、毛沢東は共産主義圏のリーダーになろうとしてフルシチョフと激しく対立したからである。当時、中国でフルシチョフは修正主義者と厳しく批判された。
結果的に中ソ対立の激化は米中の接近を現実なものにした。当時、米中にとってソ連は共通の敵だったから、敵の敵は友になる。一方、日米は同盟国であるため、日中の国交正常化も現実的なシナリオとなった。しかも、長い間、日本国内に中国との友好関係を構築すべきと主張する左派勢力が存在している。日本の左派勢力の主張は、そもそも日中は同文同種の隣国であり、日中友好は必然な趨勢であるといわれている。なによりも、第二次世界大戦中、日本は中国に多大な迷惑をかけた。その贖罪意識からも中国との関係を改善し、中国の経済発展に日本が協力すべきと主張されていた。
こうしたなかで、日中の国交正常化と中国の改革・開放は偶然にも重なった。当時、多くの日本人は中国が日本と同じように開かれた国になっていくと期待していた。中国に対する贖罪意識から日本が中国の経済発展に協力することは当たり前の話となった。この考え方こそ1980年代の日中蜜月時代を作り上げた。今から振り返れば、当時の日中友好はまるで蜃気楼のように思えるものだった。
中国人の日本をみる目はいつごろ変わったのだろうか。それは2000年前後だった。1998年ころ、日本経済が金融危機に見舞われ、いくつもの大手都市銀行と大手証券会社は相次いで倒産した。2001年に中国は念願の世界貿易機関(WTO)加盟を果たした。それを受けて、外国の製造企業だけでなく、物流や流通などのサービス企業も中国に直接投資を行った。その結果、中国経済は高度成長期に入っていった。中国人からみると、日本はもはや衰退していく国であり、代わりにアメリカが視野に入ってきた。
ある意味では、中国人のこの考え方は正しかった。というのは2010年に中国のドル建て名目GDPが日本を追い抜いて世界第2位になったからである。当時、多くの欧米評論家が21世紀は中国の世紀であると明言した。おそらく中国政府指導部もこの予言を信じたに違いない。2013年3月、習近平政権は発足してから、強国復権の夢を提唱した。要するに、中国は世界の強国になろうとしているのである。
日中による東アジア域内の覇権争いの序章
2005年にピーターソン国際経済研究所理事長だったC・フレッド・バーグステン氏はGroup of Two(G2)の構想を提唱した。オバマ政権が発足してから、元カーター大統領の国家安全保障問題担当補佐官だったズビグネフ・ブレジンスキー氏や元世界銀行総裁だったロバート・ゼーリック氏などはG2構想を基とする新しい国際秩序を提言した。ちなみにゼーリック氏は筋金入りの親中派論客である。それに呼応する形で中国では、「新型国際関係構想」が提唱された。オバマ政権下で米中関係は至って平穏だったようにみえた。
2017年にトランプ政権1.0が発足した。そのとき、中国では、すでに強国復権の夢の実現に向けて、「中国製造2025」や海外から高度人材をリクルートする「千人計画」などのプログラムが実施に移された。トランプ大統領は安全保障についての関心は高くないが、弱体化したアメリカの製造業と国際貿易の不均衡を問題視して、中国に対する厳しい制裁を発動した。これは米中貿易戦争の発端となった。
いくら中国の国力が台頭したからといって、アメリカには遥かに及ばない。両国の軍事力を比較してみよう。2025年、アメリカの軍事予算は8,498億ドルに上るといわれている。それに対して、同年の中国の軍事予算は2,490億ドルである(中国政府発表)。Stockholm International Peace Research Instituteの推計でも、同年の中国の実際の軍事予算は3,300~4,500億ドルであり、アメリカの半分以下の規模である。中国にとってアメリカは対等に戦える相手ではない。
では、習近平政権の本当の目的は何だろうか。それは東アジア域内におけるリーダーシップ、すなわち、地域的覇権を手に入れることであろう。安倍元首相が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想は習近平政権が描いた東アジア域内覇権の獲得と真正面から対立するものである。したがって、日中の対立が始まったのは高市政権になってからではない。ただし、今までの歴代政権は習近平政権との正面衝突を避けてきた。高市首相はこれまでの歴代首相と違って、言うべきことを言うだけでなく、はっきり言ったのである。習近平政権は今までおとなしかった日本が突然物事をはっきり言うようになったことに驚いたに違いない。今の日中対立はそのショック反応といえる。
中国はアメリカと対等に戦えないが、日本を抑えるのは簡単であると思われている。中国にとって問題が複雑なのは日本が単独の存在ではなくて、日米同盟を結んだ存在であり、集団的自衛権の発動が可能になっていることである。高市首相は国会答弁で確かに台湾有事が日本有事であることを明言した。この言葉のあとにもう一言がある。すなわち、日本有事はアメリカ有事であるとのことである。
したがって、習近平政権にとって台湾有事の概念の広がりを防いでおかないと、収拾がつかなくなる。このことの本質は何かというと、日中の間で繰り広げられる東アジア域内の覇権争いの序章である。
問われるのは高市政権の国際戦略のあり方
マスコミの報道をみると、一部の評論家は、高市首相は国会答弁の発言を撤回すべきだと主張している。なかには、高市首相が発言を撤回しないと、中国で日本商品の不買運動が呼び掛けられるという問題を提起する論客まで現れている。しかし、事の本質は明らかにその低レベルの議論ではない。経済学的に考えれば、消費者の消費行動はいつも合理的である。中国の歴史上、何回も不買運動を呼び掛けられたが、長続きしたことがない。
重要なのは中国にとっても日本にとっても持続的な経済発展を担保するには安定した域内情勢が必要不可欠である点だ。韓国で行われた日中首脳会談のコンセンサスの戦略的互恵関係は正しい認識である。それに立ち返らないと、この方程式を解くことができない。むろん、日中関係という連立方程式を解くのは決して簡単な作業ではない。なぜならば、日中両国は価値観を共有できないからである。価値観を共有せずに、心を許して協力できるとは思わない。戦略的互恵関係の構築は言葉でいうことよりも難しいはずである。
高市政権がどのような国際戦略を描いているかは明らかではないが、経済学のゲーム理論的な考えに基づいてどういう選択肢があるかを探ってみよう。まず、日本は自らの実力を直視して、グローバル社会のリーダーになろうとは思わないで、いかにして日本の国益を守るかを考えるべきであろう。日本の歴代政権の正しい戦略の一つは日米同盟を重視する姿勢である。逆に欠けている点もある。すなわち、日米同盟に頼りすぎることである。主体性のある安全保障戦略が描かれていない。ここで問われるのは安全保障にかかわる日本の主体性である。日本の左派の論客の主張にまさにこの点が欠けている。彼らは日米同盟を批判するが、主体性はいっさい言及しない。あたかも平和は空から降ってくるもののように主張している。
一方、日本の主流派の論客は口癖のように日本が国際社会でリーダーシップを取っていくべきと述べている。残念ながら、日本の国力をみても、国際社会でリーダーシップを取れるほど強くない。日本は国際社会に貢献することができるが、覇権国家にはなれない。中国や韓国で日本が軍国主義を復活させようとしているとの批判があるが、このように指摘する中韓両国の論客は明らかに日本のことを知らないのである。
結論的に総括すれば、現下の日中関係の悪化は偶然に起きたものでもなければ、避けられるものでもない。言ってみれば、起きるべきことが起きただけである。中国政府が宣告している種々の制裁措置はほとんど日本に実害の小さいものばかりで、日本を困らせるものというよりも、日本に不快感を示すものである。したがって、騒ぐ必要はまったくない。重要なのは日中関係だけでなく、現下の流動的な国際情勢を正しく認識して、日本の取るべき戦略を明確に描くことである。そのすべてをはっきり述べる必要はなく、中国との対立の激化を避けることも日本にとって重要なことである。実は日中両国が抱える共通のリスクは両国の国民感情が悪化することである。両国の政治が対立するのは避けて、経済や文化の交流を続けるべきである。