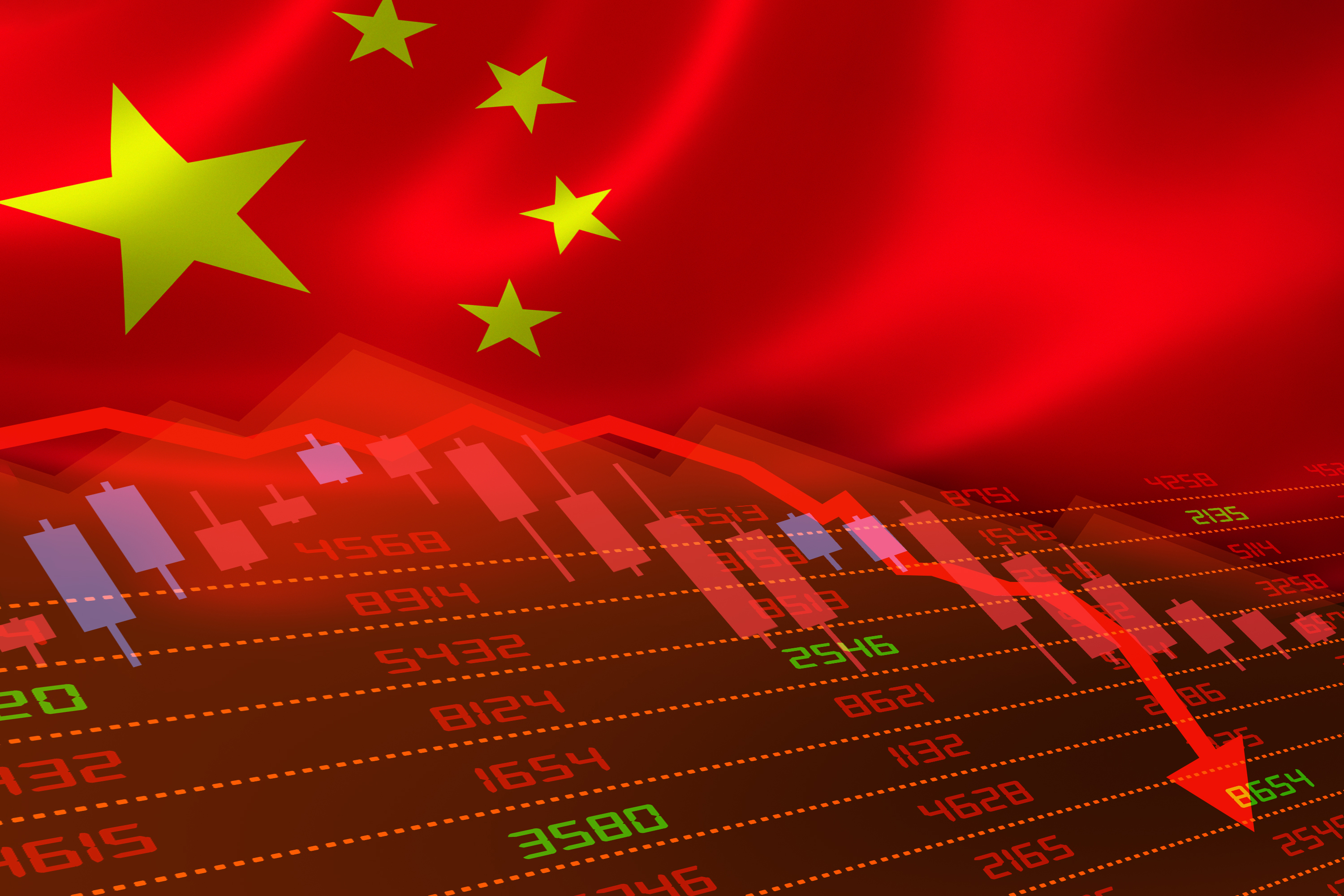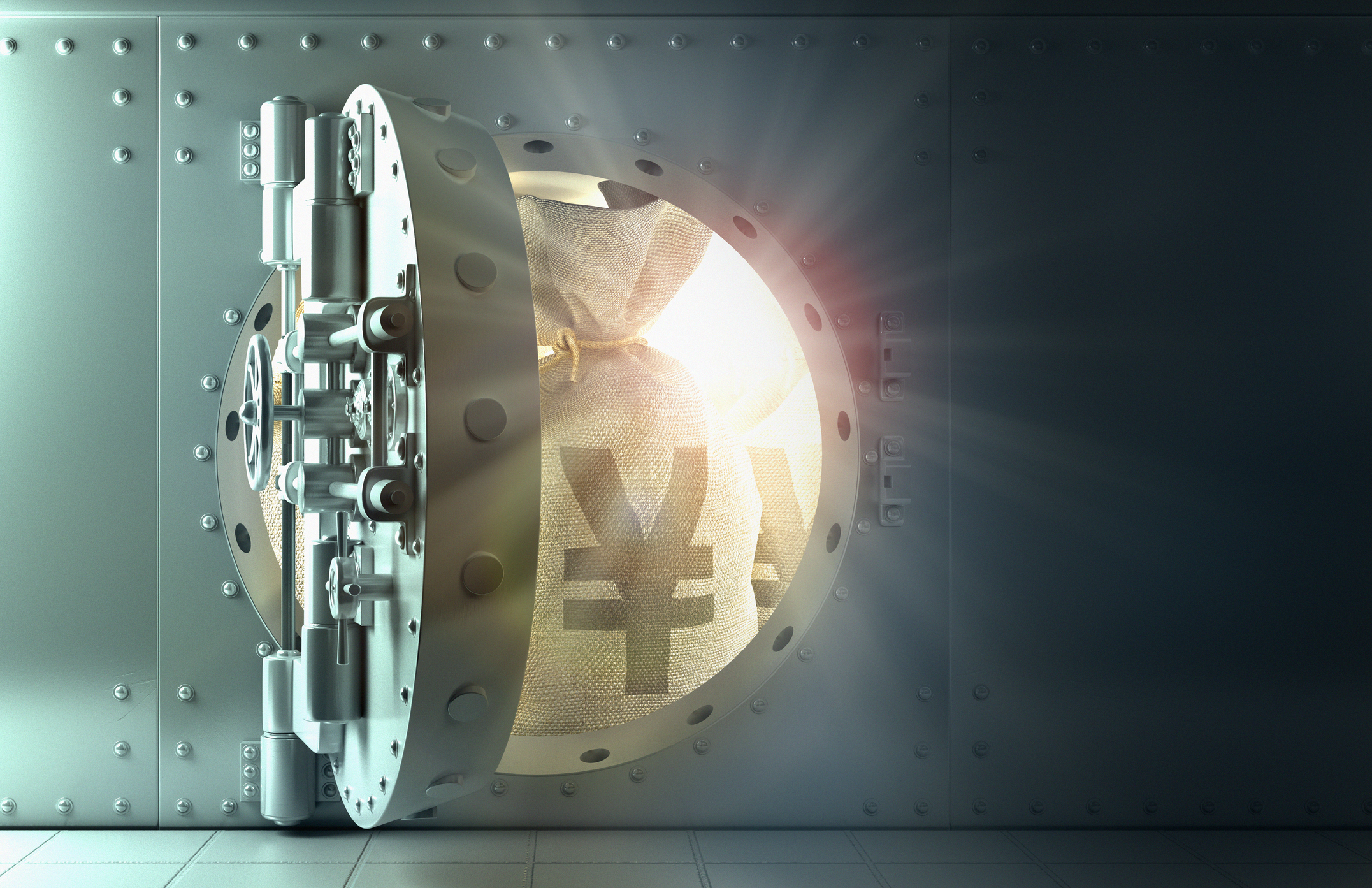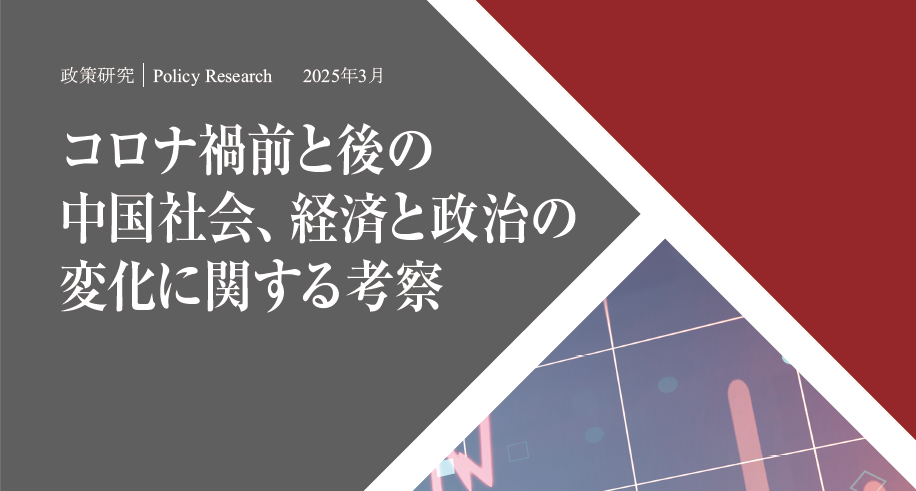
P-2024-002
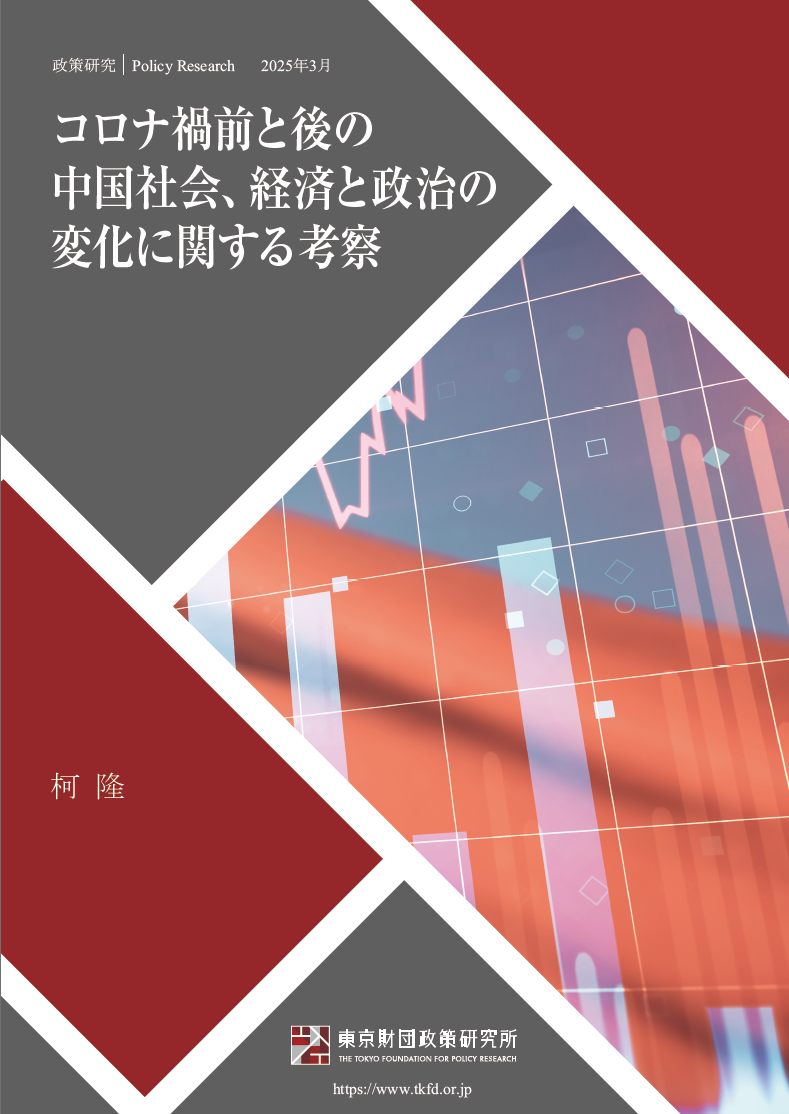
本「政策研究」は東京財団政策研究所「コロナ禍前と後の中国社会、経済と政治の変化に関する考察」研究プログラムの成果物として取りまとめたものです。本プログラムは2023年7月に発足し、1年半にわたり、政治、経済、歴史など多面的な考察を経て、最終的に政策提言を目的とする本「政策研究」を取りまとめました。
要旨
- 2020年1月、突然世界は新型コロナウイルス感染症(コロナ禍)に襲われた。世界保健機関(WHO)の発表では、新型コロナウイルス感染症により、700万人に上る死亡者が出たといわれているが、その裏付けは取られていない。特に、中国政府が公表した死亡者数12万人には新型コロナウイルス関連死が含まれていないとみられ、実際の死亡者数ははるかに多いと推察される。
- パンデミックが発生した背景として、グローバル化の進展により、感染抑止の制度的メカニズム・科学的バックアップが整っていなかったことが挙げられる。コロナ禍に対して、WHOはその役割を十分に発揮できなかった。
- コロナ禍によるグローバリズムの後退が懸念されている。1990年代初頭の冷戦終結以降、世界経済はグローバル化により急成長を遂げたが、この30年間の成長エンジンとなったのは中国経済だった。一部の有識者は「21世紀は中国の世紀になる」と予言し、イギリスのシンクタンクは中国のドル建て名目GDPが早ければ2028年にアメリカを追い抜くと展望していた。
- コロナ禍による中国経済の影響は想像以上に大きい2013年の習近平政権発足以降、中国経済は一貫して下り坂をたどっている。コロナ禍の影響により、若者の雇用が一段と悪化し、不動産バブルも崩壊した。中国経済はデフレに突入しているが、習近平政権はいまだに有効策を講じていない。
- 習近平政権は都市封鎖を中心とするロックダウン政策を講じたが、現場は混乱し、大都市では幾度も医療崩壊が起きた。厳格なロックダウン政策により飲食店や食品スーパーなどのライフラインが止まり、市民生活に支障を来した。
- コロナ禍の影響で、数百万社の中小零細企業が倒産したため、若者の雇用が難しくなり、コロナ禍の後遺症がいまだに克服されていない。
- トランプ政権2.0による米中対立のさらなる激化に日本も巻き込まれる公算が大きい。日本経済は想像以上に中国経済との一体化が進んでおり、自動車産業を中心に日中相互依存度が高い。日中は経済協力を続ける可能性と合理性が十分に存在する。日本にとって日米同盟が重要な柱であるが、中国との経済協力も続けなければならない。日本独自のグローバル戦略の構築が求められている。
目次
提言全文
![]() コロナ禍前と後の中国社会、経済と政治の変化に関する考察(PDF:5MB)
コロナ禍前と後の中国社会、経済と政治の変化に関する考察(PDF:5MB)